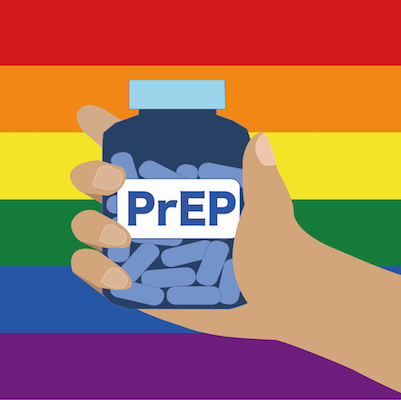NEWS
LGBT理解増進法の成立を受けて、プライドハウス東京とLGBT法連合会が声明を発しました
6月16日に可決、成立したLGBT理解増進法について、プライドハウス東京とLGBT法連合会が声明を発しました。
6月18日、プライドハウス東京は「「LGBT理解増進法」に対する懸念の表明と差別を許さない運用のための声明」を発しました。プライドハウス東京は毎月2回、トランスデーを開催し、多くのトランスジェンダー当事者やアライが集える場を設け、理解や支援の輪を広げることに貢献してきました。4月から共同代表に就任した小野アンリさんもトランスジェンダーの方です。今回の件でトランス女性への差別やヘイトスピーチがさらに激化する恐れがあると指摘しながら、「私たちはこうしたヘイトスピーチの拡散に強い懸念と抗議の意を表明」しています。同時に、多くの企業や団体、大使館、スポーツ関係者などと良好な関係を結んできた団体として「あらゆるステークホルダーと連携し、本法律の原点を見据え、適切な運用がなされる取り組みを進め、誰も排除されないLGBTQ+インクルーシブな社会を共に実現することを呼びかけます」と述べています。
「6月16日の参議院本会議にて、「LGBT理解増進法案(正式名称:性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案)」が、議員立法の全会一致の不文律に反する形で成立しました。
LGBTQ+当事者に対する差別を禁止する法律は、社会の中で偏見や差別を受けているLGBTQ+当事者にとって、安心・安全に生活を送るために必要不可欠なものです。
しかしながら、本来はLGBTQ+当事者が今もなお受けている差別や困難を解消するための法案だったにも関わらず、紆余曲折を経て、今回成立した法律がLGBTQ+当事者への差別を助長し、より困難な状況を強いる危険性がある内容となってしまったことに対する悲しみや憤りの声が上がっています。
特に、法案の審議の過程で十分な議論もないなか追加された、「性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意するものとする」という文言により、LGBTQ+当事者への理解を増進する活動や取り組みは多数派への配慮が前提となると捉えられる可能性があります。これは「多数派が不安だ」と言うだけで、LGBTQ+の啓発活動に歯止めをかける効力の可能性を意味します。また、「家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつ」という文言の追加は、家庭や地域からの協力を得られなければ、LGBTQ+に関する啓発活動すらできないと捉えられる危険性があります。
さらに、今回の法案の成立によって、特にトランスジェンダー女性に対する差別を助長する恐れがあることも危惧されています。実際、トランスジェンダーの人々に対する実態とかけ離れた事実誤認や歪曲、差別や偏見に基づく発言などが継続的に行われており、SNS上などでそれが増幅され拡散されるという過酷な状況があります。また、プライドハウス東京コンソーシアムが設立当初から取り組んできたスポーツの現場においても、トランスジェンダー女性が排除される動きが活発になっています。トランスジェンダーの方々の命や健康に重大な悪影響をもたらし、排除や抑圧を深めるものとして、私たちはこうしたヘイトスピーチの拡散に強い懸念と抗議の意を表明します。
プライドハウス東京コンソーシアムは、本法律の懸念点を厳しく批判し、内容の見直しを強く要望します。また、LGBTQ+当事者への差別の助長につながることがないように、今後も本法律の運用を厳しく注視し、LGBTQ+当事者の実態を踏まえた提言等を行っていくことを表明します。あわせて、識者・当事者団体らの声を法律を運用する際にきいていただけるよう、要望します。
さらに、全国各地のLGBTQ+支援団体、専門家、民間企業、大使館、スポーツ団体・関係者、ジェンダー平等やマイノリティ支援に取り組む様々な団体の皆さんをはじめ、あらゆるステークホルダーと連携し、本法律の原点を見据え、適切な運用がなされる取り組みを進め、誰も排除されないLGBTQ+インクルーシブな社会を共に実現することを呼びかけます」
LGBT法連合会も19日、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案の成立についての声明」を発しました。LGBT法連合会はそもそもLGBT差別禁止法の制定に向けて、国会内の超党派LGBT議連への政策提言を行なうために、全国の100以上のLGBTQ団体が集まって結成された団体で、かれこれ6年以上もLGBT法の制定のために尽力してきました(だからこそ、LGBT法をめぐる動きに関してLGBT法連合会がその都度コメントしたり、会見を開いたりしてきました)。2年前の、与野党合意を見ながら(ただ差別発言だけが垂れ流されて)国会に提出されなかった事件を経て、今回の、議論されるたびに内容が後退し、挙げ句の果てに土壇場でマジョリティ配慮の(差別増進的な)内容に変質させられてしまった件を、誰よりも悔しく感じていることでしょう。声明にもその憤りが表れていると同時に、「差別を禁止する法制度が確立されるよう、歩みを止めることなく、多くの人々とともに連帯して運動を続けていく」との決意表明が述べられています。
「2023年6月16日、参議院本会議において、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案」が成立した。本法は、極めて異例の審議・修正の過程をたどり、短期間で法の内容が後退するものとなった。日本で初めて性的指向及びジェンダーアイデンティティについて位置づけた法律として、歴史的な意味を持つべき法律であるにもかかわらず、私たちが求めてきた差別禁止法とは大きく異なり、懸念を表明しなければならないものであることは極めて残念である。長年の運動の結果が、このような法律の制定であることは受け入れ難く、厳しい姿勢で臨まなければならない。また、今後、この法律については、取り組みの後退が懸念される部分、前進に活かし得る可能性のある部分の双方について、対応を早急に検討しなければならないであろう。
この法律は、「全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下」理解増進の施策を進めるとの基本理念を掲げている。この理念に則り、国の基本計画の策定、省庁連絡会議の設置、学術研究の推進、毎年の白書の発行などが政府に義務付けられている。また、国、地方公共団体、事業主、学校は、基本理念に則った施策の実施に努めるものとされており、啓発や相談体制の整備その他の必要な措置を努力義務として課している。ただし理念法でありながら、「全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意するものとする」と、性的マイノリティ当事者の尊厳を踏み躙るかのような条文を設け、政府が具体的な指針を策定するものと規定している。
理解増進の名を冠しながらも、啓発等は努力義務に留まっており、国の体制整備を義務付ける法律と捉えるべきものである。ただ、国会答弁によれば、すべての施策は「全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意するものとする」こととなる。更に、指針が策定されることにより、現在、もしくは今後の地方自治体や教育現場の取り組みに対し、実質的な萎縮効果をもたらすことが懸念される。一部の勢力によって、さまざまな取り組みが「安心できないもの」であるとされ、停滞させられることのないよう、今後の基本計画や指針の策定経過はもとより、地方自治体や教育現場への、学術的に裏打ちされ、統計的な根拠を持った働きかけを強めなくてはならない。
本法律が日本で初めて性的指向及びジェンダーアイデンティティ(性自認)について位置づけた法律であるにもかかわらず、このような内容となったことに憤りを禁じ得ない。法律制定までの審議過程も含め、これが当然に導き出される経緯や法の内容ではないことは、強調しておきたい。当事者は、法律の制定に至る過程の中で、多くの傷つきと途方もない苦しみを味わうこととなったが、これを当然とせず、このような過程自体が社会的に問われるべきものであり、真摯に省みられるべきであることを指摘する。
今後、この法律が性的指向や性自認に関する取り組みを阻害する動きに使われることなく、真に基本理念に則った取り組みが進むよう、また差別を禁止する法制度が確立されるよう、歩みを止めることなく、多くの人々とともに連帯して運動を続けていく」
両団体と同様に、LGBTQを差別から守るための法整備や平等な権利、当事者の生きづらさを解消するための施策等を求め、活動してきた一般社団法人fair代表理事の松岡宗嗣さんも19日、Yahoo!に「LGBT理解増進法が成立。「多様な性」尊重の流れを止めないためにできること」と題した記事を寄稿し、これからLGBTQ+Allyコミュニティはどうしていけばよいのか、ということについて論じました。
松岡さんは「この法律はそもそも根本的な問題があり、加えて、土壇場で修正された文言によって、もはや理解の増進ではなく「理解を制限できてしまう」ものへと変質してしまったと言わざるを得ない」として、「差別禁止規定がないため、具体的な被害を解決できない」「「多数派の安心への留意指針」が盛り込まれ、理解増進の施策が制限される可能性」があるなど、この法の問題点を整理しながら解説しています。「家庭や地域住民の協力」が明記され、学校教育が制限される可能性については、行政法が専門の日本大学大学院・鈴木秀洋教授が「学校教育法の同様の規定は、学校教育を縛るものと解釈されていない」と述べていることを挙げ、LGBT理解増進法においても学校での理解を広げる動きに介入できるものではないとの見方を示すとともに、参議院内閣委員会でも法案提出者の一人である國重徹議員(公明)が「保護者の協力を得なければ取り組みを進められないという意味ではありません」と答弁していることを確認し、不安の解消につなげています(MFAJの寺原さんも「国会での議論の過程は大事」と語っているように、こうした答弁が記録に残っていることは重要だと言えそうです)
このような懸念点を踏まえたうえで、今後、どんな対応が必要になるのか?ということについて、松岡さんはこのように述べています。
「この法律をもとに、今後、政府は「基本計画」や「指針」を作っていくことになる。その際、性の多様性に関する理解を広げたくない議員や団体が、法の適切な解釈を無視してでも「多数派の安心に留意」「家庭や地域住民の協力」といった点を口実に施策を制限しようとすることが考えられる。基本計画や指針が策定される際、その審議の中で性的マイノリティ当事者が参加し、当事者の声が反映されるか、さらには特定の声だけではなく、エビデンスやデータに基づく議論がされているか、特に自治体や学校現場の施策を萎縮させるものになっていないかを注視する必要がある。連合がすでに事務局長談話で表明している通り、労働者や使用者なども参加する公開の場で、「不安」といった観念的な議論ではなく、現場の具体的・実務的な視点からの議論が必要になるだろう。さらに、前述の「多数派の安心に留意」「家庭や地域住民の協力」といった文言を使って、直接的に自治体や学校へ理解を広げないようはたらきかけが行われる可能性も十分あり得る。これによって自治体や学校が萎縮しないよう注意しなければならない」
「大きな危機感を持つ必要はあるが、一方で希望もある。これまでは何も法律がないからこそ、学校や企業、自治体等での現場の努力で取り組みが進められてきた。時代の大きな流れを見ると、確実に社会は性の多様性を尊重する方向へと進みつつある。だからこそ、今後この法律を活用できるか次第で、さらに良い方向へと社会を進められる可能性もある。2000年代には性教育やジェンダー平等に対するバックラッシュが起き、特に学校現場は萎縮、現在でも適切な性教育が阻まれている。こうした事例に学びつつ、現状の社会の流れを止めないために、一人ひとりが行動し、それぞれの現場で取り組みを広げていくことが重要だ。さらに、性の多様性をめぐる理解を阻害しようとしてくる動きの背景に、どんな団体や組織、政治的な動きがあるのかという点を明らかにしていくことも大切だろう」
「今後も保守的な家族観や国家観を守るために、あえてトランスジェンダーを標的にしたバッシングは続くかもしれない。その際、社会に対していかにトランスジェンダーのリアルを伝えられるか。社会の知識が追いついていないのだとすれば、そこを埋められるか。不安を煽り、分断させられること自体に抗えるか。すべての女性の安全を守り、同時に性の多様性を尊重する社会の流れを止めさせないかは、LGBT理解増進法を前提に、今後も適切な取り組みを広げられるかにかかっている。自治体、企業、学校など、それぞれの現場での理解を広げ、反対の動きが起きたとしても萎縮しないよう、手を取り合っていくことが今後より一層求められる。これまで「ダイバーシティ」を掲げながら、人権や政治、制度について語ってこなかった人や企業も、良かれ悪しかれ法律ができたことを契機として、今こそ立ち上がり、繋がって欲しいと思う。LGBT理解増進法ができても、当然だが差別がすぐになくなるわけではない。今後も「差別禁止法」や「婚姻の平等(同性婚の法制化)」、そして「性別変更に関する非人道的な要件の緩和」など、性的マイノリティの命や尊厳を守るための法整備が求められることは変わらない」
INDEX
- 2026
-
2025
-
12月
- 横浜のSHIPがDV被害男性やLGBTQの一時保護所を開設へ
- Bリーグで初めてカムアウトした選手がプライドセンターを訪問
- 米国が18歳未満の性別適合医療を禁止しようとしています
- 朝日新聞にLGBTQツーリズムの記事が掲載
- ドリアン・ロロブリジーダさんが主演の新作コメディ『DURIAN DURIAN』が来年4月に上演決定
- 米ニューヨーク州の牧師が性別移行中だとカミングアウト
- 二丁目のスギ薬局にHIV郵送検査キットの自販機が
- 【追悼】同性婚実現に尽力した偉大なアライ、ロブ・ライナー
- 【同性パートナーシップ証明制度】岡山県新見市が新たに導入など、各地の動きをお伝え
- ブラジルで同性婚が顕著に増加
- 【婚姻平等訴訟】東京二次訴訟の原告が上告しました
- 都議会で東由貴都議がパンセクシュアルとカミングアウト
- チャペル・ローンが「M・A・C」のアンバサダーに就任
- シンシア・エリヴォがGG賞ノミネート、黒人女性として2回は史上初
- アンドリュー・クリスチャンが24年の歴史に幕
- アジアンクィア映画祭の上映作品が決定!
- フランスで結婚した女性カップルが家事審判を申し立てました
- ジョナサン・アンダーソンが英「ザ・ファッション・アワード」3連覇、史上初の快挙
- LGBTQのための防災ガイドのご案内
- XGのCOCONAさんのカミングアウトをKATSEYEのメンバーやJUST Bベインも応援
- XGのCOCONAさんがノンバイナリーだとカミングアウト
- 『ボーイフレンド』シーズン2の舞台は冬の北海道、10人のBoysが登場
- 「もう一つのノーベル賞」を受賞したオードリー・タン、「多様な意見が台湾社会を押し上げる」
- 【婚姻平等訴訟】各地の新聞社が同性婚否定判決を批判
- 【婚姻平等訴訟】原告らが最高裁に要請「当事者の声聞いて」「違憲判断を」
- 『エミリア・ペレス』が報知映画賞作品賞・海外部門を受賞
- 今夜の『虹クロ』は「同性カップルがどんな人生を歩んでいるのか知りたい」
- この週末、大分、和歌山、北谷などでパレードが開催されました
- 12月1日は世界エイズデー:各地でさまざまなキャンペーンが展開
-
11月
- アミューズが東京高裁判決を受けて声明を発表し、エールを送ってくれました
- カミングアウトした女性がミス・イングランドに選ばれました
- 【婚姻平等訴訟】まさかの不当判決に怒りや悲しみの声…
- ラッシュジャパンがLGBT議連に要望書と4万超の賛同を提出
- 東京レインボープライドが常設コミュニティスペースを開設
- 【追悼】映画『スワンソング』での演技も素晴らしかったゲイの俳優、ウド・キアー
- イズミ・セクシーさんはじめいろんな人たちがメディアに取り上げられています
- 【甲府アウティング市議】市議会政倫審が警告、誓約書を要求へ
- 国際男性デーに合わせ、神奈川のNPO法人SHIPが男性や性的少数者を対象にした電話相談を開設
- 11/23放送のドラマ『ぼくたちん家』第7話にkemioさんが登場
- 「PRIDE指標2025」で750社が「ゴールド」に認定されました
- 安堂ホセさんの『迷彩色の男』がフランス発の国際ゲイ小説賞を受賞
- 【特例法非婚要件】一審に続き高裁も「合憲」との判断
- ドラマ『ぼくたちん家』11/16放送回にドリアンさんやUsakさんが出演
- 【婚姻平等訴訟】議員会館で「私たちだって“いいふうふ”になりたい展」が開催
- 中国当局がアップルにゲイアプリ削除を指示、取締り強化の懸念
- aktaの調査でバニラ派のほうがセックスの満足度が高いことが明らかに
- 米連邦最高裁が同性婚を認めた2015年の判決を維持
- ロックの殿堂入りを果たしたシンディ・ローパーがレインボーフラッグをバックに『True Colors』を熱唱
- 【特例法外観要件】東京高裁が高裁として初の違憲判断を示しました
- Aktaがアジア太平洋地域のHIV/LGBTQの「HERO Award」を受賞
- ピンクドット沖縄が初の北谷町開催へ
- 上智大の「ソフィアンズコンテスト」でクアラルンプール・とき子さんが優勝、ドラァグクイーンとして史上初
- 史上初!ゲイの俳優ジョナサン・ベイリーがピープル誌の「最もセクシーな男性」に選ばれました
- ニューヨーク市長に選ばれたマムダニ氏はLGBTQサポーター
- 渋谷区と世田谷区で同性パートナーシップ証明制度がスタートして10年が経ちました
- この三連休、初開催の高松ほか各地でプライドパレードが開催されました
-
10月
- 多様なLGBTQの人たちがメディアでフィーチャーされています
- 渋谷区と世田谷区が同性パートナーシップ証明制度導入10周年記念企画を実施
- 特例法の生殖不能要件は違憲だとの最高裁判断から2年が経ちましたが、法改正は実現していません
- 台北のパレードに15万人が参加
- 来年の「Tokyo Pride」プライドフェスティバルは6月6日・7日開催
- 韓国の国勢調査で「同性配偶者」との登録が認められました
- 【追悼】人間的にも不思議な魅力を放っていた映像作家、大木裕之さん
- プーケットでアジア初のInterPride世界会議が開催決定
- 13年の時を経てアジアンクィア映画祭が復活!
- 富山初のプライドパレード開催を目指す話し合いが行なわれました
- 広島、大阪、鹿児島、津でプライドパレードが開催されました
- 米国のLGBTQ成人の96%がカミングアウトしていることが明らかに
- 【甲府アウティング市議】市議会政倫審が政治倫理基準に抵触と判断
- 【那覇市議差別発言】市議長が「議会での発言は慎重に」と異例の声明
- オープンリー・ゲイの小原明大長岡京市議が6期目の当選を果たしました
- 金沢プライドウィーク2025が始まりました
- 同性パートナーも事実婚相当だと認める法令が33に拡大するも、120の法令は除外
-
9月
- 昨年の新規HIV感染(確定値)は994名
- 【特例法外観要件】札幌家裁が外観要件を「違憲で無効」であると判断
- 9/22(月)20時から「ハートネットTV」放送、「LGBTQ+とメディア」がテーマ
- 「The Wedding Banquet」のユン・ヨジョン、「同性愛者は異性愛者と平等」
- 世界陸上にオープンリー・ゲイのニコ・ヤング選手が出場中
- 【追悼】日本の行政機関の長として初めてパレード会場に来て感動的なスピーチを行なった前札幌市長の上田文雄さん
- AiSOTOPE LOUNGEの周年パーティに降臨したキョンキョンの「神ライブ」がニュースに
- 国勢調査で同性カップルも同居家族として回答できるようになりました
- エムポックスのクレード1bの国内初感染が報告、感染拡大の兆候は無し
- 性的マイノリティの3人に1人が医療サービスの利用に困難を感じた経験があることが明らかに
- 今年のエミー賞のLGBTQの受賞者は?
- 通算25回目となる札幌のパレードに約900人が参加、市役所にレインボーフラッグも
- トランスジェンダーは「“伝染”する」「“治療”できる」と述べた那覇市議に抗議の声
- 日テレで10月から放送のゲイドラマ『ぼくたちん家』にゲイのインクルーシブPが参加
- 性の多様性を否定する那覇市議が当事者の児童生徒数を議会で質問…アウティングの懸念や抗議の声
- 香港議会が同性パートナー法案を否決、最高裁判決に逆らって…
- WHOがエムポックスの緊急事態宣言を終了
- 「夫」の文字が二重線で消され…「家族として認めてほしい」と大村市のカップル
- MTVアワードのステージでサブリナ・カーペンターがトランスジェンダーの権利を訴えました
- 根室市議選で保坂いづみさんが三選を果たしました
- 米連邦控訴裁が、自認性に基づくパスポートの発給を停止した政権の措置を認めない判決を下しました
- 【追悼】モード界の帝王であり、世界で最も成功したバイセクシュアル男性でもあるジョルジオ・アルマーニ
- 「パートナーシップ宣誓制度」スタートから10周年を記念し、世田谷区役所が窓口にレインボーフラッグを掲出
- クロエ・グレース・モレッツが同性婚
-
8月
- 8/29、ゲイの弁護士の南和行さんとお母さんが「超越ハピネス」に出演
- 韓国の元軍人モデルが“同性結婚”を発表
- ぷれいす東京がボランティアを募集中
- 【同性パートナーシップ証明制度】宮城県気仙沼市が来年度に導入へ
- 【住民票続柄】東京都品川区が10月から対応
- 映画『となりのとらんす少女ちゃん』にはるな愛さんが出演!
- 9月のAiSOTOPE LOUNGEの周年にキョンキョンが出演!
- ジュリア・フォックスがパンセクシュアルであることをカミングアウト
- ボディビルの大会で優勝したゲイの方がニュースに!
- 船橋市の図書館でLGBTQ関連本を特集、中高生がセレクト
- 【追悼】『プリシラ』でバーナデットを演じたテレンス・スタンプ
- 鹿児島で初のプライドパレードが開催
- 堀ちえみさん、山根康広さん、光永亮太さん…今年のレインボーフェスタ!の出演者がアツい!!
- 米国務省の人権報告書が4分の1に、LGBTQの記述がほぼ消滅
- 『ダンシング・クィア』で芥川也寸志サントリー作曲賞を受賞した向井航さんの新作『クィーン』が上演
- 【同性パートナーシップ証明制度】奈良市など全国28の自治体が新たに全国ネットワークに加入
- アウティングを行なった甲府市の村松市議に対し、市議会が政倫審を開きました
- エイズ予防指針改正案で、HIV陽性者の診療や介護拒否は偏見・差別に当たると明記されることになりました
- 上野で浴衣祭りが開催されます
- 北海道弁護士会連合会が決議、一刻も早く同性婚の法整備に着手するよう求め
- SRHRを知っていますか?
- 全国の不動産関連事業者を対象とした初の調査が実施、LGBTQに関する課題が浮き彫りに
- 英国初の女性・レズビアンの大主教が誕生しました
- スペインサッカー界初のオープンリー・ゲイの選手が同性婚
- 東京都が夏の梅毒集中啓発を実施します
-
7月
- フィリピン人トランス女性が難民認定を求めています
- 『ババヤガの夜』が米国のLGBTQ文学賞の最終候補に
- LGBTQ支援宣言から10年が経った那覇市
- 天道清貴さんがデビュー25周年を記念して御殿場でフェスを開催
- 新潟で活躍するシンガーソングライターの岡村翼さんがパレードのテーマ曲の制作を機にカミングアウト
- ロシア下院、LGBTQなど“過激派”に関する情報の検索に罰金科す法案を可決
- 米五輪委がトランス女子選手の女子競技への参加を禁止へ。一方、IOCは…
- 香港のトランス男性が公衆トイレ法をめぐる訴訟で勝訴
- 【ご協力のお願い】LGBTQインクルーシブな医療に向けた「PRISM調査」
- 映画『ブルーボーイ事件』の公開は11月14日
- バレー米男子主将がカミングアウトについて語りました
- サマブラがいよいよ今週末開催! aktaが今年もアンケートを実施
- 【参院選】ジェンダー平等や同性婚に関する記事いろいろ
- 米国防長官が第7艦隊司令官の人事案を撤回したのは、過去にドラァグショーを容認していたせい?
- トランス男性の奏太さんと聞こえないお母さんが『超越ハピネス』に出演
- 【追悼】長年日本のダンスミュージックシーンをリードしてきたDJ SHINKAWAさん
- レズビアン作家・王谷晶さんの『ババヤガの夜』が英ダガー賞翻訳部門を受賞
- 香港議会に同性パートナー法案が提出されました
- 小田切ヒロさんが自身のジェンダーについてカミングアウト
- LUSHが「結婚の自由をすべての人に」キャンペーン展開中
- 資生堂が「自分らしさを彩るメイクアップガイド」を公開し、実際に教えるメイク講座も開催
- 八戸、小樽、真鶴でプライドパレードが開催されました
- 世界各地でバックラッシュが強まるなか「PRIDE」パレードが開催されました
-
6月
- 同性パートナーの移転費不支給の取消しを求め、大村市のカップルが提訴
- 【同性パートナーシップ証明制度】制度導入自治体は530、人口カバー率は92.5%
- 今週末は八戸、小樽、真鶴でプライドパレードが開催
- 日本は世界で最もトランスジェンダーに冷たい国になりました
- Yahoo!がトランスジェンダーインクルーシブな大阪のジムを紹介
- 【同性パートナーシップ証明制度】長崎県が来年度に導入へ
- 【ArcH】が7月4日にオープン! パンフもぜひご覧ください
- セレブたちがトランスジェンダー支援の「Protect the Dolls」Tシャツを着用して話題に
- 米最高裁、テネシー州の性別適合医療禁止を支持
- 米FDAが、半年に1度の注射で済むPrEP薬を承認しました
- 【プライド月間】「レインボーカラーの意味」を示した動画が感動を呼んでいます
- 【プライド月間】ドラマ『モダン・ファミリー』リリー役の俳優がカミングアウト
- 【プライド月間】各地の大学の取組み
- 【プライド月間】トランプ大統領が来場したレミゼ公演にドラァグが抗議の参戦
- タイの1〜5月の同性婚登録数は婚姻全体の11%超
- 今週末はソウル、鶴岡、伊東でパレードが開催
- 母国で性別変更したトランス女性が住民票の性別表記の変更を認められず起こしていた裁判で、東京地裁が請求を棄却
- おめでとうダレン・クリス! 今年のトニー賞のクィア的名場面
- レディ・ガガの4年ぶりの来日公演が決定、自身初となるドームツアー全5公演
- 【プライド月間】各地の自治体がさまざまな取組みを見せています
- リゾがLAのプライドで「私たちが存在するために闘わなくていい日がいつか来るように」とスピーチ
- 「広海・深海」の深海さんがアメリカ人男性と婚約
- KATSEYEのララに続き、メーガンもカミングアウト
- 「Tokyo Pride 2025」が開催され、過去最高の約273,000人が来場
- ワシントンDCのワールドプライドで数十万人がパレード、トランプ政権への抗議も
- 芥川賞作家の李琴峰さんがアウティングを受けたとして甲府市議を提訴
- HIV陽性者のQOLの向上に役立てるためのアンケート調査を実施中
- アリアナ・グランデらがLGBTQ+ユースの自殺防止への取組みの存続を求める公開書簡に署名
- Tokyo Pride 2025に「チーム台湾」参加へ
- パワハラ防止法が改正へ、カミングアウトの禁止・強制なども該当
- バンコク、盛岡、神戸でプライドパレードが開催されました
-
5月
- スポーツ団体への調査:LGBTQに関する相談窓口を設置しているのは2割
- カンヌで多彩なクィア映画が上映されました
- 仙台で同性婚家事審判を申し立てている小浜さんのパートナーが倒れ、脳に障害が…「早く動いてください」
- 『Forbes JAPAN』が選ぶ「50歳以上の女性50人」に村木真紀さん
- 【訃報】ゲイビデオ・スターであり俳優、ミュージシャンとしても活躍したコルトン・フォード
- 【婚姻平等訴訟】東京二次訴訟が結審、判決は11月28日
- 「結婚の平等にYES!」が25地域に拡大、LUSHが7月にキャンペーン実施
- ユーロビジョンでクィア・アーティストのJJが優勝
- 5月17日、仏プロサッカーリーグの今季最終戦で選手がレインボーのバッジを着用
- 5月17日、秋田、名古屋、大阪でプライドパレードが開催されました
- 俳優のリーヴ・シュレイバーがトランスジェンダーの娘について語りました
- 東海林毅監督が『となりのとらんす少女ちゃん』を実写映画化
- 特定生殖補助医療法案の修正を求める会が記者会見、「同性カップルが安全な医療にアクセスする道が閉ざされてしまう」
- ろうLGBTQ+の方たちの声を届ける本『ろうLGBTQ+の世界〜15人が語るライフストーリー』へのご支援を
- 『べらぼう』第18回で描かれた壮絶な性の物語
- 女子ボクシングのレジェンド・藤岡奈穂子さんが米国で同性婚、都内でウェディングパーティも開催
- フライングタイガーがレインボーグッズのキャンペーン、売上の一部を東京レインボープライドに寄付
- 今晩放送の『ドキュランドへようこそ』はピンク・トライアングルの歴史に迫るドキュメンタリー
- 新教皇レオ14世はLGBTQにとってどんな人?
- Tokyo Pride 2025のステージ出演者が発表されました
- Appleが「プライドコレクション2025」を発表、一つひとつ色や形が異なる個性豊かなデザインです
- 今夜の『虹クロ』に與真司郎さんが登場
- パリ五輪開会式のトマ・ジョリー監督を脅した7人に有罪判決
- 憲法記念日に最高裁長官や有識者が同性婚についてコメントした記事が掲載
- ブラジルのレディ・ガガ公演でLGBTQを狙ったテロが計画されていたものの、未然に容疑者が逮捕
- NHK名古屋放送局が今年もNRPに合わせてキャンペーンを実施
- チャーリーxcx、オリー・アレクサンダー、リナ・サワヤマらがトランスコミュニティへの連帯を表明
- 【訃報】同性愛をテーマにした楽曲で初めてビルボードのトップ20入りを果たしたジル・ソビュール
- ロバート・デ・ニーロがカムアウトした娘へのサポートを表明
- 移転費不支給についての審査請求を棄却された長崎のカップル、異性カップルと同等の扱いを求めて提訴へ
-
4月
- 【訃報】『ドラァグ・レース フィリピン』で審査員も務めたジグリー・カリエンテ
- 八方不美人初のフルアルバム『さんすくみ』がリリース決定!
- 札幌・沖縄限定、3300円でPrEPを始めてみようキャンペーン
- ドリアンさんが4/29、ドラマ『人事の人見』にゲスト出演
- 「JUST B」のベインがカミングアウト「LGBTQコミュニティの一員であることを誇りに」
- 【婚姻平等訴訟】3万筆に迫る署名と法制化を求める要請書が提出され、記者会見も開かれました
- クリステン・スチュワートが同性婚
- 初めて同性カップルの祝福を承認したフランシスコ教皇が逝去
- 韓国のアカデミー賞女優、長男のNYでの同性結婚式に参加していたと公表
- 米連邦地裁がトランプ政権のパスポート政策は違憲だと裁定
- 同性婚に関する最新意識調査(アンケート)実施中
- 英最高裁の判決に英国のトランスコミュニティはどう反応したか
- 「子どもの前でLGBTの話はするな」などと叱責され退職した学童支援員に辰野町教育長が陳謝
- 4/18のEテレ『超越ハピネス』にドリアンさん&KILAさんが登場
- 與真司郎さんが『AERA』の表紙を飾りました
- カナダのトランス男性歌手、ビザが下りず米国でのツアーを断念
- 【同性パートナーシップ証明制度】北海道石狩市が導入、紋別市も今年度中に導入へ
- トランスジェンダーの河上リサさんが島本町議に当選
- 『ボーイフレンド』DaiShunが5/27、初のフォトエッセイを発表
- 万博開会式に関西のドラァグクイーンが登場!!
- LUSH(ラッシュ)が3種のバスボムの商品名を「ダイバーシティ」「エクイティ」「インクルージョン」に変更
- 婚姻平等の実現を目指すTokyo Prideの特別フロートに参加できるカップルを募集中
- 同性カップルが特定生殖補助医療法案の修正を要望「私たちを排除しないで」
- 與真司郎さんが同性婚への願いを語りました
- 三重県伊賀市が同性カップルに事実婚と同じ続柄記載を認める「住民票」を交付
- 5回目の金沢プライドパレードは10/5、能登各地で映画上映会も開催
- 【婚姻平等訴訟】関西原告が「早急な立法」に向けて最高裁判断を求めて上告
- 同性婚賛同企業が600社を突破、トヨタ紡織、村田機械、ダイセルなどが新たに賛同
- ロシアのカサキナ選手がカミングアウト後、豪州に国籍変更
- GLAADメディア賞でのシンシア・エリヴォのスピーチが話題に
- ひろしまプライドパレードが10/11に初開催
- 国際トランスジェンダー認知の日にマドンナが祝福コメント、NYでは抗議デモ
- 【同性パートナーシップ証明制度】北海道富良野5市町村・登別市・江差町・幕別町、千葉県鎌ケ谷市、福岡県中間市・行橋市などでスタート
- レインボー・リール東京、6/21〜6/22と7/12〜7/13に開催決定!
- ノンバイナリーの方の申立てを京都家裁が却下、高裁に抗告へ
-
3月
- 【追悼】『将軍 SHOGUN』に主演し、70近くなってカムアウトしたリチャード・チェンバレン
- 山形県米沢市で初のレインボーパレードが行なわれました
- 昨年の新規HIV感染が3年ぶりに1000人を超えました
- 【同性パートナーシップ証明制度】沖縄県で今日から制度がスタート
- 多くの教科書で家族のあり方や性の多様性に関する記述が充実
- 【追悼】「一人パレード」を行なったキャンディ・ミルキィさん
- 「KATSEYE」のララがカミングアウト
- イズミ・セクシーさんが映画に出演! 60年代の実話に基づくトランスジェンダー映画『ブルーボーイ事件』
- 【婚姻平等訴訟】一審を覆し大阪高裁でも違憲判決、5高裁で違憲判断が揃いました
- 【婚姻平等訴訟】愛知訴訟の原告が上告、次は3/25の大阪高裁です
- ハンガリーでプライドパレード禁止法が可決され、抗議としてレインボーカラーの発煙筒が焚かれました
- 【特例法非婚要件】性別変更のために離婚を余儀なくされるのは違憲ではないと京都家裁
- 【同性パートナーシップ証明制度】北海道登別市・江差町、宮城県石巻市、東京都江東区、和歌山県白浜町・紀の川市が制度導入へ
- 米下院で公聴会の議長がトランス女性の議員を男性扱いして批判されました
- ドーチーが米Billboard「ウーマン・オブ・ザ・イヤー」を受賞へ
- 【婚姻平等訴訟】名古屋高裁判決「法律婚制度を利用できないのは違憲」
- 同性ペアの雛人形を扱う人形店がニュースに
- 與真司郎さんが4/16、カミングアウトについて綴ったフォトエッセイを発表
- 【婚姻平等訴訟】7日に名古屋高裁で判決、違憲判決の積み上げに期待
- 3/4の「虹クロ」は当事者の子を持つ親が語り、メンターが涙する、感動的な回です
- 特定生殖補助医療法案の同性カップル排除について問題提起する連載記事が朝日新聞に掲載
- ペドロ・パスカルがトランスジェンダー支援のメッセージを投稿
- シンシア・エリヴォとアリアナ・グランデの歌で幕を開けたアカデミー賞授賞式
- 【同性パートナーシップ証明制度】大阪府豊中市が導入、北海道美唄市は来年度からの導入を検討
- 東京マラソンにノンバイナリーのランナーが初参加
- 3月1日はエイズ差別ゼロの日、国連合同エイズ計画がコミュニティとの連帯を表明
- レディ・ガガ「Stupid Love」MV出演のIGさんが同性婚
-
2月
- 米LGBTQクルーズ船がメキシコ湾で難民を救出
- 米「大統領の日」に大規模なデモ、トランスジェンダー迫害はますます厳しく…
- サム・アルトマンが子どもを授かりました
- 「Tokyo Pride 2025」公式サイトがオープン
- Appleが株主総会でDEI廃止案を否決、多様性重視の姿勢を堅持
- ベルリン国際映画祭の金熊賞はノルウェーの同性愛映画
- トランプ米政権の援助凍結によって630万人が亡くなり、薬剤耐性のHIVが増加するおそれも…
- ハンター・シェイファーがパスポートのジェンダー表記が男性に変更されたとしてトランプ政権を非難
- 5/25、山梨レインボープライドが初開催
- 海外で日本人と同性婚した方が「定住者」資格を求めた上告が退けられました
- 『FLEE フリー』が地上波初放送、23日深夜にEテレで
- 米国成人の9.3%が性的マイノリティであると自認していることが判明
- 『ウィキッド ふたりの魔女』ジャパンプレミアでkemioさんがキュートにアリアナをエスコート
- イスラム教指導者として初めてカムアウトしたムシン・ヘンドリクス氏の殺害に追悼の声
- 日本の企業は米国のDEI政策の後退に影響されず、前進を続けるべきだとする記事が続々
- 【同性パートナーシップ証明制度】北海道厚岸町と千葉県鎌ケ谷市が4月から導入へ、その他全国の動きをお伝え
- ベルリン国際映画祭が開幕、ティルダ・スウィントンに名誉金熊賞
- NPO法人エルポート代表で婚姻平等訴訟の当事者でもある中谷衣里さんが「女性リーダー支援基金」を受賞
- ストーンウォール国定史跡のサイトから「T」と「Q」が削除され、抗議デモが行なわれました
- 北海道北見市が道内初の人権条例制定へ
- 毎日映画コンクールが俳優賞の男女区別を撤廃、カルーセル麻紀さんが助演俳優賞を初受賞
- 裁判傍聴に際しレインボーソックスを禁じたのは違法だと訴える裁判が始まりました
- 東大阪の小学生が性の多様性ポスター展を開催
- クリティクス・チョイス・アワードでゲイの俳優が感動的な受賞スピーチを行ないました
- いろんなゲイの方がメディアでフィーチャーされています
- 渋谷区が同性パートナーシップ証明制度を発表してから今日で10年
- 婚姻平等訴訟が6周年、二丁目でもイベントが開催
- 「つくたべ」全話無料公開、2/21まで
- 同性愛を理由に家族に殺されかけた北アフリカ男性が再び難民認定
- 世界初の同性ペアのアイスダンスがスイスで行なわれました
- トランス女子選手の女子競技参加を禁じるトランプ大統領令にJOC杉山文野理事が懸念を表明
- 千葉県市川市がLGBTQを含め婚前カップルに住居費用を補助する制度を設立へ
- NYでトランプ氏の反トランスジェンダー政策への抗議デモ
- 無罪が確定した浅沼さんが会見、「やっと声が出せるようになった」
- 【同性パートナーシップ証明制度】「カラフルドットライフ」が愛媛県に制度導入を要望
- 【グラミー賞】ガガがトランスジェンダーの権利についてパワフルにスピーチ
- 米大統領令で危ぶまれていた途上国のHIV陽性者への支援が継続されることに
- 同性カップルのための式場マップを製作した静大生が静岡市SDGs連携アワード大賞を受賞
- ウィリー・チャバリアがパリ・ファッションウィークで反LGBTQ法案への抵抗を表明
- 【同性パートナーシップ証明制度】栗原市、我孫子市で今日から制度スタート
-
1月
- マドンナが「決して闘いをあきらめてはいけない!」と投稿
- 【婚姻平等訴訟】東京二次訴訟控訴審で原告の方が「一日も早く配偶者に」と訴えました
- ビル・コンドン版『蜘蛛女のキス』がワールドプレミア上映、観客はスタオベ
- 「ピーウィー・ハーマン」ことポール・ルーベンスが死後のドキュメンタリーでカミングアウト
- 【同性パートナーシップ証明制度】岩手県八幡平市が今月から導入、京都府舞鶴市が4月から導入へ
- 『94歳のゲイ』が追悼上映、26日に監督とボーン・クロイドさんが登壇
- 『エミリア・ぺレス』のカルラ・ソフィア・ガスコンがアカデミー賞にノミネート、トランスジェンダーとして初
- Eテレで25日に特別番組「マイ・クローゼット」が放送されます
- トランスジェンダー団体「Tネット」が米大統領令に抗議
- タイで婚姻平等法が施行、初日は2792組が結婚
- 聖公会主教が礼拝でトランプ大統領に直接語りかけ、慈悲を求めました
- アリアナ・グランデがLGBTQにエール「何が起ころうとも、私たちは互いを守り合う」
- 事実婚カップルには認められる移転費の支給が認められず、大村市の同性カップルが審査請求へ
- 札幌弁護士会が同性婚法制化への着手を求める何度目かの声明を発出
- 政府が24の法令について同性パートナーも対象になりうると発表
- IBMの川田篤さんが「WOMEN AWARD 2024」個人部門《インクルージョン賞》を受賞
- バンコクの婚姻平等セレモニーの様子をNHKがレポート
- シカゴ・ブルズがプライドナイトを開催、ハウス40周年を称えるハーフタイムショーも
- レディ・ガガ、3年代で複数曲の首位を記録した史上3人目のアーティストに
- 台北の路上生活者をドラァグクイーンが支援
- 2月1日、ムンバイでプライドパレードが開催
- タイ政府がLGBTQカップルのために首相府中庭を開放、23日には首相らが登壇する結婚セレモニーも
- 暴行罪に問われたTransgenderJapan元共同代表に無罪判決
- 英国のゲイ・バイカーズ・モーターサイクル・クラブのことがニュースに
- オープンリー・ゲイの起業家ティム・ギルが大統領自由勲章を受章
- 祝!安堂ホセさんが芥川賞を受賞
- 『ボーイフレンド』のダイさんがドラマに初出演、明日22時放送の『日本一の最低男』(フジテレビ)
- 2024年の新規感染報告件数:HIVは昨年より微増、梅毒は昨年より微減
- ロンドンでドラァグコン開催、ルポールがヴィヴィアンを讃える場面も
- 穴水町の成人式にドリアン・ロロブリジータさんが登場
- 【同性パートナーシップ証明制度】松山市が2月3日から、奥州市が4月から制度導入へ
- 「今年行くべき都市」に大阪が選出、IGLTA総会やプライドセンター大阪も決め手に
- ゴールデングローブ賞でトランスジェンダー映画『エミリア・ペレス』が作品賞を受賞
- リヒテンシュタインで同性婚が法制化、世界で38番目
- タイで1月23日から同性婚登録が可能に。タクシン元首相も同性結婚式に出席するかも?
- クロエ・グレース・モレッツが婚約を発表
- タレントの一ノ瀬文香さんがパートナーシップ宣誓を報告
- インフルエンサーのKanさんが来日の機内でマドンナに遭遇
-
12月
-
2024
-
12月
- 紅白で『虎に翼』特別編の放送が決定
- いろんなゲイの方たちがメディアでフィーチャーされています
- 【同性パートナーシップ証明制度】沖縄県が3月末までに導入、松阪市は1月から
- 同性婚賛同企業が580社を超えました
- 【婚姻平等訴訟】九州訴訟の原告が上告、「法制化の兆しすらない」
- TRPが6月にクィア・アート展を開催
- Eテレの「虹クロ」に『ボーイフレンド』の“ダイシュン”が出演!
- テニスのジョアン・ルーカス・レイス・ダ・シウヴァ選手がカミングアウト
- エルトン、結婚10周年おめでとう!
- かずえちゃんが参院選に立候補へ
- 【住民票続柄】東京都の10区が連名で厚労省と総務省に要望書を提出
- 『ボーイフレンド』出演のKazutoさんの写真集が発売、記念イベントも
- Appleが選ぶ「2024年のベストアプリ」にHIV/エイズへの偏見をなくすゲームが選ばれまし
- 毎日映画コンクールで『94歳のゲイ』がノミネートされました
- タレントのロイさんがカミングアウト
- 同性婚法制化が「日本全体の幸福度にプラスとなる」と首相が答弁、川田龍平議員の質問に
- 【婚姻平等訴訟】高裁での3連続違憲判決を受けてメディアはどう報じているか
- 「ボーイフレンド」シーズン2制作決定
- NHK BSでカンボジアのクィアのドキュメンタリーが放送
- スイスのアイスショーで世界初の同性ペアのショーが実現
- 【住民票続柄】東京の約10区の区長が連名で政府に提言へ
- 【婚姻平等訴訟】愛知訴訟二審が結審、来年3月7日に判決
- 【婚姻平等訴訟】福岡高裁「憲法13条・14条1項・24条2項に違反」 13条違反との判断は初
- 【婚姻平等訴訟】九州訴訟二審判決言い渡しを前日に控えた原告の方たちの思い
- ゴールデングローブ賞にノミネートされたクィア関連作品一覧
- 【同性パートナーシップ証明制度】仙台市で制度スタート、初日は3組が宣誓
- 『オッペンハイマー』出演のエマ・デュモンがカミングアウト
- 那覇市で12回を数えるピンクドット沖縄が開催、国際通りでパレードも
- 中野区が同性パートナーにも災害弔慰金の支給や区立校校医等の遺族補償を実施へ
- 【同性パートナーシップ証明制度】岩手県花巻市が東北で初めての条例制定へ、青森県弘前市はファミリーシップ制度へ拡充
- LGBTQの児童生徒から相談を受けた養護教諭の半数近くが、本人の承諾を得ずに校内で情報を共有
- 賃貸契約の同意書に「LGBTの方は家主への相談が必要になる」の文字…沖縄の不動産会社
- 史上初! トランスジェンダーのアレックス・コンサーニがモデル・オブ・ザ・イヤーを受賞
- 【同性パートナーシップ証明制度】仙台は10日から、長崎・時津町も導入
- 【住民票続柄】三重県伊賀市が来年1月頃に対応へ
- エルトン・ジョンが視力を失い、自身が音楽を手がけた『プラダを着た悪魔』の舞台を見れず…
- タイで同性婚がスタートする来年1月22日、およそ280組のカップルが結婚
- 【同性パートナーシップ証明制度】仙台で来週、京都府与謝野町でクリスマスにスタート
- 高知でプライドパレードが初開催されました
- ノンバイナリーの方が戸籍の「長女」を「第1子」に変更すべく家裁に申立てへ
-
11月
- TRPがリニューアル、来年は「Tokyo Pride 2025」として6月に開催
- 【住民票続柄】事実婚と同じ表記の対応をした11自治体の半数でシステムエラーとなることが明らかに
- R&Bアーティストのカリードがカミングアウト
- 12/1、ながさきレインボープライドが初開催
- 俳優のケリー・マリー・トランがカミングアウト
- マレーシア政府が押収したレインボーカラーの腕時計が返還へ
- 香港最高裁が、海外で同性婚したカップルに相続などの権利を認めました
- 大分市で県内初のレインボーパレードが開催されました
- メイプルソープの映画で男性器の写真修正を求めた映倫を映画配給元が提訴
- 【同性パートナーシップ証明制度】東京都江東区で制度創設にストップがかかっています
- 氷川きよし(KIINA.)さんが、紅組/白組の枠を超えた特別企画で紅白出演
- LGBT支援団体をX上で中傷していた投稿者に賠償命令
- 小説家51名と映画監督97名がLGBTQ+差別に反対する声明を発表
- トランス男性の臼井さんの姿を追った山陽放送のドキュメンタリーが日本医学ジャーナリスト協会賞優秀賞に
- 【追悼】LGBT法連合会監事・金沢レインボープライド理事の岩本健良さん
- 「PRIDE指標2024」の認定企業・団体が過去最多の計966となりました
- グラミー賞で過去最多のクィア・アーティストがノミネート
- 【追悼】映画『94歳のゲイ』の長谷忠さん
- レインボーカラーのソックスでの裁判傍聴を止められた方が裁判所を訴えました
- 【婚姻平等訴訟】関西訴訟控訴審が結審、判決は来年3月25日
- タイではトランスジェンダーの受刑者にも配慮がなされているようです
- 経産省が最高裁判決から1年以上経ってようやくトイレ利用制限を撤廃しました
- 日本百貨店協会が同性婚推進団体とコラボし、「いいふうふの日」キャンペーンを展開
- 来秋、高松と広島でプライドパレードが開催
- トム・デイリーがニット作品をオークション、収益はMarriage For All Japanに寄付
- 【婚姻平等訴訟】東京一次訴訟の原告が上告しました
- 米国史上初のトランスジェンダーの連邦議会議員が誕生しました
- “編み物王子”トム・デイリーの世界初の展覧会が渋谷パルコで開催
- クロエ・グレース・モレッツがカミングアウト
- 上越、福岡、山形でパレードが開催されました
- ラガンジャ・エストランジャがアイソに降臨、Crystal Kayも出演!
- 警報級の大雨で九州レインボープライド1日目が中止に
- 【婚姻平等訴訟】全国の新聞社、国会で直ちに議論を始めるべきだとする社説を続々と掲載
-
10月
- 【同性パートナーシップ証明制度】全国19の府県と150の市町村が加入する自治体間連携ネットワークが11月スタート
- アミューズが東京高裁の違憲判決を受けて異例の声明を発表
- 【婚姻平等訴訟】東京高裁でも違憲判決、札幌に続き高裁で2例目
- 尾辻かな子さん国会に返り咲き、衆議院議員に再び当選
- 大阪で10回記念のレインボーフェスタ!が開催、過去最多の64000人が来場し、3700人がパレード
- 台北で第22回台湾同志遊行が開催され、18万人が参加しました
- IGLTA総会で小泉伸太郎さんと村木真紀さんがアワードを受賞
- 【同性パートナーシップ証明制度】仙台市が年内に導入へ、導入ゼロ都道府県がようやくゼロに
- 投票所での氏名の読上げをやめる自治体が増加
- 「PRIDE VISION」が全国7割超の選挙区で使えるように
- 4回目となる金沢プライドパレードが開催され、約450人が市内を行進しました
- LGBT法連合会が政党・候補者アンケートの結果を公表中
- 【追悼】ファッション評論家でタレントのピーコさん
- パリの老舗ドラァグ・キャバレー「マダム・アルチュール」がEXとアイソにやって来る!
- 金沢プライドウィークがスタート、金沢駅コンコース内のビジョンがレインボーに
- シンディ・ローパーの最後の来日公演が発表
- 今晩Eテレで放送:「“クィア”な人生の再出発 ボリウッド式カミングアウト」
- 韓国で同性婚訴訟がスタート、憲法裁にも審判請求予定
- トランス男性のサッカーチームがスペインサッカー連盟に加盟、欧州初
- 日本初のLGBTQ+センターパネル展が大阪の中之島図書館で開催
- 同性カップルの出産を罰則までつけて排除する差別的な法案が通りそうです
- 東京23区の職員互助組合が同性パートナーも家族として扱う運用を3年前に始めていました
- 台湾籍と中国籍の同性カップルが初めて婚姻届を受理されました
- マドンナが弟のクリストファーを追悼、「彼は今もどこかで踊っている」
- 福島、前橋、岡山でプライドパレードが開催されました
- 米TIME誌「次世代の100人」、台湾のバイセクシュアルの国会議員を選出
- 九州朝日放送が10/21〜10/27に「レインボーウィーク」開催、テレビやラジオでLGBTQをフィーチャー
- 【同性パートナーシップ証明制度】鹿屋市や津山市で制度がスタート、橿原市でも導入へ
- 【住民票続柄】犬山市で第1号カップルが手続き、大村市長が修正しない方針を表明
- 賃貸物件の紹介資料に「LGBT不可」の文字…不動産会社が修正対応へ
- 『ピッチ・パーフェクト』のレベル・ウィルソンが同性婚
- TPRの杉山文野さんが共同代表を退き、新体制に
- 11月23日、大分市で初のプライドパレード開催へ
-
9月
- 京大病院が同性パートナー間の生体腎移植を実施したことを発表
- 酒田市と和歌山市でプライドパレードが開催されました
- 台北市がLGBTQテーマのバスツアーを実施、ドラァグクイーンがバスガイド
- 【婚姻平等訴訟】東京二次訴訟の控訴審が始まりました
- 【署名のお願い】PrEPを安価に、安心して利用できるように!
- トランス男性の俳優・若林佑真さんが戸籍性の変更を認められました
- タイで正式に婚姻平等法案が成立、アジアで3番目の同性婚承認国へ
- 9月23日はバイセクシュアル可視化の日
- 台湾の方と中国本土の同性パートナーとの婚姻が認められました
- 【住民票続柄】世田谷区と中野区が11月から交付へ
- バイデン政権下で歴代最多となる12人目のLGBTQの判事が誕生
- エミー賞でグレッグ・バーランティが理事会賞を受賞
- 子育てをしている(していた)性的マイノリティが242人に上ることが明らかに
- さっぽろレインボープライドに1000人が参加、初めて市役所にレインボーフラッグも
- Z世代のクィア・アイコン、チャペル・ローンがMTVアワードで最優秀新人賞を受賞
- 【同性パートナーシップ証明制度】北海道石狩市、鹿児島県鹿屋市が制度導入へ
- 【住民票続柄】愛知県犬山市も事実婚と同様の表記を承認、神奈川県三浦市でも検討中
- 金沢プライドパレード2024にSHELLYさんが初参加
- 都内の梅毒感染者数が2400人超、過去最多だった昨年に迫る勢い
- パラリンピック男子走り幅跳び4位入賞のディミトリ・パヴァデ選手がカミングアウト
- パリパラリンピックに44名のOUTアスリートが出場し、19のメダルを獲得しました
- アルモドバル監督作がヴェネツィア金獅子賞に
- 独協医大埼玉医療センターに全国初の「ジェンダー外来」が開設
- もともと結婚していたトランスジェンダーの夫婦が、同時に性別変更することを認められました
- 【同性パートナーシップ証明制度】福島県、新潟県、滋賀県、山口県などで制度がスタート
- 9/5のNHK「BSスペシャル」は台湾の同性カップルなどをフィーチャーします
- 『ボーイフレンド』のボーイズたちが東京ファッションウィークに登場
- 昨年(確定値)と今年の第1・第2四半期の新規HIV感染者数が発表
- AiSOTOPE LOUNGEの周年パーティにアン ミカさんが出演!
- 【婚姻平等訴訟】九州訴訟の二審が結審、12月13日に判決言い渡しへ
- 大阪のレインボーフェスタ!に愛内里菜さん、はるな愛さん、花*花さんらが出演
-
8月
- 【同性パートナーシップ証明制度】福島県が9月2日から導入へ
- パラリンピック開会式にクィアのシンガーが出演
- 【住民票続柄】逗子市と葉山町も9月から交付
- 【エムポックス】主な感染経路は接触感染、WHOが見解を明らかに
- ツルバダのPrEP薬としての使用が承認されました
- 仙台弁護士会があらためて婚姻平等の実現を求める声明を発表
- 福岡県古賀市が同性婚の法制化を国に要望
- パリパラリンピックに出場するOUTアスリートは少なくとも32名
- オランダのジェンダークリニックを訪れる若者に密着した番組が今夜放送
- オーストラリアの水族館のペンギンの同性カップルのうちの1羽が天寿を全う
- サム・スミスが宇多田ヒカルとコラボ、「Stay With Me」新バージョンがリリース
- 【エムポックス】どうやらクレード1bも性的接触によって感染するようです
- 【同性パートナーシップ証明制度】宮崎県国富町でスタート、新潟県も9月から導入
- 台北高裁、性別変更に診断書を要求するのは違憲と判断
- 『虎に翼』に中村中さんや水越とものりさんらが当事者役として出演
- 『虎に翼』神回…「爺さんになって人生を振り返った時、俺は心から幸せだったと言いたいんだ」
- 松山市のトランス女性市議のドキュメンタリーが今夜BSで放送
- 【エムポックス】重症化しやすいタイプの変異株の流行について
- 「Outsports」創設者のジム・ブジンスキ「4年後のロサンゼルス五輪が史上最も“gay”な大会になる」
- いろんなLGBTQの方たちがメディアにフィーチャーされています
- 『虎に翼』に同性カップルが登場、おそらく朝ドラ史上初
- 【パリ五輪】誹謗中傷を受けたイーマーン・へリーフ選手が告訴
- トム・デイリー選手が引退を表明
- 【パリ五輪】史上最多となる195名のOUTアスリートが参加し、計42個のメダルを獲得
- 半年に1回注射するだけのPrEP薬ができそうです
- パリがバンコクプライドにLGBTQIA+権利賞を授与
- プラウド香川の藤田博美さんが草の根で活動する女性リーダーを讃える賞に入賞
- 【追悼】1999年にカムアウトした元メジャーリーグ選手、ビリー・ビーン
- ニンフィア・ウインドがやって来る! 10月東阪で開催の「OPULENCE」
- Netflix『ボーイフレンド』のダイがシュンと同じ事務所へ
- 【パリ五輪】ヌガンバ選手が難民選手団に初のメダルをもたらしました
- 【パリ五輪】バッシングを受ける女子ボクシング選手をIOCが毅然と擁護
- 【パリ五輪】開会式を演出した芸術監督への殺害予告に対し、検察が捜査を開始
- 【同性パートナーシップ証明制度】京都府木津川市でスタート、滋賀県は9月から
- 【住民票続柄】栃木市でも事実婚と同様の記載が認められました
- 来年の国勢調査で配偶者としての集計を求める集会が開催
-
7月
- 【パリ五輪】台湾が「文化オリンピアード」で同性愛演劇を上演
- 【パリ五輪】トム・デイリーが銀メダル、レインボーカラーのタオルを使う場面も
- 【パリ五輪】トム・デイリーが英国選手団の旗手を務めました
- 【パリ五輪】開会式にレディ・ガガやドラァグクイーンが登場しました
- 最新の調査でZ世代の44%が「完全にストレートというわけではない」と回答
- 【特例法外観要件】特例法の早期改正を求める社説、続々
- 【米大統領選2024】民主党の副大統領候補としてゲイのブティジェッジ氏が有力視
- ゆるキャラのちぃたん☆がトランスジェンダーのアライであることを宣言
- 元F1ドライバーのラルフ・シューマッハがカミングアウト
- 画期的! 韓国最高裁が同性パートナーの健康保険の被扶養者の登録を認めました
- Netflix「ボーイフレンド」が海外TOP10入り
- 【パリ五輪】少なくとも199名のOUTアスリートが出場へ
- 今年の世界エイズデーキャンペーンのテーマはU=U
- 【パリ五輪】開会式、閉会式のショーの演出はゲイの芸術監督
- なぜ離婚しなければならないのか――特例法非婚要件は違憲だと申し立てられました
- SHISHAMOの吉川美冴貴さんがパートナーシップ宣誓「いつか、結婚できる日が来たら」
- 【仙台市同性婚家事審判】太白区長が却下求める意見書を提出、原告「とても冷たいものを感じてがっかり」
- ラグビー日本代表戦会場でLGBTQ啓発
- 性同一性障害特例法の非婚要件は違憲だとして当事者が京都家裁に申立てへ
- 【特例法外観要件】広島高裁差戻し審判決を当事者や有識者はどう受け止めたか
- 東京都が24時間予約可能なHIV等検査予約サイトを開設
- 広島高裁が特例法の外観要件を「違憲の疑いがある」とし、申立人の性別変更を認めました
- 【住民票続柄】総務省の曖昧な回答に対して大村市長「われわれの問いに明確に答えていない」
- 世界26ヵ国のなかで日本は同性婚への反対が最も少ないことがわかりました
- 【パリ五輪】ノンバイナリーの選手がパリ五輪陸上女子1500m米代表に
- 性的マイノリティ男性をトイレ個室におびき出して現金を脅し取った男女4人が恐喝容疑で逮捕
- 【同性パートナーシップ証明制度】福島市でスタート、人口カバー率85%超え
- 同性愛を理由に家族に殺されかけた北アフリカ男性が難民認定されました
- 【住民票続柄】大村市の手続きが「慎重さ欠く」との決議案が出されるも賛同得られず撤回
- 同性婚に賛同する企業が500社を超えました
- 今年もNYやサンフランシスコでパレードが開催されました
- 栃木県鹿沼市、神奈川県横須賀市、香川県三豊市で住民票続柄「夫または妻(未届)」の記載がスタート
- 7月7日は都知事選、LGBTQ支援の候補者は?
- 山口、旭川、小樽、青森、真鶴でパレードが開催されました
-
6月
- 福祉現場でのSOGIハラは虐待に該当しうると政府が答弁
- 性別変更要件の見直しに向けて与党が議論
- バイデン大統領が同性愛で有罪とされた退役軍人への恩赦を発表
- 【プライド月間】メディアの取組みをご紹介
- 【同性パートナーシップ証明制度】福島県が今秋導入へ
- 85歳の米退役軍人が死亡告知記事でカミングアウト
- 【プライド月間】大学の様々な取組み
- 日本性別不合学会理事長が最高裁判決についてコメント、同様の事例があることも明らかに
- 最高裁が性別変更後に生まれた子との親子関係を認めました
- 【プライド月間】渋谷モディで「SHIBUYA MODI RAINBOW DAYS」が開催
- タイ上院が圧倒的多数で婚姻平等法案を採択、タイは年内に同性婚承認国へ
- ジョナサン・グロフらがトニー賞初受賞
- 群馬と高知でパレードが初開催されます
- 名古屋レインボープライド、過去最高の約55,000人が参加して大成功
- 那覇市が性の多様性条例を制定へ、沖縄県内で3例目
- 【同性パートナーシップ証明制度】北海道北広島市、埼玉県川口市、新潟県新発田市、奈良県桜井市、岡山県津山市も制度導入へ
- 【住民票続柄】メディアや有識者はどう見たのでしょうか
- 立憲民主党が性同一性障害特例法改正案を衆院に提出
- シンガー・ソングライターのマレン・モリスがカミングアウト
- 【住民票続柄】東京都世田谷区も「夫・妻(未届)」と記載へ
- 【プライド月間】企業の様々な取組みをご紹介します
- 『虎に翼』同性愛放送回後、脚本の吉田さんが「私は、透明化されている人たちを描き続けたい」とコメント
- NHK「国際報道 2024」がタイの同性婚法制化を特集
- 超党派LGBT議連が事実婚の諸規定を同性カップルに適用するよう申入れへ
- 【住民票続柄】東京都杉並区も前向きに検討
- 【プライド月間】マドンナがLGBTQコミュニティを讃える動画を投稿「プライドを隠さないで!」
- 【プライド月間】各地の自治体が市庁舎などをライトアップ
- 【プライド月間】テイラー・スウィフトとアデルがコンサートでプライドを祝福
- 【プライド月間】NHK名古屋が特番を放送、名古屋レインボープライドにも参加
- ソウルとバンコクでプライドパレードが開催されました
- 【プライド月間】Googleで「LGBTQ」と検索してみましょう
- 【プライド月間】企業の様々な取組みをご紹介します(2)
-
5月
- 栃木県鹿沼市が後に続き、7月から「夫(未届)」「妻(未届)」記載を開始
- 厚労省、雇用保険法上の就労移転費の支給について単身分の費用しか認めず
- 英国政府のニック・ハーバートLGBTQ+権利特使が同性婚について「法整備を進めたらいいですよ」
- 長崎県大村市の園田市長が会見「裁量の範囲内でできる限りの対応をした」
- HIV感染の受刑者が治療中断でエイズを発症、大阪弁護士会が適切な情報の引き継ぎを大阪府警に要望
- カンヌでトランスジェンダーの方が初の女優賞を受賞
- 長崎県大村市が男性カップルに続柄「夫(未届)」と記載した住民票を交付
- 先週末は盛岡、名古屋、大阪、神戸でレインボーイベントが開催されました
- 小泉司法相が同性婚を認めれば「幸せの量は間違いなく増える」と答弁
- 【同性パートナーシップ証明制度】福島市が7月1日から制度導入、大分県が制度導入記念イベントを開催
- 追悼:マツケンサンバII」の振付で国民的人気を博した真島茂樹さん
- 函館市に常設のコミュニティセンター「はこにじ」がオープン
- 『ウィキッド』エルファバ役のシンシア・エリヴォがスピーチ「私が演じることになったのは必然
- ソウルのパレードが今年も受難…広場や施設の利用が相次いで不許可に
- LGBTQの仕事と暮らしに関するアンケートが実施中
- バンコクで6月1日にパレードが開催されます
- 日本人の女性カップルがカナダで難民認定されました
- 「結婚の平等にYES!」に新たに埼玉・愛媛・山口・宮崎が加わり14地域に
- ニンフィア・ウインドが台湾総統府でパフォーマンス
- PSB最新アルバムのリリースパーティが二丁目AiiRO CAFEで開催!!
- 【同性パートナーシップ証明制度】福島県南相馬市が13日から「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を導入
- 5月17日は「多様な性にYESの日」です
- ユーロビジョンでスイスのネモがノンバイナリーの歌手として初めて優勝
- 埼玉県の大野知事、同性カップルの権利保障の早急な議論と対応を国に要望
- 今年の宮崎レインボーパレードは5/11から毎月第2土曜開催
- 名古屋家裁が「婚姻に準じる関係」だとして同性パートナーの名字変更を承認
- BIKE150周年を祝い、タイムズスクエアでブロードウェイ俳優がケツワレ姿を披露
- 今年のAppleのプライドエディションはパーソナライズ可能な蛍光色のデザイン
- 香港のトランス男性活動家に晴れて新しい身分証が交付されました
- 第2回ひろしまレインボーパレードが行なわれました
- 日弁連会長に就任した渕上玲子さんが抱負語る「男女共同参画やLGBTQへの理解促進を中心に」
- 最高裁の戸倉三郎長官、LGBTQ関連の訴訟について裁判官に「広い視野」「知見」を要求
- 東京高裁、同性カップルの内縁関係認めず財産分与申立てを却下
-
4月
- ソフィア・ブッシュがクィアであることをカミングアウト
- 【婚姻平等訴訟】東京一次訴訟控訴審が結審、原告「何万人もの命の問題と捉えてほしい」
- 『94歳のゲイ』の長谷さんがパレードに参加しました
- 『ル・ポールのドラァグ・レース』で台湾人のニンフィアが優勝、蔡英文総統も祝福
- TRP2024、過去最高規模で成功
- NHKラジオが初めてTRPを生中継!
- TRP1日目が強風のため中止に。明日以降は開催予定
- 女性初の機動隊員にもなった元警察官の女性が退職&カムアウトし、新たな人生を始めました
- 今年の金沢プライドウイークは10/18〜10/21に開催、復興支援イベントも
- 最高裁が性別変更後に生まれた子の認知を認めなかった高裁判決を覆す可能性が出てきました
- 『94歳のゲイ』長谷忠さんがTRPに参加
- Amazonが今日からレインボーカラーの梱包テープを展開、TRPにも協賛
- 【同性パートナーシップ証明制度】埼玉県の川口市を除く全62市町村が連携協定
- ファミマがレインボーカラーのショートソックスをリリース、4/16から
- マドンナがフロリダでの公演で「パルスの悲劇」の被害者や遺族を招待し、感動的なスピーチを行ないました
- 警察庁が死亡した被害者と同性であることを理由に給付金を不支給としない旨の通知を各都道府県警に発出
- 【同性パートナーシップ証明制度】災害時の安否確認や、犯罪被害者見舞金の支給を保障する動き
- タイ上院第一読会で婚姻平等法案が採択
- 【同性パートナーシップ証明制度】大分県、徳島県、山口県、兵庫県、愛知県などで一斉にスタート
-
3月
- ゲイの牧師・平良愛香さんがEテレ「こころの時代〜宗教・人生〜」に出演
- 犯罪被害者給付金訴訟最高裁判決を受けて新聞社説「法整備を急げ」
- 札幌弁護士会が直ちに同性婚法整備に着手することを要望、大阪市議会も意見書可決
- 【同性パートナーシップ証明制度】大分県、愛知県犬山市・東浦町、福井県大野市が4月から導入、福島県も導入を表明
- 【婚姻平等訴訟】札幌の原告が上告「最高裁でも違憲判決を勝ち取り、国会にプレッシャーを」
- タイ下院で婚姻平等法案が採択されました
- 昨年の新規HIV感染は960名、前年より微増
- 熊本のこうぞうさん&ゆうたさんがNNNドキュメントに登場!
- アイルランドのバラッカー首相、辞意を表明
- レディ・ガガが誹謗中傷にあったトランス女性に激励のメッセージ
- TRP2024に大黒摩季さんやちゃんみなさんが出演
- 林夏生さんを偲ぶ会が開催されます
- 【同性パートナーシップ証明制度】愛知県が4月から「ファミリーシップ宣誓制度」を導入
- 国会は早く同性婚の法制化を、と訴える新聞社説が続々
- カヴァッロ選手がパートナーにプロポーズ、本拠地のピッチで
- GID学会が改名へ、国際的に「性同一性障害」が使われなくなったため
- 石川大我議員の質問に総理が「トランスジェンダーへの誤解に基づく誹謗中傷は許されない」と答弁
- 【婚姻平等訴訟】各地の原告の喜びの声や有識者コメントが報道
- 【婚姻平等訴訟】札幌高裁は違憲と判断、憲法24条1項での違憲判断は初
- 【婚姻平等訴訟】東京二次訴訟一審で違憲判断、これで違憲判断は5件目
- エルトン・ジョンAIDS基金が過去最高の16億円の寄付を集めました
- 與真司郎さんが新曲「FUN FOREVER」MV公開&ツアーを発表
- 【婚姻平等訴訟】いよいよ明日、札幌と東京でW判決
- トランス女性の受刑者に丸刈りを強制するのは人権侵害だと大阪弁護士会が勧告
- 『哀れなるものたち』やビリー・アイリッシュがオスカー獲得
- pecoさんがryuchellさんとのことも綴ったエッセイを発表
- 俳優の坂口涼太郎さんが同性婚実現にエール
- シドニーのマルディグラに日本の2団体が出場
- 日本アカデミー賞で映画『怪物』が3つの俳優賞を受賞
- 遺族給付金をめぐって最高裁で弁論、26日の判決で一・二審が覆る可能性
- 【同性パートナーシップ証明制度】奈良県と北海道北広島市が制度導入へ
-
2月
- ツルバダのPrEP利用の承認申請が行なわれました
- 『THE LAST OF US』の俳優がヘイターにお見舞いした言葉が話題に
- ドリアンさんとKILAさん、ご結婚おめでとうございます!
- 性別変更が認められた臼井さんが戸籍謄本を受け取り、喜びを語りました
- 【同性パートナーシップ証明制度】沖縄県、滋賀県が導入へ、山口県は9月から
- 日テレの『世界を変えた20人のアーティスト』に美輪様が生出演しました
- 【婚姻平等訴訟】福岡高裁で「歴史をよい方向に変える判決を」と訴え
- 日テレが今週末、多様性をテーマにした『カラフルウィークエンド』を実施
- 【同性パートナーシップ証明制度】福島県南相馬市、新潟県村上市、兵庫県洲本市、南あわじ市が導入へ
- 明石市がLGBTQ+/SOGIE施策担当者を募集中
- トランス女性の矢神サラさんがモデルオーディションで優勝し、LAファッション・ウィークに出演
- 米国のゲーマーの17%がLGBTQ
- ギリシャ国会が同性婚法を承認しました
- タイの婚姻平等法改正プロセスは70%完了、コミュニティが年内施行を要望
- 【婚姻平等訴訟】訴訟開始から5年の節目を迎え、様々なアクションが行なわれました
- 毎日映画コンクール表彰式で鈴木亮平さん「我々異性愛者に認められている権利は当たり前ではない」
- 同性婚を認めないのは違憲、仙台の男性カップルが家事審判を申し立てました
- 杉並区議の選挙公報でのトランス差別に人権侵犯の申立て
- 徳島のゲイカップルが結婚式を挙げました
- 24年前の新木場殺人事件についてまとめたサイトが復活
- 英『VOGUE』エドワード・エニンフル引退号のためにセレブ40人が集結
- 東大が作成したSOGIに関するガイドラインが話題に
- 日弁連初の女性会長となる渕上玲子氏は同性婚実現サポーター
- 仙台市が婚姻届を受理せず、同性カップルが家裁に申立てへ
- 岡山県の臼井さんが法的性別変更を認められました
- 仙台の小浜さんが婚姻届を提出、不受理の場合は違憲だとして家事審判申し立てへ
- グラミー賞主要4部門のうち3部門をクィア女性が占めました
- 仙台の同性カップルが市への「婚姻届」受理命令を求めて家事審判申し立てへ
- 【同性パートナーシップ証明制度】和歌山県などでスタート、人口カバー率8割超え
-
1月
- IVANさんが、性的マイノリティかもしれない子の母親からの相談に回答
- 全米フィギュア女子シングルでアンバー・グレン選手が優勝、LGBTQとして初
- 毎日新聞、婚姻平等の実現は「日本が真に人権を守る国になれるかどうかの試金石」
- ギリシャで2月にも同性婚が法制化される見込みです
- ウィル・フェレルがトランス女性の友人と旅するドキュメンタリーにサンダンスで異例のスタオベ
- 【同性パートナーシップ証明制度】山口県が導入へ、和歌山県は来月から
- アカデミー賞にノミネートされたLGBTQ関連作品は?
- 経産省トランス職員裁判の論説を読んで考えを変えた島根の高校生が、新聞コンクールで表彰
- aktaの岩橋さんが今年の日本エイズ学会学術集会・総会の会長に
- LAのゲイバーでJLoを演じたクイーンの目の前にご本人が登場!
- 【追悼】LGBT法連合会代表理事の林夏生さん
- 毎日映画コンクールで主演・助演男優賞を『エゴイスト』の鈴木亮平さん&宮沢氷魚さんがW受賞
- 明治が多様な価値観・キモチを表現した「マーブル」チョコの限定パッケージを発表
- 【同性パートナーシップ証明制度】旭川市、山形県、淡路市で初のパートナーシップ宣誓
- 同性パートナーも犯罪被害者給付制度の対象かについて最高裁が判断へ
- 今年のエミー賞のクィア的名場面
- エルトン・ジョンがEGOTを達成
- ルポールがエミー賞授賞式で「ドラァグクイーンの声を聞きなさい」
- OpenAIのサム・アルトマンCEOが同性婚
- 【訃報】Jリーグでもプレーし、引退後にカミングアウトしたスティーブン・レイバットさん
- 台湾総統選で蔡英文氏の後継者である頼清徳氏が勝利、台湾初のLGBTQ国会議員も誕生
- 関テレの「元警察官と元消防士のゲイカップル」特集がアジアテレビ賞の最優秀賞に
- 東京都が男子のHPVワクチン接種費用を補助する方針を示しました
- 『きのう何食べた? season2』、2023年秋ドラマ満足度No.1に
- LGBTQユースのためのセーフスペースがメタバース上に開設
- トランスジェンダーの弁護士を脅迫した男に実刑判決
- 【同性パートナーシップ証明制度】高知県大月町で制度スタート、岩手県大船渡市と紫波町が4月から導入へ
- 元高校球児のトランス女子レスラーが手術前の壮行試合で初勝利
- フランス初のオープンリー・ゲイの首相が誕生
- 今年のゴールデングローブ賞を受賞したLGBTQは?
- 広島弁護士会が、トランス女性の受刑者に丸刈りを強要した刑務支所の対応は人権侵害だと勧告
- 金沢レインボープライドから震災に関するお知らせがありました
- 【同性パートナーシップ証明制度】小樽市、滝川市、山形県、伊達市、市原市、福井市でスタート、徳島県は4月から
- タイ国会が婚姻平等法案を一次審議で採択
- 松中権さんが能登震災の被災者への企業からの支援を受け付ける事務局を設立
- 被災したLGBTQの方のための電話相談が立ち上げられました
- 紅白でクイーン+アダム・ランバートが熱演、MISIAさんのステージにはドラァグクイーンも
-
12月
-
2023
-
12月
- 芥川賞ノミネートの5作品のうち2作がクィアを主人公とした小説
- 日刊スポーツ映画大賞で『エゴイスト』の鈴木亮平さんと宮沢氷魚さんがW受賞
- 【同性パートナーシップ証明制度】旭川市・上川7町が1/16、山形県が1/4、上越市が2月、泉佐野市が1/1に制度導入
- 民放連が「人権に関する基本姿勢」を公表、LGBTQ差別が禁止に
- 【同性パートナーシップ証明制度】岩手県久慈市、陸前高田市、宮城県栗原市も導入へ、神戸市は12/25から
- 精神・発達障害を持つLGBTQが安心して利用できる就労移行支援センターが大阪にも開設
- トランスジェンダーの弁護士を脅迫した男に懲役1年6ヵ月が求刑
- 千葉県で「多様性尊重条例」が成立
- タイ政府、婚姻平等法案を21日に国会提出へ
- 宮崎県延岡市で12/24、今年最後のプライドが開催
- ローマ教皇、司祭が同性カップルを祝福することを承認
- 韓国の男の子たちの恋愛リアリティ番組がテレビ大阪で地上波初放送
- 特例法要件裁判の先人である岡山県の臼井さんが再び申立へ
- 来年のTRPは4月19日(金)〜21日(日)の3日間
- エムポックスで埼玉県の30代男性が亡くなりました
- ネパールで同性婚登録が受理、アジアで2例目の同性婚承認国に
- 【同性パートナーシップ証明制度】岡山県早島町、石川県かほく市、山梨県甲斐市などで制度スタート
- 露最高裁が“国際的なLGBT市民運動”を過激派組織と断定し、警察がゲイクラブを強制捜査
- アフリカから逃れてきた男性が難民認定を求めています
- 違憲判断を勝ち取った鈴木げんさんが、性別表記が変更された住民票を受け取りました
- トランスジェンダー差別助長につながる書籍の刊行が中止に
- トランス男性が「ミスターオブザイヤー」でグランプリに
- 【同性パートナーシップ証明制度】山形県、市原市、松山市が導入へ
- 今晩の『超多様性トークショー!なれそめ』は、パートナーの性別移行を支えたという感動的なお話です
- ビリー・アイリッシュがカミングアウト
- 【婚姻平等訴訟】東京二次訴訟が結審、原告8人が思いを熱く語りました
- 12月1日の世界エイズデーに、二丁目の看板がリニューアル
- 『ゼクシィ』誌が同性カップルや事実婚カップルを起用した広告を渋谷に設置
-
11月
- 紅白にクイーン+アダム・ランバートが出場!
- 「Business for Marriage Equality」賛同企業が450社超え
- 【同性パートナーシップ証明制度】北海道、仙台市、松山市などの動きをご紹介
- LGBT法連合会がGID特例法手術要件の速やかな撤廃を求めました
- 『エゴイスト』の鈴木亮平さんがTAMA映画賞・最優秀男優賞を受賞
- フレディ・マーキュリーの新たなドキュメンタリーが来年2月公開
- タイ政府が婚姻平等法案を承認、12月議会で審議入り
- LGBTQ1万人超への調査で「SNSでの差別的な発言によるダメージ」などの問題が浮き彫りに
- トランスジェンダー支援の動き、さまざま
- 島根県知事の「主観での性別変更は悪用される恐れがある」発言に対し、当事者団体や女性団体が撤回を要請
- 蔓延するトランスヘイトについて法務大臣「誤解に基づく差別・差別的な発言はあってはならない」
- 神奈川県が同性パートナーを持つ職員に扶養手当を支給、来年度から
- 徳島、長岡、那智勝浦でレインボーイベントが開催されました
- 「work with Pride 2023」にAAAの與真司郎さんが出演、企業経営者アライネットワークの設立も
- 渋谷区の制度開始から8年、利用者の約6割が安心感を感じる一方、半数が世間の理解不足を経験
- 三原市長、LGBT批判投稿の市議に対し「説明責任を果たすべき」
- ゲイゲームズ香港が無事に開幕しました
- MISIAさんがドラァグクイーンと一緒に「御堂筋ランウェイ2023」に登場しました!
- 「定住者」の在留資格を求めた日米同性カップルの控訴審で、東京高裁は原告の訴えを棄却
- 【同性パートナーシップ証明制度】東京都の制度スタートから1年、宣誓したカップルは951組
- 来年3月、松山で愛媛県初のプライドが開催!
-
10月
- 【婚姻平等訴訟】北海道訴訟の控訴審が結審、判決は来年3月
- 奈良・台北・山形でプライドパレードが開催されました
- NHKで11月もLGBTQ関連の番組が放送されます
- 【同性パートナーシップ証明制度】大分県と滋賀県長浜市が来年4月から導入
- 【特例法要件最高裁憲法判断】多くの新聞社が社説で速やかな法改正を訴えています
- 【婚姻平等訴訟】名古屋高裁で控訴審が始まり、原告が婚姻平等の実現を訴えました
- 「偏った指導で同性愛に誘導」発言の台東区議が議会で謝罪、一部発言撤回も
- 【特例法要件最高裁憲法判断】TransgenderJapanとLGBT法連合会が声明を発表
- 【特例法要件最高裁憲法判断】申立人の方や、4年前の裁判の臼井さんなどのコメント
- 【特例法要件最高裁憲法判断】注目の判決文の要旨
- 【特例法要件最高裁憲法判断】最高裁大法廷が不妊手術の規定を違憲と判断
- 新潟、鯖江、岡山でパレードが開催されました
- アウティング禁止条例を持つ自治体は26、3年で5倍に
- 厚労省が製薬会社にPrEP薬を開発要請
- 電通「LGBTQ+調査2023」の結果が発表、LGBTQの割合は9.7%
- 福井県鯖江市でパレードが初開催されます
- トランス男性のボクサー・真道ゴー選手が初の準公式試合へ
- 手術要件の撤廃についての最高裁判断は今月25日
- インド最高裁、同性婚を認めず
- 【同性パートナーシップ証明制度】福井県が11月、神戸市が12月下旬に導入
- 性別変更が認められた鈴木げんさんが会見、「声を上げることでたくさんの仲間ができ、社会は変わる」
- 性別適合手術を受けなくても戸籍の性別を変更できるよう求めたトランス男性の訴えが認められました
- NHKが今月、LGBTQの番組を集中放送
- 米シアトルのLGBTQクラブを狙った放火事件の犯人に実刑判決
- フランスで同性婚したカップル、家事審判申立てへ
- 仲岡しゅん弁護士を脅迫したと見られる男性が逮捕されました
- 大阪・三重・金沢でプライドパレードが開催されました
- ミス・ポルトガルに史上初のトランス女性が選ばれました
- 台東区議が謝罪・撤回へ、しかし今度は横浜市議のトンデモ発言が…
- トランスジェンダーの方たちが最高裁に出向き、手術要件の撤廃を求めました
- 黒人でオープンリー・レズビアンのラフォンザ・バトラー氏、米連邦上院議員へ
- 米CDCがクラミジア・淋病・梅毒の曝露後予防薬を推奨
- 【同性パートナーシップ証明制度】鳥取・島根両県、岩手県宮古市、和歌山県新宮市で運用開始
- 「偏った教材で同性愛に誘導」発言の区議、謝罪・撤回を求められるも発言拒否
-
9月
- 【婚姻平等訴訟】東京二次の口頭弁論で原告がLGBTQへの理解増進には婚姻平等が不可欠と訴え
- 法的性別変更の手術要件の撤廃を求める申立について、最高裁大法廷で審理が行なわれました
- TOMO KOIZUMIによる「絵画ドレス」がパリで展示
- 初代の正統続編『おっさんずラブ-リターンズ-』が放送決定、林遣都さん(牧)もカムバック
- NFLで初めて現役でカムアウトした選手、カール・ナッシブが引退へ
- 台東区議が小学校の性教育について「偏った指導あれば同性愛に誘導」などと発言し、批判の声が上がっています
- HIV検査結果を1年間知らされずエイズを発症した元受刑者が国を訴えた裁判で、原告が実質的に勝訴
- タイのBLドラマで恋人役を演じた2人が実際に恋愛関係に発展し、婚約を発表
- TIME誌「次世代の100人」に13名のLGBTQが選ばれました
- 9/21のABC『newsおかえり』で高砂市の制度を実現した方の密着番組が放映
- 男性に特化した性被害のホットラインが開設されます
- 【同性パートナーシップ証明制度】仙台市、滋賀県が来年度中に導入へ
- 北海道のきみちゃん&ちかさんがお子さんを授かりました
- 【同性パートナーシップ証明制度】福島県伊達市が来年1月に、鳥取県が県として初めてファミリーシップ制度を導入
- さっぽろレインボープライドが開催され、約900人がパレードしました
- インドで270万人登録の日本人YouTuberがカミングアウト
- LGBT議連で当事者団体などへのいやがらせの実態が報告されました
- 9/22、オナンさん追悼イベントが開催
- 今年のMTVアワードで活躍したクィア・アーティスト
- ハノイプライドに清貴さんが出演
- 【同性パートナーシップ証明制度】山梨県や板橋区が11月から導入、山口市が来年4月に導入へ
- 性別やジェンダーにかかわらず利用できるウエディングブランドが誕生
- アンドラ公国の首相がカミングアウト
- さっぽろレインボープライドが今週末開催
- 【朗報】大阪に新たなゲイサウナができそうです
- 山形県酒田市で庄内レインボーマーチが初開催されました
- 同性パートナー扶養認定訴訟で、札幌地裁が原告側の訴えを退けました
- 【同性パートナーシップ証明制度】北海道幕別町、福井県敦賀市・小浜市、広島県府中市、香川県が導入へ
- ラグビーW杯でフランスのLGBTQチームの創設者に栄誉
- Netflixの実写版「ONE PIECE」でコビー役を演じたトランス俳優が話題に
- 10/9の金沢プライドパレードにアンミカさんが参加
- 東西のゲイクラブがシルバーウィークに豪華周年パーティを開催
- ガガ様がラスベガス公演の初日、トランスジェンダーのために「Born This Way」を熱唱
- 香港最高裁が、同性カップルの権利を保障する法的枠組を政府に要請
- 今年のピンクドット沖縄は12月10日、テンブス館前広場で開催
- ホテルニューオータニ大阪でドラァグクイーン出演の『Water Queen Night』開催
- 島根県で「私たちだって”いいふうふ”になりたい展」が開催されました
- 千葉県が多様性尊重条例の骨子案を公表、パブリックコメント実施中
- 【追悼】夢のようなショーの数々で人々を魅了してきたドラァグクイーン、オナン・スペルマーメイドさん
- 【同性パートナーシップ証明制度】岐阜県、大分市でスタート、関市でも第1号カップル誕生
-
8月
- 【同性パートナーシップ証明制度】和歌山県が今年度中、福島市が来年度に導入へ
- HIV/エイズ関連6団体が流行終結に向けた要望書を国に提出
- 今年のレインボーフェスタ!に酒井法子さんが出演!
- ウガンダで20歳の男性が「重度の同性愛」で訴追、死刑の可能性も…
- 同性婚法制化に賛同する企業が400社を超えました
- フロリダ銃乱射事件やBallroomカルチャーをテーマにした「ダンシング・クィア」が芥川作曲賞を受賞
- 【同性パートナーシップ証明制度】岐阜県が9月1日から、大村市は10月11日から導入
- 台湾で結婚登録したお二人に蔡英文総統から祝電が送られました
- トランスジェンダー支援の取組みを紹介する記事、続々
- 全国家庭動向調査で既婚女性の4人に3人が「同性婚認めるべき」
- 愛知県に住む台湾と日本のゲイカップルが台湾で婚姻登録
- 交通事故で同性パートナーを亡くした方が遺族として法廷に立つことが許されず…
- レインボーフラッグを守った店主がヘイターに撃たれて亡くなるという悲劇に、地元コミュニティが追悼のメッセージ
- 昨年の新規HIV感染は884人で過去最少、PrEPの効果か
- 【サッカー女子W杯】選手たちが様々な方法でレインボーカラーをピッチに持ち込み、LGBTQを支援
- カナダに渡ったゲイの方たちのことが朝日新聞に掲載
- 【同性パートナーシップ証明制度】愛知県が都道府県初の「ファミリーシップ制度」導入へ
- 8/18、Eテレ『超多様性トークショー!なれそめ』に関西の同性カップルが出演
- スピーチコンテストで同性愛者の方が優勝
- 『エゴイスト』鈴木亮平さんのNYアジアン映画祭でのコメントが素晴らしかったです
- マレーシアでレインボーカラーの腕時計をすると3年以下の禁錮刑に…
- LGBT理解増進法を受けて省庁横断型の連絡会議が発足
- 山形県酒田市の高校生が『パレードへようこそ』を上映、レインボーマーチ開催に向けて
- 盛岡市の加藤市議が引退を表明しました
- コメディアンで俳優のウェイン・ブレイディがパンセクシュアルであることをカミングアウト
- 【同性パートナーシップ証明制度】愛知県、鳥取県が制度導入へ
- SNSでトランス女性弁護士への中傷を繰り返していた女性に慰謝料80万円の支払いを命じる判決
- 松本市の夏祭り「松本ぼんぼん」にLGBTQ連が初めて参加
- LGBTQ+コミュニティセンター協議会が設立、8日夜にオンラインイベント開催
- 吉本坂46のマサルコさんが同性パートナーとの「結婚」を発表
- 梅毒患者が昨年を上回るペースで増加中、都が検査体制拡充へ
- 国連人権理事会の視察団が日本のLGBTQの人権侵害リスクを指摘
- ビヨンセが、自身の曲で踊っていた際に刺殺されたダンサーを追悼
- 平良愛香牧師監修の『LGBTとキリスト教』がキリスト教書店大賞2023を受賞
- 【同性パートナーシップ証明制度】長野県、愛知県瀬戸市で制度スタート
-
7月
- リゾがフジロックで「Everybody's Gay」を歌い、LGBTQにエール
- 【追悼】恐れ知らずのアライだったシネイド・オコナー
- リナ・サワヤマさんも與真司郎さんにエール、「あなたの勇気に感謝」
- 【サッカー女子W杯】史上初、ノンバイナリーの選手が出場
- 超党派LGBT議連、政府が策定する基本計画や指針に当事者の声を反映させたいとの考えで一致
- 会社でアウティング被害に遭った方に初の労災認定、緊急連絡先として同性パートナーの名前を伝えた方
- 【同性パートナーシップ証明制度】福井県と福井市が秋頃導入へ、その他愛知県や兵庫県などの動き
- 茨城県知事が県庁内のトイレ環境の整備を表明、経産省トランス女性職員訴訟最高裁判決を受けて
- 【サッカー女子W杯】カムアウトした選手が過去最多の94名に
- 【追悼】ドラマ『腐女子、うっかりゲイに告る。』の原作者でもある作家の浅原ナオトさん
- 愛知・大村知事、事実婚のカップルにも婚姻に準じた法的保護を与える制度の新設を国に要請する意向
- 【同性パートナーシップ証明制度】千葉県の6市が連携協定
- 【追悼】様々な既成観念を覆した映画『ジュ・テーム・モワ・ノン・プリュ』でゲイのような役柄を演じたジェーン・バーキン
- ピンクドット沖縄がryuchellさんへの追悼声明を発表
- 日本エイズ学会が海外の安全なエムポックスワクチンの国内承認を提言
- 【追悼】TRPに5年連続で出演し、LGBTQコミュニティに多大な貢献をしてくれたタレントのryuchellさん
- 経産省トランス女性職員訴訟の最高裁判決を受けて、当事者団体が声明を発表
- トランス女性の経産省職員が逆転勝訴、最高裁が職場のトイレ使用制限は不当だと判断
- ラトビアでオープンリー・ゲイの大統領が誕生
- インドで最高裁が同性婚について審理中、年内に判決
- トランスジェンダーへの性感染症検査推進と感染予防啓発の取組みが「セクシュアル・ヘルス次世代基金」を受賞
- タイで下院第一党の党首が首相に選出されれば、同性婚が実現しそうです
- 今年の金沢プライドウイークの概要が発表されました
- LGBTQ差別発言の荒井元首相秘書官が経産幹部に復帰、差別容認だと批判続出
- ネパールで同性カップルが婚姻登録できるようになりました
- 著名人250人超がネット上に氾濫するトランスヘイトを食い止めるようSNS経営者に要望
- ジェイ・Zの母が同性パートナーと結婚しました
- 東京都現代美術館が「ドラァグクイーン・ストーリー・アワー」を毅然と擁護
- 自らドラァグしてアンチの攻撃に対抗したストックホルム副市長に拍手!
- 【同性パートナーシップ証明制度】神奈川県全33市町村でコンプリート、山梨県、淡路市、庄原市、佐伯市でも導入へ
- ロンドンのパレードに『ハートストッパー』のキャストが登場!
- ソウルクィアパレードに3万5000人が参加、アンチのいやがらせにも負けず
-
6月
- 公衆浴場では「身体的特徴で男女区別を」と厚労省があらためて周知
- 日弁連があらためて国に同性婚の法制化を求めました
- 【プライド月間】虹色ダイバーシティへのチャリティとなるグローバルDJイベント開催中
- 同性カップルも婚姻相当と承認する自治体が7割超に!
- 経済同友会新浪代表が「多様性ある、公正で、包摂的な社会の実現」目指す宣言への600人分の賛同署名を首相に提出
- 【プライド月間】ニューヨークでドラァグマーチが開催されました
- 【プライド月間】世界各地でパレードが開催、バンコクではマルディグラのような華やかなパレードも
- 【プライド月間】小樽、青森、真鶴でパレードが開催されました
- 【プライド月間】群馬県、佐野市、古賀市の庁舎などもレインボーカラーに
- 【プライド月間】渋谷モディで「SHIBUYA MODI RAINBOW DAYS」開催中
- グレタ・ヴァン・フリートのジョシュ・キスカがカミングアウト
- 山口、広島、青森…朝日新聞が地方のプライドパレードを特集
- エストニアが婚姻平等を承認、旧ソ連圏で初めて
- 【同性パートナーシップ証明制度】旭川市周辺の8町、上越市、兵庫県、徳島県、大分市が導入へ、大分県も検討
- 東京特別区職員の同性パートナーを配偶者と同等とみなす通知が発出、20区が秋までに待遇改善へ
- 「不同意性交等罪」が成立、多様な性被害の実態を反映し、手指や物の挿入も対象へ
- LGBT理解増進法の成立を受けて、プライドハウス東京とLGBT法連合会が声明を発出
- 【プライド月間】英版『ヴォーグ』誌が「Pride & Joy」を特集、表紙はLGBTQのパイオニア
- LGBT理解増進法が成立…各地の当事者や支援者はどう受け止めたのか
- トニー賞で史上初めてノンバイナリーの俳優2人が受賞
- TRP、NRP、九州・山口の16団体が法案への声明を発表
- 「LGBT差別増進法」に抗議する緊急大集会の第2夜が開催されました
- 【同性パートナーシップ証明制度】北海道美瑛町、岩手県宮古市、群馬県玉村町、神奈川県秦野市伊勢原市、福井県、岐阜県、山口市が導入へ
- 【プライド月間】世界最大のプライドパレードがサンパウロで開催、パブロ・ヴィターらのライブも
- 【プライド月間】二丁目にプログレスプライドフラッグのバナーが!
- 【朗報】エムポックス(サル痘)のワクチン接種が可能に!
- 「LGBT差別増進法案」が衆院で可決、LGBT法連合会が声明
- 「LGBT差別増進法案」の問題点を複数のメディアが報道
- 「根本的に変質した」「理解阻害法案」への抗議集会が開催されました
- 【プライド月間】ホワイトハウスでLGBTQコミュニティを支援するイベントが開催されました
- 差別者配慮の法案が採択、LGBTQ団体は「当事者が不幸になる」と危機感
- 【プライド月間】高知市が「プライド月間」のフラッグを商店街に掲げました
- 子どもを授かったトランス男性とゲイのカップルを追った番組が放送文化基金賞で最優秀賞を受賞
- 【結婚の自由をすべての人に】福岡地裁判決を原告の方々はどう受け止めたのでしょうか
- 【結婚の自由をすべての人に】福岡地裁で違憲状態との判決が下りました
- LGBT法案が9日、衆議院内閣委員会で審議入りへ
- バンコクでプライドパレードが開催、前進党のピタ党首が同性婚法制化を約束
- トランス女性の弁護士に殺害予告メール、TGJが抗議声明を発表
- 「結婚の自由をすべての人に」訴訟名古屋地裁判決の意義
- 3つの案が提出されたLGBT法案、今国会での成立は不透明な情勢に
- 【プライド月間】Googleで「LGBTQ」と検索してみましょう
- 【プライド月間】ディーゼルがトム・オブ・フィンランド財団とのコラボでコレクションを発表
-
5月
- 【結婚の自由をすべての人に】名古屋地裁が画期的な違憲判決を下し、喜びの声があふれました
- 大阪で今年もプライドクルーズが開催されました
- 6/4の『新婚さんいらっしゃい!』にバレエダンサーの竹田純さんと同性パートナーのクリスさんが登場
- 「結婚の自由をすべての人に」東京二次訴訟で原告の福田理恵さん「埋もれている少数派の小さい声を聞いてほしい」
- 3つのLGBT法案が国会に提出…維・国独自案も問題だとの批判の声
- 【追悼】クィアカルチャーの礎を築いた前衛映像作家、ケネス・アンガー
- LGBT法案与党修正案・維新国民案にLGBT法連合会が懸念を表明
- 『SPUR』の「改めて"結婚の平等"について知ろう。同性婚がある社会を見つめる」という記事がとても良いです
- ドラァグクイーンのガチャガチャが発売決定!
- LGBT差別のない社会の実現を謳ったG7首脳宣言を受け、この国際的な約束をどう果たすかが問われます
- 京都市が今年もプライド月間の取組みを実施します
- Akita Pride Marchが開催、約200名が秋田駅前を晴れやかに行進
- G7首脳声明にLGBTQの人権を侵害する暴力を非難すると明記
- 【追悼】ヴィスコンティ監督と公然の仲であった伝説的な俳優、ヘルムート・バーガー
- 与党が修正LGBT法案をG7前日に駆け込み提出、野党は与野党合意を見た原案を国会に提出
- 婚姻平等実現に向けた全国的なキャンペーン「結婚の平等にYES!」が発足
- 5月17日は「多様な性にYESの日」、内外で様々なアクションがありました
- 大きく後退したLGBT法修正案に抗議する緊急院内集会が開催されました
- アラフィフに突入したシロさんとケンジを描く『きのう何食べた?』シーズン2が10月に放送決定
- P&Gジャパンとウエルシアがドラッグストアでのインクルーシブな接客ガイドを発表
- LGBT法修正案に対して野党が「後退だ」「なぜ勝手に修正するか」と批判、超党派LGBT議連で
- 「骨抜き」は許されないとの声、明日緊急院内集会開催へ
- G7は広島サミット首脳声明に「LGBTQの権利を保護し人権状況改善に取り組む」旨を明記する方針、一方、保守派に配慮したLGBT法与党修正案は…
- 米大使が15名の大使と共同でビデオメッセージ、LGBTQの平等の権利を訴え
- 魂を揺さぶる名文:李琴峰「LGBT迫害から立ち上がる シドニーで見た歴史への敬意」
- 西田政調会長代理が「LGBTQの権利擁護=共産主義」という旧統一教会と同じ主張を…
- LGBT法をめぐる会合で「学校でLGBT教育するのか」との意見…京都新聞「差別解消になぜ、ここまで後ろ向きなのか」
- お子さんも書いた、同性婚実現を求める約500通の手紙が政府に届けられました
- 「不当な差別」と修正した与党案、公明は否定せず、野党は問題視
- サム・スミス、5年ぶりの来日公演! 10月に横浜と大阪で
- LGBT法案、自民党内で異論相次ぎ、まとまらず…「サミットまでの成立は困難」と議連会長
- GW期間中に各紙誌で展開されたLGBTQ関連の良記事
- このGW、神戸でレインボーフェスタが、山口でレインボープライド (パレード)が初開催されました
- 毎日新聞が憲法記念日にLGBTQを特集
- 最高裁長官、LGBTQの権利について「広い視野と深い洞察力が必要」
- 共同通信の世論調査で同性婚へ賛成が71%にも上りました
- 荒井元首相秘書官の差別発言から3ヵ月、法整備が進まない背景に宗教右派の影
- 【同性パートナーシップ証明制度】盛岡市の第1号は加藤市議、長野県が8月1日から、近江八幡市が7月1日から導入
-
4月
- 神政連が同性愛を“精神疾患”扱いする文書を配布し、条例に反対していたことが明らかに
- LGBT法案「差別は許されない」文言について西田議員「日本の国柄に合わない」と発言
- 品川区の13の橋と町田市庁舎・駅前がレインボーカラーに!
- aktaがお店やイベントで掲示できるMPOXのポスターを制作
- 与党が「差別は許されない」に「不当な」を加えて国会提出へ…批判が噴出
- 神政連が統一地方選候補にLGBT法への反対を求める公約書を送っていました
- 【訂正】統一地方選で、上川あやさん、石坂わたるさんをはじめ10名の当事者の候補が当選
- TRP2023「プライドフェスティバル」に約24万人が来場、過去最大規模で成功を収めました
- P7コミュニケと差別禁止法などを求める署名が政府に提出されました
- KANE&KOTFEさんが出演する『超多様性トークショー!なれそめ』が今夜再放送
- 都営住宅の結婚予定者向け入居募集は、都パートナーシップ宣誓制度利用カップルも対象です
- 【同性パートナーシップ証明制度】盛岡市で5月からスタート。その他、パートナーシップ証明を受けた各地の方々の喜びの声
- G7外相共同声明、LGBTQの権利の促進と保護を主導すると明記
- ファミマがソックスだけでなくレインボーのハンカチも発売
- レディ・ガガ、バイデン大統領の芸術人文委員会の委員長に就任
- LGBTQ+ろう者の全国組織が設立されました
- 10/28、奈良で初のレインボーパレードが開催
- 「This Hell」がTRP2023のテーマソングに! リナ・サワヤマさんからビデオメッセージも
- 4/16、沖縄国際映画祭のレッドカーペットをかつきさんとご両親が歩きます
- LGBTQ法整備を求める5万6千筆の署名が超党派LGBT議連に提出
- ドクターマーチンが世界のPRIDEアーティストと3ヵ月連続でコラボ、第1弾はカナイフユキさん
- サル痘(MPOX)についての情報をまとめた「MPOX GUIDE BOOK」が発表
- 【統一地方選】渕上綾子道議が再選されました
- 米最高裁が、トランス女子の中学生が陸上の女子チームに参加することを認めました
- サル痘(エムポックス)感染が累計で95名に、ワクチンについては協議中
- 川越市の最明寺で、埼玉県初の仏式の同性結婚式が行なわれました
- 今年の金沢プライドウイークは10月の三連休に開催、パレードは10月9日
- 同性婚法制化に賛同する企業が350社を超えました
- ダニエル・ラドクリフが「LGBTQの若者の自殺を根本的に食い止めるためには同性婚を認めるべきだ」と語りました
- アギレラがGLAADメディア賞受賞スピーチでLGBTQコミュニティを賞賛
- 【追悼】LGBTQフレンドリーでもあった坂本龍一さん
- 広報すぎなみに「性の多様性尊重条例」施行を祝う区長コメントが掲載、お祝いの街宣も
- 【同性パートナーシップ証明制度】香川県で全市町での導入がコンプリートしたほか、多くの自治体で制度がスタート
- 5/5、山口初のレインボープライド開催
-
3月
- 【悲報】「北欧館」と「ロイヤル」が突如閉店
- 来春から小学校の教科書でLGBTQについての記述が大幅に増えます
- マドンナがドラァグ禁止法が成立したテネシー州でLGBTQをセレブレイトするチャリティ公演を開催
- 性的マイノリティの子を持つ親の有志の会が森まさこ氏に要望書を手渡しました
- 『BUTT』32号刊行を記念し、ARTY FARTYでパーティが開催
- 難民認定のガイドラインが初策定、性的マイノリティも明記
- 世界水泳選手権2023福岡大会に合わせて「プライドハウス福岡」がオープン
- 同性愛者と自認しただけで“犯罪者”になるウガンダの法案、国際社会が非難
- 3/24(金)18:00〜新宿西口でLGBT法と同性婚法の実現を求める緊急街宣開催
- 昨年のHIV新規感染報告数が870人で過去最少を記録しました
- 台湾同性婚第3号であるゲイの劇作家、リン・モンホワンの作品が上演
- G7に向けてLGBTQの政策提言を行なう世界初の市民組織『P7』が発足
- エムポックス(サル痘)の感染が大阪府、徳島県、茨城県などでも確認されました
- 経団連会長がLGBT法整備の審議が進まない状況に苦言を呈しました
- 『台湾同性婚法の誕生』が栄誉ある家族法学術賞を受賞
- 明日の『情熱大陸』に衣装デザイナーのHIROSUMIさんが出演!
- 立民福山氏がトランス女性バッシングについて政府に対応を求めました
- LGBT法連合会がトランス女性をめぐるデマに抗議する声明を発表
- 性的マイノリティに関する特命委員会事務局長の城内実議員、「同性婚はウクライナが正しいという人と同じで少数派」と発言
- G6とEUの7人の大使が連名でLGBTQの人権を守る法整備を促す書簡を送付
- 米国で日本人と同性婚した米国人男性に「特定活動」の在留資格が初めて認められました
- 同性婚の法制化を求める団体が独自の民法改正案を発表
- 【同性パートナーシップ証明制度】島根県は10月から、室蘭市、別海町、石巻市、南丹市も導入へ、杉並区で条例制定など
- 大阪地裁がウガンダから逃れてきた同性愛女性を難民と認定
- 今晩20時からハートネットTVで「LGBTQ+座談会」放送、かずえちゃんも出演
- 公明山口代表、LGBT法「一刻も早く成立させるべき」
- マーク・タカノ米下院議員、日本のLGBTQが「差別禁止を求める声はまったく正しい」とコメント
- 川越市の最明寺で初の仏前式LGBTQウエディングが開催
- 『エゴイスト』の宮沢氷魚さんがアジア・フィルム・アワードで助演男優賞を受賞!
- 台湾での同性婚が1万組の大台に乗りました
- 【アカデミー賞】エブエブが最多7部門を受賞し、主要部門をクィア映画が席巻!
- 元水曜日のカンパネラのコムアイさんや、徳川家康の末裔・家広さんが同性婚法制化に賛同
- 【追悼】ケニアで有名な若手ファッションデザイナーでLGBTQ活動家のエドウィン・チロバさん
- LGBTQ+ユースと企業の人たちがともに「働く」を考えるイベントが開催
- 性的マイノリティの子育ては「むしろ優れている」との研究結果が明らかに
- 【追悼】世界で初めてトランスジェンダーとして国会議員に当選したジョージナ・ベイアー
- 国際女性デーにLGBTQ関連の動きもいろいろありました
- IGLTA世界総会2024が大阪で開催決定、アジア初の快挙
- 格闘家が、脅迫で中止になりかけたドラァグ・イベントの警備を申し出ました
- 東京マラソン2023にプライドハウス東京も参加・連携しました
- 石川大我議員がLGBTQ施策について国会で追及
- 【速報】立憲民主党が同性婚を認める民法改正案を国会に提出
- 【同性パートナーシップ証明制度】富山県、静岡県でスタート、石川県、斑鳩町、大村市なども導入へ
- 岸田総理が同性婚を認めないのは「差別だとは考えていない」と発言しました
- ベルリン映画祭、主演俳優賞・助演俳優賞がトランスジェンダー役に授与
-
2月
- 3/9まで実施中! サル痘(mpox)に関するアンケート
- 「同性婚気持ち悪い」などの差別発言を繰り返す愛知県議の議員辞職勧告決議を求める要望が出されました
- 日経の世論調査でも同性婚への賛成が65%に上りました
- 性的マイノリティの子を持つ親の有志の会が明確に差別の禁止を規定した「子どもたちの命を守る法整備」を要望
- シドニーでマルディグラ&ワールドプライドのパレードが開催されました
- 米オカシオ=コルテス議員「同性婚やLGBTの権利擁護が日米関係に重要」
- またしても問題発言…中曽根元外相の典型的なトランス排除言説と「訴訟が乱発」論
- 【同性パートナーシップ証明制度】和歌山県、徳島県が検討を表明、滝川市、深川市、町田市、米原市、三木市が導入へ
- LGBTQなど多様なマイノリティのためのコミュニティセンター「金沢にじのま」がオープン
- 同性婚実現を求める「#岸田総理に手紙を書こう!プロジェクト」
- 岸田首相が理解増進法案準備を党幹部に指示、コミュニティから「差別禁止」文言の行方を懸念する声も
- 画期的! 韓国で同性カップルに健康保険の被扶養者資格認める高裁判決
- 日本での婚姻平等(同性婚法制化)が社会に与えるポジティブな影響についての試算が発表されました
- アンドラ公国が世界で34番目の同性婚承認国となりました
- 【追記あり】性の多様性を尊重する社会の実現に向け、全国23県の知事有志が共同で声明
- 多くのメディアが同性婚世論調査を一斉に実施、賛成が最高72%、20代では9割超
- 豊島区の条例に救われたゲイの方:「理解増進法では不十分」「差別を禁じ、救済制度のある法律が必要」
- 鈴木亮平さんが「社会を変えてみる勇気が求められている」と語りました
- 美輪様「人が人を愛したことの何が悪いのか」、亮平様「ずっとこうやって演じて生きていかなきゃいけないのか」
- 「結婚の自由をすべての人に」訴訟が4年を迎え、弁護団が3判決の意義や今後について配信
- 岸田総理が当事者団体と面会し直接謝罪、法整備については「今後の対応を検討していく」、今夜オンライン報告会開催
- LGBT法連合会と「Marriage For All Japan」が差別禁止法制定を訴え、日弁連は速やかな同性婚法制化を求めました
- 【同性パートナーシップ証明制度】小樽市、酒田市、埼玉県新座・朝霞・志木市、愛知県日進市、兵庫県丹波篠山・丹波・加古川・高砂市、愛媛県今治市も
- 超党派LGBT議連の総会で当事者団体が差別禁止法や同性婚法などの法整備を求めました
- サッカーチェコ代表のヤンクト選手がカミングアウト
- 共同通信の世論調査で同性婚に賛成が64%、若年層で81.3%に上りました
- 11/25に島根レインボーパレードが開催、山陰地方で初
- NHK「日曜討論」で各党が論戦、全国の新聞社が当事者の声を掲載
- 「足立区が滅ぶ」発言の区議が再び…「たまたまLGBTの話をしたためにマスコミに徹底的に叩かれた」と議会で発言
- カミングアウトしたノア・シュナップが祖父から心温まるメールを受け取りました
- 立憲民主党や公明党の代表がLGBTQ団体と懇談し、差別禁止法を目指すことで合意しました
- 「Marriage For All Japan」が森首相補佐官と面会、AKB48の柏木由紀さんや和歌山県知事らも同性婚を支持
- ヒューマン・ライツ・ウォッチ「LGBT差別禁止法導入など改革を」、鈴木亮平さん「同性婚の法制化を急ぐべき」、熊本県知事も同性婚に賛成
- 全国のプライドが一斉に声を上げ、新潟ではデモが開催されました
- LUSH JAPANが「結婚の自由をすべての人に」をメッセージ
- 「異常な性癖」発言の浜松市議が謝罪しました
- LGBT議連が米国LGBT人権特使と意見交換
- 2/14、差別禁止法を求める院内集会が緊急開催
- 【同性パートナーシップ証明制度】旭川市は来年1月から、長岡市でスタート、茨城県と三重県が連携など
- LGBT法連合会など3団体が会見し、LGBT差別禁止法などの法整備を訴えました
- 『エゴイスト』の松永監督と宮沢氷魚さんが差別発言に対してコメントしました
- 法整備求める署名が1日で2万5千超、要請書も提出
- G7を前に同性婚などLGBTQの法整備を!と求める世論が形成、一方、政府は…
- サム・スミスとキム・ペトラスがグラミー受賞、トランスジェンダーとしての快挙達成
- 荒井氏更迭後も批判の声が続々、署名も立ち上がりました
- NZ国会で同性婚に反対した議員が「ゲイの息子との約束」でLGBTQに謝罪した演説が話題に
- 「見るのも嫌」発言の荒井勝喜首相秘書官が更迭されました
- テイラー・スウィフトが新曲のMVでトランス男性を恋人役として出演させ、賞賛されています
- 「社会が変わってしまう」発言に対してピンクドット沖縄が声明を発しました
- 「社会が変わってしまう」発言に対し、各方面から批判の声
- スロベニアで同性婚が実現、一方、日本の国会では…
-
1月
- 大河ドラマ『べらぼう』で平賀源内が「男一筋」だと語る場面が話題に
- NZ代表「オールブラックス」としても活躍したキャンベル・ジョンストン元選手がカミングアウト
- 【同性パートナーシップ証明制度】富山県が3月から導入、北海道で5市が連携協定、山形市で団体が要望など
- 東京都と埼玉県で新たに3名がM痘(サル痘)感染確認
- “友情結婚”しても幸せになれなかった現実…「結婚の自由をすべての人に」東京二次訴訟の原告が語りました
- ryuchellさん、ロバートキャンベルさん、井手上漠さん、下山田志帆さんらが出演!「虹クロ」今夜21時放送
- 米国が献血禁止基準から男性間性交渉の条件を撤廃、ゲイ・バイセクシュアル男性差別が解消へ
- 「同性婚気持ち悪い」発言の愛知県議がさらにひどいコメントを投稿
- グラミー賞授賞式のステージで多数のクィア・アーティストがパフォーマンス
- M痘(サル痘)の9例目、10例目の感染が東京都で確認されました
- アカデミー賞の最多ノミネートはアジア系女性が主人公のクィア映画
- 【ご協力のお願い】私たちのコミュニティの歴史を記録するためのプロジェクト
- 沖縄県の人権条例でLGBTQ差別を禁止へ、1万3927筆の署名が県を動かしました
- 明治が多様性に寄り添うバレンタインチョコを開発、プライドハウス東京と協働で
- リナ・サワヤマが来日公演でレインボーフラッグを振り、「Chosen Family」も歌ってくれました
- ジョージ・マイケルの伝記映画の企画が浮上、ジョージを演じるのは…
- 台湾人と同性婚未承認国の外国人との同性婚が、ついに認められました!
- 2/18、金沢にコミュニティセンター誕生&クラブイベントも開催
- 『ハートネットTV』でろう者のLGBTQがフィーチャーされました
- 米国ではついにサル痘の感染抑制に成功、日本の今後は?
- ウィスコンシン州退役軍人長官にオープンリー・ゲイのジェームズ・ボンド氏
- 同性カップルも祝福した佐賀県のPR動画が広告賞グランプリを受賞
- 【同性パートナーシップ証明制度】静岡県が2月から受付、島根県は今年中に導入へ
- 同性婚法制化を求める社説、続々
- 同性カップルも「フラット35」を利用できるようになりました
- リアル・キンキーブーツ? トランス女性や男性に向けたパンプスブランドが誕生
- 高校時代にカミングアウトしたryuchellさん。そのとき母は…
- ライアン・マーフィがゴールデングローブTV功労賞を受賞
- アロマンティック・アセクシュアルの方たちへの調査結果が公開
- 『ストレンジャー・シングス』ウィル役のノア・シュナップがカミングアウト
- 【同性パートナーシップ証明制度】苫小牧市が白鳥王子アイスアリーナをレインボー・ライトアップ、丸亀市、日田市でも制度導入
- 年末年始、たくさんのドラァグクイーンがメディアでフィーチャーされました
- 西村宏堂さんが紅白の審査員席から「同性愛者」としてコメント
-
12月
-
2022
-
12月
- 【追悼】LGBTQコミュニティにも影響を与えたデザイナー&アクティヴィスト、ヴィヴィアン・ウェストウッド
- 東京都の今年のHIV新規感染者数が300人を下回る見込みです
- 来年6月、浜松で初のプライドパレードが開催されます
- HIVワクチン候補の初期臨床試験で97%の方に免疫反応
- 杉田水脈総務政務官が更迭されるも、任命責任など批判の声やまず
- 【同性パートナーシップ証明制度】一関市が岩手県で初めて導入、北関東3県が連携協定ほか
- 西村宏堂さんが紅白のゲスト審査員に。LGBTQとして初?
- 三重県議会が「議員の政治倫理に関する条例」改正案を可決、同性カップルへの人権侵害から1年半
- オープンリー・ゲイのレオ・バラッカー氏が再びアイルランド首相に
- 『ディア・エヴァン・ハンセン』のベン・プラットが婚約
- シャロン・ストーンが90年代にHIV/エイズ研究を支援したことで「8年間、仕事がなかった」と明かしました
- インド最高裁が同性婚法制化を審理へ
- 米国も献血におけるゲイ・バイセクシュアル男性差別を解消へ
- 【同性パートナーシップ証明制度】福島県で初めて富岡町が導入へ、そのほか岩手県一関市、千葉県木更津市、愛知県小牧市、愛媛県大洲市など
- 氷川きよしさんが「一人の尊い命を色物にしないでほしい」と投稿、マイノリティ差別への抗議として
- ゴールデングローブ賞のノミネートが発表、LGBTQ関連作品も多数
- バイデン大統領の署名によって「結婚尊重法」が成立、米国全土で婚姻の権利が守られました
- 「結婚の自由をすべての人に」東京訴訟の原告が控訴、「一日も早く婚姻平等の実現を」
- 米女子プロバスケットボール選手でレズビアンのブリトニー・グライナー選手がロシアから解放されました
- ゲイ・バイセクシュアル男性のセックスライフ等のアンケート「LASH調査」が実施中
- 杉田水脈総務政務官の更迭を求める抗議集会が行なわれました
- 【カタールW杯】レインボーのシャツでLGBTQ支援を示していた米記者グラント・ウォール氏が試合中に急逝…弟さんがゲイの方だったそうです
- 「結婚の自由をすべての人に」九州訴訟が結審、来年6月8日に判決
- 生徒指導提要改訂版に「性的マイノリティに関する課題と対応」が追加されました
- 石川大我議員が参議院法務委員会で同性婚の議論を求め、杉田氏差別発言を追及
- 東京都住宅供給公社が運営する全物件ヘの入居申込みが受付中です
- インドネシアでゲイSEXが禁止に…バリ島も楽園ではなくなってしまいます
- 法的性別変更に不妊手術を必須とする現行法について最高裁大法廷が改めて憲法判断へ
- リル・ナズ・Xが二丁目のEAGLE TOKYO BLUEに!
- 杉田総務政務官の更迭を求め、札幌でゲイの高校生がデモ
- 多くの新聞社が社説で同性婚実現を訴えています
- 魔法使いアキットさんがトランスジェンダーであることをカミングアウト
- LGBTQへの大規模アンケート調査「REACH Online 2022」にご協力を!
- 【同性パートナーシップ証明制度】帯広市、名古屋市、長野市でスタート、島根県、丸亀市も導入の意向
- 『ハートストッパー』のキット・コナー、「映画やドラマでもっとバイセクシュアルが描かれるべき」
- LGBT法連合会が東京弁護士会人権賞を受賞
- 杉田議員が「LGBTは“生産性”がない」発言をようやく謝罪・撤回、辞任求める声止まず
- ゲイコミュニティ誌「ヤローページ2022」が発行、仲通り交差点に看板も
- 米上院が同性婚保障法案を可決、近く成立へ
-
11月
- 今日の判決は同性婚を認めないのは違憲だとする歴史に残る判決でした
- 「同性婚気持ち悪い」発言の愛知県議への厳正対応と再発防止を求め、LGBTQ団体が共同声明
- 同性婚訴訟東京地裁判決に向けて、多くのメディアが記事を掲載
- 同性婚訴訟東京地裁判決を前に、前夜祭イベントが開催されました
- 『片袖の魚』が映文連アワード2022準グランプリを受賞
- アンチLGBT法成立間近のロシアで、ドラァグクイーンたちが最後のショーを…(涙)
- 11月30日の「結婚の自由をすべての人に」訴訟東京地裁判決に向けて前夜からイベントが開催
- 【同性パートナーシップ証明制度】岩見沢市、和光市、加須市、長岡市、三次市、日田市、阿蘇市で導入決定
- 【カタールW杯】ドイツ代表が口を覆う仕草でレインボー腕章禁止に抗議しました
- 米コロラド州のLGBTQクラブで起こった銃乱射事件の被害者を追悼する集会が開催
- 米上院で同性婚保障法の採決に進むための動議を賛成多数で可決、制定に前進
- 女性同性愛を描いた漫画が実写ドラマ化&オリジナルグッズが同性婚実現チャリティに
- 豪プロバスケ選手、アイザック・ハンフリーズがカミングアウト
- 氷川きよしさん、「白組、紅組の枠を超え、特別企画として」紅白に出場
- 【カタールW杯】米国代表チームがレインボーのチームロゴでLGBTQ支援
- 神社で働くLGBTQの方々が神政連への意見書を発表しました
- 誰もが“いいふうふ”になれる世の中を目指してKANE&KOTFEさんが挙式、花*花さんがお祝いLIVEを披露
- 「work with Pride 2022」にラーム・エマニュエル駐日大使が登壇しました
- 【米中間選挙2022】初のトランス男性の州議会議員が誕生
- 【米中間選挙2022】初のオープンリー・レズビアンの州知事がマサチューセッツ州で誕生
- 石川大我議員らが総務政務官に就任した杉田議員を「生産性ない」発言で追及
- 【同性パートナーシップ証明制度】名古屋市は12月から、豊後高田市、勝山市は来年4月から導入の意向
- 青森レインボーパレード主催のお二人に取材したラジオ番組が民放連賞グランプリを受賞
- 【米中間選挙2022】全50州から過去最多1000人超のLGBTQ候補が出馬、「Rainbow Wave」となるか?
- 昨日、西日本の各地でパレードやレインボーフェスタが開催されました
- 【追悼】本当に多くの方たちに愛された二丁目のレジェンド、『九州男』のまっちゃん
- ミス・アルゼンチンとミス・プエルトリコが電撃結婚!
- 11/6は福岡で九州レインボープライドが開催、横山久美さんなども登場
- 【同性パートナーシップ証明制度】静岡県、富山県、神戸市、旭川市、野々市市、世田谷区などの動き
- ドラァグクイーンなども出演する「歌舞伎超祭」が明日開催
- 東京都パートナーシップ宣誓制度がスタート、11/1朝までに177組が届け出
-
10月
- 20回目を記念する台北プライドが開催、雨のなか12万人が行進
- メキシコの32州のすべてで同性婚法案が採択され、正式に婚姻の平等が達成されました
- サム・スミスとキム・ペトラスがビルボードチャートで首位! ノンバイナリー、トランスジェンダーとして初の快挙
- 来日中のシャーマン米国務副長官がプライドハウス東京レガシーを訪問、日本のLGBTQ+コミュニティへの応援メッセージも
- 11/1、都庁ライトアップの瞬間を一緒に見るカウントダウンイベントが開催
- 来年1月、『ル・ポールのドラァグ・レース』のクイーンたちが来日!
- 三重県小林県議辞職勧告案が1票差で否決、伊賀のゲイカップルが反対議員に質問状
- 山形でのパレード開催を祝い、JR北山形駅の小便小僧がレインボーに「衣替え」
- 11/20、沖縄・国際通りでピンクドット沖縄10周年を記念する初のレインボーパレードが開催
- 【同性パートナーシップ証明制度】各地で喜びの声――東京都の受付開始、高知県香南市、和歌山県橋本市など
- フィギュアスケートペアでソチ五輪にも出場した高橋成美さんがカミングアウト
- 11月6日、徳島でプライドパレード開催
- トランスジェンダー国会が初開催され、当事者や有識者が法整備による生きづらさの解消を訴えました
- 今日から東京都パートナーシップ宣誓制度受付スタート、都庁がレインボーにライトアップ
- 10/16の岡山レインボーフェスタ開催を祝して岡山髙島屋がレインボーフラッグを掲出
- 大阪と三重でプライドイベントがひさしぶりにリアル開催されました
- カイリー・ミノーグ、来年のシドニー「ワールドプライド」で3年ぶりの大規模ライブ、新曲も披露
- トランスジェンダーの社会的課題を国会議員に伝える初の院内集会が開催
- 京都嵐山のお寺で「RUSHCRUISE」が開催! 歴史的なイベントになる予感しかありません
- 「同性婚気持ち悪い」発言の渡辺昇愛知県議が謝罪しました
- スロベニア国会が同性婚と養子縁組を承認する法案を採択
- 【同性パートナーシップ証明制度】福井県越前市で4組が宣誓&イベントも開催、そのほか戸田市、座間市、瀬戸内市、那覇市などの動きをお伝えします
- 「日米同性カップルの在留資格を認めるべき」東京地裁が初の違憲判断
-
9月
- 【同性パートナーシップ証明制度】名古屋市が11月に導入、旭川市、小樽市、大田原市、那須塩原市、佐渡市なども導入へ
- キューバで同性婚(婚姻の平等)が実現!
- エルトン・ジョンがホワイトハウスで演奏、バイデン大統領から勲章を贈られました
- 【訃報】「のど輪締め」で人気を博したコレステロールタクヤさん
- 新潟と山形で初のプライドパレードの開催が決定
- 都パートナーシップ制度導入が「少子化につながる」「制度悪用の可能性がある」などと議会で発言した江東区議に謝罪と撤回を求める声
- 「お花畑正義感の人たち」発言の城内議員に対し、地元選挙区の団体が公開質問状を提出
- 金沢プライドウィークが開催、LGBTQと伝統文化とのコラボが光る有意義な4日間になりました
- さっぽろレインボープライドが初の2日開催、鈴木亮平さんがサプライズで登場する場面も
- 本日、日本と台湾のゲイカップルが婚姻届を提出し、結婚が正式に認められました
- 『キンキーブーツ』でローラ役を演じる城田優さんが17日の「MUSIC FAIR」に出演
- 【同性パートナーシップ証明制度】東京都職員の待遇平等化がついに実現しそうです
- 元警察官&元消防士のゲイカップルが「男社会」の職場から抜け出した理由を語りました
- トランス女性へのハラスメントをピクシブ社が全面的に認め、全額を賠償へ
- 9/17、9/18はさっぽろレインボープライド2022
- 【同性パートナーシップ証明制度】盛岡市がついに導入へ
- 沖縄県知事選・統一地方選候補者のLGBTQ関連政策は?
- ゲイの愛や喜び、苦悩、希望、PRIDEを描いた舞台『すこたん!』がDVDに
- ベネチア国際映画祭でブレンダン・フレイザーが巨漢のゲイの英文学教授を演じた映画『The Whale』が上映
- ガガ様が『Born This Way』を歌いながら「この曲をLGBTQ+コミュニティに捧げます」とメッセージ
- 小泉智貴さんが「FASHION PRIZE OF TOKYO」を受賞、パリでコレクション発表へ
- 工藤司さんが東京コレクションのショーで同性結婚式を思わせる「マリエ」ルックを登場させました
- 下野市の石川市議が「LGBT隠して生きて。その方が美しい」などと発言したことに多方面から非難の声
- 【同性パートナーシップ証明制度】栃木県などで制度スタート、長野県が来春導入へ
- 全国のコミュニティセンターで郵送検査無料キャンペーン実施中
- 世界が美輪様を再発見、「もののけ姫」のモロの声を演じた”ドラァグクイーン”として
- ウクライナのハルキウで9/25にパレードが開催されます
-
8月
- MTVアワードのLGBTQ的名場面:ダヴ・キャメロン、リル・ナズ・X、ソーシー・サンタナほか
- 札幌・チカホでプライドイベントが初開催、9/11は映画祭、9/17〜9/18はさっぽろレインボープライド!
- 金沢プライドウィークの詳細が発表、ハイアット系列のホテルでキャンペーンも
- 犯罪被害者給付金不支給訴訟で名古屋高裁が控訴を棄却、「社会的な意識が醸成されていなかった」
- リナ・サワヤマさんが「news zero」に出演、「日本はG7で唯一LGBTQ差別禁止法がなく、同性婚も認められていません」
- リナ・サワヤマさんが今晩「news zero」に出演、LGBTQ+コミュニティへの思いも
- 韓国最高裁が、行政が性的指向を理由に団体の体育館使用を拒否したのは差別だと判断
- 自民・城内議員「お花畑正義感の人たち」発言が炎上
- 【同性パートナーシップ証明制度】三条市、佐野市、越前市、帯広市など
- 【追悼】90年代に同性パートナーとレッドカーペットを歩いたハリウッド・スター、アン・ヘッシュ
- ブータンでカミングアウトしているタシ・チョデンさんがミス・ユニバース世界大会に出場
- シンガポールでようやく、男性同性間の性行為を違法とする刑法が撤廃されそうです
- 「私たちだって”いいふうふ”になりたい展in西宮2022」のオンライントークイベントが今晩開催
- 米政府のサル痘への対応が遅いのはホモフォビアが原因だとジョナサン・ヴァン・ネスが批判
- 【同性パートナーシップ証明制度】茨城県と佐賀県が連携協定、都道府県として初
- リナ・サワヤマさんがサマソニで「私は日本で同性婚できません。平等な権利のために一緒に闘って!」と訴え
- 東京高裁が性別変更前に生まれた子のみ認知、トランス女性の凍結精子出産の2子をめぐって
- 京都の劇場でドラァグクイーンが子どもに向けて絵本を読み聞かせたりするショーが行なわれました
- 米国初のアジア系ゲイの国会議員であるマーク・タカノ氏が日本にLGBTQの権利擁護を促しました
- 学校教員用の手引書「生徒指導提要」にLGBTQ児童生徒への理解を求める文言が追加
- 日本と中国のゲイの生きやすさの比較調査のためのアンケートが実施中
- 「“生産性”がない」発言の杉田議員が総務大臣政務官に、「種の保存に背く」発言の簗議員が文部科学副大臣に…
- サル痘の治療や予防接種について国立感染症研究所に取材しました
- 米MLBマイナーリーグのソロモン・ベイツ投手がカミングアウト
- 台湾・高雄で2025年開催予定だったワールドプライドが中止へ…
- オープンリー・ゲイでアルビニズムのモデル/シンガー・ソングライターのショーン・ロスがパートナーと婚約
- レディ・ガガがツアーで同性婚の権利を擁護するパワフルなメッセージを発信
- アムステルダムの運河で3年ぶりにプライドパレードが開催
- 【追悼】「ザナドゥ」「フィジカル」のオリビア・ニュートン=ジョン
- MR GAY JAPANとMISS GRAND JAPANが同日開催、世界的なミスコンテストの日本大会とミスター・ゲイ・コンテストの協働は史上初
- ビヨンセの最新アルバム『ルネッサンス』はクィアコミュニティへの讃歌
- 旧統一教会が日本の政治に巧妙に入り込んでいることがLGBTQ施策の妨げに
- 米国が「サル痘」で緊急事態宣言を発しました
- エポスカードの同性パートナーへの対応が素晴らしいと話題に
- ゼレンスキー大統領が同性パートナー法を認める方針を表明
- 宮崎市でレインボーパレードがスタート!
- シンガー・ソングライターのアソビウイルスさんがカミングアウト
- ゲイであることを受け容れられない少年の苦悩を描いた海外小説が邦訳出版へ
- トム・デイリー選手が声明「LGBTQアスリートが迫害や死を恐れることなく、安全に活躍できる世界を」
-
7月
- 宮崎国際大にレインボーカラーの「虹色ベンチ」が登場、支援サークル「虹色カフェ」の取組み
- 【同性パートナーシップ証明制度】栃木県、苫小牧市、神奈川県清川村、愛知県一宮市、愛媛県大洲市、熊本県菊池市などの動き
- 自民党の性的マイノリティ特命委が、旧統一教会系の媒体で「同性愛の多くは治癒可能」などと発言してきた八木秀次氏を“有識者”として招聘
- ブリトニーが音楽活動を再開、6年ぶりの新曲はエルトン・ジョンとのデュエット
- 差別冊子の内容についてキリスト教団体からも抗議の声、続々
- LGBT差別冊子への抗議署名5万筆が提出されました
- WHOが「サル痘」緊急事態宣言、厚労省が薬やワクチンなどを整備中
- 「帰国すれば終身刑」タンザニアから逃れたゲイカップルが難民申請を切望
- 【訃報】漫画家の松崎司さんが心筋梗塞で逝去
- 大ヒットドラマ『ストレンジャー・シングス』のメインキャストがゲイであることが明らかに
- 待ちに待った『POSE』シーズン3がついに放送!
- 日本と台湾のゲイカップルの婚姻を認める判決が出ました
- 米下院が同性婚擁護法案を可決、最高裁に対抗して
- 女子テニスでロシアNo.1のカサキナ選手がカミングアウト
- ソウルで3年ぶりのプライドフェスティバル&パレードが開催されました
- 任天堂が同性パートナーシップを婚姻と同等に扱う制度を導入、SOGIハラやアウティングも禁止
- 同性愛差別演説を繰り返してきた井上氏、統一教会の信徒であることが判明
- スロベニアで婚姻の平等が実現します
- キリスト教系大学教授のLGBTQ差別講演録に対し、マイノリティ宣教センターが意見表明
- 抗議集会の主催者が、差別的な冊子の内容の否定を求める要望書を提出
- SATCサマンサ役のキム・キャトラルがコスメ界の女王に:Netflix新作『Glamorous』
- ミーガン・ラピノー選手が大統領自由勲章を授与されました
- 7/10夜、VOGUEが中部電力 MIRAI TOWERをレインボーカラーにライトアップ
- 【同性パートナーシップ証明制度】鳥取県境港市が山陰初の導入
- ゴルチエの半生を描いたミュージカル、来年春頃に日本でも上演
- 埼玉県でLGBTQ差別禁止条例が可決・成立
- 各地の投票所でトランスジェンダーに配慮した取組みが進んでいます
- 【追悼】人類で初めてAIと融合して「サイボーグ」として生きる決断をしたピーター・スコット-モーガン博士(の肉体)
- 日刊キリスト新聞が神政連や楊尚眞教授に取材、今回の差別的冊子配布事件が起こった経緯が見えてきました
- 「同性愛は依存症」冊子配布を受けて「差別を止めて」と訴える抗議集会が開催(2)
- 「同性愛は依存症」冊子配布を受けて「差別を止めて」と訴える抗議集会が開催(1)
- シンシア・エリヴォがカミングアウト、英『VOGUE』誌8月号のプライド特集に登場
- “家族ができない同性愛者”を排除するための闘い…自民比例・井上候補の発言が波紋
- 米フロリダ州でゲイ・バイセクシュアル男性を中心に髄膜炎菌感染症が流行し、死者も出ています
- LGBTQフレンドリーな神社を知るための「#私のお賽銭のゆくえ プロジェクト」が立ち上がりました
- ロンドンで50周年を祝うプライドパレードが開催、100万人超が参加
- 対面/オンラインが選べる無料相談会「moyamoya」おしゃべりサロンがaktaで開催
- スイスで婚姻平等法が施行され、初の同性カップルの結婚式が行なわれました
- 「同性愛は依存症」「LGBTの自殺は本人のせい」にkemioさん、Mattさんら多くの著名人が抗議
- 【婚姻平等訴訟】大阪地裁の判決を不服として「結婚の自由をすべての人に」訴訟の原告が控訴
-
6月
- 「同性愛は精神障害で依存症」「LGBTの自殺は本人のせい」などと主張する冊子が自民党系議連で配布
- 【プライド月間】タイのパタヤで2年ぶりにプライドが開催
- 【プライド月間】マドンナがニューヨーク・プライドのコンサートで女性ラッパーとキス
- オスロのゲイバーで銃乱射事件が発生し2人が死亡…パレードは中止に
- 【同性パートナーシップ証明制度】岩手県で初めて一関市が導入へ、小樽市、福井県なども検討へ
- 新宿区保健所のゲイ・バイセクシュアル男性向け検査会が復活
- LUSHが「結婚の自由をすべての人に」キャンペーン第2弾「ArtでAction」を明日から展開
- 【婚姻平等訴訟】大阪地裁判決に対し、各方面から批判の声
- 宮崎放送がクエスチョニングであることをカムアウトしている元なでしこジャパンの齊藤夕眞選手を特集
- アテネ五輪陸上女子2冠のケリー・ホームズ氏がカミングアウト
- 【婚姻平等訴訟】大阪地裁初判決「同性カップルが結婚できないのは違憲ではない」に批判続々
- プライドセンター大阪がレインボーな中之島クルーズイベントを開催
- 歴史的! タイの下院第一読会で婚姻平等法案が採択されました
- 【プライド月間】米バイデン大統領がLGBTQ当擁護の大統領令を発しました
- 都議会で「パートナーシップ宣誓制度」が全会一致で可決、成立しました
- 祝!堂山の「EXPLOSION」が7月から営業を再開
- 若い黒人のゲイを主人公にしたミュージカル『A Strange Loop』がトニー賞を受賞!
- アギレラがマッチョなボディスーツ&ペニバンという刺激的な衣装でLAプライドに出演
- 【同性パートナーシップ証明制度】名古屋市今年度中に導入へ、山梨県も検討
- PrEP経験者の手記を募集中
- ブリトニーが結婚パーティでマドンナとキス、伝説のMTVアワードの再来と話題に
- 『ピッチ・パーフェクト』のレベル・ウィルソンがプライド月間にカミングアウト
- 野党会派がLGBTQ差別解消法案などジェンダー関連の3法案を衆院に提出
- 【訂正】タイの同性婚関連法をめぐる情勢について
- ビリー・ジーン・キングがレジオンドヌール勲章を受章
- バンコクでプライドが開催されました
- 【プライド月間】本日のGoogleロゴは、「全米LGBTQ名誉の壁」に殿堂入りしたキヨシ・クロミヤ
- 【プライド月間】『GQ Japan』に飯塚モスオさんの漫画が掲載
- JobRainbowの星賢人さんが日本人として初めて「NBC OUT Pride 30」に選出されました
- 田亀さんのトークイベントがスペイン大使館で開催
- 「The Old Gays」というシニアのゲイの方たちのTikTokアカウントが話題です
- 副外相が同性外国人パートナーも入国が可能だとの見解を示しました
- 【プライド月間】バイデン大統領がプライド月間を祝し、力強い声明を発しました
- 【プライド月間】Googleで「LGBTQ」と検索してみましょう
- 【プライド月間】6月26日、世界各地でプライドパレードやデモが行なわれました
- 【同性パートナーシップ証明制度】鳥取県境港市、高知県土佐清水市、北海道北見市など
-
5月
- 世田谷区が、災害発生時の水防活動や応急措置で亡くなった方の遺族への死亡補償一時金支給する制度を同性パートナーにも拡大
- ぷれいす東京が「サル痘」についてのオンライン学習会を緊急開催
- 「結婚の自由をすべての人に」東京訴訟が結審、判決は11月30日
- バンコクで6/5にプライドパレード開催、記者会見には都知事も参加
- 伊勢丹新宿店が「Disney Pride Collection」とコラボ、ドリアンさんがアンバサダーに
- 大阪の弁護士カップルに密着したドキュメンタリーが今夜放送
- 「男だから平気」と上司にセクハラされ、社に相談するも「(女性とは)重みが違う」と言われたトランス女性が提訴
- 卒業スピーチで「LGBTQの権利」への言及を禁じられた高校生、ひと言も「ゲイ」と言わず、圧巻のスピーチ
- 【同性パートナーシップ証明制度】栃木県が9月導入へ、その他、静岡県、長野県などの動きをお伝え
- 京都市がプライド月間のキャンペーンを実施、市役所や大丸など市内各所がレインボーに
- TRP2022プライド月間のプログラムの詳細が決定
- 上司らに性別変更についてハラスメントを受けた元看護助手と病院側の間で和解が成立
- 台湾の同性婚法施行前と後で同性婚支持率が23.5ポイントも上昇したことが明らかに
- オリヴァー・シムが新曲「Hideous」でHIV陽性であることをカミングアウト
- 石川大我議員が「こども家庭庁」について質問、野田大臣「LGBTQの子ども、同性カップルが育てる子どもも支援」
- LGBTQの仕事と暮らしに関するアンケート調査実施中
- 英国王立造幣局がロンドンプライド50周年の記念コインを発行
- 米エマニュエル大使「誰もが結婚の自由と平等を達成できるまで共に歩み続けよう」
- UGGの今年のプライドコレクションはLGBTQの自殺予防を支援、TRPにも寄付
- ブロードウェイミュージカル『RENT』25周年記念Farewellツアー来日公演開催中
- いわてレインボーマーチが明日開催、アイーナ・いわて県民情報交流センターがレインボーカラーに!
- 「サル痘」の感染に性的指向は関係ありませんし、性感染症でもありません
- 三重県が性的指向や性自認を含むあらゆる差別の解消を目指す包括的条例案を可決
- 大阪のセンターで相談事業を行なう団体「QWRC」への支援のお願い
- 17歳サッカー選手がカミングアウト、英男子プロでは32年ぶり
- 「多様な性にYESの日」に国連がメッセージ、横須賀ではティボディエ邸がレインボー・ライトアップ
- パートナー共済が中部電力ミライズコネクト社と共同でお金とほけんの無料相談サービスと、新総合保障共済をリリース
- カミラ・カベロが「ゲイと言ってはいけない」法案に抗議し、LGBTQ+の子どもたちや家族を守る緊急基金を設立
- 本物のドラァグクイーンが登場する笑いあり感動ありの舞台『リプシンカ』が6月に上演!
- トランスジェンダー差別をなくすためのオンラインイベントが5/17に開催
- 東京都パートナーシップ宣誓制度、11月1日から運用開始へ
- 浜崎あゆみさんがトランスジェンダーのファンへの中傷コメントに「こんな言葉許されないよ」と毅然と反撃
- 名古屋のドラァグクイーン、ライラさんが木下大サーカスの空中ブランコに挑戦
- ゲイバッシングの被害を受けたK-POP歌手・ホランドに人気俳優がエール
- 米大統領報道官に黒人レズビアン女性のカリーヌ・ジャンピエール氏が就任、オープンリーLGBTQとして史上初
- 栄の松坂屋がレインボー垂れ幕&レインボーロードで名古屋レインボープライドを応援
-
4月
- ウォシャウスキー姉妹が『マトリックス』の小道具類をオークション、売上はトランスジェンダー支援団体へ
- 松山市議選でトランスジェンダーの方が当選、四国初
- TRP2022会場の見どころ、楽しみどころをご紹介
- ファミマが全国の店舗でレインボーソックスを発売
- 長谷川博史さんを偲び、ドキュメンタリー映画『私はワタシ~over the rainbow~』が期間限定で無料配信
- NHKがTRP会場に「レインボーどーもくん」を登場させます!&LGBTQ番組を一挙アンコール放送!
- コーチェラのRina Sawayamaのライブが素晴らしかったです
- 沖縄でピンクドット創立10周年を記念したパレードが開催!
- レディー・ガガ、8年ぶりとなる待望の来日公演が決定!
- 英国のLGBTQ国際会議がキャンセルへ…政府のトランスジェンダー差別にコミュニティが反発
- ディズニー後継者がカミングアウト、「ゲイと言ってはいけない」法案を批判
- トランスジェンダーのよだかれん新宿区議が参院選に出馬へ
- 静岡県島田市がLGBTQ専門職員を募集
- ニューヨーク市長がフロリダ州のLGBTQを「歓迎します」との広告を自腹で出稿
- サンマリノで世界初のゲイの国家元首が誕生
- 石川大我議員が、海外で日本人と同性婚した外国人パートナーについても在留特別資格を認めるよう前向きに検討するとの答弁を引き出しました
- 東京レインボープライドの詳細が発表、会場への入場の事前申込は先着順です!
- 今週末の日曜、京都レインボープライドパレードフェス2022開催!
- 今年のグラミー賞のLGBTQ的名場面
- ロンドンに英国初のLGBTQ+歴史博物館がオープン
- いわてレインボーマーチの開催が決定、5月〜6月は東北で4つのパレード
- 尼崎市が、幹部が市職員に性的指向を伏せるよう指導したのをSOGIハラと認定
- 2022年4月1日、LGBTQの歴史に新たな数ページが加わります
- 【同性パートナーシップ証明制度】全国の約50自治体で制度がスタート、人口カバー率が総人口の過半数に
-
3月
- 東京都が性的マイノリティに関する調査結果を公表、「都パートナーシップ宣誓制度」素案への意見募集は4/11まで延長
- 「今夜はゲイナイトです」アカデミー賞授賞式のゲイ的名場面
- レインボーフェスタ和歌山1日目が終了、明日は和歌山初のパレード開催!
- 日本初の同性婚をテーマにした映画祭、招待上映作品と審査員が決定
- ディズニー社内で「ゲイと言ってはいけない」法案への抗議の声、続々
- PrEP導入に向けた意見公募が行なわれています
- 【同性パートナーシップ証明制度】深谷市で本日スタート、そのほか秋田県・秋田市、習志野市、厚木市、姫路市などでも導入へ
- 東京レインボープライドが3年ぶりに代々木公園で開催! 参加には申込みが必要です
- 『チェチェンへようこそ』の監督が語る、ウクライナのLGBTQの未来
- 2021年の新規HIV感染者報告数は昨年よりさらに減少
- 『バズ・ライトイヤー』で同性カップルのキスシーン、ディズニー/ピクサー長編アニメとして初
- アカデミー賞3部門ノミネート、ゲイのアフガニスタン難民を描いた映画『FLEE フリー』が6月公開決定
- 青森県で県営住宅への入居や病院での家族としての扱いが認められることになりました
- 『九州男』かつきママの映画『沖縄カミングアウト物語』がaktaで特別上映、SPトークショーも!
- 欧州のゲイアプリ「ROMEO」がウクライナから避難するゲイやその家族を支援
- 米国で転向療法(コンバージョン・セラピー)による損失が1兆円に上るという研究結果が発表されました
- チリで同性婚がスタート、世界で30ヵ国目
- 米ディズニーが「ゲイと言ってはいけない」法案への反対を表明しました
- LUSHが同性婚法制化に向けた啓発キャンペーン「結婚の自由をすべての人に」を3/17からスタート
- フロリダ州の「ゲイと言ってはいけない」法案に各方面から非難の声、高校生の抗議デモも
- 大阪で多様性についての企業シンポジウムが開催、W大阪のゲイの社員も登壇
- 【追悼】90年代からHIV陽性であることをカムアウトして活動してきた偉人、長谷川博史さん
- 【同性パートナーシップ証明制度】越前市、八潮市、厚木市、海老名市、綾川町、宇多津町、まんのう町など
- ウクライナの10代のトランス男子が語る希望:「戦争が終わったらみんなでこの国を立て直そう。そして僕は性別変更するんだ」
- コルトン・アンダーウッドが婚約!
-
2月
- トランス女性が凍結精子でもうけた子を認知する権利、東京家裁が却下
- 国連合同エイズ計画がウクライナのHIV陽性者の治療が中断なく継続することを求める声明を発表
- 国連でも活躍する団体がウクライナのLGBTQへの緊急支援を呼びかけ
- 【同性パートナーシップ証明制度】函館市、帯広市、苫小牧市、埼玉県児玉郡、湖西市、丹波篠山市など
- 町田市の東友美市議が再選を果たしました
- ウクライナのLGBTQ団体:「私たちは決してあきらめない」
- 高知市役所にレインボーカラーの階段が登場
- 大阪府茨木市が同性カップルの公正証書作成費用を助成へ
- 婚姻届の受理を求めて提訴した日台同性カップルを応援する合同記者会見が開かれました
- 日本で暮らす同性カップルに密着した番組が2/25、関西テレビで放送
- 世田谷区が災害義援金についても同性パートナーにも平等に配分する方針を示しました
- 【同性婚訴訟】関西訴訟が結審、6月20日に大阪地裁で判決へ
- 伝説のゲイ雑誌『BUTT』が10年ぶりに復活、ボッテガ・ヴェネタのパートナーシップにより
- 【北京五輪】"チームLGBTQ"は金4銀2銅3、36名中14名がメダルを獲得しました
- 【北京五輪】ノンバイナリーとして初の冬季五輪出場選手となったティモシー・レデューク、フィギュアペアで8位入賞
- 『エターナルズ』未公開シーン:ファストスは息子との会話から最終作戦を思いついていた
- HIV感染の米女性が幹細胞移植後に治癒、世界で3例目
- 米国でLGBTQと自認する人の割合が過去10年で倍増、Z世代では21%
- 那覇市が4月から同性パートナーシップ証明制度を拡充、コロナ傷病手当金や扶養手当を支給へ
- 【同性パートナーシップ証明制度】栃木県も導入へ、江別市、たつの市も
- 【同性パートナーシップ証明制度】秋田県が新年度から、秋田市も2022年度中に導入へ
- 横浜家裁が同性カップルの内縁関係認めず、財産分与申立てを却下。批判の声、続々
- 【北京五輪】ギヨーム・シゼロン選手が悲願の金メダル
- 【同性パートナーシップ証明制度】東京都が制度の素案を発表、意見募集中
- 【バレンタインデー】今夜23:05からEテレで『弟の夫』『カミングアウト・レターズ』など紹介
- 東京都が性的マイノリティ関連施策案を公表、意見募集中
- 【バレンタインデー】バンコクで同性カップルにも結婚証明書を発行するイベントが企画されました
- 【同性パートナーシップ証明制度】関市が岐阜県で初めて導入へ、熊本市と鹿児島市が連携を開始
- 沖縄県中城村、同性カップルにも挙式費用最大10万円を助成へ
- iPhone用の次期OSで、妊娠した男性などの絵文字が追加されます
- 【北京五輪】フィギュア男子の素晴らしい戦い――その中にゲイの選手やコーチの活躍も
- 【同性婚訴訟】国側が「同性カップルには"社会的承認"がないから結婚できなくてよい」との驚きの主張を展開、原告側は「差別の容認だ」と反論
- 今年のアカデミー賞にノミネートされたLGBTQ関連映画は?
- 【北京五輪】「チームLGBTQ」の一人、イレーン・ビュスト選手が前人未到の記録を打ち立てました
- 【北京五輪】米国のブリタニー・ボウ選手が開会式で旗手をつとめた唯一のOUTアスリート
- 【同性パートナーシップ証明制度】青森県が2月7日から導入、和歌山県橋本市も10月から
- 【更新】北京五輪に出場するLGBTQの選手は少なくとも36名
- 世田谷区が4月から同性パートナーにも災害弔慰金を支給
- 【追悼】伝説のゲイ映画『ピンクナルシス』のジェームズ・ビドグッド監督
-
1月
- 【同性パートナーシップ証明制度】福岡県、東京都多摩市、神奈川県綾瀬市・寒川町など
- 日台のゲイカップルを追った番組が1/31にBS1で放送
- リアーナの下着ブランドがバレンタインに男性向けランジェリーをリリース
- プロレスラーのAC Mackがゲイとして初の世界チャンピオンに
- 【追悼】世界的なファッションデザイナー、ティエリー・ミュグレー
- 腸内環境が悪いとHIVに感染しやすくなるとの研究結果が発表
- 米国初のゲイのフィギュア選手として平昌で活躍したアダム・リッポンが結婚
- 台北でLGBTQのためのスポーツ競技大会「アジア・プライド・ゲームズ」がキックオフ
- フランスでゲイ・バイセクシュアル男性の献血に関する差別が全面的に撤廃
- 荒川区議の「同性カップルは子を産まない」「男女の結婚という「標準的な形」を保護すべき」などの投稿が波紋
- 同性カップルが内縁関係を解消した後の財産分与請求権をめぐる初の司法判断が下されます
- 【追悼】フロリダ州の同性婚裁判を勝訴に導いた原告の一人、ジョージ・ディアス=ジョンストン氏
- Out Asia Travelの小泉伸太郎さんが「Attitude101」に選ばれました
- 『月刊TENGA』が同性パートナーシップ証明制度を特集
- MJロドリゲスがトランスジェンダーとして初めてGG賞主演女優賞を受賞
- 群馬県大泉町の議場でブラジル人の同性カップルが挙式、町長さんが祝福
- ニューヨークでモデルとして活躍する柳喬之さんが、ゲイとして地元紙に掲載
- 台湾で初めて男性カップルの養子縁組が認められました
- 【同性パートナーシップ証明制度】鹿児島市、所沢市など全国6自治体でスタート
-
12月
-
2021
-
12月
- ファミリーシップ制度導入自治体によるオンラインサミットが開催されました
- 日本と台湾の同性カップルが台湾での婚姻届の受理を求めて訴えを起こしました
- 米FDAがPrEPの注射薬を初めて承認、HIV感染を劇的に減少させるブレイクスルーに
- ageHa GAY NIGHT the FINAL “GLITTER BALL”:前売は12/23から、GX3が招待券付き商品を販売!
- 【追悼】涙なしには聴けないゲイアンセム「Smalltown Boy」の生みの親、スティーブ・ブロンスキ
- 人権週間に合わせ、あらかわ遊園や日光市役所がレインボーにライトアップ
- 今週末、PrEPに関する2つのオンラインイベントが開催
- チリの国会で同性婚法案が承認、いよいよ同性婚が実現へ
- 【同性パートナーシップ証明制度】東京都が2022年度内に導入へ
- 東京レインボープライドが来年4月、3年ぶりにリアル開催!
- 福井県越前市が市役所の大階段をレインボーカラーにデコレーション
- 【同性パートナーシップ証明制度】秋田県も導入を検討
- 大阪でもLGBTQセンター設立へ、虹色ダイバーシティがアナウンス
- 名古屋でLGBTQの落語が聞けます
- 【同性パートナーシップ証明制度】富山県も導入を検討、実現すれば中部地方初
- 【同性パートナーシップ証明制度】12月1日、山梨県初の甲州市など全国6自治体で導入、総社市などではファミリーシップも
- うつや発達障害、HIV陽性などのLGBTQも安心して利用できる福祉事業所が12/14にオープン
- 今年の世界エイズデーのトピックをまとめてご紹介
-
11月
- 岡山で中国地方初となるパレード「ももたろう岡山虹の祭典」が初開催されました
- 【追悼】ミュージカル界のレジェンド、スティーブン・ソンドハイム
- 12/11、ピンクドット沖縄2021が那覇・琉球新報ホールで開催
- タイ政府がいよいよ「シビルパートナーシップ法」を国会に提出
- 横山久美さんが結婚を発表、「たくさんの方々に日本の現状を知っていただきたい」
- フレディ・マーキュリーの人生の最後の数年間を描いたドキュメンタリーがBBCで放送
- 12/18、大阪でひさしぶりにビッグなパーティ「Rainbow × Christmas」が開催!
- 岡山のパレードに虹トラ登場、ギルバート・ベイカー財団からメッセージも
- 米国会で亡くなった46名のトランスジェンダーの名前が読み上げられました
- 【同性パートナーシップ証明制度】青森県が早期導入を目指す意向、実現すれば北日本初
- 【同性パートナーシップ証明制度】福岡県が導入の意向、三原市や飯能市でも導入へ
- 11月22日は「いいふうふの日」、今年も結婚の平等についての様々な催しが開かれます
- IOCがトランスジェンダーなどの選手の国際大会への参加資格についての新指針を発表
- MTVヨーロッパ・ミュージック・アワードがハンガリーで開催、LGBTQコミュニティへの支援として
- BS1スペシャル「カミングアウトの“向こう側”」、21日に放送
- 2025年のワールドプライドが台湾で開催決定、東アジアで初
- 静岡県浜松市がアウティング禁止を盛り込んだ差別禁止条例を制定へ
- オンライン講座「音楽に於けるクィアカルチャーとセクシュアルアイデンティティ」のご案内
- EY Japanの貴田守亮さんが英INvolveの「100 LGBT+ エグゼクティブ」第1位に選出されました
- HIVを完治させる技術が開発へ
- サマンサは僕らを見捨てていなかった!
- 米海軍が補給艦をハーベイ・ミルクと命名
- 誰もが性的マイノリティになる可能性がある!?
- 九州レインボープライド、奈良レインボーフェスタが開催されました
- 英国がアフガニスタンからLGBTQを救出しました
- クリステン・スチュワートが同性婚へ
- 11月20日の「国際トランスジェンダー追悼の日」、日本初のトランスマーチが新宿で開催
- 俳優のカル・ペンがカミングアウト
- F.C.大阪がLGBTQ支援のスペシャルマッチを開催、選手がレインボーマスクで入場
- 丸亀レインボープライド2021が開催されました
-
10月
- Happy Pride! 台湾のオンラインパレードが開催中
- 豪Aリーグのジョシュ・カバッロ選手がカミングアウト
- トランス男性であることをカムアウトした横山久美選手が婚約へ
- 衆院選×LGBTQ、テレビや新聞はどう報じたか(3)
- 衆院選×LGBTQ、テレビや新聞はどう報じたか(2)
- アメリカで初めて性別欄に「X」と記載したパスポートが発給
- 衆院選×LGBTQ、テレビや新聞はどう報じたか(1)
- 11/3、Living Together「オンラインLIVEショー」をAiSOTOPE LOUNGEから配信!
- 最高裁判所裁判官の夫婦別姓・同性婚へのスタンスは?
- 欧州議会が台湾との関係を強化「台湾はLGBTQの権利の擁護者。称賛されるべき」
- 米アトランタ市議会が10/20をリル・ナズ・Xの日に認定
- G-TOUR@ageHaの全貌が明らかに! ダンスコンテスト応援投票も実施中!!
- 宮城県知事選の候補者アンケート結果が公表されました
- NFLで初めて現役選手としてカムアウトしたカール・ナッシブに新しい恋人が
- 台湾の感動のドキュメンタリー『愛で家族に〜同性婚への道のり』が無料配信!
- 愛知県が犯罪被害者支援条例の制定に向け、骨子案への意見公募を実施中
- オランダで王位継承者も同性婚の権利が認められることに
- 新スーパーマンがバイセクシュアルであることをカミングアウト
- 新木場ageHa「G-TOUR」のダンスチームの応募は15日まで!
- AiSOTOPE LOUNGE 9周年パーティ「FABULOUS AIRLINE」開催決定
- 今日は国際カミングアウトデー、いよいよ『沖縄カミングアウト物語』が21時に公開!
- 北陸初の金沢プライドパレードが開催され、晴天の下、熱い盛り上がりを見せました
- ゲイの金メダリスト、トム・デイリー選手が「同性愛者を死刑にする国は五輪出場を許されるべきではない」とスピーチ
- 史上初! ゲイ男性が『プレイボーイ』誌の表紙を飾りました
- 今週末は大阪と金沢でプライドイベント開催!
- 米国で月に1回注射すればOKなPrEPが承認目前
- 浜松市のトランス男性が、性別適合手術を受けなくても戸籍の性別を変更できるよう家裁に申し立てました
- 国会議員の同性婚へのスタンスが一目でわかる便利ツールがリリース
- オープンリー・ゲイの小原明大長岡京市議が5期目の当選
- 東急ハンズ新宿店が25周年企画でAiSOTOPE LOUNGEやドラァグクイーンとコラボ
- 静岡市が来年4月から同性パートナーシップ証明制度を導入、10月1日には全国9つの自治体で制度がスタート
- アドベンチャーワールドが和歌山と奈良のレインボーフェスタに協賛・ブース出展
- 来年のGW、同性婚をテーマにした初の映画祭が開催
-
9月
- 【追悼】青森レインボーパレードを立ち上げるなどして地方でのLGBTQコミュニティの可能性を切り開いた宇佐美翔子さん
- アメリカの大学のマーチングバンドが感動的なハーフタイム・ショーを披露
- カミングアウトした歌手クォン・ドウン、活動再開へ
- トニー賞でゲイ演劇『インヘリタンス』が作品賞を受賞しました
- ゲイカップルと地下鉄にいた赤ちゃんが家族になるまでの本当にあった奇跡の物語『ぼくらのサブウェイ·ベイビー』について
- COVID-19サバイバーズ・グループ東京の中間報告会が開催
- スイスで国民投票が実施された結果、同性婚が正式に承認されることになりました
- 全国でHIVや梅毒の郵送検査無料キャンペーンを実施中
- 台北の裁判所が、性別適合手術なしで性別変更を認める判決を下しました
- 「エルヴァイラ」ことカッサンドラ・ピーターソンがカミングアウト
- 『クィア・アイ in Japan!』出演のKanさんが英国に移住し、結婚しました
- 金沢プライドウィークがスタート、JALが小松空港でPRも
- ベルリンの教会でレザーマンたちのクラシックコンサートが開催されました
- リル・ナズ・Xがアルバム発売時、LGBTQやHIVの団体へのチャリティを実現
- 【追悼】『SATC』でゲイのスタンフォードを演じたウィリー・ガーソン
- 【追悼】レズビアンのパフォーマー、イトー・ターリさん
- 【追悼】トム・フォードの夫であり伝説的なファッション・エディターだったリチャード・バックリー
- ル・ポールが偉業を達成――エミー賞のトピック総まとめ
- 25周年を記念するさっぽろレインボープライドが晴れやかに開催
- ゲイゲームズ香港、2023年11月に延期へ
- コロラド州のジャレッド・ポリス知事が同性パートナーと結婚
- LGBTQが職場でセクハラを受けやすい実態が明らかに
- 【同性パートナーシップ証明制度】福岡県、甲州市、唐津市が導入へ
- 立憲・枝野代表がLGBTQ担当閣僚の設置を表明、プライドハウス東京レガシーを視察後
- 日光市の同性パートナーシップ証明第1号はカナダで結婚したゲイカップル
- リル・ナズ・Xやトロイ・シヴァンといったゲイ・セレブがMETガラで注目を集めました
- リル・ナズ・X、MTVアワードのステージでHIVについてメッセージ
- リル・ナズ・XがMTVアワードでVIDEO OF THE YEARに輝きました
- 金沢レインボープライド、パレードなど一部イベントを10月に延期へ
- ドラマ『glee/グリー』のリバイバル版が制作されるかもしれません
- プライドハウス東京レガシーが「LGBTQ+いのちの相談窓口」を開設
- 性的指向や性自認についての侮辱「SOGIハラ」で初の労災認定
- 札幌市がデジタルサイネージでのLGBT支援&テレビ塔ライトアップを実施
- 『マトリックス レザレクションズ』予告編に複数のゲイの俳優が登場
- 【追悼】ガガの「Born This Way」にインスピレーションを与えたゲイ賛歌「I Was Born This Way」を歌ったカール・ビーン
- ゲイクラブ界の重鎮がゲスト出演するトークショーがDOMMUNEで配信
- 台湾同志遊行、初のオンライン開催へ
- 栃木県が「性の多様性条例」を制定へ
- 同性パートナーの扶養を認めないのは憲法違反だと訴える裁判が始まりました
- 鹿児島市が「パートナーシップ宣誓制度」を来年1月から導入、市議会での差別発言を乗り越えて実現へ
- 映画『ジェンダー・マリアージュ』が今夜、無料配信されます
- リル・ナズ・XがLGBTQの自殺防止に取り組む団体から表彰
- 沖縄県労働金庫が教育ローンの利用を同性カップルや事実婚のカップルにも広げました
- パラリンピックで36名の「チームLGBTQ」が活躍、メダルの総数は25個に
- ゲイの閣僚ピート・ブティジェッジと夫チャスティンが2児の親に
- 米プロ野球界で初めて現役選手がカミングアウト
- レディ・ガガ、クィア・アーティストが多数参加するアルバムを2枚同時リリース
- エルトン・ジョンが、たくさんのクィア・アーティストとコラボしたニューアルバムをリリース
- 「あなたはひとりじゃない」と書かれたレインボーカラーのトラックが登場
- 車いすバスケットボール女子英国代表のロビン・ラヴ選手「LGBTの障害者がメインストリームに受け容れられたのは素晴らしいこと」
- 三重県第1号カップル「コロナで入院した時を考えて」パートナシップ宣誓
-
8月
- さっぽろレインボープライド、オンライン開催へ
- ロック・ハドソンをフィーチャーした番組「エイズの衝撃〜スターの告白が世界を変えた〜」が今夜放送
- 佐賀県が同性パートナーシップ証明制度を開始、県単位では九州初
- 九州レインボープライドがオンライン開催決定、岡山は延期に
- オープンリー・ゲイのリー・ピアソン選手が金メダルを獲得し、LGBTQの受容を世界に訴えました
- 石岡瑛子展がオンラインで公開、hossyさんやドリアンさんが出演するトークセッションも
- パラリンピック開会式にはるな愛さん、想真さんらが出演
- 2020年の新規HIV感染報告数が4年連続で減少、発症してわかる人の割合は増加
- 東京パラリンピックに出場するLGBTQアスリートは少なくとも30名、リオの2倍以上
- 米政府高官が新学期を前に、トランスジェンダーの生徒に支援のメッセージ
- 三重県、宇部市、入間市が9月1日から同性パートナーシップ証明制度を開始、倉敷市も年内に導入
- 英国のトップモデル、リリー・コールがカミングアウト
- エイズの流行開始から40年を経て、ようやくHIVワクチンの実用化が見えてきました
- リル・ナズ・Xが恋人の存在を明らかにしました
- カナダが2万人のアフガン難民の受入れを発表、LGBTQも対象
- 中山咲月さんがトランス男性かつ無性愛者であることをカミングアウト
- 日テレがLGBTQスポーツメディア「Outsports」編集部にインタビュー
- コペンハーゲンでワールドプライドが開幕
- 台湾とマカオの同性カップルの結婚が正式に認められました
- 新木場「STUDIO COAST」が来年1月閉館へ
- 『バットマン』の相棒・ロビンが、ついにカミングアウト
- ナスダックが上場企業にマイノリティの役員の登用を義務付けます
- 『九州男』のマスターのドキュメンタリー映画が今秋公開、感涙必至のカミングアウトストーリー
- ロンドンのクラブ「ヘブン」がワクチン接種会場に。一方、ロンドンのパレードは中止に…
- フランスのスポーツ担当大臣「性別移行をしても、スポーツから排除されることは一切ない」
- 【東京五輪】男子4×400mリレーでオランダのアンカーをつとめた選手など、LGBTQアスリートが続々とメダルを獲得
- 【東京五輪】トム・デイリーが2つめのメダル、感動のコメントも
- ドラァグクイーンが曽根崎のお初天神で打ち水
- 【東京五輪】英国のトム・ボスワース選手「『彼はいい選手だ、そしてゲイでもある』と言われたい」
- 旭川の道議補選にトランスジェンダーの夢月萌絵氏が出馬表明
- 【東京五輪】イタリアのルッチラ・ボアリ選手も銅メダル獲得後にカミングアウト、その他LGBTQ関連トピック
- 【東京五輪】ローレル・ハバード選手の健闘を讃える声、続々
- 東京都新宿東口検査・相談室で7月30日に告知を受けた方へ
- 【東京五輪】コンビニのおにぎり開封失敗動画で話題になった女性リポーターはレズビアンの方
-
7月
- アリアナの兄フランキー・グランデが婚約、「結婚式はオタクっぽくしたい」
- 【東京五輪】カンボジアの孤児を引き取り、高飛込アメリカ代表に育て上げたゲイのパパ
- サンフランシスコで2年ぶりにストリートフェスが開催されました
- 【東京五輪】トランスジェンダーの審判員も史上初参加、カナダのキンバリー・ダニエルズさん
- 秋田県がLGBTQ差別禁止条例を制定へ
- ラッパーのダベイビーによる差別発言を、デュア・リパやエルトン・ジョンらが非難
- 【東京五輪】女子クオドルプルスカル銀メダルのポーランドの選手がカミングアウト
- 『ジャングル・クルーズ』でディズニー映画初のカミングアウトのシーン
- ハンガリーで史上最多の3万人がパレード、反LGBTQ法への抗議として
- 【東京五輪】高飛び込みのトム・デイリー選手が念願の金メダルに輝きました
- 『13の理由』俳優のトミー・ドーフマンが女性にトランスしたことをカミングアウト
- 米最大規模のLGBTQ向け高齢者施設がテキサス州に設立
- 【東京五輪】史上初めてトランスジェンダーの選手が五輪でプレーしました
- 【東京五輪】開会式で旗手をつとめたLGBTQ選手は6人
- 【東京五輪】MISIAさんが五輪開会式にレインボーカラーの衣装で登場!
- LGBTQ高齢者や障害者のための介護・福祉サービスが続々登場、ゲイフレンドリーなシニアハウスの第2回内覧会も
- さっぽろレインボープライドが駅前通地下広場でイベントを開催
- 元「WASSUP」のジエと、ラッパーのAQUINASがカミングアウト
- 9月26日に北陸初のパレードが金沢で開催、20日には岡山でも
- トランスジェンダーを公表する選手の大会出場に関する特別ウェビナーが開催
- EU欧州委員会が、反LGBTQ政策のハンガリーとポーランドに法的手続きを開始
- 豊田スタジアムがレインボーカラーにライトアップ
- 李琴峰さんの『彼岸花が咲く島』が芥川賞を受賞
- 東京五輪に出場予定のLGBTQのアスリートは少なくとも131人、史上最多記録を更新
- 『POSE』のMJロドリゲスがトランスジェンダーとして初めてエミー賞主演女優賞にノミネート!
- 80年代のエイズ禍に翻弄されるゲイの若者たちを描いたドラマ「IT’S A SIN」配信決定!
- トビリシ・プライドが妨害された翌日、7000人の市民が議事堂前でLGBTQへの連帯を表明
- クオモNY州知事の娘ミカエラがデミセクシュアル・カミングアウト
- 英政府が過去のLGBTQ差別待遇に対して公式に謝罪
- 2024年、ニューヨークにAmerican LGBTQ+ Museumが設立
- ヴィッテルスバッハ家の家長、バイエルン公フランツがカミングアウト
- 米国務省、パスポートの性別欄のサードジェンダー表記を検討
- 茨城県と県内17団体がLGBTQを含めたダイバーシティ宣言を発表
- ブラジル大統領候補で現州知事であるエドゥアルド・レイテ氏がカミングアウト
- 北陸三県初! 金沢市で同性パートナーシップ証明制度がスタート
- 7月4日は都議選:LGBT法案や同性パートナーシップ証明制度への各党・候補者の意見は?
-
6月
- 中国女子サッカーの李影選手がカミングアウト
- カリフォルニア州がLGBTQ差別を容認する州法を制定した州への公費での渡航を禁止
- リル・ナズ・XがBETアワードで男性とキスするパフォーマンスを披露
- 米最高裁がトランスジェンダーのトイレ使用制限は違憲であると裁定
- 【プライド月間】クイーン・ラティファがついにカミングアウト
- 【プライド月間】ニューヨークで2年ぶりにプライドマーチ開催、小樽でも
- 新進気鋭の若手サックス奏者・中山拓海さんがカミングアウト
- 【プライド月間】川越の老舗和菓子屋と古民家が取り組むLGBTQ支援
- 『ハイスクール・ミュージカル:ザ・ミュージカル』主演のジョシュア・バセットがカミングアウト
- マドンナがサプライズでニューヨークのプライドをお祝い!
- 【プライド月間】『セサミストリート』でゲイカップルとその子どもが準レギュラーに
- ハンガリーの反LGBTQ法への抗議として、ドイツ各地がレインボーカラーに
- うつや発達障害があるLGBTQも安心して利用できる就労移行支援事業所が開設へ
- 英国でアラン・チューリングの新紙幣が発行、レインボーカラーの巨大なアート作品も
- バイデン大統領がカール・ナッシブ選手と横山久美選手のカミングアウトを祝福しました
- エミー賞が、ノンバイナリーの俳優に配慮した新規則を承認
- 東京五輪が史上初めてトランスジェンダー選手を迎える大会へ
- カール・ナッシブ選手がNFL現役選手として初めてカミングアウト
- 【同性パートナーシップ証明制度】佐賀県は8月中、豊田市、さぬき市、大津町なども導入へ
- フロリダ州でパレードの隊列にトラックが…テロかどうかは不明です
- 【プライド月間】ホワイトハウスで初のLGBTQ歴史展開催、廊下もレインボーカラーに
- ハンガリーの反LGBT法への抗議として、ミュンヘンのアリアンツ・アレナがレインボーに
- 元なでしこジャパンの横山久美選手がトランス男性であることをカミングアウト
- 人類初のサイボーグ化を成し遂げたことで話題のピーター・スコット・モーガン博士はゲイの方でした
- 元日本一女子ボクサーの菊池真琴さんがカミングアウト
- ニュージーランド国会で同性婚賛成の名スピーチをした元議員が日本にメッセージ
- LGBT法の制定を求めてきた方たちが記者会見を行ないました
- 米教育省、学校でのトランスジェンダー生徒のスポーツ参加を支援する方針を発表
- 今晩23時、ストーンウォールのドキュメンタリーが放送!
- 【プライド月間】JALがSNSのアイコンをレインボーに
- LGBT新法が提出されることなく今国会が閉会、差別発言だけが残されました…
- 世田谷区が学校医や水防従事者などの同性パートナーに遺族補償、日本初の快挙
- 【プライド月間】オランダに世界一の長さとなるレインボーカラーの自転車道が出現
- カマラ・ハリスが初めてプライドパレードを歩いた副大統領になりました
- G7首脳共同宣言がLGBTQ支援や差別撤廃に言及
- 『アメアイ』で有名になったデヴィッド・アーチュレッタがカミングアウト
- オーランドの悲劇から5年――ゲイクラブ『パルス』が国定記念建造物に
- フィギュア全米王者ジェイソン・ブラウンがカミングアウト
- 劇団フライングステージが「座・高円寺」で公演
- 最新の世論調査でアメリカ人の70%が同性婚を支持、共和党支持層でも賛成派が過半数に
- 劇場版『きのう何食べた?』、11月3日(水祝)公開決定!
- 駐日英大使「性的指向や性自認を問わず自由に生活できる社会に至るためには、政治的主導も不可欠です」
- レインボークッキーを焼いたテキサスのお店で起こった奇跡
- LGBT法案の国会提出を求める弁護士らの署名が1285筆に上りました
- 松山市でパートナーシップ制度の実現を求める署名がスタート
- 雑誌やWebメディアでもLGBT法案の今国会での成立を求める記事が続々と
- 佐賀県が同性パートナーシップ証明制度導入へ。東京都では都議会本会議で請願採択
- 山口県弁護士会が国に同性婚の承認を求める声明を発表
- チリのピニェラ大統領が同性婚推進を表明
- 【時間変更】渋谷ハチ公前で6/6、今国会でのLGBT新法制定を求めるDJイベントが開催
- LGBT法案の今国会中の提出を求め、大勢の弁護士が連名で緊急声明を発表
- LGBT自治体議連が自民党の党三役への面談を申し込みました
- 凍結精子で生まれた実の子の認知届が受理されず、レズビアンカップルが提訴しました
- パナソニックがLGBT平等法への賛同を表明
- 北海道に続き、東京、大阪、愛知など各地の自民党支部へ要望書が提出
- 6月は「東京都HIV検査・相談月間」です
- 大阪観光局がプライド月間を祝うキャンペーンを実施、観光局・DMOとして日本初
- IOCがLGBTQ差別禁止を改めて訴える声明を発表
- 全国の新聞社が社説で「差別は看過できない」と述べ、LGBT法の制定を支持
- 新経連が「あらゆる性的指向・性自認の人々が安心して暮らし、活躍できる社会づくりに全力を」との声明を発表
- トランス女子中学生を描いた海外ドラマが6/4放送スタート
- 北海道LGBTネットワークが与党議員の差別発言に抗議
- 東京都が同性パートナーシップ証明制度の導入を検討することを表明
- 元北海道職員が、事実婚カップルに支給される扶養手当等が認められないのは憲法違反だとして提訴
- アメリカ大使館公式Twitterにレインボーフラッグが戻ってきました
- バイデン大統領がプライド月間に際し、平等法の実現とトランスジェンダーの保護を宣言
- 今日からプライド月間。GoogleでLGBTQと検索してみると…
- 杉山文野さんがJOC次期理事へ
-
5月
- 日テレのお天気キャラクターとしてレインボーカラーの「にじモ」が誕生!
- LGBT差別発言の撤回と謝罪を求める署名が提出されました
- 住まいを失ったLGBTQにシェルターを提供する団体へのチャリティグッズが販売中
- ニュージーランド国会で同性婚賛成スピーチをした議員さん「日本からのフォロワーがたくさん!」
- LGBT差別に抗議する24時間シットインが開催、失われた命への黙祷も
- 外国人の日本語弁論大会で同性愛者の方が優勝
- LIFULLが子育てするゲイカップルをCMに起用しました
- 沖縄弁護士会が与党国会議員による差別発言に抗議
- LGBT差別に抗議する24時間シットインが緊急開催
- LGBT法案の今国会への提出が見送られると報じられました
- 今夜放送! Eテレ『バリバラ』 #同性カップルSP
- ついにゲイフレンドリーなシニアハウスが実現! 内覧会が開催されます
- レディ・ガガ『Born This Way』から10年、LAのウェストハリウッドが5月23日を「Born This Way Day」に制定
- 台湾で同性婚2周年、LGBTQ団体「民法で結婚の平等の保障を」
- LGBT法案をめぐる自民部会が紛糾、今国会での成立は難しいとの見方も
- ろう者のLGBTQの方たちが「差別は許せない」と手話で抗議
- リル・ナズ・XがUGGのプライド・キャンペーンに登場
- 東京レインボープライド、プライドハウス東京も抗議声明
- 山谷議員のトランスジェンダー差別発言に対する抗議集会が行なわれました
- 映画『カランコエの花』が明日まで無料公開、「すべての人が、自分らしく生きられる社会のために」
- 謝罪と撤回を求める署名が50000筆超え、LGBT法連合会も緊急声明
- LEGOが初めてLGBTQのミニフィギュアのセットをリリース
- 【署名】「LGBTは種の保存に背く」「道徳的にLGBTは認められない」発言の撤回と謝罪を
- 自民党内の会議で「道徳的にLGBTは認められない」「人間は生物学上、種の保存をしなければならず、LGBTはそれに背くもの」などの差別発言
- ビリー・ポーターがHIV陽性であることをカミングアウト
- Vans(ヴァンズ)が「Pride Month 2021」コレクションを発表、東京レインボープライドにも寄付
- 都内の同性パートナーシップ証明制度導入自治体が連携、都営住宅入居などを都に要請へ
- 三重県議会が住所無断公開を「人権侵害」と認定し、議員の人権意識高揚を図る決議を採択
- 今年のApple Watchプライドエディションは黒人トランス女性をフィーチャー
- 横須賀市長が「多様な性にYES!」のメッセージを贈りました
- 国際反ホモフォビア・トランスフォビア・バイフォビアの日、ブリュッセルのEUビルがレインボーカラーにライトアップ
- 同性婚承認国で結婚した外国籍の同性パートナーに「特定活動」の在留資格を付与へ
- 世界初! 英ウェールズでノンバイナリーの市長が誕生
- LGBT法の基本理念に「差別は許されない」と明記することで与野党が修正合意
- 名古屋で日曜、レインボープライド(オンライン)とIDAHOの街頭アクション+ミニパレードが開催
- バイデン大統領が医療におけるトランスジェンダー差別禁止を再び確証、コミュニティから賞賛の声
- エルトン・ジョンとオリー・アレクサンダーがペットショップ・ボーイズの名曲『It’s a Sin』を演奏
- 「結婚の自由をすべての人に」九州訴訟で熊本のこうぞうさんが意見陳述
- 美輪明宏さんが6年ぶりにNHK『SONGS』に出演します
- LGBT法をめぐる与野党の協議が山場を迎えています
- 住所無断公開の三重県議が、同性カップルに直接謝罪しました
- 浦安市で同性パートナーシップ証明制度がスタート
- ゲイのキャラクターの描かれ方が問題だとして『ドラゴン桜』が炎上中
- 【追悼】レッドリボンの生みの親、パトリック・オコンネル
- ビービー・レクサが自身のセクシュアリティを明らかに
- 台湾とマカオの同性カップルが同性婚訴訟で勝訴、婚姻届を受理するよう求める判決が下りました
- 大学教授らが、住所無断公開の三重県議に「辞職勧告を含めた厳しい措置を」と求めました
- LGBT法に「差別禁止の明記を」と訴える記者会見が開かれました
- 最高裁長官が同性婚について「広い視野で判断を示すことが求められている」と語りました
- 沖縄県議の7割が同性婚に賛成していることが明らかに
- LGBTQ差別を容認し、同性婚等の諸権利運動を阻む可能性のある法案にNO!を
- 【追悼】ぷれいす東京「Gay Friends for AIDS」コーディネーターとして活躍した桜井啓介さん
- イシヅカユウさんがトランス女性の役を演じる映画『片袖の魚』が7/10公開決定
-
4月
- 延岡市で同性パートナーシップ証明制度がスタート、延岡城跡のライトアップも
- 4月30日、Eテレで「11歳、僕はゲイとして生きていく」という番組が放送
- 「性別がない」井手上漠さんのフォトエッセイが反響を呼んでいます
- 今年のアカデミー賞はLGBTQ的にどうだったのか?
- 秋元才加さんが出演する「スーパーフラットな結婚トークライブ」が4/29に開催
- ソニー・インタラクティブエンタテインメントがバーチャル背景・壁紙を配信中
- GAPがLGBTQヒストリーをデザインしたプライドコレクションを発表
- 丸井グループが東京レインボープライドに協賛、マルイ・モディ各店で店内POPをレインボーデザインに
- GYAO!で名作映画が無料配信中!
- プライドウィークに合わせ、Instagramがレインボーカラーに!
- レインボー・リール東京が7月に開催決定!
- 住所無断公開の三重県議が謝罪しました
- ファミチキがレインボーカラーに! 東京レインボープライドを祝して
- Hotels.comがTRPに協賛&独自のキャンペーンを展開
- 2020年の新規HIV感染者数が前年から2割近く減少、コロナ禍による検査休止が影響か
- 給付金除外の性風俗業者の訴訟で国が「本質的に不健全」と反論、職業差別だと炎上中
- 三重県議会代表者会議が小林県議に説明を要求、自民党県議団長が「議会」に謝罪
- 恋愛リアリティ番組『バチェラー』の主役も務めた元NFL選手がカミングアウト
- イケアがレインボーカラーのアイテムを国内で発売
- スターバックスが色が変わるカップを発売、売上の一部は中高生向けLGBT授業へ
- LGBTQ支援企業「IRIS」が不動産仲介の全国展開を開始しました
- 世界の同性婚20周年の日にパートナーシップ制度を導入した大和市をオランダ大使が表敬訪問
- 電通「LGBTQ+調査」の結果、同性婚に賛成する方が82.2%に上りました
- TRP2021にテリー伊藤さん、夏木マリさん、YOUさん、アンミカさん、SHELLYさんら著名ゲスト16名が出演!
- デミ・ロヴァートがパンセクシュアルであるとカミングアウト
- ディズニーストアがレインボーカラーのプライド・コレクションを発売へ
- 同性パートナーシップ証明制度を導入している阪神間7市1町が連携、転居時の手続きを簡略化
- 徳島県内の全首長に対して同性婚への賛否を聞いた結果、賛成8、反対1、その他16となりました
- 伊賀市長らが「住所公開は人権侵害」として三重県議会に申し入れ
- 同性カップルの住所をブログで晒した三重県議について県議会が経緯調査・対応協議へ
- 初開催の京都レインボープライドパレードに約200名が参加、門川市長もスピーチ
- 「国際トランスジェンダー認知の日」、モデルのKEISHANが素敵な動画をシェア
- 千葉市で配布されるフリーペーパーの4コマ漫画がひどいと炎上しています
- セレーナ・ゴメス、アナ・ウィンターら440名超がトランス女性を支援する声明に署名
- 世界初の同性婚スタートから20周年を迎えた4月1日、同性パートナーシップ証明制度承認自治体が100に達しました
-
3月
- 北海道の同性婚訴訟の原告が控訴、「一日も早く国会で同性婚を承認してほしい」
- 来年度から高校の公共や家庭科の教科書に「LGBT」が掲載されます
- 米国史上初、トランスジェンダーの連邦政府高官が誕生
- 英国の新50ポンド紙幣がチューリングの誕生日に発行されます
- トランス男性やパンセクシュアルの方を含む8名の性的マイノリティが同性婚訴訟に加わりました
- マースクの「レインボーコンテナ」が横浜港に到着
- 沖縄県知事が「性の多様性尊重宣言」を発しました
- 大分県臼杵市、兵庫県西宮市・猪名川町、宮崎県延岡市、奈良県生駒市が同性パートナーシップ証明制度導入へ
- 胸熱…ナヤ・リヴェラ追悼として『glee/グリー』キャストが再結集
- 石川大我議員の質問に小泉環境相が「同性婚には賛成だ」と答えました
- 明日、LGBTQの平等をめぐる重要なイベントが2つ配信されます
- ゲイの兄のために代理母出産を決意した女性を描くドラマ『サロガシー』が今晩放送
- 「スカイ ウォッカ」が売上の一部を「Marriage For All Japan」へ寄付
- 三重県議会で「アウティング」禁止条例が可決、都道府県で初
- 浦添市議会が「性の多様性条例」を可決、同性パートナーシップ証明制度も
- 「東京都にパートナーシップを求める会」が小池都知事に要望書を手渡しました
- 東北のLGBTQのインタビュー集が刊行されました
- 電話世論調査の結果、同性婚を「認めるべき」との回答が65%、若年層では86%
- 小豆島2町、足柄2市町などが同性パートナーシップ証明制度導入へ
- 3/21、「レインボーフェスタ!オンライン」が開催
- 違憲判決を受けて、同性婚の法整備を訴える世論が高まっています
- 最高裁が、同性カップルも婚姻に準じた関係であり、法的保護の対象になると認めました
- 札幌地裁の画期的な判決に、全国から喜びの声続々
- 「法的に同性カップルが結婚できないのは憲法14条に違反」との歴史的判決。実質的な勝訴!
- 「ワンカップレインボー」が国内販売開始へ、数量限定で4月12日から
- グラミー賞で史上最多のLGBTQアーティストが賞を獲得
- いよいよ明後日、札幌地裁で日本で初めての同性婚に対する司法判断が下されます
- 「世界初のトランス男性議員」細田智也さんが2位で入間市議に再選
- リナ・サワヤマが晴れて「ブリット・アワーズ」にノミネートされました
- 三重県の同性パートナーシップ証明制度は、公正証書の証明も可能に
- EUが「LGBTIQフリーダムゾーン」であると宣言しました
- ゲイ・アーティストが等身大の「スーパー・ゲイ・バービー」を制作
- レディ・ガガが東日本大震災から10年を迎えた日本へメッセージ
- 姫路市、唐津市、大井町が同性パートナーシップ証明制度導入へ
- 米ユニバーサル、ハリウッド大手スタジオとして初めてゲイのロマコメ制作へ
- バイデン大統領、今度はLGBTQの生徒を取り巻く教育環境の改善に着手
- 3/11夜、無料講座「同性パートナーと医療面会、説明、同意」がオンライン開催
- 山形県新庄市で高校生たちが性的マイノリティの写真展を開催
- aktaでオンライン「LIVEショー」開催、エスムラルダさんのショーも
- コロラド州知事が同性パートナーとの婚約を発表
- 孫からのカミングアウトに対するおじいちゃんの返事が素敵すぎると評判に
- 『POSE』シーズン3は米国で5月に放送&シーズン3をもって終了となります
- 91歳の方が一日だけ女装して歌い踊る「ボールルーム」が釜ケ崎に
- バンクシーが旧刑務所の外壁で新作を発表、オスカー・ワイルドへのオマージュとして話題に
- イマジン・ドラゴンズのダン・レイノルズが実家をLGBTQユースのセンターに寄付
- 【追悼】韓国で強制的に除隊させられたトランス女性ピョン・ヒスさんと、済州のパレードの主催者キム・ギホンさん
- 3/6埼玉レインボープライドにりゅうちぇるさんがゲスト出演!
- アメリカのZ世代の6人に1人がLGBTQであるとの調査結果が明らかに
- 埼玉県伊奈町、京都府亀岡市で同性パートナーシップ証明制度スタート
- 今年のゴールデングローブ賞、LGBTQ的には?
-
2月
- 政治家の性差別「ワースト発言」を決める投票が受付中、足立区議や春日部市議の発言もノミネート
- 杉山文野さんが「世界一受けたい授業」に登場、「マイノリティの方との向き合い方」について授業
- 世田谷区が同性パートナーにもコロナ傷病手当金を独自支給する運用を開始
- 米下院でLGBTQ差別を禁止する「平等法」が可決、テイラーやシェールが祝福
- パナソニックがLGBTQをフィーチャーしたショートフィルムを発表
- 衆議院法制局「同性婚の法制度化は憲法上の要請である、との考えは十分に成り立ち得る」
- 日弁連が、事実婚の同性カップルが異性カップルと同等に扱われることを求める意見書を送付
- 同性婚訴訟で永野弁護士が亡くなった原告の佐藤郁夫さんの願いを代弁
- 埼玉県の調査で性的マイノリティの65%が死を思ったことがあると回答
- 災害時の避難所運営マニュアルなどにLGBTQへの配慮を盛り込む自治体は?
- 仙台や松山でも同性パートナーシップ証明制度導入を求める動き
- ドイツのサッカー選手800名以上がアライ宣言
- 「LGBT平等法」署名の締切は明日です!
- 『AERA』にレスリーさん&ジョシュアさんへのインタビューが掲載中
- 国立市が条例を改正し、同性パートナーシップの職員の福利厚生も法律婚と同等に
- 国会で尾辻議員が同性婚について質問、首相は「極めて慎重な検討が必要」
- 【追悼】ゲイのシンガー・ソング・ライター、アリ・ゴールド
- 韓国のクィア映画『ユンヒへ』が青龍映画賞で2部門受賞
- 東京都南新宿検査・相談室が3/6、新宿東口に移転
- HIV/エイズに翻弄されるゲイたちを描いたドラマ『It’s a Sin』が英国で社会現象に
- ニューヨーク州でHIV陽性者がワクチン優先接種の対象に
- 女性へとトランスした元プロレスラーのストーリーが感動的…
- 同性婚訴訟2周年イベント開催、短歌の公募企画も
- ゲイのフィギュア選手として平昌で注目を集めたアダム・リッポンが婚約
- 国分寺マルイの多様性を重視したバレンタイン企画が素敵です
- 函館市が同性パートナーシップ証明制度の導入を検討
- 大阪でLGBTQツーリズムコンファレンスが初開催、ドラァグクイーンも出演
- サンフランシスコにゲイサウナが帰ってきそうです
- 実在のゲイの水球チームを描いた映画『シャイニー・シュリンプス!』が今夏公開
- LUSHがLGBT平等法制定署名への協力を呼びかけ
- プライドハウス東京コンソーシアムが東京五輪組織委に公開質問
- ドイツで185人ものLGBTQ俳優が一斉にカミングアウト
- カントリー界のスター、T.J.オズボーンがカミングアウト
- 新宿区にパートナーシップ&ファミリーシップ証明制度の条例の制定を提案へ
- 秋田プライドマーチが5/22開催決定
- ゴールデングローブ賞で『ザ・プロム』などLGBTQ関連作品が多数ノミネート
- 森会長の“両性”発言に批判が相次いでいます
- 別府でドラァグクイーン多数出演の「十人十色映画祭」開催
- ピート・ブティジェッジ氏の運輸長官への指名が上院で承認、LGBTQ初の閣僚が誕生
- 高知市で「パートナーシップ登録制度」がスタート、初日に3組が申請
- 東京都に同性パートナーシップ証明制度を認めていただきたい!
-
1月
- バイセクシュアル女性の選手がサーフィン界の「アスリート・オブ・ザ・イヤー」を受賞
- 【追悼】マドンナや安室奈美恵さんなどに楽曲提供してきたトランスジェンダーのSOPHIE
- 父親とゲイの息子を描いたドリトスのCMに称賛の声
- 鹿児島市も同性パートナーシップ証明制度導入へ
- 台湾のオードリー・タン氏が「世界一受けたい授業」に出演!
- インドネシアで男性2人が愛し合い、公開鞭打ち刑に…人権侵害だと非難
- アダム・ランバートがプライド月間最大級のコンサートの司会等を担当
- バイデン大統領が米軍のトランスジェンダー差別を撤廃
- 演歌界初! 浜圭介さんが男どうしの恋心を歌う「憧れて」を発表、作詞は湯川れい子さん
- カリスマYouTuberのジョジョ・シワがカミングアウト
- 「Equality Act Japan」が国内外115の団体の賛同を得て世界規模で展開へ
- バイデン政権が米国大使館のレインボーフラッグ掲揚を再び承認、LGBTQ特使も復活
- EY Japanの貴田守亮さんが「傑出したLGBTロールモデル」世界2位に
- さっぽろレインボープライドの活動を評価し、JT北海道が助成
- 『news zero』が月1で生番組を配信、初回テーマはLGBTQで松岡宗嗣さんらがゲスト出演
- バイデン大統領が初日に行なったトランスジェンダー保護施策
- 台湾で国際結婚の制限が撤廃され、日本人との同性婚も可能になりそうです
- バイデン大統領が就任初日にLGBTQ差別禁止の大統領令に署名
- カマラ・ハリスとミシェル・オバマの服を手がけたのはゲイのデザイナー
- 大統領就任式でレディ・ガガとジェニファー・ロペスが熱唱
- 【追悼】ぷれいす東京理事で、同性婚訴訟原告の一人でもあった佐藤郁夫さん
- バイデン次期大統領が史上初めてトランスジェンダーの人物を連邦政府高官に指名
- 足立区がファミリーシップ制度導入へ、全国で2例目
- ドラァグクイーンのジンクス・モンスーンが結婚
- エイズ病棟で亡くなりゆく患者をケアしていた看護師さんが描いたコミック本を翻訳出版しよう
- 「自分史上最高のドラマ」アンケートで『おっさんずラブ』が1位に
- 台湾の高雄市がNYタイムズ「愛すべき場所52選」に入選、LGBTフレンドリーさも好評価
- アマゾンの先住民の村で暮らす若いゲイたちのことが報道されました
- 40年以上連れ添った同性パートナーの火葬に立ち会えず、共同経営の会社も親族に奪われたのは不当だとする裁判で、二審の大阪高裁も原告の訴えを退けました
- アダム・ランバートが1/29、バースデー・コンサートをライブ配信
- 田亀源五郎さんとエスムラルダさんのオンライン・トークイベントが無料開催
- ティルダ・スウィントンがカミングアウト 「いつも自分がクィアだと感じていた」
- バイデン大統領の就任式でガガが国歌独唱、J.Loが音楽パフォーマンス
- 二丁目のシンボル「CoCoLo Cafe」が今月いっぱいで閉店、20年の歴史に幕
- リル・ナズ・Xの「オールド・タウン・ロード」がまたしても史上最高記録を更新
- 日本で初めてカミングアウトした牧師の平良愛香さん
- 英国でコロナワクチン開発に携わってきたゲイのヒーロー
- 明石「LGBTQ+フレンドリープロジェクト」がキックオフ、街中レインボーに
- HIV内定取消訴訟をフィーチャーした舞台『Rights, Light ライツ ライト』が無料配信
- ゲイのスタバ店員と白血病の男の子との心あたたまる友情の物語
- 米ジョージア州上院決選投票の結果がLGBTQコミュニティにもたらす意味
- 広島市ほかで同性パートナーシップ証明制度がスタート
- 今夜の『ねほりんぱほりん』に、二人の母親に育てられている子どもたちが出演
- コロナ禍終息への希望とともに…同じ病院で働くゲイカップルが感動のプロポーズ
- ベルギーの女子テニスのダブルスペアが婚約を発表
- 『クィア・アイ』のジョナサン・ヴァン・ネスが結婚!
- 紅白に杉山文野さんのレインボーファミリーが!
-
12月
-
2020
-
12月
- 年末の総まくりやランキングに登場したLGBT
- 【訃報】“モード界の革命児”ピエール・カルダン
- 同性婚訴訟の弁論でカミングアウトした加藤弁護士へのインタビュー記事が掲載
- 明石市の新制度は「結婚届」を含め、自分の気持ちに合った届出ができます
- エルトン・ジョンが結婚記念日に、ゲイコミュニティへメッセージ
- 【追悼】「ストーンウォール・イン」のGOGO BOY、ボビー・ソレット
- 大和郡山市と清瀬市の市議会で同性婚法制化への意見書が可決
- 「LGBTQの命の神聖さと尊厳」を守る超宗派の宗教者国際会議が発足
- 群馬県で同性パートナーシップ証明制度がスタート、長岡京市、白山市も導入へ
- 来年の東京レインボープライドが4/24〜開催決定!
- 『Drag Race UK』シーズン2のアー写が素敵
- 今年のホリデー映画の中のLGBTQ作品の数が過去最多を記録
- スイスで結婚の平等が認められました
- 「レズやゲイが法律で守られたら足立区は滅びる」が2021年に持ち越したくない「流行禁句大賞2020」にノミネート
- 舞台『チョコレートドーナツ』12月20日に開幕
- 12/19(土)、「U=U」がよくわかるオンライントークショーが開催
- ゲイのブティジェッジ氏が運輸長官に任命、初のLGBTQの閣僚に
- 英国が献血禁止基準を見直し、性別や性的指向による差別を撤廃へ
- 伊賀市のゲイカップルが地元伝統産業とのコラボで「虹焼」や「虹紐」を制作
- 『ル・ポールのドラァグ・レース』がギネス世界記録に認定
- 北見市、唐津市も同性パートナーシップ証明制度導入を検討
- トランス女性がトランス女性の役を演じる映画が公開へ
- 金沢市、岐阜県も同性パートナーシップ証明制度導入を検討
- マニラ市がLGBTQ差別禁止条例を施行、レインボーカラーの横断歩道も
- 米最高裁がトランスジェンダーの自認性でのトイレ使用を認めました
- 兵庫県明石市が全国で初めて「パートナーシップ・ファミリーシップ制度」を導入へ
- 【追悼】70年代からカミングアウトして活躍したプロレス界のレジェンド、パット・パターソン
- シンディ・ローパーがLGBTQユース支援のチャリティイベントを開催
- レインボーカラーのワンカップ大関が発売決定、日本酒として初
- 今年も宮崎県庁がレインボーカラーにライトアップされました
- 原告の同性カップルが法廷で直接思いを語るのは不要だとする東京地裁に抗議の声
- 世田谷区報にパートナーシップ宣誓5周年の記事が掲載
- 『Attitude』誌のアワードでテイラーやデュア・リパ、リナ・サワヤマらが受賞
- 舞台版『チョコレートドーナツ』が開幕延期、Netflix映画配信は7日まで
- 『his』の宮沢氷魚さんが3つの映画祭で新人賞を受賞
- 東北初! 青森県弘前市が同性パートナーシップ証明制度を実現しました
- 同性パートナーを持つ都職員が都の条例改正案に抗議しました
- 男の子がサンタに「神様はゲイの僕も愛してくれる?」と手紙を書き、全米が泣いた
- エレン・ペイジがトランスジェンダーであるとカミングアウト、エリオットへ改名
- Netflix映画『ザ・プロム』が12/4から先行劇場公開!
- 会社からアウティングを受けて豊島区に申立てを行なっていたゲイ男性に、会社が謝罪・和解
-
11月
- 南極で初のプライドが開催されました
- 性的マイノリティに関する意識調査で、同性婚支持が64.8%に
- 11/30夜に「魂の解放!LGBTパレードはこうして生まれた」という番組が放送
- 茅ヶ崎市、東かがわ市が同性パートナーシップ証明制度導入へ
- グラミー賞で史上最多のクィア・アーティストがノミネート
- 【一橋大学アウティング裁判】二審判決についてLGBT法連合会が「極めて遺憾」との声明を発表
- 同性婚実現を求める第2回院内集会が配信、約28,000人が視聴
- レインボーフェスタ和歌山にアドベンチャーワールドがブース出展
- AiSOTOPE LOUNGEが周年パーティの中止を発表
- 【一橋大学アウティング裁判】アウティングは「許されない」としながらも、二審でも大学側の責任は認めず
- 感染症の専門家がゲイセックスでのコロナ感染の可能性を解説
- 雨が降って、虹が出ました−−足立区がパートナーシップ制度を来年度から導入へ
- レスリー&ジョシュアさんが結婚披露宴を開催、小室哲哉さんの演奏も
- 三重県が同性パートナーシップ証明制度を導入へ、高校生も署名を提出
- #いいふうふの日にゲイウエディングの動画が公開されました
- 「クラブはクィア・コミュニティにとってのライフライン」と語る記事が『ニューズウィーク』に掲載
- 国分寺市で同性パートナーシップ証明制度がスタート、鴻巣市でも12月から
- 日系大手企業を含む134社が同性婚への賛同を表明
- 二丁目で第2回コロナ対策勉強会が開催されました
- ブラジルの統一地方選でトランスジェンダーが躍進
- 晴天の下、明石プライドパレードが開催、市長さんもご来場
- Googleで「LGBT」と検索してみてください
- 全日本仏教会がLGBTQシンポジウムを開催し、初めて公に支援を表明
- EUが、LGBTQの権利を保障する新たな指針を策定へ
- 日本で同性婚が実現した場合の経済への影響を分析した初のレポートが発表
- 「LGBT差別は存在しない」発言の春日部市議をワイドショーが的確に批判
- 足立区長がLGBTQの方から話を聞く会を開きました
- 『プリズン・ブレイク』のウェントワース・ミラーが、もう異性愛者の役は演じないと宣言
- HIV陽性のゲイの州議員、車椅子ユーザーのバイセクシュアルの州議員が誕生
- 群馬県安中市、山口県宇部市でも同性パートナーシップ証明制度導入へ
- バンコクでプライドパレードが行なわれました
- 米史上初のノンバイナリーの州議会議員が誕生
- 今年の香港同志遊行はオンラインで開催
- バイデン氏が史上初めて大統領勝利演説でトランスジェンダーに言及
- ハワイ州で28歳のアジア系のゲイが州下院議員に初当選
- 【米大統領選】バイデン&ハリスが勝利! 米LGBTQコミュニティの反応は?
- 11/22、レスリー・キーさんが豪華ゲスト出演のウェディングパーティを生配信!
- 米サンディエゴで初のゲイの市長が誕生しました
- 台北市が外国人同性カップルに豪華仕様の「パートナー記念証」を発行
- 同性パートナーシップ証明制度が始まってから5年が経ちました
- クマ好き必見!のゲイ映画『天空の結婚式』が来年1月公開
- 亡くなった息子に代わってドラァグクイーンのクラブを建て直す母親の映画『ステージ・マザー』、来年2月公開
- 群馬県が同性パートナーシップ証明制度を導入へ
- エイズで亡くなったNFLのスター選手を描く映画が製作へ
- 【米大統領選】黒人ゲイ男性2人が初めて米連邦下院議員に当選
- 【米大統領選】米史上初、トランス女性が州議会上院議員に当選
- 複数の自治体首長選の候補が同性パートナーシップ証明制度の導入を明言
- 今年のピンクドット沖縄は11/28、オンラインで開催
- ニュージーランドで初めてゲイの副首相が誕生
- LGBTQは4倍近くも犯罪被害に遭いやすいことが米調査で明らかに
-
10月
- 千葉県松戸市が同性パートナーシップ証明制度を導入
- 台湾同志遊行に約13万人が参加、世界最大のパレードに
- オーストラリア代表としても活躍した元ラグビー選手がカミングアウト
- 【米大統領選】バイデン氏が大統領就任後100日以内に「平等法」を成立させると公約
- 来年4月4日、京都でレインボーパレード開催!
- 同性婚訴訟・札幌地裁の弁論で、弁護士さんがカミングアウトしました
- 台北市がプライドを前に「Rainbow Cities Network」への加入を発表、アジア初
- 神奈川県三浦市が来年1月から同性パートナーシップ証明制度導入へ
- 足立区でLGBTQの居場所づくりが始まりました
- 大黒摩季さんが、レスリー・キーさんとジョシュアさんへのウェディングプレゼントとして新曲をリリース
- ローマ教皇が史上初めて同性パートナー法を認めるべきと発言
- ニュージーランド国会でLGBTQ議員の占める割合が10%となり、世界一に
- 【足立区議】謝罪後も、続々と批判の声が上がっています
- アベプラで男性の性暴力被害者の貴重な証言が放送されました
- 【足立区議】白石区議が謝罪し、問題発言を議事録から削除
- 世田谷区が初めて、同性カップルも事実婚関係に相当するとの社会通念が形成されていると表明
- 結婚式でレディ・ガガの「Stupid Love」を踊ったゲイの方が素敵!
- オレオが同性愛者と親の関係を描く感動の映像をリリース
- 国会にLGBT差別禁止法の早期制定を求める署名キャンペーンが始まりました
- レズビアンが主役のブロードウェイミュージカル『The PROM』が来年、日本初上演
- 【足立区議】3万3000筆超の署名提出、白石区議が20日本会議で謝罪へ
- いろんなスターたちがカミングアウトデーを祝いました
- 東京都小金井市が10月20日から、栃木県栃木市が11月から同性パートナーシップ証明制度をスタート
- ドラァグクイーンに憧れる男子高校生のミュージカル映画『ジェイミー!』が来年公開!
- 新宿御苑前にLGBTQセンターがオープン、バッハ会長からの祝辞も
- 10月11日「国際カミングアウトデー」を祝し、Netflixがキャンペーン
- 【足立区議】LGBT差別発言の足立区議への抗議集会が北千住で開催
- 10代20代が直面しがちなリスクが浮き彫りに…依存症などに悩む方たちを支援する情報サイトがOPEN
- 沖縄県がLGBT支援宣言、同性パートナーシップ証明制度を検討へ
- 【足立区議】ハッシュタグ「#私たちはここにいる」が素敵です
- 【足立区議】レインボー・アクションが公開質問状を発表、区議が2018年から差別発言を繰り返していたことも明らかに
- 韓国演歌歌手のクォン・ドウンがゲイであることをカミングアウト
- 【足立区議】ゲイの孫がいるおばあちゃんが差別発言の区議に書いた手紙が胸熱…
- #ProudBoysでTwitterを検索してみましょう
- 【追悼】ファッションデザイナーの高田賢三さん
- リアーナの下着ブランドのファッションショーが素敵!
- 台湾同志遊行は今年開催される世界最大のパレードに。出発地点にレインボー「スタートライン」も登場
- 岡山県笠岡市、静岡県富士市などでも同性パートナーシップ証明制度導入を検討へ
- 日本初!? お寺を会場にレインボーフェス開催
- ベルギーで発足した新内閣の副首相はトランス女性の方
- 【追悼】編集者・エッセイストとして活躍した高山真さん
- フィンランドのバーガーキングが素敵なキャンペーンを展開
- TIME誌「世界で最も影響力のある100人」に選ばれたLGBTQ10人
- JALの「LGBT ALLYチャーター」がジャパン・ツーリズム・アワードを受賞
- パンテーンがトランスジェンダーをフィーチャーした広告で話題に
- 10/1発売の『BIG ISSUE』がLGBTを特集
-
9月
- 東京都、パートナーが同性である都職員への慶弔休暇などの適用を検討へ
- 来年の新しい絵文字に性や人種が多様なカップル、ヒゲの人などが追加
- ホン・ソクチョンがカミングアウトして20周年を迎えました
- レスリー・キーさんと婚約者のジョシュアさんが渋谷区でパートナーシップ証明
- 日本学術会議が「性同一性障害特例法」の廃止と「性別記載変更法」の制定を提言
- 結婚後ゲイと自覚したお父さんと、今はゲイバー飲みにもつきあってくれる素敵な息子さん
- 俳優のフランソワ・アルノーがバイセクシュアルとカミングアウト
- 長岡京市「同性婚法制化に向けた議論を」意見書採択、全国初
- エミー賞でル・ポールと『シッツ・クリーク』が大記録を達成!
- 性的マイノリティの実情に即した「強制性交等罪」の見直しが求められています
- 【追悼】米国のLGBTQの権利を守った最高裁のギンズバーグ判事
- 米国の同性カップル世帯数が98万に達したことが明らかになりました
- 埼玉県北本市が11月から同性パートナーシップ証明制度を導入へ
- 名古屋市で同性パートナーシップ証明制度導入、2021年度中に
- 横浜市の図書館でLGBTQへの理解を深めるための巡回パネル展が実施中
- 兵庫県西宮市が同性パートナーシップ証明制度を来春導入へ
- 埼玉県坂戸市が来月から同性パートナーシップ証明制度を導入
- 『POSE』シーズン3、ようやく撮影再開!
- HIV検査が前年の約4分の1に激減。発症してわかる方が増えています
- 英国の22歳の現役ラグビー選手がカミングアウト
- 同性カップルもOKな「おためし同棲」サービスが展開中
- 通算20回目を数える「さっぽろレインボープライド2020」が無事に開催されました
- 「レインボーマラソン2020」オンライン開催へ
- 高知市が同性パートナーシップ証明制度導入へ、来年2月から
- LGBTQ支援のチャリティとして、キース・ヘリングの個人コレクションがサザビーズに出品
- 大阪のレインボーフェスタ!が来年に延期されることが発表されました
- アカデミー賞が多様性に配慮した画期的な新基準を発表
- LGBT国会議員連盟の総会で国勢調査の同性カップル集計などが議論されました
- LGBTがコロナ禍で困窮したり、メンタルヘルスが悪化…「niji VOICE 2020」結果速報
- 10月11日、常設の総合LGBTQセンター『プライドハウス東京レガシー』が新宿にオープン
- テイラー・スウィフトが博士号を取得したゲイのファンにお祝いの手紙を贈りました
- 兵庫県尼崎市がラブホテルの定義に同性も含めるよう条例を改正へ
- ハードロックカフェがフレディ・マーキュリーをデザインした「Pride Collection」を発表
- 三浦春馬さん主演の『キンキーブーツ』15分の特別映像公開へ
- 沖縄県の普天満山神宮寺がレインボーフラッグを掲げ、仏前結婚式なども
- 全米オープンが有色人種やLGBTQに光を当てる「Be Open」キャンペーンを展開
- 鹿児島県指宿市が同性パートナーシップ証明制度導入へ、県内初
- MTVアワードでレディ・ガガがアリアナとの「Rain On Me」を初披露
- 京都タワーと二条城がレインボーカラーに輝きました
-
8月
- 大阪地裁がトランス女性タクシー運転手の性表現の権利を擁護
- 札幌市と大阪市が、同性パートナーも犯罪被害遺族給付金の対象として認めました
- ハリウッド大通りがレインボーカラーに!
- 世界初? LGBTQの乗員による「プライド・トレイン」が運行
- 青森県弘前市が同性パートナーシップ証明制度導入へ、東北初
- PrEPユーザーへの調査の結果、セックス依存や薬物使用が減ったことが明らかに
- 名作映画『チョコレートドーナツ』が世界初舞台化
- NY州がマーシャ・P・ジョンソンの功績を讃え、州立公園の名前に
- 米国のLGBTQの若者の4割が過去1年以内に自殺を考えたと回答
- レインボー国勢調査プロジェクト9団体が総務省に要望書を提出
- ジェニファー・ロペスが親族のトランス男子をフィーチャーした映画を発表
- 一橋大院生の死から5年。弁護士になった同級生「差別をなくしたい」
- 「花形文化通信」掲載のシモーヌ深雪さんインタビューが絶品
- 【追悼】「ル・ポールのドラァグ・レース All Stars」にも出場した実力派ドラァグクイーン、チチ・デヴァイン
- メジャーリーグの実況アナがゲイ侮蔑発言で試合中に降板
- レインボー国勢調査プロジェクト、国会の超党派LGBT議連に要望書を提出
- 国勢調査での同性カップルの集計・発表を求めるプロジェクトが発足、国に要望書を提出へ
- ロシアのゲイ・アーティストが大きなレインボーフラッグをクレムリンに飛ばしました
- 待望のトム・オブ・フィンランド初個展が9月18日から開催決定!
- トランスジェンダーを医療から排除しようとする米政権の政策を連邦地裁がブロック
- 世間の偏見を変えるために地道な努力を続けてきたゲイカップルの25年を振り返る良記事が掲載
- 京都市の同性パートナーシップ証明制度スタートに合わせ、京都タワーと二条城がレインボーカラーにライトアップ
- ディズニー・チャンネルのアニメ作品の主人公がバイセクシュアルであることが明らかに
- Netflixが、ゲイを排除するトルコ政府の検閲に応じず、ドラマ製作を撤回
- 9/5、PrEPについてのオンライン学習会が開催されます
- アメリカのビデオゲーム人口の10%がLGBTQであることが明らかに
- 上海プライドが12年の歴史に幕、香港プライドは開催を継続
- 民主党の副大統領候補に選ばれたカマラ・ハリス氏が、選挙スタッフのチーフに黒人レズビアン女性を選びました
- ベイルートの爆発で壊滅状態に陥ったLGBTQコミュニティを救うためのチャリティが立ち上げられました
- ドラァグレースがお腹が出た方を初めてピットクルーに起用
- さっぽろレインボープライドに道内全ての市長から応援メッセージ
- 秋元才加さんがTwitterで同性婚を応援
- 東京都国立市が在勤・在学者も対象とした同性パートナーシップ証明制度の導入へ、全国初
- LGBTを支援するポーランドの議員たちがレインボーの服で国会に登庁
- 映画『マトリックス』にトランスジェンダーの寓意が込められていたことが明らかに
- レインボーフラッグを境内に掲げ、LGBTQを救済する愛知県のお寺
- コロナ禍にも負けず…宮崎レインボーウィーク7日まで開催中
- 「家族ぐるみのつきあいをしてきた」「結婚している夫婦と同じ」と法廷で訴えました
- 横浜市で宣誓した同性カップルが100組を突破、川西市でも制度がスタート
- 8/5、札幌地裁で同性婚訴訟の原告カップルが語ることの意味とは
- MTV VMA最多ノミネーションのガガ&アリアナ、『Drive 'N Drag』でのステージ初共演が幻に…
- エルトン・ジョンが「ネクスト・ガガ」とも称されるクィア・アーティストRina Sawayamaを絶賛
- GLAADメディア賞で『POSE』が2年連続で最優秀ドラマ賞を受賞
- ハリウッドのゲイたちにセックスを斡旋していた人物の半生が映画化
-
7月
- 【追悼】90年代から敢然と同性婚を支援してくれたジョン・ルイス議員
- EUが、LGBTQを排除するポーランドの自治体の補助金申請を却下
- 『POSE』クリエイターが新たなLGBTQドラマを製作
- 芝生にゴロンして『ロケットマン』を鑑賞する素敵イベントが開催
- 米熊系雑誌が渡辺直美さんのレディ・ガガMVパロディ動画を絶賛
- 今年のエミー賞も、LGBTQ関連の作品がいろいろノミネートされました
- 2020年大注目のクィア・ソングライター、ジャスティン・トランター
- LGBTQのアイドルがファンに勇気を与えているという記事が掲載
- LGBTQ性暴力被害者支援団体が、男性への暴力被害も支援するよう渋谷区に苦情申立て
- カナダのBC州が公にグローリーホールの使用を推奨したことを受け、YouPornがグローリーホール建設を提案
- 先日の二丁目でのコロナ対策勉強会がネットニュースでレポートされました
- ベントレーが地元のプライドに協賛し、レインボーカラーに彩色した高級車を発表
- パートナーと死別した経験をもつゲイの精神科医が教える心の癒し方
- 野原くろさん『キミのセナカ』を日本で出版しましょう
- 全米初のゲイの州知事がLGBTを守る複数の州法に署名
- 【追悼】関西のオネエ系タレントの草分け的存在、リリアンさん
- 二丁目のaktaのセンター長が交代しました
- お客様のために「尺奉仕」もいとわず、ヒーローとなったゲイのおじさんのこと
- 【追悼】『キンキーブーツ』でのドラァグクイーン役が素晴らしかった三浦春馬さん
- 英版『VOGUE』編集長のエドワード・エニンフルが最優秀編集長等を受賞
- メーン州とオレゴン州が、出生証明書の性別欄にノンバイナリーと記載することを認めました
- ライアン・マーフィら『glee/グリー』のプロデューサー陣が、ナヤ・リヴェラの息子の学費基金を設立
- セクシュアルマイノリティの知の巨人たちが未来を語る対談が掲載されました
- ヴァレンティナ・サンパイオが『スポイラ』の水着特集に登場、トランス女性として初
- 【追悼】『glee/グリー』サンタナ役のナヤ・リヴェラ
- 全国でパートナーシップ登録を行ったカップルが1000組を突破&大阪府富田林市・兵庫県川西市も制度導入へ
- ハル・ベリーがトランス男性の役を降りた理由とは
- 毎日パレード! 宮崎レインボーウィーク2020が8月1日〜7日に開催
- ヘンリー王子が、ギャレス・トーマスが立ち上げたHIV団体にエールを送りました
- 二丁目のお店の方に向けたコロナ対策の勉強会が開催されました
- タイがアジアで2番目の同性パートナー法承認国に…いよいよ本当に
- 『ル・ポールのドラァグ・レース』と『クィア・アイ』のいいとこ取りをした話題作がついに日本上陸!
- ウォーク・ザ・ムーンのフロントマン、ニコラス・ペトリッカがカミングアウト
- 手編みのレインボーフラッグがアンダルシアを彩りました
- HIV陽性者や性同一性障害者も加入できる共済ができました
- スコットランドが学校教育のカリキュラムにLGBTQの社会的課題について学ぶ授業を導入、世界初の快挙
- 英国がエルトン・ジョンの記念硬貨を発売、ソロアーティストとして初
- 東京2020出場予定だったボート競技選手がカミングアウト
- 米フィギュア連盟がLGBTQの選手を支援、村主章枝さんの名前も
- 『ウォーキング・デッド』俳優のダニエル・ニューマンが、バイセクシュアルへの偏見に苦言
- ハリウッドのゲイ・セレブたちがツーショット画像でプライド月間を祝福!
- 7月5日は都知事選、LGBTフレンドリーな候補者は?(その2)
- 【署名のお願い】ピンクドット沖縄創設者の砂川秀樹さんが、沖縄のLGBTを守りたいとの思いで
- 7月1日、川崎市など4市町で同性パートナーシップ証明制度がスタート
- 実は娘だったミニラを優しくサポートするゴジラの姿を描いた動画が泣ける…
- テイラー・スウィフトが米国勢調査の性別欄に「男/女」の選択肢しかないことを批判
- パリス・ジャクソンが同性愛をカミングアウト、父マイケルも認めていたそうです
- 結成50周年を記念し、クイーンの切手が英国で発売
- 7月5日は都知事選、LGBTフレンドリーな候補者は?
- 高級ブランド「ロエベ」が伝説のドラァグクイーン、ディヴァインをフィーチャー
-
6月
- 『ヘアスプレー』主演のニッキー・ブロンスキーがカミングアウト!
- 90歳のおじいちゃんがカミングアウト、若い頃の恋の思い出を真実にするために
- イングランドの元サッカー選手トーマス・ビーティがカミングアウト
- 米プロサッカーチームが性の多様性を祝福するレインボーユニフォームを発表
- DIESELが24時間ノンストップのオンラインプライドパーティを開催、東京を皮切りに
- レディ・ガガがチャリティ・オンラインイベントにサプライズ出演
- 「Kompass」がプライド月間を彩るSpotifyのプレイリストを解説、身近なイベントもフィーチャー
- ブリトニー・スピアーズ、LGBTQ+のファンたちへ「痛いほどあなたたちのことを愛してます」とメッセージ
- キース・ヘリングのビニール傘がセブンイレブンで販売されます
- アメリカのセクシー系ブランドが続々とBLACK LIVES MATTERムーブメントに合流
- 『Stonewall day』ライブ配信にオバマ氏、テイラー、ケイティらが出演
- 住まいを失いそうな方へのアンケートの結果が発表
- 【追悼】『バットマン・フォーエヴァー』『オペラ座の怪人』などの監督、ジョエル・シュマッカー
- LGBTQユースへの緊急調査で、コロナ禍による様々な困難が浮き彫りに
- ディーゼルが「プライドカプセルコレクション」とトランスジェンダーをフィーチャーしたフィルムを発表
- 茨城県の大井川知事が同性婚を「認めるべきだ」と表明、知事として初
- COVID-19について、抗HIV薬を服用しているHIV陽性者は一般の患者とほぼ同様
- 同性パートナーシップの登録を行ったカップルは全国で900組超
- VERSACEがプライドコレクションを発表、レインボーカラーのケツワレも
- RUSH裁判は弁護側の訴えを退ける無慈悲なものでした…控訴の予定です
- HBOがオンラインプライドイベントを開催、ジャネール・モネイやトドリック・ホールらが出演
- P&GとiHeartがオンラインプライドイベントを開催、ケイティ・ペリーやシーアらが出演
- 長野県松本市が同性パートナーシップ証明制度を導入、来年4月から
- 岩手県盛岡市が同性パートナーシップ証明制度導入を検討へ
- 京都府亀岡市が同性パートナーシップ証明制度を導入へ
- 米最高裁の歴史的な判決に、各方面から喜びの声
- 全米で黒人トランスジェンダーへの暴力に抗議する集会やパレードが行われました
- 米連邦最高裁が性的指向・性自認に基づく解雇を違法とする判決を下しました
- ニューヨーク市がCOVID-19予防のためのセーファーセックスの指針を改定
- スイス下院が同性婚法案を可決
- 『ハリポタ』作者J.K.ローリングのトランスジェンダー差別発言に対し、映画に主演したダニエル・ラドクリフらがトランスジェンダーを擁護する声明を発表
- 上司のアウティングでうつ状態に陥ったゲイの方が、職場がある豊島区に救済申し立て
- 【支援のお願い】コロナ禍で住まいを失ったLGBTのためのシェルター増設
- 世田谷区が同性パートナーも遺族として認めることを発表、日本初の快挙
- プライド月間を祝し、世界中の『VOGUE』ロゴがレインボーカラーに。
- カイラー・リー、カーラ・デルヴィーニュ、リリ・ラインハート…「プライド月間」にセレブが続々とカミングアウト
- プライド月間を祝し、ナイキ、コンバース、リーボック、IKEAなどがレインボーアイテムを発表
- 全米で同性婚が認められたことによる経済効果は38億ドル、4万5000人もの雇用を創出
- 『名探偵ピカチュウ』のジャスティス・スミスがカミングアウト
- 「社会通念」を理由とした犯罪被害者給付金不支給の判決に、各方面から異論
- レポート:名古屋・犯罪被害者給付金裁判 オンライン報告会
- 名古屋地裁、同性パートナーは犯罪被害遺族給付金支給の資格なしと判決
- ドラァグクィーンが「Black Lives Matter」チャリティ・ショーをオンラインで世界に配信
- 三重県がアウティングの禁止などを含むLGBT差別禁止条例を制定へ
- 全米の70以上のLGBT団体が人種差別と闘う声明を発表
- KDDIが同性カップルの子を家族に含める「ファミリーシップ申請」制度を導入
- 6月1日はLGBTにとって喜ばしい、記念すべき日になりました
- ドラマ『きのう何食べた?』が昨年度のギャラクシー賞「マイベストTV賞 第14回グランプリ」に選ばれました
- スペインの若きスター、パブロ・アルボランがカミングアウト
-
5月
- 6月1日から都内でも映画館が再開! ゲイ映画情報をセレクト
- 【追悼】エイズ危機下での政府の無策に抗議し「ACT UP」を立ち上げた偉大な活動家、ラリー・クレイマー
- アイスダンスのギヨーム・シゼロン選手がゲイであることをカミングアウト
- 三重県いなべ市がLGBT差別の禁止や同性パートナーシップ証明制度を盛り込んだ条例の制定へ
- コスタリカで同性婚がスタート、大統領も祝福
- 川越市の最明寺が仏前式の同性結婚式をはじめました
- 京都市で同性パートナーシップ証明制度導入、9月1日から
- 台湾で外国人同性カップルのパートナーシップ登録が可能に
- HIVコミュニティが厚労省に「新型コロナウイルス感染症に対する要望書」を提出
- ドラァグクィーンが史上初めてエミー賞の俳優部門にノミネート
- メディア関係者にLGBTのプライバシー保護などの配慮を求める要望書が内閣府に提出されました
- 30年の歴史を誇る京都のドラァグクイーン・パーティ『DIAMONDS ARE FOREVER』が初のオンライン開催
- 9家族をたらい回しにされた男の子をゲイカップルが養子縁組、「Zoom」公聴会で
- ディズニー史上初! ゲイが主人公のアニメ作品が公開
- 中国の大学生の約23%が「異性愛者ではない」と表明
- フェイス・ノー・モアのロディ・ボッタムが彼氏と新ユニットを結成
- アップルがプライド月間を祝し、Nikeとコラボした新しいApple Watchスポーツバンドやプライド文字盤をリリース
- 同性婚法成立1周年を祝し、台湾の蔡英文総統が同性婚カップルのための祝電をプレゼント
- 国連事務総長がコロナ禍で「LGBTが攻撃を受けやすくなっている」と警鐘
- LGBT団体が医療現場等で同性パートナーを家族として扱うことや差別禁止法の制定を求め、政府に要望書を提出
- 福岡市植物園がレインボーカラーの花壇をつくり続ける理由とは?
- WHOが同性愛は精神病ではないと宣言してから今日で30年、EUビルがレインボーカラーのライトアップでLGBTを祝福
- 尼崎市のラブホテル2軒が男性カップルの利用を断り、市の行政指導を受けました
- クイーンがコロナ禍へのチャリティとして「フレディ・マーキュリー追悼コンサート」を配信
- 伊丹市で同性パートナーシップ証明制度がスタート
- オンラインでは初のベア・ウィーク・イベントが開催
- 韓国で同性愛者のプライバシー保護に配慮した匿名検査を導入後、検査数が8倍に上昇
- ガガ様がゲイのファンのためにケツワレを販売!
- 【追悼】『バディ』や『G-men』で活躍した漫画家の上条毬男さん
- コスタリカが中米初、世界で29ヵ国目の同性婚承認国となります
- LGBTアライアンス福岡が、コロナ禍で不安を覚える性的マイノリティへの支援を県に要望
- 【支援のお願い】二丁目のイベントスペースが存続の危機
- プライドハウス東京がLGBTQユースを応援するオンライン企画『RAINBOW YOUTH COMMUNITY』を始動
- 日本で性別変更か婚姻解消かを迫られた外国籍トランス女性が裁判を決意
- 【追悼】ラスベガスの伝説「ジークフリード&ロイ」のロイ・ホーンが新型コロナウイルスで死去
- 【追悼】ロックンロールの創始者の一人であり、ゲイだったリトル・リチャード
- 厚労省が初めて職場におけるLGBTの実態を調査・公表
- トム・オブ・フィンランド生誕100年を祝い、世界中のゲイたちがオマージュを捧げています
- NETFLIX公式が「もうゲイのキャラ要らなくね?」ツイートに反撃
- 2人の黒人のゲイのアーティストがピュリッツァー賞を初受賞
- テイクアウトするときにドラァグクイーンがサービスしてくれるレストランが話題に
- コロナ禍のLGBTへの影響についての緊急アンケートの結果報告会がオンラインで開催
- 【署名のお願い】二丁目の街の灯が消えてしまわないように… #SAVEthe2CHOME
- 台湾の同性婚がもうすぐ1周年、結婚した同性カップルは3553組に
- ハンター、リーバイス、プーマが「プライドウィーク」に合わせてプライドコレクションを発表
- 【緊急アンケート】収入が減って、住まいに困っている方はいらっしゃいませんか?
- 豊明市、川越市で同性パートナーシップ証明制度スタート、5月17日導入予定の芦屋市で50自治体に
- オープンリー・ゲイの超大物キャスター、アンダーソン・クーパーに息子が誕生。コロナ禍のなかでの希望の知らせに
- トドリック・ホールが自宅待機中の人々への応援ソングをリリース!
-
4月
- 「感染したら同性パートナーとの関係が公に」自治体の対応に不安の声
- GLAADがオンライン・プライド・イベントを開催、25万ドルをLGBTセンターに寄付
- 約44万人が楽しんだTRP2020オンライン『#おうちでプライド』
- 20万人超が視聴したTRP2020オンライントークLIVE、明日はMISIAさんも出演!
- クイーン+アダム・ランバート、自宅から「We Are the Champions」をプレゼント
- ユーミンやMISIAが共演した夢の一夜、『LIVE PRIDE』のライブ映像が4/26から無料配信!
- TENGAがLGBTとタッグ、「RAINBOW PRIDE CUP 2020」「9モンEGG」
- 新型コロナウィルス感染拡大によって「今まで後回しにしてきたことが喫緊の問題として目の前に」
- 中野区報でLGBT特集
- 「法律上の家族ではないから」とパートナーの入院先を教えてもらえなかった…コロナ禍で顕在化するゲイの不安
- 俳優のJ・オーガスト・リチャーズがカミングアウト
- アンチLGBTのポーランドで、ゲイカップルがレインボーカラーのマスクを配布中
- 台湾の閣僚らがピンクのマスクを着ける男の子を応援し、一大ムーブメントに
- GLAADがオンライン・プライド・イベントを開催、アダム・ランバートやケシャが出演
- レディ・ガガがプロデュースしたチャリティ・コンサートに137億円超の寄付
- 上海プライドフェスティバルは予定通り開催
- 月刊『サムソン』が廃刊へ
- サム・スミス&デミ・ロヴァートが最高にファビュラスな「クィア・オリンピック」を届けてくれました
- 新型コロナウイルス感染症患者を救うため、アメリカがゲイ・バイセクシュアル男性の献血禁止措置を緩和
- サム・スミス&デミ・ロヴァートがコラボ曲をリリース、TOKYO2020イメージのアートワークも公開
- LGBTアンケートに続々と回答が寄せられ、さまざまな問題が明らかに
- 東京レインボープライド2020、オンライン開催決定
- 「モアナ」のスターがカミングアウト
- リル・ナズ・X、ゲイであることを一生秘密にするつもりだったと告白
- 「ヒース・レジャーは『ブロークバック・マウンテン』をネタに笑うことを許さなかった」と、共演者のジェイク・ジレンホールが述懐
- レディ・ガガが世界を救うため、「ライブエイド」的なフェスを開催
- あおぞらクリニックが日本で初めてクリニックでのHIV遺伝子検査を開始
- 6月27日(土)、オンラインで「GLOBAL PRIDE」開催
- コロナ禍のLGBTへの影響を探るアンケート実施中、相談先も
- ケツワレをマスクのように装着する動画がバズっています
- BBCが露出度高めなダンサーのゲイテイストなエクササイズ動画をシェア
- 愛知県豊明市が5月から同性パートナーシップ証明制度を導入
- アップルが医療従事者向けのフェイスシールドの開発や、失業者を支援する基金の設立を発表
- アイルランドのゲイの首相が、人手不足を受けて医療現場への復帰を決意しました
- 川崎市の同性パートナーシップ証明制度は7月から
- 『POSE』シーズン2放送決定記念! FOX「レインボースペシャル」
- 『POSE』シーズン2、5月24日から放送決定!
- 「#SAVEthe2CHOME」二丁目を愛する人たちのメッセージ
- 全国13の自治体で同性パートナーシップ証明制度がスタート
- 自宅から出られないゲイのためのオンラインSEXパーティが開催され、3000人が参加
- ユヴァル・ノア・ハラリ氏が「コロナ禍の後の世界」について語りました
-
3月
- エルトン・ジョン主催のチャリティコンサートに100万ドル超の寄付が集まりました
- 「本当にあったいい話」感染の不安と闘うゲイの方が、アプリで知り合った男性に助けてもらいました
- アジア初の同性愛者の大統領が誕生するかもしれません
- ゲイの水球チームが「セーラームーン」コスプレで笑顔!
- g-lad xxでも広告を無料で提供します
- 9monstersがLGBT支援として広告の無償提供を発表
- 『きのう何食べた?』の実写映画化が決定、2021年に全国公開
- 世田谷区が出産支援休暇も含め、休暇制度を完全に異性婚と平等に
- エルトン・ジョン、新型コロナウイルスとの闘いを支援するチャリティコンサートを開催
- トロイ・シヴァンが「Take Yourself Home」というタイトルの新曲をリリース
- 4月1日、全国13の自治体で一斉に同性パートナーシップ証明制度がスタート
- 欧州の小国・アンドラで同性婚が認められます
- 宮崎県木城町が同性パートナーシップ証明制度導入へ
- ゲイのデザイナー、クリスチャン・シリアーノが医療従事者のためにマスクを製作
- 『CDジャーナル』がLGBT的読書案内を特集!
- 外出を禁止された人々のためにドラァグクイーンがデジタルフェスを開催
- トム・オブ・フィンランドの初の個展が開催決定
- MISIAさんがLGBTについて語る番組がTBSラジオでスタート
- 東京レインボープライド2020の開催中止が発表されました
- 「ハートネットTV」でレインボーファミリーを特集
- 愛知県の男性カップルが養育里親に認定、東海で初
- プロレスラーのマイク・パローが同性結婚式を挙げました
- アップルやグーグルなど米40社超が連盟でトランスジェンダーの権利を侵害する法案に抗議
- 新潟市で4月1日から同性パートナーシップ宣誓制度導入、北信越で初
- 熊本の同性カップルが「結婚の自由をすべての人に」九州訴訟に合流
- 初のオープンリー・ゲイの金メダリスト、マシュー・ミッチャムが結婚式を挙げました
- 【米大統領選】ブティジェッジ氏が撤退を表明
- 三井住友銀行、同性カップルにも住宅ローンの連帯債務型借入を適用
- 徳島市が4月から同性パートナーシップ証明制度を導入
-
2月
- アメリカ疾病予防管理センターが髭男に注意喚起
- 台湾の合法化初年の同性婚件数は2939組
- ロンドンに「フレディ・マーキュリー通り」誕生
- 2月26日は「ピンクシャツデー」–−ピンク色のシャツを着て登校して暴行を受けたゲイの生徒への支援としてカナダで生まれた運動です
- 【米大統領選】ブティジェッジ候補に9歳の男の子が「あなたのように勇敢になりたい」
- トランスジェンダーである台湾の天才IT大臣が新型肺炎で「神対応」
- 第1回BLアワード大賞受賞の傑作『窮鼠はチーズの夢を見る』が実写映画化
- サッカー界で初めてカミングアウトした選手が英国サッカー殿堂入り
- 堂山の「dista」でトランスジェンダーの写真展が開催中
- TBS『NEWSな2人』がLGBTアスリートをフィーチャー
- マーベル初! 映画『エターナルズ』でゲイのキスシーン
- 「ゲイ・ユースのためのピア・サポーター養成講座 2020」開催
- 東京都小金井市も同性パートナーシップ証明制度を導入へ
- 同性パートナーシップ証明制度、川崎市も2020年度導入へ
- 福島でパレード初開催
- 奈良市が同性パートナーシップ証明制度を導入へ
- 「プライドハウス東京」の場所が「新宿マルイ アネックス」1階に決定
- ラーメンの一風堂が、性別問わずペアでバレンタインデーに来店で1杯無料サービス
- アカデミー賞でエルトン・ジョンやレニー・ゼルウィガーが受賞、ビリー・ポーターの豪華ドレスも話題に
- スイスの国民投票で同性愛者差別も刑事罰の対象とする法案が可決されました
- 新たなドラァグクイーン番組の制作が決定、その司会&審査員に抜擢された女性タレントがカミングアウト
- 先日のスーパーボウルに出場した49ersのコーチの1人が、同性愛を公表した人でした
- 岡山市と広島市が同性パートナーシップ証明制度を導入、相互利用も可能に
- 浜松市の同性パートナーシップ証明制度、4月1日から施行
- 【米大統領選】オープンリー・ゲイのピート・ブティジェッジが初戦で勝利
- 同性婚訴訟1周年を記念するイベントが開催、チャリティグッズも販売中
- 大阪府で同性パートナーシップ証明制度がスタート、第1号のゲイカップル「いつか法的権利を」
- 枚方市がLGBT支援の一環で同性カップルに対して結婚等新生活支援事業の利用を認めたそうです
- 2020年版絵文字にトランスジェンダー旗やジェンダーニュートラルなバリエーションが多数、追加されました
-
1月
- リル・ナズ・X、グラミー賞の全身ピンクの衣装をディスった同性愛嫌悪なラッパーに軽やかなコメント返し
- 埼玉県の大野知事、LGBT支援に向けた実態調査を実施へ
- グラミー賞でリル・ナズ・Xが2部門受賞、パフォーマンスも話題に
- MISIAさんのレインボーフラッグについて、NHKのプロデューサーに聞いた記事が掲載されました
- レスリー・キーが今晩、同性パートナーと『有吉ジャポン』に出演
- アダム・ランバートがLGBTQ+団体をサポートする基金を設立
- MISIAさんが紅白でのパフォーマンスに言及
- 全国の28の自治体で災害時の施策にLGBTへの配慮を盛り込んでいることが明らかに
- 星野源さんが同性カップルをフィーチャーしたMVを公開、賞賛の声多数
- 香川県三豊市で四国初の同性パートナーシップ証明書の授与が行われました
- 英国の男性間でのHIV感染が劇的に減少、PrEPの効果大
- 芥川賞候補のゲイ小説『デッドライン』が話題に
- 大阪府が同性パートナーシップ証明制度を導入へ、都道府県で2例目
- テイラー・スウィフトがGLAADメディア賞で最高栄誉賞を受賞へ
- ビリー・ポーターが『ALLURE』誌の表紙に、男性として史上初
- 東京都港区が全国で初めて性表現の自由を謳う条例改正を行う方針を固めました
- 今年のゴールデングローブ賞授賞式のクィア的見どころ
- MISIAさんが紅白でやってくれました!レインボーフラッグが掲げられ、ドラァグクイーンが登場
-
12月
-
2019
-
12月
- 『スター・ウォーズ』最新作にシリーズ初の同性キスシーンが登場
- 神奈川県庁で「性的マイノリティ理解促進フォーラム」開催、横浜三塔がレインボーライトアップされました
- さいたま市の同性パートナーシップ証明制度は来年4月からスタート、川越市や越谷市も導入に向けて動き出しました
- 性的マイノリティは全人口の10%という調査結果が発表されました
- トランス女性に対するトイレ利用制限措置は違法であるとの初の司法判断が下されました
- 氷川きよしさん、「男らしく生きてって言われると、自殺したくなっちゃうから…」
- 今年の「Word of the Year」に性別を問わない代名詞「they」が選ばれました
- 世界150ヵ国のLGBT観光客に対する危険度/安全度ランキングが発表
- ミス・ユニバースに史上初の同性愛者の候補者が出場
- 同性カップルが笑顔で表紙を飾る「しぶや区ニュース」が話題に
- 世界最年少となるフィンランドの次期首相は、母親とその同性パートナーに育てられた方
- LGBT差別防止の指針案、カミングアウトしない当事者は対象外に?
- U2のライブで日本のレズビアン・カップルの写真がフィーチャーされ、話題になっています
- 鎌倉市と大東市で同性パートナーシップ証明制度がスタート、全国で30例目
- ジョナサン・ヴァン・ネスが英国版『コスモポリタン』の表紙を飾りました
- 高松市が来年4月から同性パートナーシップ証明制度を導入、三豊市でも年明けからスタート
- 8歳の子がいるMtFの方が、性別変更できるよう家裁に申し立て
- 横浜市で同性パートナーシップ証明制度がスタート、初日に9組が宣誓
- HIV陽性でもドナーになれる世界初の精子バンクが誕生
-
11月
- 世界で初めての同性結婚式を執り行なった草間彌生さんのドキュメンタリーが公開中
- 奈良県大和郡山市が同性パートナーシップ証明制度導入へ
- 「第三の性」の方が『VOGUE』の表紙を飾りました
- 兵庫県明石市がLGBT支援の専門職員を募集
- リル・ナズ・Xが「AMA」受賞スピーチでLGBTにエール
- 大阪府大東市と交野市が同性パートナーシップ証明制度を導入
- kemioさんが「GQ MEN OF THE YEAR」2019の「ユース・インフルエンサー・オブ・ザ・イヤー賞」を受賞
- 同性婚承認国でゲイの自殺率が大幅に減少していることが明らかになりました
- さよなら RADIO CITY! 俺達の青春ゲイナイト!!
- クイーンの軌跡を辿る特別展が来日に合わせて開催
- 今年の香港プライドは広場での集会となりました
- 港区の同性パートナーシップ証明制度は、新しいパターンになりそう
- ピート・ブティジェッジが支持率トップに…本当に史上初のオープンリー・ゲイの大統領になるかも?
- 『総務部長はトランスジェンダー』がムロツヨシさん主演でドラマ化
- 『きのう何食べた?』が東京ドラマアウォードの優秀賞を受賞、お正月SPの放映も決定!
- 神奈川県が、同性カップルの県営住宅への入居を認めました
- 神奈川県葉山町も同性パートナーシップ証明制度を導入へ
- 横浜市の同性パートナーシップ証明制度が12/2からスタート
- 『チャーリーズ・エンジェル』主演のクリステン・スチュワート、新しい同性の恋人と結婚?
- 兵庫県明石市で初のパレードが開催されました
- 『センス8』のブライアン・J・スミスがカミングアウト
- エレン・デジェネレス、ゴールデングローブTV功労賞を受賞
- 渋谷スクランブルスクエアのTATRAS新店舗でレスリー・キー写真展が開催中
- ホイットニー・ヒューストンが同性と恋愛関係にあったことが明らかに
- ワールドシリーズ優勝投手がホワイトハウス表敬訪問を辞退
- 新ドラマ『おっさんずラブ-in the sky-』は今晩から!
- 草彅剛さんがトランスジェンダー役で映画に主演します
- ギャレス・トーマスが来日、「(今回のW杯は)歴代No.1の大会」「全ての人を受け入れてくれた」と語りました
-
10月
- フランク・オーシャンがNYで「PrEP+」というクラブパーティを立ち上げました
- 福岡市と熊本市が同性パートナーシップ証明制度の相互認証で合意、全国初
- ケネディ元駐日米国大使が同性婚シンポジウムで多様性への行動を訴えました
- コロンビアの首都で初の同性愛者の市長が誕生
- 台北で同性婚法成立後初の台湾同志遊行が開催され、約20万人が参加しました
- 朗報! 来年にはPrEPが導入されるそうです
- 北アイルランドで同性婚が実現しました
- 2023年のワールドプライドはシドニーで開催、南半球初、アジア太平洋地域でも初
- ビリー・ポーターが実写版『シンデレラ』にフェアリーゴッドマザー役で出演
- 同性婚訴訟(東京)第3回口頭弁論のゲイの方のスピーチが泣けます
- ユーミン、MISIA、清水ミチコ…『LIVE PRIDE』に出演する全アーティストが明らかに
- 大阪や三重のパレードは無事に開催、島谷さんは急遽ホールライブの神対応
- 『僕らの色彩』2巻発売を記念し、田亀源五郎さんの直筆サイン入り色校をプレゼント!
- 10/19、映画『ボヘミアン・ラプソディ』がWOWOWで放送
- 11/4、二丁目に岩崎宏美さんが降臨!
- 台風接近に伴い、いわてレインボーマーチの中止が発表されました
- アジア初のゲイ・ラグビーの国際親善試合で、日本選抜チームが世界選抜チームに勝利
- 日本ラグビーフットボール協会と国際ゲイラグビー団体がLGBT差別撤廃に向けた覚書を締結
- ラグビーをテーマにした木村べんさんの特別原画展が開催中!
- ZEDDのライブでプロポーズしたゲイカップルをディスるコメント、ZEDD本人が一蹴
- 10/5、日本で初めてのゲイ・ラグビーの国際親善試合が開催されます
- ドラマに登場したメニューが食べられる「きのう何食べた?のごはん処」が東京・名古屋・大阪で開店中
- 台湾で国際カップルが行政処分不服申し立て
- 秋田で来年5月23日、初のパレード開催
-
9月
- 逗子市が来年4月から同性パートナーシップ証明制度を導入
- 『おっさんずラブ』新作ドラマが11月2日放送開始、千葉雄大さんも出演
- 東京都が日本初となるSOGI基本計画の素案を発表、9月30日まで意見を募集中
- 台北の西門にレインボーカラーの横断歩道が出現、10月26日のパレードを前に
- 『僕らの色彩』の舞台でもある鎌倉市、年内に同性パートナーシップ証明制度を導入へ
- 『クィア・アイ』のジョナサン・ヴァン・ネスがHIV陽性をカミングアウト
- ビリー・ポーターがエミー賞で主演男優賞を受賞、ゲイとして初
- 「ルポールのドラァグレース」が東京にやってくる!
- 兵庫県明石市も同性パートナーシップ証明制度を導入へ、11/10にパレードも開催
- ラグビーW杯開幕戦で笛を吹いたのはオープンリー・ゲイの名レフェリー、ナイジェル・オーウェンスでした
- 世田谷区が災害弔慰金の支給対象に同性パートナーも含めるよう検討する意向を発表
- LGBTチャリティイベントにユーミンやMISIAが出演!
- 同性カップルも事実婚に準ずる関係として法的保護の対象になると認める画期的な判断が示されました
- HIV陽性であることをカムアウトした元ラグビー選手を、ヘンリー王子が「あなたは偉大なレジェンド」と讃えました
- HIV内定取消訴訟の判決が下り、原告の男性が勝訴しました
- プライドハウス東京2019が9月20日にオープン、畠山健介氏ら著名アスリート9名によるLGBT応援ムービーも公開!
- 既婚女性の約7割が同性婚を支持、20代では9割超
- 兵庫県三田市が10月11日から同性パートナーシップ証明制度を施行
- 神奈川県相模原市が同性パートナーシップ証明制度を創設
- 積水ハウス、パートナーが同性である従業員にも異性婚と同等の福利厚生を適用
- RAINBOW FESTA!後援のゲイナイトにmisonoさんが出演
- 福岡県古賀市が同性パートナーシップ証明制度を導入へ
- 【ご協力のお願い】旅行に関するアンケート
- 横浜市が年内めどに同性パートナーシップ証明制度を導入
- 「クィア・アイ in Japan!」が11月1日からNetflixで配信決定!
- 市長さんのスピーチが決定! さっぽろレインボープライド
- 尼崎市が来年1月から同性パートナーシップ証明制度を開始
- 沖縄の7市町村が同性パートナーシップ証明制度の導入を検討中
- 島谷ひとみさんの出演が決定! 大阪の「RAINBOW FESTA! 2019」
- 外国籍の「同性」パートナーに在留特別許可、「ありがとう、日本」
- 日本初のLGBTチャーター便が運航されました
-
8月
- シャネルがトランスジェンダーモデルを初起用
- 浜松市が年度内に同性パートナーシップ証明制度を制定
- MTVアワードでテイラーの「You Need To Calm Down」がVIDEO OF THE YEARを受賞!
- 香川県丸亀市で中四国初のレインボーパレードが開催されました
- いわてレインボーマーチ主催の加藤麻衣さんが盛岡市議選に挑戦し、2位で初当選
- おくらさんの新刊『うちの息子はたぶんゲイ』発売、トークイベントも
- ニュージーランド国会議長が審議中、ゲイの議員の赤ちゃんを抱っこしてミルクを与える姿が話題に
- マーベルの映画にゲイとレズビアンのスーパーヒーローが登場!
- 『きのう何食べた?』がドラマアカデミー賞で4冠を達成&ギャラクシー賞7月度月間賞を受賞
- 世田谷区で同性パートナーシップ証明を受けたカップルが100組になりました
- はるな愛さんが初監督した伝説の吉野ママのドキュメンタリー映画が上映されます
- 長崎市で9月2日から「パートナーシップ宣誓制度」がスタート
- パートナーが同性である東京都職員が福利厚生の平等を求めて都に措置を要求
- オタワ市長が感動のカミングアウト、「私のように40年も待つ必要はない」
- 韓国のモデル・歌手、ソム・ヘインがバイセクシュアルであることをカムアウト
- 一橋大卒業生有志が学内にLGBTセンターを開設、アウティング事件をきっかけに
- 西尾市が9月から同性パートナーシップ証明制度を導入、愛知県で初
- 熊本市で「パートナーシップ宣誓」第1号カップル誕生
- ディズニー・チャンネル初のゲイのキャラクターを演じたジョシュア・ラッシュがカミングアウト
- 佐賀市で初めてパレードが行われました
- ジャスティン・トルドーがカナダの首相として初めてゲイバーを訪問
- PrEPに関する日本語情報サイトが開設されました
- ヴィクトリアズ・シークレットが初めてトランスジェンダーのモデルを起用
- メタルバンド・ラムシュタインがロシア公演でキス、LGBT支援として
- 米「同性婚の父」エヴァン・ウォルフソン氏が来日、札幌と福岡で講演会
- 兵庫県尼崎市が同性パートナーシップ証明制度の導入を発表
- コンフィデンスアワード・ドラマ賞で『きのう何食べた?』 が作品賞・主演男優賞を受賞
- リル・ナズ・Xが全米シングル・チャート1位の歴代最長記録を更新!
-
7月
- 宮沢氷魚さんが初主演! 来年公開のゲイ映画『his』
- 日弁連が政府・国会に対し同性婚の法制化を求める初の意見書を公表
- サンフランシスコ国際空港が第1ターミナルを「ハーヴェイ・ミルク・ターミナル1」と改称、ハーヴェイ・ミルクの写真展示も
- NHKの「TOKYO 2020」特設サイトにレズビアンの動画が掲載
- 埋め込み型医療機器によって1年間HIVの感染を防ぐ最新の予防法が発表されました
- フィリピンの国会に同性パートナーシップ法案が提出されます
- ゲイや女性を侮辱したプエルトリコ知事の辞任を求めるデモに、リッキー・マーティンが参加
- 石川大我さんが当選し、初のオープンリー・ゲイの国会議員になりました
- ビリー・ポーターが黒人のゲイとして初めてエミー賞主演男優賞にノミネートされました
- 英国の新50ポンド札の肖像にアラン・チューリングが選ばれました
- 茨城県で同性パートナーシップ証明制度がスタート、水戸市や笠間市で8月から市営住宅の入居が可能に
- サッカー女子W杯でアメリカを優勝に導いたミーガン・ラピノーのコメントが話題に。「このチームにはピンクの髪もタトゥーもゲイもいる」「同性愛者なしのチームで優勝なんてできない」
- 『さよなら、ぼくのモンスター』主演のコナー・ジェサップがゲイであることをカミングアウト
- ロンドン・プライドに約150万人が参加、ヒースロー空港で特別なキャンペーンも
- 7月21日は参議院選挙です
- 「LGBTと職場に関するアンケート調査2019」実施中
- 第6回青森レインボーパレードに過去最多の208人が参加、9市町からのお祝いメッセージも
- 福岡市のゲイカップルも同性婚訴訟へ 「同性を好きと感じる子どもたちが、一生の孤独を覚悟しなくていい社会が来るまで、自分たちにできることをしたい」
- ラッパーのリル・ナズ・Xがカミングアウト
- 同性愛者が初めて難民認定、母国での迫害を理由に
- 【STONEWALL50】ストーンウォール50周年を記念するワールドプライドinニューヨークに400万人が参加し、マドンナやレディ・ガガなどのセレブが多数登場し、歴史的なイベントになりました
-
6月
- ピンクドット沖縄2019が9月1日に開催、JALが日本初の「ピンクフライト」を運航!?
- 英国のウィリアム王子が「子どもがLGBTQであっても全く構わない」と語りました
- 茨城県が紆余曲折を経て同性パートナーシップ証明制度の導入を決定、都道府県で初
- 【STONEWALL50】米マスターカードが通称名を使えるカードを発行&NYのゲイタウンに新たな標識を設置しました
- サッカー選手の下山田志帆さんが現役アスリートとして初めて同性愛者であることをカミングアウト
- 長崎市が9月から同性パートナーシップ証明制度導入へ
- 【STONEWALL50】テイラー・スウィフトの新曲のMVに30名近いLGBTQのセレブが出演、まるでパレードのようです
- 同性愛者が主人公の小説が芥川賞にノミネート
- 田亀さんの作品が『CDジャーナル』の特集&表紙に!
- 田亀さんの『弟の夫』が金沢大の入試問題の題材に
- 宮崎市で同性パートナーシップ証明制度がスタートしました
- 【STONEWALL50】テイラー・スウィフトが「ストーンウォール・イン」でサプライズパフォーマンス!
- 【STONEWALL50】テイラー・スウィフトがゲイ応援ソングをリリース!
- HIV陽性者が病院から内定を取り消され、提訴。本人尋問での病院側弁護士の質問があまりに差別的で、問題視されています
- 【STONEWALL50】『ニューヨーク・タイムズ』が最初に煉瓦を投げたのは誰か?を検証する動画を発表
- タイでLGBTの国会議員が4人誕生、同性婚実現にはずみ
- エクアドルで同性婚が認められました
- 福岡県北九州市で7月1日から同性パートナーシップ証明制度がスタート
- タキシードドレスで話題をさらったビリー・ポーター、トニー賞では「子宮ドレス」を披露
- 「幸せの国」ブータンで同性間の性行為が非犯罪化されました
- 香川県三豊市が同性パートナーシップ証明制度の導入を目指す方針を明らかにしました
- 香港最高裁が同性カップルに異性婚と同等の待遇を認めました
- 【STONEWALL50】ニューヨーク市警がストーンウォールに謝罪しました
- 宮崎市の同性パートナーシップ証明制度が10日からスタート
- 静岡県浜松市が同性パートナーシップ証明制度の創設を検討していることが明らかになりました
- ヘンリー王子とメーガン妃が、故ダイアナ元妃がエイズ患者を見舞う写真などを掲載し、LGBTQ+コミュニティのサポートを表明しました
- ディズニー史上初の公式プライドイベントがディズニーランド・パリで開催されました
- 日本で初めて、同性どうしの結婚を可能にする民法改正案が野党3党によって衆院に共同提出されました
- テイラー・スウィフトがプライド月間を祝し、本格的にLGBT支援を宣言しました
- 【STONEWALL50】Googleがストーンウォール50周年のプライド月間を祝福する特別なDoodleをプレゼントしてくれました
- ソウルで第20回を記念するパレードが開催、約7万人の歓声が街に響きました
- ソウルで初のピンクドットが開催、8000人で盛り上がりました
-
5月
- パワハラ防止を義務付ける関連法が可決、SOGIハラとアウティングの防止も盛り込まれることに
- 前川清さんの次女で歌手の侑那さんがレズビアンであることをカミングアウト
- シンガポール「建国の父」の孫で現首相の甥にあたるリー・フアンウーさんが南アフリカで結婚しました
- 台湾で同性婚実現を祝う披露宴イベントが開催、2000人近くが喜びを分かち合いました
- エルトン・ジョン、グザヴィエ・ドラン、ペドロ・アルモドバル…今年のカンヌ国際映画祭で注目を集めたゲイ・セレブたち
- 「LGBT差別は犯罪です」ブラジル最高裁が判断
- 台湾で同性婚がスタート! 300組以上の同性カップルが婚姻届を提出
- ジョニー・ウィアーが来日、映画『氷上の王、ジョン・カリー』公開記念イベントに登壇
- 国際反ホモフォビアの日、メキシコのキスマラソンなど、世界中でいろんなイベントが開催されました
- プライドハウス東京と国連合同エイズ計画(UNAIDS)がLGBTの人権とセクシュアルヘルスに関する普及啓発において協力関係を構築するための覚書を締結しました
- おめでとう! アジア初の同性婚! 台湾の国会で婚姻の平等を定める特別法が採択されました
- 国際反ホモフォビアデーにあたる5月17日、台湾国会で同性婚をめぐる特別法案が採決されます
- 三ツ矢雄二さんプロデュースの「LGBT THEATER」第1弾が上演決定
- 第30回GLAADメディア賞で『POSE(ポーズ)』が最優秀ドラマ賞を受賞、マドンナのスピーチも話題に
- 読売テレビの報道番組の「性別がわかりづらい」人への差別的な行動に対し、コメンテーターが「許しがたい人権感覚の欠如」と激怒。ネットで賞賛の嵐に
- 埼玉県のLGBT団体が、同性パートナーシップ証明制度導入の要望書を全市町村に提出
- 「多数派に戻る治療ないのか」発言の茨城県医師会副会長が、謝罪しました
- 「キャンプ」をテーマとしたMET GALA 2019が話題を呼びました
- ブルネイが同性間性交渉に死刑を課す新刑法の執行を猶予すると発表
- 【STONEWALL50】マドンナがストーンウォール50周年にオマージュを捧げる新曲「I Rise」を発表しました
- kemio(けみお)さんがカミングアウト、TRPにも言及
-
4月
- 東京レインボープライド「プライドフェスティバル」が盛大に開催され、パレード参加者数が初めて1万人を超え、動員数は2日間で20万人を記録しました
- 東京レインボープライド開催を祝し、渋谷の街がレインボーに!
- 大阪市で実施された大規模無作為抽出調査の結果、LGBTの割合は約3%でした
- 栃木県鹿沼市が同性パートナーシップ証明制度導入へ、6月から
- 台湾で5月25日に同性婚を祝うウエディングイベントが開催、少なくとも157組が結婚
- 【統一地方選挙】LGBT候補者はみなさん当選、なめかわ友理さんも水戸市議に当選
- 【米大統領選】ピート・ブーティジェッジが正式に米大統領選への出馬を表明しました
- 同性婚訴訟で初弁論 「同性婚が認められることは、自分自身に対する否定的な気持ちをこれからの世代の人たちが感じなくてよい社会にすることです」「国は、同性婚を認めないためのどんな『理由』を持ち出すとしても、その矛盾に立ち往生するはずです」
- 養子縁組をしたにもかかわらず法で認められた手紙のやり取りの権利を剥奪された受刑者の男性カップルに対し、国に賠償を命じる判決が言い渡されました
- TRP2019のゲストが確定! 青山テルマさん、りゅうちぇるさん、水曜日のカンパネラのみなさんが初登場、清水ミチコさんも再登場
- デザイナーのマーク・ジェイコブスが結婚しました
- トランスジェンダーの渕上綾子さんが北海道議に初当選
- OECDが加盟国の同性愛受容度を発表、日本は36ヵ国中25位
- 『X-MEN:ダーク・フェニックス』のソフィー・ターナーがパンセクシュアルであることをカムアウト
- LGBT電話相談に寄せられたアウティング被害件数は110件超 その深刻さが浮き彫りに
- ビヨンセがGLAADメディア賞特別賞を受賞し、エイズで亡くなったゲイの叔父にこの賞を捧げるとスピーチして感動を呼びました
- 米シカゴで初の黒人同性愛女性市長が誕生
- アダム・ランバートがモデルとの2ショットを初公開、交際を公に
- 熊本市など全国9自治体で同性パートナーシップ証明制度がスタート
- 統一地方選後半で区議選等に立候補するLGBTの方々は4名?
-
3月
- ジョージ・クルーニーがブルネイのホテルのボイコットを呼びかけました
- Yahoo!ニュースがLGBT差別禁止を盛り込んだ新たなコメントポリシーを策定
- エルトン・ジョンの半生を描いたミュージカル映画『ロケットマン』が公開決定
- 来春からの小学校教科書に初めて性の多様性のことが記載されることになりました
- メ~テレ(名古屋テレビ)でもゲイドラマが放送されます
- 昨年、新たにHIVに感染していることがわかった方が1288人で、2005年以来初めて1300人を下回りました
- 豊島区で条例改正案が採択され、4月から同性パートナーシップ証明制度がスタートすることになりました
- 日本で25年間パートナーと連れ添ってきた台湾籍のゲイの方に、在留特別許可が下りました
- 取材するメディアと、取材を受けるLGBTに向けた、報道のガイドラインが作成されました
- 大分県が製作したLGBT啓発マンガ「りんごの色」が今年度の法務大臣表彰を受けました
- 山田邦子さんがLiving Togetherのど自慢@九州男に登場します!
- 江戸川区も同性パートナーシップ証明制度を導入、築地本願寺で結婚式を挙げたゲイカップルの尽力で
- 完全な平等の達成を目指し、国としてLGBTQ差別を禁じる法案が米国会に提出されました
- 80年代NYでヴォーグに生きるクィアな若者たちを描いたドラマ『POSE』が、ついに放送決定!
- マーベル社がゲイのスーパーヒーローの映画を製作?
- 『ボヘミアン・ラプソディ』の続編が製作される!?
- 今年の東京レインボープライドのゲストはm-floに決定!
- タイで「ミス・インターナショナル・クイーン」が開催され、アメリカ代表の方が黒人として初めて優勝しました
- Yahoo! JAPANがLGBTも含めた「防災ダイバーシティ」プロジェクトを展開中
- 二丁目版シンデレラ? ミュージカル『ソーホー・シンダーズ』が3/9から開幕
- 古田新太さんが女装家の高校教師に扮するドラマが4月スタート、キャラクター監修はブルボンヌさん
- 同性婚の実現がゲイのメンタルヘルス向上につながることが明らかになりました
- 水原希子さんがTV番組で、二丁目でよく遊んでいたことや多様性の素晴らしさについて語りました
- LGBT支援イベント「東京レインボーマラソン」が初開催されました
- キューバで憲法改正によって同性婚が実現、世界で26ヵ国目
- 2019年版の「ゲイフレンドリーな国ランキング」が発表されました
- 大阪府枚方市がLGBT支援宣言を発し、同性パートナーシップ証明制度も導入
- 性的マイノリティのためのお寺が建立されました
- 茨城県で都道府県として全国2例目のLGBT差別禁止を明文化する条例が成立、同性パートナーシップ証明制度は先送りに
-
2月
- 【一橋大学アウティング裁判】 訴えを棄却する判決に対し、「アウティングが不法行為であるかどうかという判断すらしていない」「学校や職場における当事者の安全に関わる問題だ」など、批判が噴出しています
- 三重県が職員や企業に向けた多様なSOGIについてのガイドラインを策定、都道府県としては初
- 沖縄県浦添市が同性パートナーシップ証明やLGBT差別禁止を含むセクシュアルマイノリティに特化した全国初の条例を制定することになりました
- 神奈川県小田原市が4月から同性パートナーシップ証明制度を導入、県内2例目
- 宮崎市が6月にも同性パートナーシップ証明制度を導入
- 二丁目のイベントに畠山健介さんが登場!
- クイーンのライブで幕を開けたアカデミー賞は、『ボヘミアン・ラプソディ』が奇跡の最多受賞を果たしました
- 最上もがさんと東小雪さんが、お茶の水女子大でのLGBT特別授業に登壇しました
- 台湾が同性カップルに結婚とほぼ同等の権利を認める特別法を閣議決定、5月24日施行予定
- 米航空会社が、男/女以外の性別の選択肢を導入する方針を明らかにしました
- クイーン&アダム・ランバートがアカデミー賞のオープニングを飾ります
- 岡山県総社市が同性パートナーシップ証明制度導入を発表、中四国で初
- NHK BS1が中国のLGBTを特集、語りは清水ミチコさん
- 『君の名は。』の聖地、岐阜県飛騨市も同性パートナーシップ証明制度を導入
- 東京都港区が、条例によって同性パートナーシップ証明制度を導入する意向を明らかにしました
- 同性婚を認めないのは違憲であるとして全国13組の同性カップルが一斉提訴しました
- レディ・ガガやブランディ・カーライルらが受賞した今年のグラミー賞は、素晴らしくクィアでした
- マドンナが第30回GLAADメディア賞授賞式で非常に特別な賞を受賞することになりました
- 結婚していることを理由に戸籍上の性別変更が認められない性同一性障害者が、性別変更できるよう申し立てを行うことになりました
- 香川県でもゲイカップルが婚姻届を提出しました
- ジャシー・スモレットが復活ライブのステージに立ちました
- 3月に銀座で「日本のゲイ・エロティック・アート展」開催
- 4月からNHK総合でドラマ『腐女子、うっかりゲイに告る。』放送決定
- 大阪府堺市が4月1日から同性パートナーシップ証明制度を施行
-
1月
- ジャシー・スモレット暴行事件を受け、ナオミ・キャンベルらセレブリティが続々とサポートを表明
- 千葉市で同性パートナーシップ証明制度がスタート、事実婚の異性カップルを含めたのは全国初
- 茨城県が同性パートナーシップ証明制度の導入を検討、都道府県では初
- 史上初のオープンリー・ゲイのアメリカ大統領になるかもしれない人物が現れました
- 京都府亀岡市議選でトランスジェンダーの候補がトップ当選
- ドラマ『きのう何食べた?』のビジュアルが公開、「再現度高すぎ」と話題に
- 史上初! スーパーボウルにゲイのチアリーダーが出場
- 「クィア・アイ」のファブ5が来日!
- 性別変更するために不妊手術を必須と定める法律の違憲性を問う裁判で、最高裁が「現時点では合憲」と判断しました
- 『ボヘミアン・ラプソディ』の躍進が止まらない! アカデミー賞5部門ノミネート、日本での興行収入は100億を突破
- 同性婚訴訟、2月14日に全国一斉提訴へ
- 大手企業も参加するHIV陽性者向け就職支援セミナーが開催されます
- ドラマ『家売るオンナの逆襲』第3話(23日放送)でLGBTがフィーチャーされます
- 大阪市が市内の事業者のLGBTフレンドリー度を認証する制度をスタート、同性パートナーがいる職員への結婚休暇などの取得も可能に
- 電通が最新の調査結果を公表、LGBT人口は全体の8.9%、同性婚賛成派が8割近くに上りました
- NHKのドラマで次にトランスジェンダーを演じるのは千葉雄大さん
- 千葉市が性別を問わないパートナーシップ証明制度を施行
- 『ボヘミアン・ラプソディ』作品賞&主演男優賞受賞!だけじゃなかった今年のゴールデングローブ賞
- 待望の『僕らの色彩』単行本が12日に発売、20日には田亀先生のサイン会も
- 同性婚一斉提訴の原告のゲイカップルが、市役所に婚姻届を提出しました
- 今年2月、結婚の平等を問う一斉提訴が行われます
- マドンナが「ストーンウォール・イン」にサプライズで登場し、ストーンウォール事件50周年を祝福しました
-
12月
-
2018
-
12月
- タイの内閣が同性パートナーシップ法案を承認しました
- 『総務部長はトランスジェンダー』の岡部鈴さんが「Forbes JAPAN WOMEN AWARD」編集部特別賞を受賞しました
- 群馬県大泉町が同性パートナーシップ制度を来月から導入
- カナダで来年、同性愛合法化50周年を記念した新しいコインが発売されます
- 号泣必至の名作、藤本郷さんの『帰郷』がpixivで公開されました
- 大阪府が人種・民族差別やLGBT差別を禁止する条例を制定する方針を示しました
- 名古屋市が性的マイノリティに関する市民意識調査を実施、当事者は1.6%という結果に
- ミス・ユニバース世界大会に史上初めてトランスジェンダーの方が出場しました
- 第3回レインボー国会が開催、LGBT差別解消の法制度について議論が行われました
- アップリンク吉祥寺が14日オープン、オープニング上映作品は『カランコエの花』『ムーンライト』など
- 増原裕子さんが来夏の参院選で京都選挙区から立候補することになりました
- ボヘミアン・ラプソディ、レディー・ガガ、ライアン・マーフィ…ゴールデン・グローブ賞のノミネートが発表されました
- 同性愛嫌悪発言のケヴィン・ハートがアカデミー賞の司会を降りることになりました
- 『おっさんずラブ』映画化決定、年始にドラマ全話一挙放送も
- コスタリカのケサダ大統領が、2020年5月から同性婚できるようになると発表しました
- 熊本市が同性パートナーシップ証明制度を導入、来年4月から
- 今年30周年を迎えた世界エイズデーに合わせ、ドラマ『Empire』でHIV陽性者のエピソードが放映され、アップルストアが赤く染まりました
- クロエ・グレース・モレッツが主演した同性愛矯正施設の映画がDVD化されることになりました
-
11月
- 英国版『ブロークバック・マウンテン』とも言うべきエロティックにして感涙必至の超名作映画『ゴッズ・オウン・カントリー』、12月に日本でのラストチャンスとなる劇場公開が決定!
- ゲイカップルの日常を描く『きのう何食べた?』が実写ドラマ化、主演は西島秀俊さんと内野聖陽さん
- 東京都府中市が来年4月から同性パートナーシップ証明制度を導入することになりました
- ジャッキー・チェンの娘、エッタ・ンが同性婚したことを発表
- ぷれいす東京へのチャリティとなるグッズが1週間限定で販売
- 同性愛を描いた資生堂のWeb動画が国際広告賞のグランプリを受賞
- 台湾の住民投票で同性婚は支持されませんでした…が、台湾初の同性愛者の議員が誕生しました
- 台湾のツァイ・ミンリャン監督が、同性婚をめぐる住民投票を前に、初恋のエピソードを初披露しました
- LGBT差別解消法案が、今国会で提出される見通しになりました
- 結婚の平等を正面から問う裁判が行われることになりました
- 神奈川県横須賀市が来年5月に同性パートナーシップ証明制度を導入する方針を発表
- ろう者でミックス・ルーツのトランス男性が「IMGモデル」と契約
- 【米中間選挙】フロリダ州ウィルトンマナーズの市長選&市議選で当選したのは全員ゲイでした
- 【米中間選挙】マサチューセッツ州では住民投票でトランスジェンダー保護の州法が承認されました
- 【米中間選挙】アメリカ初のオープンリー・ゲイの州知事が誕生
- フィギュアスケートを芸術へと昇華させたレジェンドであり、初めてカミングアウトした五輪選手であり、エイズで亡くなったジョン・カリーの栄光と孤独を記録した映画『氷上の王、ジョン・カリー』が来年公開決定
- 米中間選挙に立候補したLGBTは618人、過去最多を記録
- アップルやグーグルなど50社超が、トランプ政権のトランスジェンダー排除政策を非難
-
10月
- 大阪府堺市が、来年4月から同性パートナーシップ証明制度の導入を検討
- ゲイは子孫を残さないのに同性愛遺伝子が消えずに受け継がれているのは「同性愛遺伝子を持つ異性愛者がセクシーで子孫を残しやすいからである」という仮説が提唱されました
- 急速に変わりつつあるキューバで、来年にも同性婚が認められそうです
- 台北プライドに過去最多の13万7000人が参加、結婚の平等を訴えパレード
- 11月開催のラテンビート映画祭で、2本のクィア映画が上映されます
- 台北でレインボーフェスが初開催
- レディ・ガガ、シーア、たくさんの方たちが、トランプ政権によって無きものにされようとしているトランスジェンダーへの支援を表明
- 台湾で同性婚をめぐる住民投票が実施されることになりました
- 日本初のドラァグクイーン・ムービー『ダイヤモンド・アワー』の伝説のショーが二丁目で再演される!
- オープンリーゲイのアジア系俳優、B・D・ウォンが結婚式を挙げました
- 英ヴァージン航空が乗員全員がLGBTという世界初の「プライドフライト」を運航
- テイラー・スウィフトが政治的沈黙を破り、「同性婚を支持しない人には投票できない」と語りました
- 東京都でLGBT等への差別を禁じる人権尊重条例が成立、都道府県として初
- 大阪の「レインボーフェスタ!」が参加者1万人超えで大成功 札幌や津でもパレード開催
- 『弟の夫』で内外の様々な賞を受賞した田亀源五郎氏を祝うパーティが開催されます
- 大阪市が同性カップルの市営住宅入居を承認し、11月から募集をスタート
- ゲイだらけのアパートを舞台にした演劇『-初恋2018』が上演中、全国ツアーも
-
9月
- セサミストリートの元脚本家が「バートとアーニーはゲイカップル」だと認めたことについて、バート役の声優が「素晴らしい」とコメントしました
- 英国ロイヤルファミリー初のゲイ・ウェディングが行われました
- 『新潮45』休刊発表 新潮社への抗議集会の直前に
- 香港政府が正式に同性パートナーへの配偶者ビザの発行を承認しました
- 在日米国商工会議所が「LGBT支援を進めれば生産性が上がる」と政府に提言しました
- レインボーフェスタ!にはるな愛さんが登場!
- 東京都豊島区でも同性パートナーシップ証明制度導入へ 渋谷区に続き、条例制定を目指す意向
- メアリー・デイリー氏が米サンフランシスコ連銀総裁に 同性愛者として初
- エミー賞で『ル・ポールのドラァグレース』が史上初の快挙を達成
- 東京都がLGBT差別解消とヘイトスピーチ抑止を目指す条例案を発表しました
- 安室ちゃんへの愛を全身で表現してきたドラァグクイーンのアブラマミレさんが、琉球新報に載りました
- 全米オープン最年少出場記録を持つ日系アメリカ人のゴルフ選手がカミングアウト
- 『クィア・アイ』『ル・ポールのドラァグレース』がクリエイティブアーツ・エミー賞を多数、受賞しました
- IVANさんがトランスジェンダーとして初めて東京ガールズコレクションのブランドステージのトリを飾りました
- 「プライドハウス東京」がキックオフ、大会終了後はLGBTユースが安心・安全に過ごせるセンターへ
- インドでソドミー法が撤廃され、同性間の性行為が合法化されました
- 中野区で同性パートナーシップ証明制度がスタートし、証明書の交付式が行われました
- キース・ヘリング生誕60周年を祝うオフィシャルパーティがageHaで開催、ジュニア・ヴァスケスの最後の来日公演となります
- 町田市の東友美市議がカミングアウト
- 2017年の新規HIV感染者数が、11年ぶりに1400人を下回りました
-
8月
- トランスジェンダーの保坂いづみ市議が根室市長選へ出馬
- ドイツ政府が第三の性を承認、公的書類の性別欄に「ディバース」が追加されることに
- ジェイソン・ムラーズ、ブレンドン・ユーリー、マックス・ビーミス…ミュージシャンが相次いでカミングアウト
- ポスト・ザック・エフロンの呼び声も高い若手俳優のギャレット・クレイトンがカムアウト
- ゲイゲームズinパリが閉幕、台湾勢が金10個獲得
- 【追悼】アレサ・フランクリン
- 【二次受付あり】「AMR-安室奈美恵ナイト」が公式イベント「namie amuro Final Space」とコラボ!
- 全米初!トランスジェンダーの州知事候補が誕生
- 祝!マドンナ60歳
- ロバート・キャンベル東京大名誉教授がカミングアウト、衆院議員によるLGBT差別発言への批判として
- 東京医大が、女性の一律減点だけでなく、同性愛傾向があるかどうかを尋ねる差別的な適性テストを実施していたことが明らかに
- 国境や法の制限を越えて誰もが「結婚」できるプラットフォームが注目されはじめています
- ジェットエアウェイズのパイロットがゲイの乗客の「命を救った」と感謝されています
- 住む家をなくしたLGBTのための支援ハウスをつくる運動が始まっています
- 宮崎県庁がレインボーにライトアップされています
- 第10回ゲイゲームズinパリ、今週末から開催
- ダン・レイノルズ主催のLGBTチャリティ・フェスでAppleのティム・クックがスピーチ、「LGBTは世界への贈り物です」
-
7月
- 立憲民主党が同性婚法整備を検討、差別解消の一環として
- 9monstersでスクエア・エニックス社製ゲームアプリ「DJノブナガ」がキャンペーンを展開
- 中野区の同性パートナーシップ証明:8月20日から宣誓書提出の予約を受付、受領証交付は9月から
- シンガポールのPINK DOTが第10回を迎え、「建国の父」リー・クワン・ユーのお孫さんがカムアウトしました
- 【追悼】トニー賞俳優のゲイリー・ビーチ
- 青森レインボーパレードを主催してきた岡田実穂さんが青森市議選に出馬します
- スカーレット・ヨハンソンがトランスジェンダー役を当事者に譲り、賞賛されています
- ソウルでプライドパレード開催、数万人が参加
- 同性のパートナーを殺害された遺族の方が、犯罪被害遺族給付金の支給が認められず、裁判を起こしました
- 大阪市で同性パートナーシップ証明制度がスタート、カード型の証明書も発行
- 香港最高裁が、香港在住の英国人レズビアンカップルに対し、家族ビザと同等の就労権を認めました
- さいたま市が同性パートナーシップ証明制度の導入を決定、県や他の自治体に取組みを求める運動もスタート
- 仙台で7月7日・8日に「せんだいレインボーDay」開催、清貴さんらも出演
- お茶の水女子大がMtFトランスジェンダーの受入れを決定、2020年度から
-
6月
- 一橋大アウティング事件の裁判で同級生と遺族が和解、大学とは訴訟が続きます
- 名古屋市が同性パートナーシップ証明制度の導入を検討
- 女性装の東大教授・安冨歩氏が東松山市長選への出馬を表明
- WHOの「国際疾病分類」が改訂され、性同一性障害が「精神疾患」から外れることになりました
- エリザベス女王のいとこが英王室初の同性婚へ
- 【追悼】現存する最古のゲイディスコ「NEW SAZAE」のママ、紫苑さん
- 長崎市でも同性パートナーシップ証明制度が導入されることになりました
- 東京都が今月30日まで、LGBT差別禁止条例案についての意見を受け付けています
- 「LGBTの戦後史」という壮大なドキュメンタリーが6/16、Eテレで放送
- トニー賞授賞式で『エンジェルス・イン・アメリカ』に主演したアンドリュー・ガーフィールドがLGBTに捧げる感動のスピーチを披露
- レディー・ガガ、歴代のゲイアイコンが主演した名作『スタア誕生』で満を持して映画初主演
- 同性パートナーシップ証明制度の導入を求める会が全国27自治体に一斉請願を行いました
- プライド月間を祝し、アリアナ・グランデがLGBTQコミュニティにラブレターを贈ってくれました
- Shangri-La@ageHaに代わるパーティ"Tokio"が始動−−“It’s a Brand-new Gtopia”
-
5月
- 勝間和代さんのカミングアウトに賞賛の声、続々
- SUUMOが同性カップルの家探しの実状に迫る調査結果を公表、部屋探しで苦労したという人が4割に
- 今年も日テレ『映画天国』でLGBT映画祭開催
- 東京都が里親の認定基準を緩和、同性カップルも養育里親として認められることになりました
- 同性パートナーシップの公的認証やLGBT差別禁止施策の導入を求め、埼玉県の6市町で一斉に請願が行われます
- 東京都の条例案について、LGBT法連合会が「実効性が不明瞭」との声明を発表
- 東京都がLGBT差別解消を目指す条例の骨子案を発表、9月議会提出、来年春施行へ
- 中野区で8月から同性パートナーシップ証明制度がスタート
- 「弟の夫」が第47回日本漫画家協会賞の優秀賞を受賞しました
- 浜崎あゆみさんも出演した東京レインボープライド2018が、過去最高の約15万人の参加者で盛り上がり、大成功を収めました
- 今年はフジテレビ社屋だけでなく、自由の女神像と東京ビックサイトもレインボーカラーに
-
4月
- 東京レインボープライド2018がスタート!
- 千葉市が来年度から同性パートナーシップ証明制度を導入する方針を固めました
- 歌手・女優のジャネール・モネイがパンセクシュアルであるとカミングアウト
- 40年以上連れ添ったパートナーの火葬に立ち会えず、共同経営の会社も親族に奪われるという不条理に対し、ゲイ男性が裁判を起こしました
- タイでもうすぐ同性婚が認められそうです
- 米ディズニーランドで、レインボーカラーのミッキー・イヤーが発売
- 『glee』アーティ役のケビン・マクヘイルがカミングアウト
- TRP2018前夜祭に大黒摩季さんが出演!
- TRP2018のメインゲストとして浜崎あゆみさんの出演が決定!
- 中国「新浪微博」での同性愛コンテンツ禁止措置が、反対運動によって撤回されることになりました
- 5月4日、ドラマ『弟の夫』全3話が地上波で放送!
- 神奈川県がLGBT支援事業を本格化、相談員の派遣も実施
- ボブ・ディランやケシャが、ウェディング・ソングを同性婚向けに歌い直すコンピレーションに参加
- IVANさんと野村祐希さんの交際報道に祝福の声が上がっています
- ジェイ・Zが、母親のカミングアウトに安堵の涙を流した時のことを初めて語りました
- 福岡市で「パートナーシップ宣誓制度」がスタート、14日にはKABA.ちゃんが登場するトークショーも開催
- 4月1日、熊本と大阪でパレードが行われました
-
3月
- 中学の道徳の教科書にLGBTのことも載るようになりました
- フロリダ州の高校で起きた銃乱射事件のサバイバーでオープンリー・バイセクシュアルのエマ・ゴンザレスが、沈黙の演説で世界を感動させました
- セザール賞、リュミエール賞で最多6部門を受賞した映画『BPM ビート・パー・ミニット』が公開されました
- 今年もダイヤモンド社から『Oriijin(オリイジン)』が発売されました
- SATCミランダ役のシンシア・ニクソンがNY州知事を目指します
- 性的マイノリティの高校生の約1/3が自傷を経験していることが明らかになりました
- 千葉市が同性パートナーシップ証明制度の導入を検討
- 「カラフルステーション」「irodori」が惜しまれながら3月末に閉店
- 第2回レインボー国会が開催され、東京2020大会が「多様性の祝祭」となるよう、スポーツ界でのLGBT差別解消に向けた有意義な議論が行われました
- 歌川たいじさんの『母さんがどんなに僕を嫌いでも』が映画化、今秋公開
- 大阪市の同性パートナーシップ証明制度は9月までに施行、企業向けガイドラインも作成
- アメリカ全土での結婚の平等を勝ち取った弁護士のエヴァン・ウォルフソン氏が来日します
- 京都で「OUT IN JAPAN」写真展&トークショーが初開催されます
- 同性婚実現後初となる第40回シドニー・ゲイ&レズビアン・マルディグラ・パレードが盛大に開催、シェールも登場
- 第90回アカデミー賞でトランスジェンダー映画『ナチュラルウーマン』が外国語映画賞に輝き、ジェームズ・アイヴォリーが脚色賞を受賞
- 不朽の名作ゲイ映画『モーリス』が、30年の時を経て4K無修正版で公開されます
- 東京都が2020年に向けてLGBT担当部署を立ち上げる意向を表明、2018年度内に条例も制定
- 世田谷区で、LGBTと外国人への差別を禁じる条例が成立しました
- 第2回レインボー国会、開催決定
- 大阪市が同性パートナーシップ証明制度の導入を検討すると発表
- FtMユニット「SECRET GUYZ」が惜しまれながら解散……一方、同じスターダストからMtFユニット「秘密のオト女」がデビュー
-
2月
- 【平昌五輪】チームLGBTの獲得メダル数は金2銀2銅3、記録更新も多数
- 【平昌五輪】エリック・ラドフォードとガス・ケンワージーがプライドハウスを表敬訪問
- 【平昌五輪】ガス・ケンワージー選手と彼氏のキスが全米に生中継され、「歴史的な瞬間」と反響を呼びました
- 米LGBT団体GLAADがブリトニーに栄誉ある賞を贈ることになりました
- ゲイドラマの金字塔『クィア・アズ・フォーク』の日本語字幕付き上映会が二丁目で開催
- ドラマ『弟の夫』メインビジュアル公開、原画展やトークショーも開催決定
- 「バーバリー」のチェック柄がレインボーカラーに…LGBTQ支援の心意気として
- 【注意】A型肝炎が流行しています
- 東京都国立市が「アウティングの禁止」を盛り込んだ条例を初めて制定しました
- 【平昌五輪】カナダのエリック・ラドフォードが冬季五輪初の金メダルを獲ったゲイの選手となりました
- 【平昌五輪】オランダのイレーネ・ウースト選手が今大会のLGBTアスリートの中で初のメダル獲得者となりました
- 福岡市が同性パートナーシップ証明制度を導入する方針を固めました
- 【平昌五輪】今回出場するLGBTアスリートは、冬季五輪としては過去最高の15名
- ミャンマーのヤンゴンで初のオープンLGBTイベントが開催
- ホテルが同性カップルの宿泊を拒否することがないよう、厚労省が全国の自治体に通達を発しました
-
1月
- サンダンス映画祭2018グランプリ獲得作品は「治療」施設に入れられた同性愛者の物語
- 韓国初のオープンリー・ゲイのアイドル「Holland」が鮮烈にデビュー、MVでは男の子とのキスシーンも
- アメフト部出身でGAYかつHIV+とカミングアウトしているコリー・ジョンソン議員が、NY市議会の議長に選ばれました
- インドのマンベンドラ王子が同国のLGBTを受け入れる施設を建設
- リッキー・マーティンが結婚!
- オーストラリアで同性婚が正式にスタート、陸上選手カップルも誕生
- 【平昌五輪】フィギュアのアダム・リッポンがアメリカ初の五輪出場を決めたオープンリーゲイの選手になりました
- エレン・ペイジが同性婚
- NHK朝ドラ『半分、青い。』にゲイの美青年が登場
-
12月
-
2017
-
12月
- 京都府長岡京市の小原市議がゲイであることをカミングアウト
- 大津市がLGBT支援宣言、同性パートナーシップ証明制度の導入も検討
- 岐阜県関市が印鑑登録証明書をはじめとする78の公文書の性別記載を削除することを発表
- フジテレビが新ドラマ「隣の家族は青く見える」でゲイカップルをフィーチャー、主題歌はあのミスチル
- マネックス証券が同性カップルのための「パートナー口座」サービスを開始
- 米国防総省が、司法判断を受け、来年からトランスジェンダーの入隊を受け入れると発表
- オーストラリア連邦議会で同性婚法案が可決されました
- 東京都港区議会で同性パートナーシップの認証などを求める請願が採択されました
- オーストリアも同性婚承認へ、世界で26ヵ国目
- 『弟の夫』ドラマ化が大反響、マイク役に把瑠都を起用したことも好評
- 来年度から性別適合手術に保険が適用される見通しとなりました
- 人権週間に合わせ、広島城や神奈川県庁本庁舎がレインボーにライトアップされます
-
11月
- トルドー首相がカナダの過去の性的マイノリティ迫害を公式に謝罪、涙を拭う場面も
- 「TOKYO AIDS WEEKS 2017」がスタートし、中野区役所にレッドリボンが掲げられました
- 台湾の同性婚実現の立役者である活動家の祁家威氏に総統文化賞が贈られました
- 元女子バレー選手の滝沢ななえさんが同性愛者であることをカミングアウト
- 米地方選でトランスジェンダーの議員が多数当選、全市議会議員がLGBTとなった市も誕生
- オーストラリアの同性婚をめぐる自主投票で賛成が反対を大幅に上回り、ターンブル首相がクリスマスまでに同性婚法案の成立を目指す意向を示しました
- 日本人の同性パートナーと20年以上連れ添ったにもかかわらず国外への退去を命じられた台湾籍のゲイの方が、男女の事実婚カップルと同様の特例許可を求めて訴訟を起こしたことに関連し、同性国際カップルの在留資格をめぐるシンポジウムが開催されます
- ジョージ・タケイさんが来日し、国会議員と意見交換を行いました
- 福岡で九州レインボープライドが開催、福岡市によるサプライズも
- モデル/俳優のコルトン・ヘインズが同性婚
- クリステン・スチュワート、スーパーモデルの恋人と結婚秒読みか
- 米ディズニー・チャンネルで史上初めてのゲイのキャラクターが登場
-
10月
- 2022年のゲイゲームズが香港で開催されることが決定、アジア初の快挙
- 台北でアジア最大のプライドパレード開催、参加者は過去最多の約12万3000人
- 来年刊行の「広辞苑」第7版に「LGBT」の項目が追加されることになりました
- 台湾同志遊行(Taiwan LGBT Pride)のTRPフロートにMISIAさんが登場!
- 元でんぱ組.incの最上もがさんがバイセクシュアルであることをカミングアウトしました
- 「OUT IN JAPAN」札幌撮影会で、滝川市議の舘内孝夫さんがカミングアウト
- 祝!尾辻かな子さんが衆議院議員に初当選
- LGBT法連合会が衆院選候補者および各党に政策アンケートを実施、調査結果が掲載されました
- 名古屋大学内に日本初のジェンダー専門図書館「ジェンダー・リサーチ・ライブラリ」がオープン、オールジェンダートイレも設置
- サム・スミスの新しい恋人は俳優のブランドン・フリン
- 10月22日(日)、あなたの未来への一票を投じましょう
- 5年ぶりとなる奥津直道さんの個展が開催中
- ジャッキー・チェンの娘がレズビアンであることをカミングアウト
- ”Shangri-La@ageHa”が今年いっぱいでその輝かしい歴史に幕を下ろすことが発表されました
- 伊勢丹新宿店、ドラァグクイーンが多数登場するファッションパレードを開催
- 楽天銀行が「スーモカウンター新築マンション」と提携し、同性パートナーシップ証明書等の提示なしに利用できる住宅ローンの提供を開始します
- 文京区が事業者向け契約書類にLGBT差別禁止を明記しました
- ドイツで「すべての人のための結婚」がスタート、日曜でも窓口を開けてくれた自治体も
- 日本学術会議が性的マイノリティ差別を解消する法律の制定や「結婚の平等」を提言しました
- 9月
-
8月
- 史上初めて有名ファッションブランドが黒人ゲイカップルを広告に起用
- 愛知県豊明市がLGBT支援宣言
- 性分化疾患の方が性別適合手術を受けずに戸籍上の性別を変更することを認められました
- 厚労省が全国の児童養護施設に「性的マイノリティの子どもに対するきめ細かな対応の実施」を通知しました
- グッド・エイジング・エールズの松中さんが東京五輪での「プライドハウス」の設置に向けて本格始動
- かつてトップ・アイドルだったアーロン・カーターが、バイセクシュアルであることをカミングアウトしました
- 韓国政府が、同性愛を処罰する軍刑法の改定を検討しはじめました
- オープンリー・ゲイのエドワード・エニンフルが英版『ヴォーグ』誌の編集長に就任
- 聴覚障害を持つ子どもにLGBTへの理解を深めてもらうためのDVDが制作されています
-
7月
- 日本で初めて自認する性別での通学を認められたトランスジェンダーの小学生がこの春、高校を卒業し、社会人になりました
- トランプ大統領の「トランスジェンダー従軍禁止」発言に対して各方面から一斉に非難の声が上がりました
- 琉球銀行が、夫婦で住宅ローンを組む制度を同性カップルにも拡大することを発表
- 自殺総合対策大綱が見直され、性的マイノリティに関する施策も引き続き盛り込まれました
- 雨にも負けず、8万5千人が行進−−ソウル・クィア・パレード
- 改正刑法が施行され、男性へのレイプも厳罰化されることになりました
- 欧州で最もゲイフレンドリーとされる地中海の島国・マルタで同性婚が認められました
- 第26回レインボー・リール東京が開幕!
- みずほ銀行が住宅ローンについて同性カップルも配偶者扱いとすることを発表
- 文京区の前田邦博区議がカミングアウト、LGBT自治体議連発足で
- トランス女性の麻倉ケイトさんがハリウッドデビューへ
- ソウルクィアパレード開催、東京レインボープライドもフロートを出展
- ドイツ国会で同性婚を認める法案が可決され、年内に施行される見通しとなりました
-
6月
- 都議選の候補者へのLGBT関連政策アンケートが実施されています
- 6月のプライド月間に世界各地でパレードが開催されました
- ドイツで同性婚が認められる見通しとなりました
- グーグルやマイクロソフトなど50社が連邦裁判所に意見書を提出、同性愛者擁護を訴え
- 【ご協力のお願い】海外旅行に関するアンケート調査を実施中
- ユジク阿佐ヶ谷でLGBT映画特集
- 世田谷区で同性カップルが区営住宅に入居できるようにする条例改正案が可決されました
- 性別適合手術を受けていながら男性の更衣室の利用を強要されたMtFトランスジェンダーの方がコナミスポーツクラブを訴えていた裁判で、和解が成立しました
- セルビアでオープンリー・レズビアンの首相が誕生、東欧初
- 第5回ピンクドット沖縄、9月23日(土祝)に開催
- 1990年代のパリでエイズと闘いながら、愛しあい、力強く生きたゲイの若者たちの輝きを描いた映画『BPM』が、カンヌ国際映画祭でグランプリを受賞
- 『AERA』がLGBTを大特集
- アイルランドで初めて閣僚としてカミングアウトしたレオ・バラッカー氏が、同国初のゲイの首相となる見通しに
- 札幌市で「パートナーシップ宣誓制度」がスタート
- Googleトップページが8色のレインボーフラッグに
- 5月
-
4月
- 東京レインボーウィークに合わせて「OUT IN JAPAN」写真展が新宿マルイ メンとSHIBUYA TSUTAYAで開催!
- BuzzFeed JapanがLGBT特集を掲載、東京レインボープライドにも参加
- 東京都文京区が、性的マイノリティが行政窓口や学校で差別的な言動を受けないようにするための職員・教員向けの対応指針を策定しました
- 4月30日にEテレで「オネエ」問題を検証する番組が放送されます
- 早稲田大学に性的マイノリティ学生を支援する「GSセンター」がオープン
- 一橋大学ロースクールのゲイの学生が自殺した事件の裁判について遺族側が記者会見「彼が亡くなったのは、彼が同性愛者だからではない。同性愛者を差別し、蔑み、認めない社会があるからだ」
- 東京オリンピック・パラリンピックに関わるすべての企業がLGBT施策の実施を求められることになりました
- 5月7日(日)の東京レインボープライドに中島美嘉さんがスペシャルライブ出演!
- バリー・マニロウがゲイであることを初めて公に語りました
- 大阪市が全国で初めて同性カップルを里親に認定
- 2016年の新規HIV感染はほぼ前年同様、横ばい状態
- 【追悼】レインボーフラッグをデザインしたギルバート・ベイカー
-
3月
- 札幌市のパートナーシップ制度が6月から施行されることが正式に決定しました
- 同性カップルも一緒のお墓に入れる時代になりました
- ダイヤモンド社からLGBTをフィーチャーした新雑誌『Oriijin(オリイジン)』が刊行
- FTMトランスジェンダーの細田智也さんが入間市議選で初当選
- 国会議員にLGBTへの差別をなくすための法律の制定を求める「レインボー国会」に約300名が集まりました
- ゲイの韓国系アメリカ人青年を描いた映画『SPA NIGHT』がジョン・カサヴェテス賞を受賞
- 妻夫木聡さんがゲイの役で日本アカデミー賞最優秀助演男優賞を受賞し、恋人役の綾野剛さんと熱く抱き合いました
- 国のいじめ防止基本方針に、LGBTの生徒へのいじめを防止するために教職員の理解を促進するよう明記されることになりました
- 2月
- 1月
-
12月
-
2016
- 12月
-
11月
- 渋谷区がコミュニティスペース「#渋谷にかける虹」を設置、東京レインボープライドがイベント運営
- 「ゲイコミュニティを勇気づけたい」と世界王座に挑んだボクシングのオルランド・クルス
- エレン・デジェネレスが大統領自由勲章を受章
- リッキー・マーティンが婚約しました
- 【追悼】伝説のパーティ「The Loft」を主催したDJ、デヴィッド・マンキューソ
- 邦銀で初めて、東京スター銀行が同性パートナーにも家族優遇を適用
- 千葉市が、同性パートナーがいる市職員も結婚・介護休暇制度を利用できるようにすると発表
- オープンリー・バイセクシュアルのケイト・ブラウン氏がアメリカで初めてカミングアウトして選挙で選ばれた州知事となりました
- レディー・ガガ「愛は憎しみに勝る」、マドンナ「私たちは決してあきらめない」、ケイティ・ペリー「私たちは自分の国を憎しみに支配させたりはしない」、チャド・グリフィン「私たちは闘い続ける。文字通り、命がけで」…トランプ当選のショックを和らげる心強い言葉たち
- 東京国際映画祭でトランスジェンダーの生涯を描いた『ダイ・ビューティフル』が観客賞と主演男優賞を受賞、日本での公開も決定
- 10月
-
9月
- 【追悼】トランスジェンダー女優(ドラァグクィーン)アレクシス・アークエット
- 性の多様性を無視した学習指導要領を変えるため、声を届けましょう
- 今年のエミー賞授賞式は素晴らしくクィアでした
- 宇多田ヒカルさんが同性愛者のストレートへの恋心を歌った新曲「ともだち」を披露!
- 国連でLGBTの人権をめぐる初の首脳級会合が開催されました
- オーストラリアで同性婚合法化の是非を問う国民投票が行われるかもしれません
- 沖縄県浦添市がLGBT支援宣言へ
- 同性カップルにも関連する内容が含まている民法改正案に対して9月末まで意見募集中です
- ソフトバンクも社内で同性パートナーを家族と認め、慶弔休暇などを付与
- 京都市が若者を対象にLGBTについての意識調査を実施、性的マイノリティが暮らしやすい社会をつくるための取組みが必要と回答した人が8割超
- 台湾で世界初のトランスジェンダーの閣僚が誕生
-
8月
- ローランド・エメリッヒ監督の映画『ストーンウォール』が今冬、公開決定
- 連合が勤労者1000人に調査を実施し、セクシュアルマイノリティが8%、職場のLGBT差別をなくすべきとの回答が8割超となりました
- ネット調査で「我が子がセクシュアルマイノリティなら受け入れる」と回答した親が9割に
- 東京海上日動火災保険が同性パートナーを「配偶者」として扱う火災保険や自動車保険を開発
- 虹色ダイバーシティが同性パートナーシップ証明制度を施行した各自治体の登録数を発表
- 【リオ五輪】LGBTIアスリートのうち25人がメダルを獲得【更新】
- 【リオ五輪】ゲイやレズビアンの選手が公開プロポーズ!
- 岐阜県関市がLGBT支援宣言
- 【リオ五輪】世界で最も有名なトランスジェンダーモデル、リア・Tが五輪開会式に出演した初のトランスジェンダーに
- 台湾で年内にも同性婚法案が国会に提出される見通し
-
7月
- 【リオ五輪】リオ五輪に出場するオープンリーLGBTIの選手は過去最高の53名【更新】
- フィリピンで初めてトランスジェンダーの国会議員が誕生
- 楽天が同性カップルにも配偶者と同等の福利厚生を適用、楽天ウェディングなど5サービスでもLGBT向けの取り組みを実施
- 【改定】今回の都知事選でLGBT施策を掲げる候補者は?
- セクシュアルマイノリティをフィーチャーした特番「FOXレインボーアワー」が放映
- ピンクドット沖縄で那覇市の同性パートナーシップ証明制度第1号のゲイカップルが結婚式を挙げ、MAXのLINAさんや中島美嘉さんらが祝福しました
- 第25回レインボー・リール東京が開幕!
- 映画祭で「OUT IN JAPAN」1000人の写真展が開催決定、レスリー・キー氏の映画上映も!
- 京都で古橋悌二『LOVERS』展が開催、OKガールズら出演のクラブパーティも
- 那覇市が全国5例目となる同性パートナーシップ証明を8日から施行、17日のピンクドット沖縄ではゲイカップルの結婚式も
- 米軍がトランスジェンダーの従軍禁止措置を撤廃し、関連医療費も負担することに
- 三重県議会で「性的少数者に対する差別の解消と共生社会を実現するための法整備を求める意見書」が全会一致で可決されました
-
6月
- 世界各地でプライド・パレード開催、銃乱射事件の犠牲者への追悼も
- 日本でも企業のLGBT施策を評価する「PRIDE指標」が策定されることになりました
- ゲイ解放運動のメッカ「ストーンウォール」が国定史跡に!
- 7月10日(日)の参院選における各政党・候補者のLGBTに関する公約・考えが発表されました
- 英国のウィリアム王子がゲイ雑誌の表紙に!
- ソウルのプライドパレードに5万人が参加し、盛り上がりを見せました
- 二丁目でオーランド銃撃事件の犠牲者を追悼するイベントが行われました
- 博報堂の調査で、性的マイノリティ人口が8%にのぼると発表されました
- 兵庫県宝塚市が同性パートナーシップ証明制度をスタート、全国で4例目
- 5月
-
4月
- 【熊本地震】札幌でチャリティイベント開催
- 【追悼】戦後を代表するクィア・アイコンの一人、戸川昌子さん
- 【追悼】本当に多くの方たちに愛されたゲイタレント・前田健さん
- 【熊本地震】ゲイシーンでも被災地支援が始まっています
- 伊賀市の20代カップルが同性パートナーシップ証明取得第1号に
- ミシシッピ州の反LGBT法に抗議し、ブライアン・アダムスが公演をキャンセル
- コロンビアが世界で20番目の同性婚を認める国となりました
- ノースカロライナ州のトランスジェンダー差別法案に抗議し、ブルース・スプリングスティーンが公演をキャンセル
- アメリカ全50州で同性カップルが養子を迎えることが可能になりました
- 伊賀市パートナーシップ宣誓制度がスタートし、市役所前で記念イベントが行われました
- 3月
-
2月
- イタリア上院がシビルユニオン法案を可決しました
- 台湾の台南市と新北市、嘉義市でも同性パートナー登録がスタート
- 那覇市が7月をめどに同性パートナーシップ証明の要綱を制定
- 【改訂版】日本航空が全日空に続き、同性パートナーを家族と認め、マイル特典利用がOKになりました
- パナソニックが社則を改定し、同性カップルも結婚に相当する関係と認めることになりました
- 三重県伊賀市が同性パートナーシップ証明制度の導入を正式決定、全国で3例目
- LGBTに関する職場環境アンケートがスタート
- FC琉球がレインボーカラーをあしらった新ユニフォームを採用
- レディー・ガガ、同じ年でスーパー・ボウル、グラミー賞授賞式、アカデミー授賞式でパフォーマンスを行う初めてのアーティストに
- 文化庁メディア芸術祭受賞作品展が開催されています
- 1月
-
2015
-
12月
- 名古屋にセクシュアルマイノリティのためのグループホームがオープンしました
- ギリシャでシビルユニオンが認められました
- 中国のゲイカップルが同性婚を求めて訴えを起こしました
- 「どんな性別でも使えるトイレマーク」最優秀賞が発表されました
- アメリカのLGBT事情を視察してきた方たちによる報告会が行われます
- 三重県伊賀市も来年4月から同性パートナーシップ証明を始めます
- 民主党が来年の通常国会で性的少数者への差別の解消を推進する法案を提出する意向を固めました
- 千葉市が同性パートナーシップ証明に前向きな姿勢を示しました
- レディー・ガガがゴールデングローブ賞主演女優賞候補に
- 日本IBMが同性パートナー登録制度を新設
- 那覇市も同性パートナーシップ証明を検討することになりました
- 虹色ダイバーシティの村木真紀さんが「ウーマン・オブ・ザ・イヤー2016」を受賞!
- 名門ソウル大学の学生会長にレズビアンであることをカミングアウトしたキム・ボミさんが選ばれました
- 宝塚市が宣誓方式で同性パートナーシップ証明を行う要綱を制定すると発表しました
-
11月
- 田亀源五郎さんの『弟の夫』が第19回文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞を受賞
- 『モダン・ファミリー』の俳優、リード・ユーイングがカミングアウト
- ベテラン俳優のネイサン・レイン、長年の同性パートナーとニューヨーク市庁舎で結婚!
- 東京フィルメックスで『酔生夢死』上映、ツァイ・ミンリャン特集も
- パッション・ピットのフロントマン、マイケル・アンジェラコスがカミングアウト
- NHK『サキどり』がLGBTを特集し、Eテレ『ハートネットTV』が歌川さんをフィーチャー
- いよいよ11月14日(土)から橋口監督の『恋人たち』が上映スタート!
- ライフネット生命をはじめ大手生保各社が同性パートナーを死亡保険金の受取人に指定できるようにすると発表
- 渋谷区と世田谷区で、日本で初めて同性カップルにパートナーシップ証明書が交付されました
-
10月
- 渋谷区で同性パートナーシップ証明書の申請受付けがスタート
- REACH Online 2015がスタート!
- 11月5日から渋谷区と世田谷区で同性カップルの証明書が発行されます
- 世田谷区職員の互助会が同性婚カップルに祝い金を出すことに
- オノ・ヨーコ&ジョン・レノン「基本的に人類はみなバイセクシュアルに違いない」
- NHKがLGBTへのアンケートを実施中
- 中野区で団体が立ち上がり、LGBTシンポジウムが開催されることになりました
- ダスティン・ランス・ブラックとトム・デイリーが婚約!
- フィギュアのジュニア王者アダム・リッポンがカミングアウト
- 奈良市が自治体として初めてIGLTA(国際ゲイ&レズビアン旅行協会)に加盟
-
9月
- 同性カップルのダブルルーム宿泊の拒否について豊島区が改善を指導
- 『東京グラフィティ』がついにLGBTカップルをメイン特集&表紙に!
- レディー・ガガの新曲MVにFTMトランスジェンダーが登場
- 今夜Eテレで「LGBTの就労」をテーマにした番組が放送されます
- キース・ヘリングの生涯を描いたミュージカルが来年6月に日本初上陸!
- ゲイ映画「デスデ・アジャ(原題)」が第72回ベネチア国際映画祭金獅子賞に輝きました
- 国勢調査2015:同性カップルの扱いは?
- アメリカでLGBTムービーの公開ラッシュ、同性婚承認が後押し
- パンセクシュアル宣言したマイリー・サイラスがMTVアワードでドラァグクイーンと共演!
- 『AERA』がLGBTを特集
- 8月
- 7月
-
6月
- アメリカ初のオープンリー・ゲイの現役プロ野球選手が歴史的初勝利をあげました
- 全米での結婚の平等の実現にセレブも次々に祝福!
- 歴史的勝利!ついに全米で結婚の平等が達成されました!
- 「Best of IBM」に選ばれたビジネスマンがカミングアウト
- 淀川区に続き、那覇市がLGBT支援宣言へ
- 池上彰さんが「ニュースそうだったのか!!2時間SP」でLGBTについて解説
- 俳優の青木結矢さんがゲイであることをカミングアウト
- ソウルのパレードが無事に開催されることになりました
- チャニング・テイタムやマット・ボマーらがロサンゼルスのパレードに参加
- グアムで同性婚が認められ、結婚証明書の発行が始まりました
- ソウル・クィア・カルチャー・フェスティバルが開幕しました
- LGBTに優しい高齢者向け施設の建設が実現しそうです
- 【署名のお願い】ソウルのパレードが中止に追い込まれようとしています
-
5月
- 昨年の新規HIV感染者数が発表されました
- グリーンランドで同性婚が認められました
- 【5周年のご挨拶】
- カンヌ国際映画祭で、女性どうしの恋を描いた作品『CAROL』のルーニー・マーラが女優賞を受賞
- 台湾の高雄で同性パートナー登録が可能になりました
- アイルランドが世界で初めて国民投票で憲法を改正して同性婚を認める国になりました
- 世界的な祭典を祝し、ウィーンにゲイ&レズビアンカップルの信号が登場!
- LGBT法連合会が、国や自治体に差別禁止と支援を義務付ける法律の私案を発表しました
- EU初、ルクセンブルクのベッテル首相が同性婚
- ケイト・ブランシェット、過去に何度も女性と交際したことをカミングアウト
- AKB48の峯岸みなみさんが「女の子ともつきあえる」とカミングアウト
- マイリー・サイラスが女の子ともつきあっていたことがあるとカミングアウト
- 文科省が初めてLGBTの子どもへの配慮を求めるよう全国の学校に通知
- aktaのセーファー・セックス・キャンペーンがスタート!
-
4月
- 祝!上川あやさん、石坂わたるさん、石川大我さんが揃って当選
- 青森でもパレードが行われました
- 英国大使館でゲイカップルが結婚
- 東京レインボープライド2015「パレード&フェスタ」、過去最大規模で晴れやかに
- 電通総研の最新の調査で、日本のセクシュアルマイノリティ人口が全体の7.6%と算出されました
- 杉山文野さんと東小雪さんが外国特派員協会で会見
- タレントの一ノ瀬文香さんと杉森茜さんが同性結婚式・披露宴を行いました
- 「akta」存続の署名が厚労省に提出されました
- 法務省が性的マイノリティをテーマにした人権啓発ビデオを制作しました
- アップルのiOS 8.3でゲイ&レズビアンの絵文字がアップデートされました
- インディアナ州の同性愛者差別法に対しティム・クックらが激しく抗議、州法は修正を余儀なくされました
- LGBT支援法律家ネットワークが同性婚法制化を求め、日弁連に人権救済申し立てを行います
- 大物歌手バリー・マニロウが長年のマネージャーと同性婚
- 東京都の昨年の新規HIV感染者数が発表され、20代で過去最多となりました
- LGBTへの差別禁止や支援のための法制定へ向けた「LGBT法連合会」が設立
- 早稲田大学の学内コンペでLGBT学生センターを設立しようと提案するプレゼンが優勝しました
-
3月
- 渋谷区の新条例に対し、たくさんの祝福や歓迎の声が上がっています
- シドニーのマルディグラの期間中、大手銀行が「GAYTM(ゲイティーエム)」を出現させました
- 歴史的! 渋谷区の同性パートナー条例が可決、成立しました
- 名古屋市議選に立候補予定の安間優希さんが戸籍と異なる性別で選管に受理されました
- 渋谷区の同性パートナー条例案が委員会を通過、31日の本会議で成立の見通し
- 『東京グラフィティ』4月号が「TOKYO RAINBOW GRAFFITI」と題してLGBTを特集
- 宝塚市も同性パートナー条例の制定を検討
- 東京レインボーウィークと東京レインボープライドが一つになり、GWに「東京レインボープライド2015」を開催
- 性的マイノリティの差別解消に向けた超党派議連が発足
- 世論調査で同性婚に賛成する人が反対を上回りました
- 虹色ダイバーシティが「Google インパクトチャレンジ」のファイナリストに選ばれました
- ドラマ「Empire 成功の代償」でゲイ役を演じるジャシー・スモレットがカミングアウト
- 渋谷区議会が「(仮称)渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例案」の審議に入りました
- 世田谷区長、同性パートナーの届け出を受け付けることを表明
- 『TVタックル』で同性婚について議論されました
- 2月
-
1月
- アイルランドの閣僚がカミングアウトし、同性婚推進を表明
- タイの新憲法、「第三の性」を認める方向に
- 【追悼】「ZIP」「ARTY FARTY」のオーナー、ミッキーさん
- アメリカの最高裁が同性婚についての最終判断を下すことになりました
- アカデミー賞ノミネート作品が出揃い、アラン・チューリングの生涯を描いた『イミテーション・ゲーム』などが注目を集めています
- 「ArcH」が2月21日に再オープン!
- ティファニーがゲイカップルを広告に起用
- LUSHが同性カップルにも結婚祝い金を支給、「WE BELIEVE IN LOVEキャンペーン ~LGBT支援宣言~」も実施
- ベトナムで同性婚禁止法が撤廃されました
- LGBTに対する差別の禁止や権利の尊重を基本方針に盛り込んでいる企業が146社に上ることがわかりました
-
12月
-
2014
- 8月
- 12月
- 11月
- 10月
- 9月
- 7月
- 6月
-
5月
- 6月1日から全国でHIV検査普及キャンペーンがスタート
- ロバート・デ・ニーロがゲイだった父親のドキュメンタリーを制作
- ジョージ・タケイ氏が来日!
- いま最もブレイクが期待されるアーティスト、サム・スミスがカミングアウト
- 2013年の新規HIV感染者数が過去最多の1590名と発表されました
- オレゴン州とペンシルベニア州で同性婚が認められ、全米で19州に——国民の支持を背景に
- 兵庫県議会で「同性愛者へのHIV指導必要ない」と発言した井上県議に対し、抗議の声が多数上がっています
- 「多様な性にYESの日」に各地でアクションが行われました
- 【訃報】ディスコの時代から活躍してきた大御所中の大御所、DJ A-ichiさんが急逝
- マイケル・サム選手がドラフト指名を受け、史上初のオープンリーゲイのNFL選手に
- 由緒あるユーロビジョン・ソング・コンテストでひげのドラァグクイーンが優勝
- 同性愛者に極刑を課すと発表したブルネイに対して世界中で非難、抗議、ボイコット運動が起こっています
-
4月
- 5月4日からレインボー・アクション映像祭が開催されます
- 東京レインボープライドに15,000人参加、安倍昭恵さんや夏木マリさんも
- 俳優のマット・ボマーが3年前に同性婚していたことが明らかに
- ジョディ・フォスター、「Lの世界」の女優と結婚
- 2014年版「最もパワフルなゲイセレブリティ」にエレン・デジェネレスが選ばれました
- トム・フォードがアメリカで同性婚していたことを発表
- ジェニファー・ロペス、GLAADメディア賞で表彰
- ローランド・エメリッヒ監督の新作は「ストーンウォール」
- NPO法人パープル・ハンズが上野千鶴子さん講演会を開催
- デボラ・ハリーがバイセクシュアルであることをカミングアウト
- 昨年の東京都のHIV感染者数が発表され、新規エイズ患者が過去最多になりました
- 【追悼】差別と闘いながらハウスという素晴らしい贈り物をくれた「神」フランキー・ナックルズ
- 性別変更後の女性に特別養子縁組が認められ、晴れて母親に
- 『ER』女優のサラ・ギルバートが同性婚
- 「ネオン・トゥリーズ」のタイラー・グレンがカムアウト
-
3月
- イギリスで同性婚法が施行され、ゲイやレズビアンのカップルが一斉に結婚式を挙げました
- 米最高裁で同性婚を勝ち取ったゲイ&レズビアンカップルをモデルとした朗読劇「8」に出演してみませんか?
- 「世界の日本人妻は見た!」4時間SPでベルギーの同性婚が紹介されます
- 札幌の英語スピーチコンテストで17歳の高校生がカミングアウト
- 『ゲーム・オブ・スローンズ』のクリスチャン・ナイアンがカミングアウト
- テキサスなど南部の州で次々と「同性婚禁止は違憲」との裁決が下されています
- 中国の全人代に同性婚法案が提出されました
- ミャンマーで初めてゲイの結婚式が行われました
- アカデミー賞でのジャレッド・レトのスピーチが感動!と話題に
-
2月
- 職場環境改善につながるアンケートが実施されています
- ウガンダの同性愛者厳罰法に対し、日本でも抗議運動が起こっています
- 2月26日、「Russian Open Games」が開幕します
- ロシア大使館前で反同性愛法への抗議アクションが行われています
- ウガンダ大統領、同性愛者に終身刑を科すことができる法案に署名へ
- Facebookがプロフィールの性別を多様化、人称代名詞も選択可能に
- 『X‐MEN』女優のエレン・ペイジがレズビアンであることをカミングアウト
- NFLドラフトの有望株であるマイケル・サム選手がカミングアウト
- アメリカの同性婚カップル、司法手続きも男女と同等に
- イレーネ・ウースト選手、7人のLGBT選手のなかで初の金メダル
- 国連事務総長がソチ入りし、同性愛者差別に抗議
- 森栄喜さんが写真界の芥川賞を受賞
- GoogleがレインボーのロゴでロシアのLGBTを応援
- スコットランドに虹がかかり、同性婚が認められました
- モスクワでプーチン政権の人権問題への対応に抗議するデモが行われました
- 2月9日は都知事選の投票日です
- 1月
-
2013
-
12月
- 「コンピュータの父」アラン・チューリングが没後59年目にして恩赦を受けました
- ユタ州で同性婚が認められ、700組以上が同性婚
- ニューメキシコ州最高裁が同性婚を認めました
- アメリカの元フィギュアスケート選手、ブライアン・ボイタノがカミングアウト
- 『glee』シーズン4最終話にレズビアン役で出演したメレディス・バクスターが同性婚
- 二丁目・仲通りの交差点に「Living Together」の広告が出展されています
- 最高裁が性同一性障害の男性を正式に父と認定しました
- ブラジルで世界最大の合同同性結婚式が行われました
- 「LGBTの学校生活に関する実態調査」にご協力を
- 『コヨーテ・アグリー』のマリア・ベロがカミングアウト
- 「飛び込み王子」トム・デイリーが男性との交際をさわやかに報告
- 11月
- 10月
-
9月
- 石川大我氏が社民党党首選に立候補、当選すれば日本初のオープンリーゲイの党首に
- 映画『恋するリベラーチェ』がエミー賞で最多11部門受賞
- aktaの「Safer Sex Campaign 2013」がスタート!
- エルトン・ジョンが反同性愛法のロシアでコンサート
- レインボーマーチ札幌に1100名超が参加、有終の美を飾りました
- 韓国初の同性結婚式が盛大に行われました
- 台湾の国会に同性婚法案が提出されるそうです
- ワシントン大行進50周年を記念し、バイヤード・ラスティンが大統領自由勲章を授与されました
- 対面型SAFER SEXプログラム「REACH Onsite」のお知らせ
- LUSHがロシアの反同性愛法撤廃を訴えるキャンペーンを行っています
- フロリダ海峡完泳に成功したダイアナ・ナイアドはオープンリー・レズビアンの方でした
- イン・シンクのランス・バス、同性婚へ
- 大阪市淀川区がLGBT支援宣言
-
8月
- ホーチミンでプライドパレード初開催
- 大阪のゲイの弁護士カップルに密着した番組がMBSで放送
- 「プリズン・ブレイク」のウェントワース・ミラーがカミングアウト
- スウェーデンの陸上選手、レインボーカラーのネイルでロシアの同性愛者を支援
- ニュージーランドで同性婚ラッシュ
- 橋口亮輔監督の最新作『ゼンタイ』の試写会がArcHで開催
- エミー賞14部門にノミネートされた『恋するリベラーチェ』の劇場公開決定!
- カリフォルニア州の同性婚、経済効果は約500億円
- ロシアの反同性愛法についてセレブたちが続々とコメントしています
- 俳優のベン・ウィショーがゲイであることと「結婚」したことを公表しました
- レディー・ガガ、完全復活!
- ロシアの同性愛者弾圧に対し、国際社会から批判が相次いでいます
- 劇作家・活動家のラリー・クレイマーが78歳で同性婚
- 7月
-
6月
- 同性婚が認められたアメリカで、セレブたちが次々に喜びをコメント
- カリフォルニア州での同性婚再開を祝し、ウェストハリウッドで人々が歓喜に沸きました
- 米連邦最高裁が結婚を男女間に限る法律を違憲だとする判決を下しました
- 【署名のお願い】ロシア政府がLGBT団体を解体し、同性愛者迫害の正当化につながる法律を制定しようとしています
- 2013年トニー賞最多受賞はドラァグクイーンが主役の『キンキーブーツ』
- ナイジェリアで同性愛者を根こそぎ投獄する法が制定されようとしています
- プライド月間を祝い、ジョン・ルース米国大使がレセプションパーティを開催
- 『glee』にも出演したシャリースがレズビアンであることをカミングアウト
- EテレのハートネットTVが特集「多様な”性”と生きている」をお届け
- 6月1日から全国でHIV検査普及週間がスタート
-
5月
- フランスのゲイカップルが初の同性結婚式を挙げました
- 韓国の映画監督キムジョ・グァンスが今年9月に同性結婚式を挙げます
- 尾辻かな子参議院議員がHIV問題について国会で初質問
- 女性どうしの愛を描いた作品がカンヌ映画祭で大賞を獲得
- ロビー・ロジャースがアメリカメジャーリーグサッカー初のオープンリーゲイの選手となりました
- 中国で初めてパレードが開催されました
- 【追悼】モデル&GOGO BOYの真崎航さん、急逝
- 同性婚がデラウェア州とミネソタ州で相次いで認められ、全米で12州に
- 日本初の同性愛者であることをカミングアウトした国会議員が誕生します
- ロードアイランド州で同性婚法案が成立、米国の同性婚10州に
- 『デス妻』の俳優、タック・ワトキンスがドラマと同じくゲイ・パパであることをカミングアウト
-
4月
- NBAのジェイソン・コリンズ、メジャー現役選手として初めてカミングアウト
- 東京レインボープライド2013に12,000人が参加しました
- 【訃報】日本のHIV予防啓発に多大な貢献をしたDJパトリックさんが亡くなりました
- ニュージーランドがアジア太平洋地域で初めての同性婚を認める国となりました
- フランス上院が同性婚法案を可決し、同性婚実現がほぼ確定しました
- 大阪で法律事務所を開いた弁護士のゲイカップルが朝日新聞に掲載されました
- ライアン・マーフィによるゲイカップルのドラマ「New Normal」が4月18日から放送開始
- 今年は5月にアジアンクィア映画祭が開催されます
- マジック・ジョンソン、ゲイの息子を「誇りに思い、あらゆる形で支援する」
- レインボープライド愛媛が松山にLGBTコミュニティセンターを開設
- ウルグアイが同性婚を認める世界で12番目の国に
- 昨年の東京都の新規HIV感染者数が報告されました
- 『TIME』誌がゲイ&レズビアンカップルのキスを表紙に掲載、「同性婚はすでに勝利した」と宣言
-
3月
- 同性婚について史上初めて連邦最高裁で審理が行われ、過半数の判事が結婚防衛法は違憲ではないかとの見方を示しました
- 『GQ JAPAN』が同性カップルの子育てや結婚を支援する記事を掲載
- ヒラリー・クリントン氏が同性婚支持を表明
- ゲイの息子を守る父親の姿に「全米が泣いた」
- マドンナがGLAADメディア賞にボーイスカウト姿で登場し、「差別撤廃のために革命を」とスピーチ
- 2013年、東京のゴールデンウィークは「レインボーウィーク」になります
- LGBTの職場環境に関するアンケートを実施中
- カーリー・レイ・ジェプセンがゲイを排除するアメリカ・ボーイスカウト連盟に抗議し、イベント出演をキャンセル
- イギリスのベテラン俳優、リチャード・ウィルソンがカミングアウト
- 東小雪さん&ひろこさんが東京ディズニーリゾートで初の同性結婚式を挙げました
- 2月
-
1月
- 橋口亮輔監督最新作『サンライズ・サンセット』が公開中
- 中国で高齢のゲイカップルが結婚宣言
- オバマ大統領、就任式で「ゲイの同胞たちが完全に平等になるまでは、私たちの旅は終わらない」とスピーチ
- フランク・オーシャン、『クラウド アトラス』、『SMASH』などがGLAADメディア賞にノミネートされました
- 『タイタニック』の俳優、ヴィクター・ガーバーがカミングアウト
- ジョディ・フォスターがゴールデン・グローブ賞授賞式でカミングアウト!
- ゲイ・バイセクシュアル男性のHIV対策についてのトークショーが開催
- ドラマ『カイルXY』のマット・ダラスがカミングアウト&婚約を発表
- アンダーソン・クーパーが『Out』誌のマン・オブ・ザ・イヤーに輝きました
- 台湾がいよいよ、同性婚の実現へ向けて動きはじめました
- メーン州で同性婚がスタート
-
12月
-
2012
-
11月
- 同性婚支持に感謝の手紙を送った少女にオバマ大統領が返信
- セクシュアルマイノリティの人権擁護を公約に盛り込むよう都知事候補者にお願いするキャンペーンが展開中
- 昨年の新規エイズ患者数が過去最多に
- 尾辻かな子さんが衆院選に!
- 米大統領選で全50州の勝敗を的中させた統計学者、ネイト・シルバーがカミングアウト
- 東京都エイズ予防月間がスタート
- 今年も年末恒例「gaku-GAY-kai」開催!
- 『RENT』がLGBT Pride Week開催!
- 香港の人気女性歌手デニス・ホーがレズビアンであることをカミングアウト
- フランス内閣、同性婚法案を閣議決定
- ワシントン州が同性婚を認める全米で9番目の州になりました(その他、大統領選に伴うLGBT関連選挙の輝かしい結果を一挙にお伝えします)
- オバマ氏が再選され、メーン州やメリーランド州で同性婚法が採択され、上院で初の同性愛者の議員が誕生しました
- 『シカゴ』のプロデューサーが製作したミュージカル・ドラマ『SMASH』がいよいよ放送開始!
- ブラピが同性婚合法化のために10万ドルを、ブルームバーグNY市長も25万ドルを寄付
- 二丁目を舞台にしたゲイのお芝居「AKA-TONBO!2」が上演されます
-
12月
- レディ・ガガが若者支援のバスをツアーに同行させることを発表
- 東洋経済オンラインでもLGBT連載が始まりました
- 英政府、イングランドとウェールズでの同性婚合法化案を発表
- ケイティ・ペリーがLGBT支援団体から表彰されました
- 【署名のお願い】ナイジェリアでかつてないほど苛酷な反同性愛法が成立しようとしています
- 米ワシントン州で100組超の同性カップルが結婚式を挙げました
- レディ・ガガが同性愛規制をやめると語ったロシアの首相に謝意を表明
- 米連邦最高裁で同性婚の合憲性が初めて審理されます
- NHK Eテレ「Our Voices(アワーボイス)」で同性婚を特集
- 都知事選候補者へのLGBT政策アンケートが行われています
- フジテレビ「スーパーニュース」で同性婚が特集されました
- 愛媛LGBT映画祭が朝日新聞で取り上げられました
- ジェンダー政策をめぐる各党の違いが浮き彫りに
-
10月
- 壇蜜、バイセクシュアルであることをカミングアウト
- ゲイバーやクラブを守るための講演会が開催されます
- 第10回台湾同志遊行に65,000人が参加
- アメリカの保守的な町で1年間ゲイのフリをして暮らした男性の本が話題に
- ゲイの心理カウンセラー・村上裕さんが日テレの「解決!ナイナイアンサー」に出演
- 今年もTokyo SuperStar Awards開催。現在、投票を受付中です。
- ネパールで南アジア初のLGBTスポーツ競技大会が開催されました
- TVなどのメディアがセクシュアルマイノリティの自殺対策を特集
- REACH Online 2012がスタート
- フォトグラファーの町田敏之さんが撮り下ろした「かっこいいカラダ」
- 10代を応援する同人誌「IT'S OK!!」と10代応援サイト「10スタート」が立ち上がりました
- 香港にオープンリーゲイの国会議員が誕生
- レディー・ガガが「レノン・オノ平和賞」を受賞
- 香港のMr.Gayコンテストに日系歌手Baby Mが出演
- 男についてのフォトジン『OSSU』発売を記念した展覧会が開催中
- 世界初の同性婚の立役者、ボリス・ディトリッヒ氏が来日
- 中国のゲイカップルが公開結婚式を挙げました
- 『わたしたちの物語~北京クィア映画祭と十年間の「ゲリラ戦」』上映&トークイベントが東京で緊急開催
-
9月
- 『モダン・ファミリー』のジェシー・タイラー・ファーガソンが同性婚へ
- 『Glee』のライアン・マーフィが同性婚
- メジャーリーグ・チームの元経営者がカミングアウト
- ザック・エフロン、「ゲイだと思われてもかまわない」と語り、同性婚を支持
- ザカリー・クイント&ジョナサン・グロフ、美形俳優どうしのカップルが誕生
- 【速報】沖縄でパレード初開催!
- 今年の関西レインボーパレードは11月10日(土)に開催!
- アメリカの終身刑囚が性別適合手術を受けることを認められました
- 「オーストラリアのパスポートには性別欄が3つある。」という車内広告が登場
- キリストの受難を現代のゲイに置き換えた演劇『Corpus Christi』が上演中
- ふとめなゲイと女子高生の友情を描く映画『ふとめの国のありす』が10/6から上映
-
8月
- オープンリー・レズビアンのロージー・オドネルがパートナーと結婚
- 自殺総合対策大綱が改正され、初めて性的マイノリティの対策が盛り込まれました
- トヨタ・AURISのCMにトランスジェンダーのモデルが起用されました
- パレードも歩いた「レズビアンの父」が都政へ挑戦
- ルーファス・ウェインライトが同性婚
- 美形俳優のエズラ・ミラーがカミングアウト
- ダイヤモンドオンラインのLGBT連載の充実ぶりがスゴイです
- シドニー五輪のメダリストがHIV陽性であることをカミングアウト
- マドンナがサンクトペテルブルク公演で同性愛者を支援、告訴も覚悟のうえで
- 台湾で初めて仏式で同性結婚式が行われました
- ミュージシャンのミーカがゲイであることをカミングアウト
- AFPが同性婚の実現を求める記事を掲載
- ロンドンオリンピックに出場するゲイ&レズビアンの選手は24人
- アメリカ初の女性宇宙飛行士が同性愛者だったことが発表されました
- ベトナムで初のパレード、政府は同性婚も検討しはじめました
- 沖縄での男どうしの恋をテーマにした「American Boyfriend」という展覧会が開催されています
- 米民主党、党綱領で同性婚支持へ
- アメリカで初めて同性愛を描いた作家、ゴア・ヴィダル氏が死去
-
7月
- エルトン・ジョン「HIV予防には愛が必要」と訴え
- 同性婚特需を歓迎するニューヨーク、経済効果は年間200億円超
- ロンドン五輪に出場するゲイの選手は9人
- バーニー・フランク議員が結婚式を挙げました
- 『東洋経済』と『週刊ダイヤモンド』が同時にLGBTを特集
- ミュージシャンのフランク・オーシャン、初恋の相手が男性だったことをカミングアウト
- 米国女子サッカー代表のミーガン・ラピノー選手がカミングアウト
- 二丁目のコミュニティセンター「akta」でセーファーセックスのトークショー開催
- Facebookの共同創設者、クリス・ヒューズが同性婚
- 乙武さんが同性婚を支持「日本でも早く認められるようになればいいな」
- ダイアナ・キングがカミングアウト 、「そうすることが正しいと魂が感じているから」
- CNNの看板キャスター、アンダーソン・クーパーがカミングアウト
- ハンガリーで開催されたユーロゲームズがTVのニュースに
-
6月
- iOS6にゲイの絵文字が追加されます
- LAのゲイパレードを体験して「感動して泣きそうになった」という記事が載っていました
- フランスで来年、同性婚が認められます
- ブリトニー、ゲイのコンテスト出場者を励ます
- 【速報】8月11日(土)、代々木公園でパレードが開催されることになりました
- 東郷健さんを偲ぶ会が開催されます
- プライド月間のフィナーレを飾り、各地でパレードが開催されました
- 【速報】今年のレインボー祭りは8月12日に開催
- ナイキがプライド月間を祝し、スペシャルなデザインのスニーカーを発表
- チェイニー前副大統領の娘、メアリーさんが同性婚
- 生誕100周年が祝されている「コンピュータの父」アラン・チューリングは、同性愛ゆえに非業の死を遂げた方でした
- デンマークで同性婚が認められました
- 大阪で「ハッテン場摘発事件から考える」というセミナー開催、ゲストは「DOCK」のヨシノさん
- ジェームズ・アイヴォリー監督の最新作『最終目的地』で、真田広之さんがゲイ役を演じます
- 6月、世界中でプライドパレードが開催されています
- ジャネット・ジャクソンがトランスジェンダーの映画をプロデュース
- 韓国でゲイ映画『2度の結婚式と1度の葬式』が話題に
- 今年の東京プライドパレードは中止になりました
- アメリカ大使館がLGBTプライド月間を記念し、レセプションを催しました
- AGPがアンチエイジングについてのシンポジウムを開催
- ソウルでゲイパレードが開催されました
- 今年の映画祭は9月開催
- 「東京都HIV検査・相談月間」のサイトにゲイ雑誌が!
-
5月
- ベトナムでゲイカップルが結婚式を挙げました
- 『SATC』ミランダ役のシンシア・ニクソンがついに結婚!
- 【署名のお願い】ウクライナで同性愛が違法化されようとしています
- アダム・ランバート、ゲイ・アーティストとして初の全米チャート1位獲得
- 『ビッグバン★セオリー』のジム・パーソンズがカミングアウト
- ルパート・エベレット、同性愛で投獄されたオスカー・ワイルドの晩年を映画化
- 日本のHIV感染者・エイズ患者の累計報告数が2万件を超えました
- ウォール・ストリート・ジャーナルの調査で88%が同性婚を認めるべきと回答
- 「X-MEN」のヒーローが同性婚
- 【追悼】「かいじゅうたちのいるところ」の絵本作家モーリス・センダック
- 内藤ルネさんの展覧会が開催中
- 米人気パンク・ロッカーが性同一性障害をカミングアウト
- 【追悼】ドナ・サマーよ永遠に
- アルゼンチンで性別を自由に変えられる法案が可決されました
- ゴシップのベス・ディットーが同性婚へ
- 今年も全国でIDAHO関連アクション開催
- オバマ大統領が同性婚支持を表明、米大統領として初
- ガガ様来日! LGBTをアピールするリトルモンスターもお出迎え
- オランド大統領誕生により、フランスでも同性婚が実現!?
- 「ハートをつなごう」の後継番組「ハートネットTV Our Voice」にLGBTが!
-
4月
- 東京レインボープライドに2500名が参加、TBSでもニュースになりました
- 【追悼】孤高の人・東郷健さんが亡くなりました
- アダム・ランバートのニュー・アルバム発売記念イベントにご招待!
- 「Mr.Gay World」がアフリカで初めて開催されました
- セクシュアルマイノリティの自殺予防を訴える集会が参議院議員会館で開催されました
- 二丁目に新たなラウンジがオープン!
- 同性婚した日本人女性が在留資格を拒まれ、アメリカ政府を提訴
- 東京ディズニーリゾートでの同性結婚式がOKに
- トランスジェンダーのタラコヴァさん、ミス・ユニバースに出場できることに
- スカパー!で新番組「二丁目なう」がスタート
- レディ・ガガ、GLAADメディア賞でアーティスト賞を受賞
- 3月
-
2月
- 『人生はビギナーズ』のクリストファー・プラマーがアカデミー助演男優賞を獲得
- ゲイ差別発言でアカデミー賞から降ろされたブレット・ラトナー、同性愛者支援のビデオ制作へ
- エンパイアステートビルの最上階で初の同性結婚式
- 星屑スキャットがメジャー・デビュー!
- ゲイカップルが「キスの長さ」でギネス更新
- ニュージャージー州で同性婚法案が上院通過
- イケメン俳優のマット・ボマーがカミングアウト
- Googleのバレンタイン用アニメーションに結婚式を挙げるゲイカップルが登場
- 南アフリカでレズビアン女性に対する性暴力が相次いでいます
- ホイットニーの遺作となった映画『スパークル』が8月に全米公開
- 横須賀市職員が性的少数者について初の研修会を開催
- レディ・ガガ、自殺したゲイの子をネタにする人たちに激怒
- ワシントン州で同性婚が認められました
- 米連邦高裁が「カリフォルニア州の同性婚禁止は違憲」との判決を下しました
- ワシントン州が全米で7番目の同性婚を認める州になる見込みです
- ライアン・マーフィ、今度はゲイカップルのファミリー・コメディ・ドラマを制作
-
1月
- 佐賀市が性的少数者についての研修会を開催
- エクアドルで「同性愛治療」と称して入所者虐待、政府が摘発強化
- ゲイカップルが活躍するコメディドラマ『モダン・ファミリー』が2月から放送スタート
- 『ハートをつなごう』が最終回を迎えます
- 米国会の重鎮、バーニー・フランク氏が同性婚
- 『glee』のライアン・マーフィ、エイズ禍の時代のゲイコミュニティを描く映画を制作
- GLAAD賞にレディ・ガガや『glee』『人生はビギナーズ』などがノミネート
- エルトン・ジョンが、エイズで亡くなった友人たちのことを綴った回想録を発表…フレディ・マーキュリーのことも
- 史上初、『フォーチュン』誌の「最良企業100社」に選ばれた企業が100%ゲイ差別撤廃を掲げていました
- 性同一性障害者のホルモン療法の開始年齢が15歳に引き下げられました
- 「glee」レイチェルのゲイパパたちの登場が決まりました
- LGBT成人式が全国で行われ、感動を呼びました
- 石原都知事再び…「同性愛の人間はかわいそう」「孤独になって死ぬのは気の毒」「オカマとナマコは大嫌い」などと発言
- 女優のクリスティ・マクニコルがカミングアウト
- 同性愛表現の自由を求めて動きだしたマレーシア
- 知ってました? 澤選手「日本代表チームは性的指向による差別を認めない」とスピーチ
- ジョージ・マイケル、生死の境をさまよいながらも奇跡的に回復
- ジョニー・ウィアーが結婚指輪という金メダルを手に入れました
- 今年10月、名古屋で初のレインボーパレードが開催されます
- 映画『Coming Out Story』が都内で一般上映
- 同性婚によってゲイの健康度が向上することが判明
- ガガ、日米の紅白で『Born This Way』を熱唱
-
11月
-
2011
-
12月
- ジョージ・クルーニー、同性婚実現を求める朗読劇に参加
- オスカーも有力視される感動のゲイ映画『人生はビギナーズ』の特別試写会が「ArcH」で開催されます!
- レディ・ガガ、「チャリティに貢献したセレブ」ランキングで2年連続1位に
- LGBT成人式というイベントが開催されます
- 史上初、米海軍で同性カップルが「ファーストキス」
- クリスマスイブの「アド街」は二丁目スペシャル
- ガガ、紅白出演決定!
- レディ・ガガ再来日!
- ロージー・オドネルが婚約
- 弁護士が自認する性別で活動できるようになりました
- ジョニー・ウィアーが婚約
- レディ・ガガ、親友の同性結婚式に牧師として参列
- tptがゲイ演劇『プライド』を日本初演
- 米政府、「同性愛者の権利は人権」と訴え、国際基金の設立を発表
- ナイジェリアで同性愛禁止法案が上院通過、違反者は禁錮14年
- ベルギーで世界初のゲイの首相が誕生
- 『glee』シーズン3にリッキー・マーティンが登場
-
11月
- 今年も年末恒例の「gaku-GAY-kai」が開催されます
- サンクトペテルブルグがLGBTの発言権を奪う条例を制定しようとしています
- レディ・ガガがLGBTの若者を支援する団体から表彰されることに
- トークショー「HIVと、ドラッグのこと」開催
- ベネトンがローマ法王とイスラム教指導者のキス写真を発表
- TV TOKYOが『アメリカ 同性婚にあやかれ 経済効果240億円』というニュースを放送
- 東京都エイズ予防月間がスタートしました
- 東京プライドがHIVについての映画上映&トークイベントを開催
- バロウズの『Queer』が映画化されます
- 読売新聞に「『同性婚』権利認めて、支援団体に相談千件以上」という記事が掲載されました
- バンコクに「レディボーイ大学」が誕生
- 松山で初の映画祭開催
- 『ハートをつなごう』HIV特集第4弾のテーマは「エイズの30年」
- ブレット・ラトナーがゲイを侮辱する発言でアカデミー賞プロデューサーを辞任
- 楽しんごさんが格闘家の彼氏との交際を明かしました
- アルファロメオの特別協賛で、今年も「TOKYO SUPER STAR AWARDS」が開催
- 「It Gets Better」を日本語訳するプロジェクトが始まりました
- レディ・ガガ、いじめをなくすための財団を設立
- 「SATC」のアンソニーがプライベートでも同性婚
-
10月
- 台北プライドパレード、過去最大規模で大成功
- ヴィトー・ルッソを描いたドキュメンタリー作品がニューヨーク映画祭で上映
- デンマークで同性婚が認められそうです
- スコットランドで起きたショッキングな殺人事件…被害者はゲイの方でした
- ボツワナのモハエ前大統領、HIV予防のために「同性愛を合法化するべき」と提言
- 全米初、カリフォルニアで同性愛教育が義務化
- 「演劇とトランスジェンダー」というアートイベントが開催されます
- 『キッズ・オールライト』がTVドラマ化
- ザッカリー・クイントの影響でABCのニュースキャスターも生放送でカミングアウト
- 『HEROES』『スタートレック』のザッカリー・クイントがカミングアウト
- 毎日新聞に「偏見に苦しむ性的マイノリティ」という記事が掲載
- 75歳の父からカミングアウトされた実体験を描く映画『人生はビギナーズ』の公開が決定
- ゴールドマン・サックスがLGBT学生向け会社説明会を開催
- セクシュアルマイノリティにフォーカスした自殺予防対策を考えるシンポジウムが開催
- 香港プライドパレード、11月12日に開催
- 二丁目でゲイの役者さんが出演する二丁目の芝居が上演されます
- 東京国際レズビアン&ゲイ映画祭に連動し、横浜でレズビアン&ゲイ短編映画が上映されます
- ウガンダのセクシュアルマイノリティの団体が名誉ある人権賞を受賞
- 国際基督教大学のキャンパスでLiving Togetherなイベント&講座が開催されます
- アダム・ランバートが親の会に表彰されました
-
9月
- 北朝鮮で同性愛者が死刑に
- 「私の息子はゲイ?」というアプリが物議を醸しています
- 韓国IBM、採用にあたってセクシュアルマイノリティを優遇
- 今年4~6月の新規エイズ患者数、四半期で過去最多に
- レディ・ガガがオバマ大統領に直訴
- 『J・エドガー』来年1月公開決定
- 『ザ・プレイボーイ・クラブ』にゲイ役で出演中の俳優、ショーン・メイハーがカミングアウト
- ベルギーでゲイの首相が誕生!?
- セクシュアルマイノリティ中高生への支援を考える会が開催されます
- レディ・ガガがジェイミーくんを追悼するライブ・パフォーマンスを行いました
- ぴあフィルムフェスティバルで性同一性障害を描いた作品が上映されています
- 14歳のゲイの子が自殺…レディ・ガガが「いじめを違法とするよう大統領に掛け合う」と宣言
- 米軍の同性愛者排除規定が正式に撤廃されました
- アル・パチーノの『ワイルド・サロメ』が、ヴェネチア映画祭でクィアライオンを受賞
- レインボーマーチ札幌、雨ながら昨年より100人も多い参加者で成功
- ゲイのためのグルーポン「Gaypon」が誕生
- 産経ビジネス紙に「ギリシャ観光業 復活の鍵は同性愛者」という記事が掲載
- 9月24日、台湾の高雄でもパレード開催!
- シンディ・ローパーが家のないLGBTの若者のためのシェルターを開設
- 『glee』ライバル校のイケメンコーチが同性婚
- 今年の関西レインボーパレードは11月5日(土)に開催!
- フレディ・マーキュリーの誕生日を祝し、Googleが素敵な贈り物をくれました
- シェールの「息子」がTVにレギュラー出演
- 「被災とジェンダー/セクシュアリティ」 というシンポジウムが開催されます
-
8月
- デザイナーのマイケル・コースがニューヨーク州で同性婚
- アップルのCEOに就任したティム・クック氏がゲイのロールモデルとして期待されています
- ドラァグクイーンが登場する舞台『Lipsynca~ヒールをはいたオトコ!?たち』
- レディ・ガガがMTVアワードのオープニング・パフォーマンスをつとめます
- 台湾の同性カップル約80組が結婚式を挙げました
- 『CDジャーナル』がゲイミュージックを特集
- REACH Online 2011がスタート!
- 東京国際レズビアン&ゲイ映画祭の上映作品が決定!
- 奥津直道さんの個展が開催されています
- プラハで初のゲイパレードが成功
- レディ・ガガの新曲『You and I』のイメージは「男装」
- 今年もレインボーマーチ札幌にSoftbankが協賛
- キューバで初めて、セクシュアルマイノリティの結婚式が行われました
- 森栄喜さんの写真集発売&展示&撮影会のお知らせ
- オーストラリアのオープンリー・レズビアンの閣僚が、パートナーの妊娠を発表
- ゲイの若者への支援活動でアダム・ランバートが「Equality California」から表彰されることになりました
- シューレ大学国際映画祭でクィア映画2本が上映されます
- マイリー・サイラスがイコールのタトゥで同性婚を応援
- ヴィレッジ・ピープルが来日!
-
7月
- 9月20日、アメリカの同性愛者の「職業選択の自由」が完全なものになります
- ニューヨークで同性婚が施行され、764組のゲイ&レズビアンカップルが結婚を祝いました
- レディ・ガガ、同性愛者支援を讃えられ、シドニーの名誉市民に!
- レインボー祭りの日にキャンディ・ミルキィさんが「一人パレード」
- レインボーマーチ札幌、9月18日に開催決定!
- ブルース・ラ・ブルースの写真展&映画上映会開催
- ガガ、『SMAP×SMAP』で神輿に乗って登場
- 今年のレインボー祭りは8月14日(日)に開催!
- 『週刊朝日』7.15号巻頭カラーグラビアに世界各地のプライドパレード
- いよいよ明日からアジアンクィア映画祭(AQFF)がスタート!
- 映画版『glee』9月に日本公開決定! 歌のシーンだけ集めたDVDも発売
- モンティ・パイソンのグレアム・チャップマンの半生が3D伝記映画に
- 「徹子の部屋」に出演したガガの衣装は巨大な玉ねぎ!
- 14本のテレビ番組に出演し、ゲイのことにも触れたレディ・ガガが、11日間の滞在を終えて旅立ちました
- 少年たちの美や愛を鮮やかに写し出した写真展、7月1日から開催
-
6月
- 世界各地でプライドパレードが開催されました
- 29日、30日に「ハートをつなごう」HIV特集第3弾放送
- レディ・ガガやケイティ・ペリーがニューヨークの同性婚を祝福
- 同性婚実現を祝し、歓喜ムード一色のニューヨーク・プライド
- ガガ、MTV VMAでスペシャルなパフォーマンスを披露し、日本にエール
- 奇蹟! プライドウィークの初日、ニューヨークで同性婚法案が採択されました
- ガガ様来日! 間近で会えるチャンスも!
- 「gay」とググってみてください
- 『glee』のクリエイター、ライアン・マーフィが同性婚
- 国連で史上初めて、LGBTの人権を擁護する決議案が採択されました
- ニューヨーク州下院議会が同性婚法案を採択
- レディ・ガガが欧州最大のゲイプライドイベントに登場し、「私は多様性の申し子」とスピーチ
- イスラエルのテルアビブでパレード開催、7万人が参加
- ナタリー・ポートマンが同性婚を求めるキャンペーンに参加
- 韓国のトランスジェンダー・タレント、ハリスをフジテレビが特集
- タイのゲイ団体が二大政党に同性婚支持の選挙公約を求めました
- エイズで命を落とした有名人、その遺志を継いで闘う仲間たち
- ネパールで国勢調査の性別欄に「第三の性」が設けられました
- 「akta」と「dista」で「世界エイズデー」キャンペーンに関するフォーラムが開催されます
- ドラァグクイーン大集合な番組「JOSO-TV」がフジテレビでスタート!
- 「Billboard Music Awards」でブリトニーとリアーナがキス
- エイズ治療に光——米国のエイズ研究第一人者が「エイズの最終的な克服を今ほど大きく期待できた時はない」と語りました
- 6月1日から厚労省「HIV検査普及週間」や「東京都HIV検査・相談月間」がスタート
- 世界全体で見ると同性愛への許容度は高まっているという調査結果が発表されました
-
5月
- ウガンダの国会は反ゲイ法案の審議を延期しています
- 青森でも映画祭が開催されます
- モスクワ・プライドがまたしても暴力的に弾圧されました
- ドラマ『glee』が映画化!
- 2010年の新規エイズ患者数が過去最多に
- 今年の東京国際レズビアン&ゲイ映画祭は10月開催!
- 東京レインボープライド、来年4月29日にパレードを開催
- アジアンクィア映画祭、7月8日から開催!
- 過去10年間のベスト・ゲイ映画は『ミルク』
- ジョージ・マイケル、ゲイだらけなアルバムの制作を企画
- アムネスティ・インターナショナルがLGBTの人権を守る法制度の整備を求める署名を集めています
- ゲイ・アクターのパイオニア、サル・ミネオの生涯が映画に
- ゲイの男の子が自身の経験を語ったDVDのことが神奈川新聞の記事に
- レディ・ガガ、カンヌ国際映画祭でオープニングアクト!
- リッキー・マーティンが有名トーク番組で「カミングアウトして幸せ」と語りました
- 「セクシュアルマイノリティを理解する週間」が5月14日からスタート
- 【署名のお願い】ウガンダでゲイを死刑にする法律が採決されようとしています
- 今年も全国18ヶ所でIDAHO関連アクション開催!
- 今年も5月15日に神戸パレード開催!
- 二丁目の被災者支援チャリティイベント『PRAY』、926,766円を寄付
- ブラジル最高裁が同性パートナーに法的権利を認める判決を下しました
- ロイヤルウェディングに参列したゲイたち
- 大阪でメンタルケアのための呼吸法ワークショップ開催
- 日本初のオープンリーゲイの議員誕生が内外でニュースに
-
4月
- 松本外相が、外国首脳の同性パートナーの天皇陛下への謁見を受け入れる意向を示しました
- 「被災とセクシュアル・マイノリティ」というシンポジウムが開催されます
- 石坂さん、石川さん、上川さんが当選!
- 『OUT』誌が選ぶ「最も影響力のあるゲイ50人」のトップにアップルのティム・クックが選ばれました
- 共生ネットが避難所でのセクシュアルマイノリティのニーズについて要望書を提出
- 女優のエヴァン・レイチェル・ウッドがバイセクシャルであることをカミングアウト
- 「英国版レディ・ガガ」とも言われるバイセクシュアルのジェシー・Jが来日します
- レディ・ガガ、今度は機械の体に!?
- ガガ様が6月、被災者支援のために来日!
- 被災地のLGBTを支援する「JAPANレインボー・エイド」発足
- ニッキー・ミナージュがカシオの限定デジカメを東日本大震災チャリティに
- Fridaeが被災したLGBTを支援する「シェルター・プロジェクト」を立ち上げました
- 被災した岩手のLGBTを支援する「岩手レインボー・ネットワーク」がスタート
- カイリーが予定通り来日ツアーを敢行!
- 都知事選候補者へのセクシュアルマイノリティ関連政策アンケートが行われていました
- 森栄喜・野村佐紀子の2人展が今日から開催
- 10日は都知事選です。忘れずに投票に行きましょう
- レディ・ガガ、今度は新曲の収益でゲイの子どもを救う
- 延期されていた石原抗議デモの日程が決定しました
- ジェーン・バーキンが緊急来日し、チャリティ・コンサートを開催
- アメリカ初、マサチューセッツ州知事が同性愛者の裁判官を州最高裁判事に指名
- 北海道でも候補者アンケートを実施
- タワレコ新宿店のArcHブースがゲイのラブソングを特集
- レインボープライド愛媛が統一地方選挙でアンケートを実施中
- サンフランシスコが「ブリトニーの日」を制定
-
3月
- 『glee』がNHK・BSプレミアムで放送開始!
- メキシコでゲイのためのビールが発売されました
- ブリトニーのミニコンサート、ドラァグ・ショウで幕開け。被災者支援チャリティも
- レディ・ガガ、セクシャルマイノリティ差別に抗議
- 「AMR-安室奈美恵ナイト- × PIERROT」が被災地に10万円を寄付
- はるな愛さん、福島・相馬市に駆けつけ、被災者を慰問
- レディ・ガガがビデオレターで被災者を激励
- 新宿二丁目から「祈り」を——GWに被災者支援イベント開催
- アメリカ初のオープンリー・ゲイの大統領候補が誕生!
- グウェン・ステファニー、東日本大震災の被災者支援に100万ドルを寄付!
- 中日新聞にカナダで結婚式を挙げた同性カップルへのインタビュー記事が掲載されていました
- 【追悼】大女優にして偉大なるゲイ・アイコンだったエリザベス・テイラー
- リッキー・マーティン、ラッセル・シモンズ、シザー・シスターズらがGLAADメディア賞を受賞
- 人々に大きな感動を与えたシンディ・ローパーのライブ
- お花見の季節にふさわしいグループ展が「akta」で開催!
- 台湾のチャリティイベント、前代未聞の規模に
- カリフォルニア州司法長官、同性婚の解禁を指示
- 二丁目の「ArcH」が節電イベントを開催
- ジュディ・オングが台湾で一大チャリティ番組を実現
- 韓国のゲイの映画監督が「同性結婚」宣言
- 「JaNP+」からHIV陽性者のみなさんへのメッセージ
- サンフランシスコのLGBTボランティア団体が日本の被災者への基金を設立
- 仙台のコミュニティセンター「ZEL」が再開へ
- 被災者を支援する「LGBTレインボー基金」が設立されるそうです
- 被災により抗HIV薬の服用を中断せざるをえなくなった方へ
- ArcHは18日まで休止、19日のShangri-Laも中止に
- アンジェリーナ・ジョリー、ジョニー・ウィアー、マライア・キャリー、エレン・デジェネレス…セレブが続々と応援
- シンディ・ローパーが東京公演を敢行!
- レディ・ガガの「Japan Prayer Bracelet」が48時間で25万ドルを集めました
- 「被災地にいるLGBTが望むこと」というblogが立ち上がりました
- レディ・ガガが日本の被災者を救済!
- 【東日本大震災に際して】
- 石原氏が都知事選へ出馬する意向に転じました
- イヴ・サンローランのドキュメンタリー映画、4月23日から公開
- レディ・ガガが同性愛嫌悪グループに資金提供したスーパーに対し、取引終了宣言
- ニュージーランドでアジア太平洋アウトゲームズが開催されます
- 展覧会「パゾリーニ・オマージュ」に多数のゲイ・アーティストが参加
- 『真夜中のパーティ』製作の舞台裏を描いた映画『Making the Boys』
- 前田健さんが処女小説『それでも花は咲いていく』を映画化
- ラッセル・シモンズがGLAADメディア賞で表彰されることになりました
- ゲイ的にはあまり盛り上がらなかった?今年のアカデミー賞
-
2月
- 毎日新聞のレインボーマーチ札幌連載の番外編もまた、素晴らしかったです
- オバマ大統領、結婚防衛法は「違憲」と判断
- 横浜の「SHIP」がセクシュアルマイノリティのための電話相談を開設
- ベルリン国際映画祭のテディ賞が発表されました
- レディ・ガガ、コンドームのスーツでHIVについてトーク
- 映画『ナルニア国物語』のプロデューサーで、オープンリー・ゲイのペリー・ムーアが亡くなりました
- 「Born This Way」がビルボード1000番目のナンバーワンに。PVはいよいよ今週公開!
- ブリトニー、友人のゲイの結婚式でブライズメイドに
- フェイスブック、同性愛者向けの新ステータスを追加
- シドニーのマルディグラ、明日からスタート! タイの美女軍団も参加
- 人気モデルがレズビアン・カミングアウト
- 中野区議にチャレンジする石坂わたるさんの事務所開きが行われます
- セクシュアルマイノリティ中高生を勇気づけるためのプロジェクト「君のままでいい.jp」
- ハンガリーのパレードが警察によって中止に追い込まれました
- 相川七瀬さんのバースデイをドラァグクイーンたちが祝福!
- 石原都知事、三度目の差別発言「同性愛の男性が女装して婦人用化粧品のコマーシャルに出ることはありえない」
- 英国のゲイカップルが教会で挙式できるようになります
- 「座・高円寺ドキュメンタリーフェスティバル」でakaboshiさんの『しみじみと歩いてる』が奨励賞を受賞
- レディ・ガガ、グラミー賞で3冠に輝き、新時代のゲイアンセム『Born This Way』を初披露
- ニューヨークのゲイ猫カップルが結婚式を挙げました
- ハワイ州でシビルユニオン法案が採択されました
- バレンタインチョコに込められた同性愛者の思い
- リッキー・マーティンがGLAADアワードの最高栄誉賞に輝きました
- レディ・ガガ、「もう待てないわ」と新曲を解禁
- 「SATC」ミランダのフィアンセが男の子を出産
- 2010年の新規エイズ患者数とHIV感染者数(同年第4四半期)が過去最多に
- バイセクシュアルの女優、マリア・シュナイダーが死去
- ジェームズ・ディーンのバイセクシャリティを描いた映画が話題に
- バーレーンで100人以上のゲイが逮捕されました
- 楽しんご、壮絶ないじめ体験を告白
- 船堀でニューハーフの花魁道中が行われました
- 2月21日放送!『ハートをつなごう』ゲイ・レズビアン特別編
- モナリザのモデルはダ・ヴィンチが愛した美少年・サライだった?
- 毎日新聞のレインボーマーチ札幌連載が素晴らしいです
- インドでゲイ専門の旅行代理店が大繁盛
- 石原都知事の発言に対し、国際的な人権団体が声明を発表
- エジプト反政府運動のリーダー、モハメド・エルバラダイ氏のニューヨーク大学時代の恩師はゲイの方でした
- ブッシュ前大統領の娘が同性婚を支持
- 自転車の世界チャンピオン、グレアム・オブリーがカミングアウト
- トランスジェンダーの現代美術作家・ピュ~ぴるさんのドキュメンタリーがロッテルダム映画祭で公開
-
1月
- エルトンの伝記ミュージカル映画の企画が進行中
- ジョナサン・ナイトが正式にカミングアウト
- CNNのWebサイトが「東京のお勧めゲイ・レズビアンバー ベスト7」「事実をひた隠しにする日本のレズビアン」という記事を掲載
- エルトン・ジョン一家の写真が「有害指定」に
- ウガンダの同性愛活動家、撲殺される…オバマ大統領らが追悼
- クリス・コルファーが映画デビュー!
- タイの新航空会社、トランスジェンダーの客室乗務員を採用
- ティファニーが「ニュー・キッズ・オン・ザ・ブロック」のジョナサン・ナイトをゲイだとアウティング
- ガガの新曲のPVにトランスジェンダーが登場
- NHK教育『青春リアル』にゲイの男の子が出演中
- ティム・クック氏がアップルを継ぐなら「ゲイにとっても新しい時代の幕開け」
- パパになったエルトン・ジョンが赤ちゃんの写真を初公開
- GLAADメディア賞ノミネート発表
- ゲイカップルの宿泊を拒否したホテルに対し、賠償命令(イギリス)
- 国内で初めて、GIDの児童に抗ホルモン剤投与が認められました
- 「Facebook」創設者の一人、クリス・ヒューズが彼氏との婚約を発表!
- 朝日新聞で赤川次郎氏が同性愛者を擁護
- ゴールデン・グローブ賞発表! 『グリー』が3冠、『キッズ・オールライト』が2冠
- 韓国でゲイマーケットが注目されはじめているそうです
- 慢性肝炎を発症することが多い欧米型のB型肝炎ウィルスへの感染が増えているそうです
- 今、アメリカではゲイのスポーツバーが流行中
- メリーランド州が同性婚を認めるアメリカで6番目の州になりそうです
- 「本当に足りないもの」とは何だろう?…石原都知事の発言を考えるイベント、本日開催
- ジョニー・ウィアー、自伝でカミングアウト「隠してたつもりはないよ」
- サンフランシスコにLGBT歴史博物館が誕生
- アリゾナ銃乱射事件でギフォーズ議員を救ったのは、ゲイの学生
- レディ・ガガのニュー・シングル、『Glee』でカバーされることが決定
- リオデジャネイロに「第3のトイレ」が開設
- 脚本家、プロデューサーに贈られるWGA・PGA賞にゲイ作品多数
- 『マッドメン』2月15日から放送スタート
- 産経新聞で「Xジェンダー」の人たちが紹介されていました
- カイリー、2011年はミュージカルにチャレンジ?
- アン・ハサウェイとジュリー・アンドリュースが『Glee』にゲスト出演?
- ひろゆき氏「ゲイのテレビ出演は何でダメ? 教えてください、石原都知事」
- マライア・キャリー「バイセクシュアル説」の真実
- オバマ大統領、いよいよ同性婚実現に向けて所感を表明
- シザーシスターズ、来日公演決定! ガガのツアー・サポートも
-
12月
-
2010
-
12月
- エルトン・ジョンが代理母出産でパパに
- マツコ・デラックスさんが再び「徹子の部屋」に出演!
- レディ・ガガ、2年連続でMTV Newsのウーマン・オブ・ザ・イヤーに
- 2010年、最も「ググられた」ゲイ
- 1月2日(日)深夜、『ハーバード白熱教室』で同性婚を議論
- イスラエル・テルアビブがゲイの旅行客を誘致
- 最もチャリティに貢献したセレブの第1位にレディ・ガガが選ばれました
- オバマ大統領が同性愛者の従軍解禁法案に署名
- レディ・ガガが紅白のサプライズゲスト?
- イランにおける同性愛者迫害の実態が明らかに
- アン・リー監督の最新ゲイ映画『ウッドストックがやってくる!』が1月15日公開
- カーター元大統領、「ゲイの大統領が選ばれる日も近い」
- 欧州のゲイのクラシックカー愛好会のことがレポートされていました
- 米軍の同性愛者排除政策が撤廃され、歴史が動きました
- リッキー・マーティン「故郷プエルトリコで結婚したい」
- ゲイの従軍禁止政策の新たな法案、連邦下院を通過
- HIV感染した男性、幹細胞移植で「完治」
- 東京都の漫画規制条例が可決されました
- 石原発言に各方面から批判の声が上がりました
- 母親二人と子どもたちを描いた映画、公開決定!
- ニューヨークのHIV予防CMにゲイ団体が反発
- 年末恒例『gaku-GAY-kai』今年も開催!
- ジョン・レノンとゲイの知られざる関係
- HIV陽性の米ポルノ男優が会見し、撮影でのコンドーム着用の義務化を訴えました
- 同性愛者の軍務禁止規定の撤廃法案、上院で再度否決
- ディカプリオがゲイ役を演じます
- 世界初の「空の上の同性結婚式」が行われました
- パラグアイで同性愛者弾圧の歴史——ナント三大陸映画祭準グランプリ映画『木製のナイフ/108』で明らかに
- カリフォルニア州同性婚禁止法案の控訴審が開始
- レディ・ガガ、グラミーで6部門にノミネート
- 目標を達成し、アリシア・キーズ、レディー・ガガらのTwitterが復活
- 来年のベルリン映画祭に韓国発のレズビアン映画が出品
- 石原都知事、今度は「ゲイは足りない感じがする」と発言
- ブレイク寸前の若手女優、アンバー・ハードがカミングアウト
- ジョニー・デップが『パイレーツ・オブ・カリビアン』のジャック・スパロウはゲイだとコメント
- 「LGBTの家族と友人をつなぐ会」が神戸新聞で取り上げられました
- 人権週間なう。「性的指向を理由とする差別をなくそう」と法務省が呼びかけ
- イリノイ州でシビルユニオンが認められました
- 石原都知事がテレビに同性愛者が出ることを「野放図」と批判
- ピクサーのゲイ&レズビアンの社員が立ち上がりました
- 悲願成就!カイリーの来日公演が決定
- 中国や韓国で外国人や帰国者へのHIV検査の強制措置が撤廃されつつあります
- 中国政府「エイズ予防と感染抑制が民族の興亡と国家の存亡に関わる」
- レディ・ガガ、HIVチャリティのためにFacebookとTwitterの利用を中止
- 12月20日から『ハートをつなごう』HIV第2弾が放送されます
- NHKのLGBT特設サイト『虹色』に張由紀夫さんとぷれいす東京の生島さんが寄稿
- TOKYO FM × Living Together ポエトリー・リーディング『Think About AIDS』が最終回を迎えます
- HIV感染は依然として増加傾向。短期間で発症に至るウィルスも
-
11月
- ドリカムのニューアルバムのCMにゲイカップルが!
- 三島由紀夫の代表作『サド侯爵夫人』上演
- 「なぜ父親になれない」女性から男性にトランスした方が代理出産でもうけた子が無戸籍状態に
- 「ミス・インターナショナル・クイーン」でたけうち亜美さんが準優勝
- ドイツで同性愛者向けのひつぎ発売、レインボーのデザインも
- 「ラヴズ・ボディ―生と性を巡る表現」展でジャンジさんらの「Living Together Lounge」でのパフォーマンスが再演されます
- KE$HAの新曲はゲイの若者へのメッセージソング。そのPVに出演できるかも?
- 青森でもセクシュアルマイノリティの講座が開かれました
- トム・フォード監督の次回作はコメディ
- LAゲイ&レズビアン・センターの39周年パーティがジェーン・リンチを表彰し、60万ドルを集めました
- レインボープライド愛媛がLGBTコミュニティ誌を創刊
- 東京都エイズ予防月間スタート
- テキサス州のゲイカップルがスカイプで結婚式
- 毎日新聞が同性愛者をルポ
- リッキー・マーティンの結婚の夢を叶えてあげて!
- 森栄喜さんの個展がはじまります
- サグラダ・ファミリアの前で200人のゲイがキス
- マドンナもいじめ問題について語り、ゲイにエール
- レディ・ガガ、「MTV EMA 2010」で3冠に輝く
- レズビアン&ゲイ・カルチャーやコミュニティの発展に貢献した人を讃えるアワードが開催
- 米国中間選挙でLGBT候補者が大きな勝利
- アダム・ランバート、アコースティック・アルバムをリリース
- サンスター、「ネイルにレッドリボンを」キャンペーンで「PLuS+」に参加
- ゲイであるがゆえに強制送還の憂き目に遭うアメリカの移民たち
- シェールが性転換手術をした娘について語りました
- 絶大な人気を誇る女優ベティ・ホワイトが「同性婚を認めるべき」とコメント
- 『ミルク』のジェームズ・フランコがドラァグクイーン姿で雑誌の表紙に
- 性分化疾患患者を取り巻く実情や課題が次第に明らかに—毎日新聞がレポート
- NYの高校生の1割が同性と性交渉
- 韓国で人気のゲイTVドラマが同性婚のシーンをカット
- 相次ぐゲイの若者の自殺に対し、ニュージャージー州でいじめ対策を義務付ける法案が提出されました
- 「セクシュアル・マイノリティとカミングアウト」という講座が開催されます
-
10月
- 台北プライドパレードに3万人が参加、歌姫アーメイも登場!
- 岡山大、全国で初めてジェンダーセンター設置
- アカデミー主演女優賞はナタリー?ニコール?どちらもゲイ的に興味津々
- 韓国でも同性愛者の従軍について議論されています
- 武田鉄矢が自ら進んでゲイバーのママ役に
- オバマの同性婚に対する立場が変化しつつあるようです
- エルヴァイラ、シザーシスターズのクリップに登場!
- ブラジルのスラムでパレードが開催されました
- セサミストリートのバートはゲイではないそうです
- 欧州人権裁判所がモスクワのプライドマーチ禁止措置に対して歴史的判決を下しました
- アメリカ国防総省は、自ら同性愛者と公言する者に対しても入隊手続きを始めるよう指示しました
- ウガンダのタブロイド新聞が「ゲイを吊るせ!」キャンペーンを展開しています
- フランスのゲイ雑誌「Têtu」にカトリーヌ・ドヌーヴ登場!
- オスカー・ワイルドの生誕156周年を記念したGoogleのロゴが登場
- 同性愛者の従軍禁止政策の即時停止命令に対し、オバマ政権は高裁に異議を申し立てました
- ボーイ・ジョージが2012年にカルチャー・クラブを再結成!
- グウェン・ステファニーの夫がゲイだったことをカミングアウト
- 共和党ニューヨーク知事候補が同性愛差別発言の対応に追われています
- 米連邦地裁が同性愛者排除の軍務規定の廃止を命じました
- ゴシップ・ブロガーのペレズ・ヒルトン、「弱い者いじめ」脱却宣言
- マレーシア唯一のセクシャリティの権利についての祭典「セクシャリティ・メルデカ」が開催されました。
- セルビアのプライドパレードで反対派が暴徒化
- 社会的マイノリティの方たちによる「リビングライブラリー」が読売新聞で紹介されました
- 【速報】雨にも負けず、約600名が参加。関西レインボーパレード
- 米国の最新世論調査で同性婚反対派が初めて半数以下に
- 『Glee』もゲイの若者を応援!
- ダニエル・ラドクリフもゲイの若者のためにメッセージ
- 毎日新聞の性的少数者連載がファイザー医学記事賞優秀賞に
- 香川レインボー映画祭、開催!
- 『Tokyo graffiti』にレズビアン&ゲイカップルが登場!
- 国勢調査の同性カップルに対する扱いについて担当課長が「国勢調査は将来の人口がどうなるかを見るもので、男女の間が大前提。この精神は譲れない」とコメント
- 第2回上海プライドウィークが10月16日から開催
- 今秋の香港プライドパレードは中止、次回は2011年秋に
- 『ヘアスプレー』のアンバーがゲイの若者を救うために立ち上がりました
- 大阪東急インがゲイのためのスペシャルサービスを提供
- 南アフリカのパレードに18,000人が参加
- イギリスの活動家ピーター・タッチェルが「人間国宝」に。除幕の任をイアン・マッケランがつとめました。
- アメリカのゲイの学生、恋人とのキスをネットで配信され、自殺
- 緊急決定! 二丁目『NEXT』で田中ロウマ&米倉利紀がSPECIAL LIVE
-
9月
- 国勢調査の改善を求める動きが活発になっています。
- アメリカにはゲイのためのもう1つの「エイズデー」があります
- アメリカの国勢調査は同性カップルの1/7をカウントしそこねているそうです
- おかえりなさい! 佐良直美さん
- イギリスの国勢調査では同性配偶者の有無も答えられるそうです
- 連邦地裁が初めて同性愛者の復軍を命じる判決を下しました
- FTMの4人組ミュージシャン「GtM」がデビュー
- 出会い系サイト利用者に「ゲイだとバラすぞ」と恐喝した男が逮捕されました
- タンザニアに残る「女性同士の結婚」という風習
- ホアキン・フェニックスがFBI長官フーヴァーの同性パートナーに!
- サシャ・バロン・コーエンがQUEENのフレディ・マーキュリーに!
- マツコ・デラックスさんが『ガラスの仮面』の月影先生に!
- 「Don't Ask, Don't Tell」政策の上院での採択、さらに先送りに
- 『トップガン』の女優、ケリー・マクギリスが同性婚
- レディ・ガガが本気で「Don't Ask Don't Tell」政策の撤廃を訴えています
- ドイツのヴェスターヴェレ副首相兼外相、同性パートナーと「結婚」
- レインボーマーチ札幌がメディアで報道されました
- 吉野家ゲイカップル暴行事件のその後
- 東京都の人権冊子で東京プライドパレードが特集されていました
- 少年を虐待してきたカトリック教会の指導者・ローマ法王の英国訪問に抗議噴出
- アメリカのオカルト系タレントがカミングアウト
- ラッパーの50セント、Twitterで「ゲイの結婚式を襲撃」
- ゲイにエスコートされたレディ・ガガ、MTVアワードを総なめ!
- 瓜田純士、ゲイカップルに暴行
- 「コーランを燃やす」と宣言した牧師の住むフロリダ州ゲインズビル市の市長はオープンリー・ゲイの方だそうです
- オーストラリアの競泳金メダリストがホモフォビックなつぶやきで「ジャガー」との契約を打ち切られました
- 米連邦地裁が「米軍の同性愛者排除は違憲」という判決を下しました
- シカゴにゲイの市長が誕生するかも?
- 誰もが歌える童謡の歌詞から「ゲイ」の言葉を削除した小学校長
- 今年は台北だけでなく高雄でもパレードが開催されます
- レディ・ガガに憧れる男性、顔と体を手術?
- 最もTwitterフォロワー数が多いゲイ&レズビアン
- 毎日新聞に性分化疾患と性同一性障害についての記事
- 人気急上昇! トランスジェンダー・カミングアウトしたモデルの佐藤かよさん
- 性同一性障害をテーマにした朝日新聞の「ニッポン人脈記」がスタート
- エリカ様がドラァグクイーンとセレブショッピング
- レディ・ガガが「Ping」に書いた同性婚支持コメントをAppleが検閲?
- 米国民の過半数が同性婚を支持するようになりました
- スカンジナビア航空、世界初の「空の結婚式」をゲイカップルにプレゼント
- DV防止法が同性カップルに適用され、事実上初めて同性の婚姻関係と認定されました
- タワーレコードが「フレディ・マーキュリーをしのぶ日」に賛同し、店頭で募金を実施中
- レディ・ガガがゲイの結婚式を執り行うために牧師の資格を取得
- ヴェネチア国際映画祭のオープニング『ブラック・スワン』でナタリー・ポートマンがレズビアンを演じました
- カストロ前議長が「同性愛者迫害の責任は私にある」と認めました
- 英国法務省の政務次官を務める下院議員がカミングアウト
-
8月
- 韓国のゲイ事情〜ゲーム業界、同性愛関連用語の使用禁止を解除
- 今年のエミー賞もゲイだらけ!
- 『フィリップ、きみを愛してる』の全米公開が遅れに遅れ、12月と決定
- 『24時間テレビ』でのはるな愛さんの扱いについて、怒りのコメントが噴出
- ブッシュ政権でゲイを抑圧してきた張本人がカミングアウト
- 英国のテレグラフ紙が論じる「Grindr」
- 初のゲイパレードが大成功を収めたネパールでは、ゲイが国の経済を救うと期待されています
- 米国の同性愛者の61%が「出会いはネット」と回答
- 国際競技大会に参加する性分化疾患の選手について、基本方針の協議が進んでいます
- リッキー・マーティンの回顧録『Me』が11月に発売
- 毎日新聞がスウェーデンのゲイ事情をレポート
- ドイツのゲイカップル、相続税が男女の夫婦と同じに
- メキシコ最高裁、首都で行われた同性婚や養子縁組を他州でも認めるべきと判断
- カリフォルニア州の同性婚裁判が控訴に持ちこまれ、同州の同性婚は延期されることになりました
- 『天才少年ドギー・ハウザー』のニール・パトリック・ハリス、同性のパートナーと双子の赤ちゃん
- 来週、カリフォルニア州で再び同性婚できるようになるかもしれません
- 【速報】関西レインボーパレード2010開催日決定!
- ゲイゲームズでホワイトハウス勤務の小泉さんが金メダル
- 『Xファクター』出身のジョー・マケルダリーくんがカミングアウト
- 祝20周年!パートナーシップが築いたドルチェ&ガッバーナの成功
- 期待の若手俳優トーマス・デッカーがゲイ役でドラマに主演
- ネパール初の本格的なプライドパレード
- 南米に同性婚の波が押し寄せています
-
7月
- 『ER』のサラ・ギルバートがレズビアン・カミングアウト
- トム・ハーディがバイセクシュアル・カミングアウト
- メキシコシティがアルゼンチン初の同性婚カップルに新婚旅行をプレゼント
- ジバンシィがトランスジェンダーのモデルを起用
- 性同一性障害の方たちが海の家をオープン
- TV局のゲイフレンドリー度の格付けでMTVが初の「優」を穫得しました
- 香港の人気歌手、ゲイであることをカミングアウト?
- マーク・ジェイコブスが自身のブランドの広告でヌードを披露
- 横浜で「“先生のための”セクシュアル・マイノリティ入門DVD」上映会
- カイリーがレズビアンのバンパイア役で映画出演
- ミッキー・ローク、次回作はゲイのラグビー選手!?
- 同性カップルのプロムへの参加を禁止する裁判で、レズビアンの18歳の女の子が勝利
- アルゼンチン、ラテンアメリカで初めての同性婚を認める国に
- アイルランドでシビル・ユニオンが成立
- レディ・ガガ、カルト教団の攻撃をかわし、勝利宣言
- YMCAの名称変更にビレッジ・ピープルが困惑
- ドラァグクイーンだらけのボートがゲイリゾートをパレード
- ゲイはノンケよりSNSやTwitterを頻繁に利用
- アルゼンチンの国会が同性婚法案を可決
- 米国がエイズ対策の新戦略を発表、オープンリー・ゲイの国家エイズ政策室長が活躍
- レズビアンを演じるジュリアン・ムーア、「同性愛者の希望に」
- 明日の「朝日ニュースター」でセクシュアルマイノリティを特集
- 【追悼】つかこうへい〜同性愛者への熱い共感を表現した劇作家
- インターセックスと報じられたセメンヤ選手、陸上競技会に復帰
- フィアットがゲイ仕様の特別車をパレードで展示
- 『BIG ISSUE』がゲイ&レズビアンのカミングアウトを特集
- ドルチェ&ガッバーナがアンダーウェア広告にイタリアのサッカー選手5人を起用
- ゲイ御用達のジムが映画祭のフライヤーを拒絶
- アジア最大規模のゲイ映画祭、本日開幕!
- マツコ快進撃!「徹子の部屋」に続いて「笑っていいとも」テレフォンショッキング出演
- ハワイ州知事、同性パートナー法案を拒否
- 男女逆転版『大奥』主演の二宮「そもそも事務所が、男女逆転の大奥」
- マット・デイモンとマイケル・ダグラスがカップルを演じる『リベラーチェ』、撮影は来年の夏以降に
- ロンドン・オリンピックがゲイグッズを販売
- Googleがゲイの従業員に給与を上乗せ
- ウォーレン・ベイティとアネット・ベニングの娘が男性へのトランスを切望
- スペインのゲイがハイヒールでレース
- アダム・ランバートの来日公演が決定!
- アイルランド議会、同性シビルパートナーシップを合法化
- ゲイもセレブも出演! NHK教育 ETV特集「HIVと生きる」
- レディ・ガガ、エルトン・ジョンのチャリティ・パーティで新曲を世界初披露
- ゲイ・タレント、ホン・ソクチョンさんがパク・ヨンハさんを追悼
- 「マトリックス」の監督、次回作はゲイのラブストーリー?
- カイリーの「天の声」があなたに贈られる!?
-
6月
- カイリーがゲイのためのフリーコンサートを開催
- 世界のプライドパレード:100万人規模で盛り上がる国もあれば、暴力的に弾圧される国も…
- アイスランド首相、国家首脳として世界初の同性婚
- オバマ大統領、ホワイトハウスにLGBTを招待し、同性パートナー政策の推進を約束
- 元MENUDOのアンジェロ・ガルシアがカミングアウト
- 参院選スタート。ゲイに優しい候補者は?
- レディ・ガガの新アルバムが完成、来年リリースへ
- 米国で同性カップルに育児介護休暇が適用
- Googleで「gay」を検索してみてください
- サッカーのスター選手フレドリク・リュングベリがゲイの噂を「光栄だ」と語る
- 映画祭の日程が決定!
- ゲイに捧げられたガガの『アレハンドロ』、マスコミでも話題に
- iPad、ゲイのキスシーンを描いたイラストを「墨塗り」
- アイスランドが同性婚を認める世界で9番目の国に
- 毎日新聞で性同一性障害について連載
- 2010年のトニー賞もゲイ色はしっかりと
- 中国で女装アイドルがブレイク
- ポルトガルで同性婚がスタート
- 男女逆転版『大奥』映画化、佐々木蔵之介&玉木宏のラブシーンも
- 2009年の新規エイズ患者、過去最多だった前年と同数の431人に
- フランスのマクドナルドのCMにゲイの男の子が登場し、話題に
- 米国パスポートの性別変更、性別適合手術の証明不要に
- カイリーがNYのゲイクラブにサプライズ出演
- レズビアン家庭の子の方が精神的に安定
- サンパウロのゲイパレードに300万人
- クリスティアーノ・ロナウド、ポルトガルの同性婚を支持
- レズビアン・カミングアウトしている『Glee』のジェーン・リンチが同性婚
- SATC2、いよいよ公開!
- 米議会、ゲイ&レズビアンの軍務従事を認める法案を可決
-
5月
- 中国政府の「聞くな言うな」政策とゲイコミュニティの拡大
- マラウィのゲイカップル、釈放へ
- 辞任した英国ローズ財務担当相「ゲイだと言えず…」
- シンガポールで開かれた第2回「Pink Dot」に4,000人が参加
- NHK教育『ハートをつなごう』でHIV特集
- ガガの『パパラッチ』少年をエレン・デジェネレスが売り出します
- カンヌ映画祭でもクィア賞、グレッグ・アラキが受賞
- 東京プライドパレードで中西圭三さんがライブ!
- マドンナがマラウィで逮捕されたゲイカップルのために立ち上がりました
- 『フリーへルド』長編映画化! 主演はエレン・ペイジ
- 毎日新聞にワシントンD.C.での同性婚についての記事
- オーストラリアの水泳選手がカミングアウト
- マーク・ジェイコブズ社のCEOが彼氏と結婚
- 4月
-
12月
SCHEDULE
記事はありません。