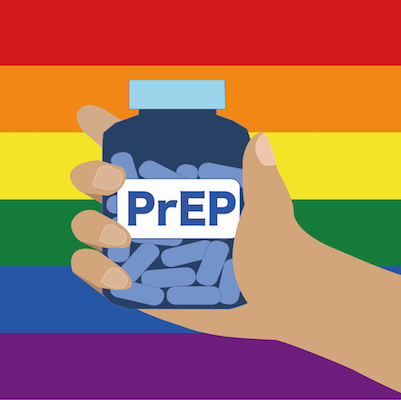REVIEW
アウティングのすべてがわかる本『あいつゲイだって ――アウティングはなぜ問題なのか?』
アウティングについて理解すべき事柄が過不足なく的確にすべて網羅されている良書です。これってアウティングなのかな…とモヤモヤすることがあったとき、自分が被害にあってしまったときなども、この本をひもとくことで解決への糸口が見えてくると思います。

『LGBTとハラスメント』の共著者であり、ゲイであることをカミングアウトして様々な媒体で活躍する松岡宗嗣さんが、初の単著『あいつゲイだって ――アウティングはなぜ問題なのか?』を発表しました。
アウティングということについて、命に関わる問題であるということを通奏低音としながら、そもそもなぜアウティングが当事者にとって危険なのか(シスジェンダー・異性愛者との温度差)、裁判や法制度についての解説、プライバシー保護との関連(米国と欧州でのアプローチの違い)、例外的に許容されるケースの検討、カミングアウトの自由ということ、戦後LGBTQ運動の流れにおける位置づけといった、およそ考えうるありとあらゆるイシューを網羅しながら的確に論じた良書です(ある社会問題に関して、これほどまでに過不足なく的確にわかりやすく解説した本ってなかなかないんじゃないかと思います)。「アウティング、ダメ、絶対」的な表層的で空虚なお題目ではなく、アウティング禁止法制のベースにあり、アウティングが危険な行為となってしまう根本要因である世間のLGBTQ差別(SOGIハラなど)についてきちんと認識させる本になっています。
目次に沿って、簡単に内容を紹介します。
「はじめに」で、松岡さんが初めて「家族間」で「アウティング」を経験した時のことを明かしています。カミングアウトしたお母様からお父様に、無断で話が伝わったのです。お父様が受け入れてくれるまでには時間がかかったそうですが、もしそのまま受け入れてくれなかったとしたら、松岡さんは実家に帰れなかったかもしれないと語っています(ご存じの方も多いと思いますが、そんなお母様も今はバリバリのLGBTQ活動家として多くの企業・団体で研修を行なったりしています)
松岡さんは、アウティングによって、もし差別的だったり、悪意を持っている人物に性的指向や性自認を知られた場合、命に関わるような事態になる可能性もあり(一橋大学の事件が念頭にあります)、だからこそアウティングは危険なのだということを、「運命の分岐点」という言い方で的確に言い表しています。
第一章は一橋大学アウティング事件についてです。「彼は私だったかもしれない」と松岡さんは述べ、裁判の傍聴にも出かけ、この事件のことをとても真剣に追いかけていただけに、簡潔ですが、決して他人事ではないという思いが伝わってくるようなルポになっています。
第二章は「アウティングとは何か」についての解説です。
なぜアウティングが起きるのかというと、この社会がシスジェンダー・異性愛を前提として成り立っていて、LGBTQは不可視化されているからです。
なぜアウティングが問題になるのか。それは社会にLGBTQに対する差別や偏見が根強く残っているため、性自認や性的指向の暴露によって不利益を被る可能性があるからにほかなりません。
第三章「繰り返される被害」では、アウティングに関するいくつかの事例が紹介されています。大阪の病院で起きたトランスジェンダーの方のケース(昨年、労災認定されました)、地方の女子高生が同性と交際していたことを友人に暴露され、学校側からひどい対応をされたケース。友人が「良かれと思って」広めてしまったが、結果的に当事者は職場を辞めざるを得なくなったケースなど。
カミングアウトということについても再確認されています。当事者は相手を選んでカミングアウトしているので、ある意味カミングアウトされるということは「信頼の証」と言えます。当事者は誰に伝え、誰には伝えたくないか選んでいますが、それは「身を守るためのゾーニング」なのです。
第四章「一橋大学アウティング事件――判決」。控訴審まで5年近く続いた一橋大学アウティング事件裁判の判決と、南弁護士や、ご遺族の言葉がまとめられています。無念の言葉。それとは対照的な、大学側の姿勢(同級生の姿勢)
第五章「アウティングの規制」では、事件後の社会の変化として、一橋大学の所在地である国立市がつくった画期的な条例のことが述べられています。
松岡さんは以前、アウティングが起きてしまうのは仕方がないと思っていたそうですが、そう思ってしまっていた理由を掘り下げています。同性愛という「経験」についての、たいへん重要な振り返りだと思います。同性愛者は自分がそうだと「気づく」わけですが、異性愛者は自分が異性愛者だと「気づく」ことはありません(”当たり前”なので)。同性愛は”異常”とか”欠陥”と見なされていて、当事者も「自分はふつうじゃないのだから仕方がない」と思ってしまっています。そのため、"ホモ"を嘲笑する周囲に同調して自分を隠して生きるか、自分を卑下して笑いを取るか、ということしか生きる道がないと思ってしまいがちです。国立市の条例の意義はそういう次元から考えるべきだと思う、と述べられています。
この条例には、アウティングの禁止だけでなく、カミングアウトの自由ということも謳われています。性的指向や性自認にかかわらず「個人として尊重される」ということの意義が語られています。
第六章「広がる法制度」では、パワハラ防止法のことが説明されています。SOGIをカミングアウトすること(暴露されること)が「大したことではない」わけではないと明記したことの意義や、苦情処理委員会を設けて対処してくれた豊島区のケースが語られています。
トランスジェンダー(Xジェンダーを含む)の方の困難について、「性自認のアウティング」というよりも法的な(戸籍上の)性別のアウティングが問題となるケースもあり、「性自認のアウティング」という言い方ではカバーしきれないのではないか、「出生時に割り当てられた法的な性別と性自認が異なること」が暴露の対象となるのであって、これを日本語で言い表す言葉が求められるのではないかと語られています(英語圏ではジェンダー・モダリティという言葉が提唱されているそうです。日本語訳すると「ジェンダー様式」だそうです)
第七章「アウティングとプライバシー」では、何がセンシティブ(機微)な情報かは人によって異なるということ、各自がコントロールする権利、人格権の一部といったことが解説されています。現状、個人情報保護法が定める「要配慮個人情報」にSOGIは入っていませんが、入れられるべきではないか、とも(終章でそのようにまとめられています)
第八章は「アウティングの線引き」です。線引きが曖昧なまま、「アウティングは良くない」と認知されてきたフシもありますが、ここで3つの切り口から線引きが検討されます。
1つめは「属性」のアウティング。在日コリアンの経験はLGBTQと似ているということ。インターセクショナリティの視点。言葉の汎用性(カミングアウトと同様、他の属性についても拡大してよいだろう。例えばHIV陽性の方や、被差別部落出身の方のプライバシー侵害において)について。
2つめはどのような「場面」がアウティングに該当するのか、しないのか。大津市の保育園児に関するアウティング、ゴシップ報道による被害、議員によるプライバシー侵害の事例が検討されています。
3つめは「許容範囲」をめぐる議論。例外的に許容される場合はあるのか。例えば、同性パートナーからのDVの被害の相談で、パートナーが同性愛者であることを相談機関に暴露することになるが…とか、同性間の性犯罪に関する報道で、加害者/被害者ともに、個人名を公表したうえで「ゲイアプリを使って」などと報じるとアウティングになるという問題提起など。自死の危険性など命に関わるような緊急の場合は例外的に許容されるのではないかとされています。
そして、原則の確認と、現実的な対応について論じられています。
第九章は「アウティングのこれから」です。
そもそも世間に差別が根強くあることが問題で、アウティングを規制する措置は差別のない社会が実現するまでの間の過渡的なもの(そんな社会の実現は並大抵のことではない)であるということ。「腫れ物」扱い、カミングアウトしてほしくないとする態度の問題について。カミングアウトを受けた人も、独りで悩むのではなく、また、友人や地域の人に話してしまうのではなく、機微な個人情報を扱える外部機関に相談を、という呼びかけ。「噂」への対応。起きてしまった時の対応、など(就活でカミングアウトしたが、入社してみてやはりゾーニングしたいと申し出たトランスのEさんの事例で、会社側が、すでに何人かには話してしまったものの、どこまで伝えたかをEさんに話し、その人たちにそれ以上広がらないように説明するという対応をしてくれたという事後対応はよかったです)
米国と欧州の個人情報保護法制のアプローチの違い(自由至上主義と尊厳至上主義)の話も興味深かったです。
そして終章「アウティング、パンデミック、インターネット」
コロナ禍で、コロナ感染とアウティングの二重の恐怖に苛まれる当事者もいるということ。LGBTQのお店でクラスターが起きたとき、そこにいた人全員がアウティングされる危険性もあるということ。
ナチスによる同性愛者虐殺、戦後のゲイ解放運動やエイズ禍の時代に用いられたピンクトライアングル、ストーンウォール以降の運動、パレードの隆盛――というLGBTQの権利回復運動の流れに「カミングアウトの自由」を位置づける話は、とてもよかったです。
職場で起こったアウティングの事例もさまざま紹介されていますし、アウティングについて理解すべき事柄が過不足なくすべて網羅されていると思います。大企業だけでなく、今年4月からはパワハラ防止法があらゆる企業に適用されますので、アウティング防止策を講じることが措置義務となります。そういう意味でも、とりあえず職場に一冊、この本を置いておくべきではないでしょうか。

あいつゲイだって ――アウティングはなぜ問題なのか?
松岡宗嗣:著/柏書房:刊
INDEX
- ミニマムなのにとんでもなくスリリングでクィアな会話劇映画『アバウトアス・バット・ノット・アバウトアス』
- 異国情緒あふれる街で人と人とが心通わせる様にしみじみと感動させられる名作映画『CROSSING 心の交差点』
- ワム!のマネージャーだったゲイの方が監督した真実のドキュメンタリー『ジョージ・マイケル 栄光の輝きと心の闇』
- アート展レポート:ネルソン・ホー「鏡中花、水中月 - A Mere Reflection of Flower and Moon」
- レポート:グループ展 “Pink”@オオタファインアーツ
- アート展レポート:東京都写真美術館「総合開館30周年記念 遠い窓へ 日本の新進作家 vol.22」
- レポート:國學院大學博物館企画展「性別越境の歴史学-男/女でもあり、女/男でもなく-」
- 実は『ハッシュ!』はゲイカップルに育てられた子どもの物語として構想されていた…25年目の真実が明かされた橋口監督×田辺誠一さんによる映画『ハッシュ!』スペシャルトークイベント
- レポート:短編集「Meet Us Where We’re At」上映会
- レビュー:BSSTO「世界の・周りの・私のジェンダー」を見つめるショートフィルム特集
- たとえ社会の理解が進んでも法制度が守ってくれなかったらこんな悲劇に見舞われる…私たちが直面する現実をリアルに丁寧に描いた映画『これからの私たち - All Shall Be Well』
- おじさん好きなゲイにはとても気になるであろう映画『ベ・ラ・ミ 気になるあなた』
- 韓国から届いた、ひたひたと感動が押し寄せる名作ゲイ映画『あの時、愛を伝えられなかった僕の、3つの“もしも”の世界。』
- 心ふるえる凄まじい傑作! 史実に基づいたクィア映画『ブルーボーイ事件』
- 当事者の真実の物語とアライによる丁寧な解説が心に沁み込むような本:「トランスジェンダー、クィア、アライ、仲間たちの声」
- ぜひ観てください:『ザ・ノンフィクション』30周年特別企画『キャンディさんの人生』最期の日々
- こういう人がいたということをみんなに話したくなる映画『ブライアン・エプスタイン 世界最高のバンドを育てた男』
- アート展レポート:NUDE 礼賛ーおとこのからだ IN Praise of Nudity - Male Bodies Ⅱ
- 『FEEL YOUNG』で新連載がスタートしたクィアの学生を主人公とした作品『道端葉のいる世界』がとてもよいです
- クィアでメランコリックなスリラー映画『テレビの中に入りたい』
SCHEDULE
記事はありません。