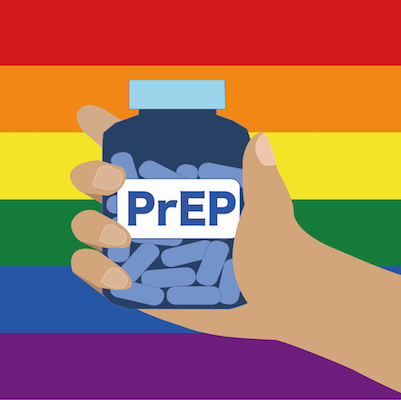FEATURES
レポート:エイズ学会2024(2)
NPO法人aktaの代表・岩橋恒太さんが大会長を務め、新宿の京王プラザホテルで開催された「日本エイズ学会学術集会・総会エイズ学会」の2日目の様子をレポートします

NPO法人aktaの代表・岩橋恒太さんが大会長を務める日本エイズ学会学術集会・総会エイズ学会(以下「エイズ学会」)が11月28日〜30日に新宿の京王プラザホテルで開催されました。PrEPが承認されたことを受けての課題や、最新のさまざまな事柄について話し合われた学会というだけでなく、ゲイコミュニティの方たちが多数活躍し、同窓会のようなコミュニティイベントのような趣もあるイベントでした。3日間のエイズ学会を3回に分けてレポートします。2回目は11月29日(金)の模様です。
(取材・文:後藤純一)



会長講演「エイズ予防とコミュニティエンパワメントの重要性:これまでとこれから」
14:05-14:20 第1会場
aktaの岩橋さんによる会長講演でした。自身がなぜHIVのことに関わるようになったのかという紹介から始まり、aktaでどのような活動をしてきたかということや、今回のエイズ学会のポスターのイラストの中にセックスワーカーやトランスジェンダーや薬物の注射を使ってる人なども含まれているというお話、なぜコミュニティエンパワメントが必要かといったお話(UNAIDSは「コミュニティが頑張ってるから応援しよう」ではなく、「必要なプロセスだ」と強く言っている。コミュニティがエイズ対策の中心的な役割を果たすこと、バリアを取り除くことが必要だ)、日本の状況について(CBOの経済的な基盤が脆弱)、すべてのひとにコンビネーション予防を(市民がアクセスできる予防の選択肢を複数示すこと)、といったお話をして、最後に、PrEPについて、経済的なことやヘルスリテラシーとの関連が強く、地方ではアクセスが難しかったり、様々な格差があるため、公助が必要だとして、署名への協力を呼びかけました。
ポスター展(HIV陽性者をテーマとしたポスター)
14:30-16:00 4Fポスター展会場
総合受付の奥にある広々とした部屋(「花」)がポスター展の会場になっていて、全国各地の団体や、企業の取組みの発表の場になっていました。考えてみれば、そうした団体・企業の活動の全てにトークセッションなどの発表の場を提供することは難しいため(コマ数が限られているため)、このように、畳1畳分くらいのスペースにポスターを掲示し、担当者が説明したりというかたちで取組みを知らせるという方法が編み出されたのだな、なるほどなぁと感心しました。
aktaやANGEL LIFE NAGOYA、カラフルドットライフの方たちがポスターの前でお話をしていて、写真を撮らせてもらいました。赤い花がついているのは、優秀賞を受賞した印だそうです(すごいですね)



また、このスペースでは(二丁目仲通交差点に看板も出している)ヴィーヴヘルスケアが無料で飲み物を提供したり、アンケートをとったり(全然難しくないです)、手書きのメッセージを募集したりというブースも設置されていました。ものすごくコーヒーが飲みたかったので、とても助かりました。「PrEPが当たり前の選択肢になりますように」とメッセージを書いて貼っていただきました。
口演16(PrEPに関して)
15:20-16:00 第5会場
口演というのは一般演題の募集に応募した方たちによる発表です。たくさんある一般演題がテーマごとに整理され、全部で22コマの口演に分類されていました。私はぷれいす東京の生島さんやカラフル@はーとの翁長さんなどよく知っている方たちが登壇するPrEPに関する口演を聴くことにしました。
座長はSH外来などにも携わってきた国立国際医療センターの水島大輔先生と、いだてんクリニックの吉田昂汰先生でした。全部で5名の方がお話されました。
◎日本のトランスジェンダーに見られるヘルスケアへの障壁
日本GI(性別不合)学会認定医であるパーソナルヘルスクリニックの池袋真先生のお話。トランスジェンダーの方は55%しか性交渉歴がないというお話にまず衝撃を受けました。世間から付与されたスティグマや、自身の生殖器を見たくないなどの恐怖心もあり、病院の受診に不安を抱える方が8割強もいて、性感染症検査が無料であったとしても検査を受けない方も多いそうです。世界的に見るとトランス女性はHIV感染のリスクが平均の49倍も高いし、研究途上ですが、トランス男性もハイリスクだと思われます。そもそもトランスジェンダーのセクシュアルヘルスの研究は少なく、そのなかでMSMに該当する方となるとさらに少ないといいます。ハイリスクであるにもかかわらず、病院に来れない方が多いということが課題です。
◎"On PrEP"の多義性とスティグマ:PrEP使用者のインタビュー調査から
早稲田大学大学院人間科学研究科の首藤さんのお話。PrEPに対する”乱交的”とか”感染リスクを高めている”などといった偏見がスティグマとなっており、そのことがPrEP利用の障壁になっているということで、PrEPを利用している8名のMSMの方に、そのことを他者に伝えたときどういった反応を受けたかについてインタビューし、その結果を発表されていました。PrEP利用者はHIV予防に積極的で意識が高いという見方をされることもあれば、生でやりたい人、性に奔放であるという見方もある、自分では予防の強化・包括的な予防のつもりでやっているのに友人に”インラン”とか”遊び人”と言われ、そういう認識の不調和がスティグマとなるケースが可視化されました。「ベアバックが本当に悪いことなのかと根源的に問うことが大事だ」という意見もあったそうです。PrEPへの理解を深めてもらいながら、多義的な価値観に対応していくよう、継続的なサポートが必要ではないか、と話されました。たいへん興味深い、有意義な発表でした。
会場からは、隠語による差別というのは薬物と一緒だと思う、リテラシーをどう高めていくか、発信する側も強靭さを、本当には国がやるべきだよね、という声が上がりました。
◎PrEP薬処方クリニックと見守りサービス提供クリニックを取材して ーPrEP 薬服用当事者の考察ー
「PrEP@TOKYO」を運営し、PrEP利用者の手記集の発行なども行なってきたカラフル@はーとの翁長祐太さんのお話。服用者が増加し、見守り医療のクリニックも増えたことを背景に、どのようなサービスが提供されているのか聞き取り調査を行ない、当事者の視点で評価するものでした。結果、見守り医療の提供だけでは利用者が少なく、ジェネリック薬の供給が求められているということ、オンラインのみの場合、陽性が判明した際の適切な対応や継続性が求められるということ、地方ではクリニックがない空白地域もあるため、オンライン診療は有効だが、やはりクリニックができてほしい、といったお話でした。また、なかには検査キットやPrEP薬だけを販売し、適切な診察をしなかったり、性感染症の治療を提供しないような悪質なクリニックもあるため、そういうところは選ばないでほしい、とも話されていました。
◎PrEPに関する4回の大規模調査から考える国内で求められる地域の医療環境についての考察
ぷれいす東京の生島さんのお話。これまでに4回の大規模調査(LASH調査)を実施してきて、PrEP自体の認知度は上がっているが、利用者で定期的な診察を受けていない人が41.7%にも上るということ(地域別に見ると、定期的に診察を受けている人の割合は意外と北陸で高い)、PrEPに毎月いくらまでなら払えるかとの質問に対して5000円まで、1万円までとの回答が多かった(費用は重要で、払える金額と利用に有意に相関関係がある)ということ、承認されたことでツルバダの薬価が7万円代になると見られており、クリニックでデシコビのジェネリックを処方してもらうと約1万5千円になるということから、誰もが使いやすいPrEPにならない懸念があるということ、自由診療のクリニックは様々で、利用者のリテラシーを支援することも大切だといったお話がされました。現在、「クリニックに行こう」というキャンペーンを計画しているそうで、行かずに陽性になってしまった方の体験を載せた冊子を配布しようとしているそうです。
◎オンラインPrEP専門クリニックを受診する全国の患者の性行動と健康課題の実態
ゲイコミュニティでおなじみ「ベアクリニック」の遠藤洵之介先生のお話。オンラインでPrEP専門のクリニックを運営し、これまで2000名以上に処方してきただけでなく、LINEを活用し、常に患者とつながり、健康観察なども行なっています。デイリーの人の半数がDoxy PEPも行ない、新規陽性者はゼロだそうです。東京圏の方たちは検査も受け慣れていて、「みんなやってるから」という動機で始める方が多いのに対し、東京圏以外の方たちは真逆で、検査を受けたことない人が多く、「念のためにやる」という方が多いというお話が興味深かったです。
日本におけるPrEPの普及と実装の課題 3分野から
16:10-17:40 第4会場
ぷれいす東京の生島さんと、東京医科大学病院臨床検査医学科の村松崇先生が座長を務めたセッションです。
トイレに行ったりしてて少し遅れて入ったのですが、場内かなり席が埋まっていて熱気が感じられました(やはりPrEPへの関心は高いようです)。が、ただ座って話を聴くだけならともかく、ノートPCでメモを取っても隣の方の迷惑にならないような席が見当たらず、心折れてしまいそうでした(まさか床に座るわけにもいかず)…とりあえず空いてる席に座り、お話だけ聴くことにしました。
国立感染症研究所エイズ研究センターの菊地先生は、もしPrEPを中途半端にして薬剤耐性ができてしまった場合の治療法についてのお話をされていました(すみません、前半のお話を聴けなかったのと、メモを取れなかったということもあり、あまり詳しくお伝えできません…)
宮の森レディースクリニックの池田先生は、北海道で初めてPrEPの見守りクリニックを始めた方で、道内の当事者のニーズに応え、せめて見守りを、との思いで頑張ってやってきたものの、PrEP薬の在庫を抱えたり、苦労が多いというお話でした、
やろっこの太田さんは、東北にはPrEPを扱うクリニックもないし、検査環境も不十分なので、自力でPrEPをやろうとするととても苦労するといったお話をされていて、東京との格差をひしひしと感じさせました(東北のゲイの方の出会いなどについてもお話がありましたが、意外にもアプリの利用頻度も少ないそうで、そもそも出会いをあきらめているように思われるというお話が身につまされました)
異なる分野のパネラーであるお三方による総合討論となりました(ここで、最前列の席が空いていることがわかったので、スキをみて移動しました)
太田さんは、耐性ウイルスの問題もあるし、東北のように見守りクリニックがない地方などでジェネリック薬を自己輸入している人に対しては検査とセットだということをしっかり伝えていく必要があると語りました。また、池田さんのお話に対して、ディスカウントまでして必要な方に届けていることに頭がさがる、東北にPrEP薬を処方するクリニックができたら、ちゃんと継続できるように後押ししたい、と語りました。
池田さんは、薬事承認によってツルバダ系ジェネリック薬が輸入できなくなったことにより、(デシコビはオンデマンドに使えない、女性はデシコビが使えないという話になっているので)やめてしまう人も出るだろう、手を引くことも考えている、と明かしました(せつないですね…ツルバダを安価で利用できる仕組みを作らない限り、PrEPが普及しないどころか、今よりも利用が減ってしまい、こうして地方で頑張っているクリニックも立ち行かなくなってしまいそうです)
続いて、フロアの観客との質疑応答の時間となりました。実に活発な議論が展開されました。
――検査キットの活用についてご意見を聞きたいです。薬価のことだけでなく様々考えると、今後、見守りクリニックが広がるとは思えず、地方の検査機会の少なさも考え合わせると、検査キットとセットでPrEPを提供することで完結するのでは?と思います。菊地先生のお話だと、そもそも検査を受ける機会がなかった人が多数でした。耐性のリスクについての認識の問題もあると思います。池田先生の調査で、啓発が行なわれていれば検査がセットで必要だと認識されるとのお話もあったことですし、ユーザーエデュケーションが進めば可能なのではないでしょうか。
池田先生:
この直前の一般演題の最後に、オンラインだけのクリニックのお話があり、こういうやり方もあると思いました。オンラインだったらそういうところにつないでいくのもよいのではないかと。検査キットの費用のことも問題で、どこかからの援助がないと難しいと思います。
太田さん:
検査キットのコミュニティ向けの無償配布は年に1回しかなく、通常は5000円くらいかかります。見守りクリニックでPrEP薬の購入も一緒にすると割引になったりもするけど、やはり費用がかさむと利用のハードルが上がると思います。
菊地先生:
検査の多様化の課題とリンクしていると思います。セルフテスティングは個人輸入だと精度の問題などもあり、すべて自分で決定していいのかとかいう問題もあり。ツルバダが承認されたからこその課題が見えてきましたね。
村松先生:
腎機能の検査などもかかわります。これは重要な問題。
生島さん:
郵送検査が高いのを変えていけないか、と思います。競争原理で安くなるという期待も。海外から輸入すると安いですよね。価格の問題は大きいです。
――デシコビをオンデマンドで使うことは承認されていませんが、当院はそのことを説明したうえで、ご希望の方には出しています。ジェネリックが買えないのでやめるという方が出てくるのは最悪なので、何かできるようにしないといけないと思っていますが、どう思われますか?
生島さん:
今後、手引きの改定があるので、そのことについての議論が始まります。デシコビに関するデータやエビデンスを再検討したいですね。
菊地先生:
エビデンスにもレベルがあって。臨床試験についてはエビデンスがないという話です。
とあるクリニックの方:
ちょっと昔だったらギリアド※を襲うっていう話になってると思う。テレビに出て、こんな問題なんだよ、と訴える。そうしないと変わらない。ギリアドは絶対に価格を下げないですよね。理想を言えば、ギリアドはエイズ予防財団にデシコビを寄付してほしいです。(※ツルバダやデシコビはギリアド社が製造しています)
村松先生:
国際会議では製薬会社のブースに押しかけるのは見慣れた光景ですよね。
生島さん:
現在、ギリアドの社長さんと厚労省宛の署名を展開してますので、ぜひみなさん、ご協力を。
とあるクリニックの方:
(ツルバダは高くて買えないので)オンデマンドを希望する方には当院の責任においてデシコビをを処方しています。大量に購入して破格の値段で提供しているので、利益は出ていません。それでも続けられない人もいます。全国に広めることを考えると、クリニックが束になって、といったことを考えるべきではないでしょうか。
――大阪でPrEPを含めたHIVの予防や治療を行なっています。去年PrEPを始めたときはオンデマンドの方が多く、偏見などもあって大変でした。MASH大阪のご協力を得てコミュニティと一緒に検査事業も進めています(ワンコイン検査)。ハイリスク層の人にアプローチするにはHIV検査事業と合わせてPrEPを促進するのが効率的ではないかと。見守りクリニックはPrEPだけじゃなく他のSTIも診るので、包括的にSTIをやってるところがやるべき。さらに先、クリニック主導で啓発や包括的な検査を行ない、患者さんに説明していくようにするのがよいのではないでしょうか。
最後に登壇者の方たちが一言ずつ、お話しました。
菊地先生:
5000円でも黒字が出ないというお話があった。海外では無料でPrEPを利用できるところが多い。低価格でも利用できない人たちのほうがリスクが高いということを考えると、他の方法が必要だと感じました。
池田先生:
どうしたら女性にPrEPを利用してもらえるか。ピルとPrEPをセットで普及できたらと思いますが、どうしたらいいか、考えます。
太田さん:
相談に来る人は、ネットに情報があるけど、コミュニティセンターで相談してから判断したいと言って来られる。そういう方たちにちゃんと届けられたらと思う。地域に還元したいです。
村松先生:
三領域合同でPrEPを今後どのように展開するか、議論しました。ツルバダが承認されて、問題が増えているように感じます。地域格差のお話を聞いて、その地域の実践からヒントが得られた部分もあると感じました。学会のなかでも、専門的に議論が進んでいる方も、ついていけてない方もいます。裾野が広がり、エイズ学会だけでなく地域でも議論が進んでいくことを期待します。
※なお、この日の夜には(残念ながら取材はできなかったのですが)懇親会で「Living Togetherのど自慢vol.67」も開催されていました。
INDEX
- 特集:レインボーイベント2026(上半期)
- レポート:年忘れお楽しみイベント「gaku-GAY-kai 2025」
- 特集:2026年1月の映画・ドラマ
- レポート:BUFF Fetish Xmas
- 2026年への希望を込めて――年忘れ&年越しイベント特集2025
- レポート:高雄同志大遊行(KHPride)
- レポート:レインボーフェスタ和歌山2025(2日目)
- 2025-2026 冬〜新春のクィア・アート展
- レポート:涙、涙の院内集会「第8回マリフォー国会」
- 特集:2025年12月の映画・ドラマ
- レポート:東京トランスマーチ2025
- 2025-2026 冬〜新春の舞台作品
- レポート:レインボーフェスタ那智勝浦(2日目)熊野古道パレード
- レポート:レインボーフェスタ那智勝浦(1日目)
- レポート:みやぎにじいろパレード2025
- レポート:香川プライドパレード
- レポート:岡山レインボーフェスタ2025
- レポート:九州レインボープライド2025
- 特集:2025年11月の映画・ドラマ
- レポート:春日井虹色さぼてんレインボーパレード2025
SCHEDULE
- 01.11アスパラベーコン
- 01.112CHOME TRANCE
- 01.11新春!セクシー性人式 -SEXY COMING OF AGE-
- 01.12祝・大人化計画