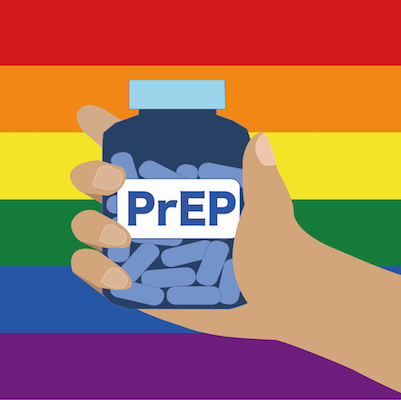FEATURES
レポート:エイズ学会2024(3)
NPO法人aktaの代表・岩橋恒太さんが大会長を務め、新宿の京王プラザホテルで開催された「日本エイズ学会学術集会・総会エイズ学会」の最終日の様子をレポートします

NPO法人aktaの代表・岩橋恒太さんが大会長を務める日本エイズ学会学術集会・総会エイズ学会(以下「エイズ学会」)が11月28日〜30日に新宿の京王プラザホテルで開催されました。PrEPが承認されたことを受けての課題や、最新のさまざまな事柄について話し合われた学会というだけでなく、ゲイコミュニティの方たちが多数活躍し、同窓会のようなコミュニティイベントのような趣もあるイベントでした。3日間のエイズ学会を3回に分けてレポートします。ラストは11月30日(土)に行なわれた市民向けプログラムの模様です。
(取材・文:後藤純一)
★1日目のレポートはこちら、2日目のレポートはこちらです
TOKYO AIDS WEEKS 2024 合唱ミニコンサート
12:40-13:20 第2会場
コロナ禍による中断を経て、5年ぶりにTOKYO AIDS WEEKSの合唱ミニコンサートが復活しました。
私は初回以来、ほぼ毎年、国立国際医療センターでこのコンサートを聴いていますし(なにしろ友人・知人がたくさん参加しているので)、今回は友人のRinoさんが初めて指揮をするということもあり、何があっても見届けなければ、と意気込んでいました。
会場はかなり満員で、熱気に包まれていました(あまりじっくり見ていないのですが、イケてるゲイの方が多数、いらっしゃったように思います)
生島さんが、このコンサートは2015年、国立国際医療センターの岡先生が学会の座長を務めたときに「好きにやっていいよ」と言ってくれたのでやりはじめました、と立ち上げの経緯を簡単にお話しました(2015年のレポートはこちら)。また、ディズニーメドレーを歌うにあたり、ディズニーの黄金期を支えた作詞家のハワード・アッシュマンが、1992年に『美女と野獣』で2度目のアカデミー賞を受賞しましたが、ハワードはすでにエイズで亡くなっていて、パートナーのビル・ローチが代わってオスカー像を受け取り、パートナーのハワードがエイズで亡くなったこと、周囲のサポートを受けながら最期まで創作を続けたことを話したというエピソードを紹介してくれました。また、今回は、日本人ゲイ男性だけでなく多様な方たちが参加しているというお話もありました。
いよいよ演奏が始まりました。指揮はRinoさん、ピアノ伴奏は(長年コミュニティ活動に携わってきた)べーすけさんです。
1曲めは、みなさんご存じ、平井堅さんの『POP STAR』でした。ノリノリで楽しく演奏され、軽く振りを踊っている方もいらっしゃいました。
確かに、レズビアンの友人もトランスジェンダーと思われる方も、外国にルーツがあるように見える方も参加していました。PRIDE CHIORの人たちを中心に、牧師の平良愛香さん、「Base」のToshiさん、和太鼓をやっているDAIさんなど、ゲイコミュニティのいろんな人たちも参加していました。体の具合がよくないのか、椅子に座って歌っている方もいらっしゃいました。
2曲めはディズニーメドレーで、「美女と野獣」はもちろん、数々の有名な歌が歌われました。「レット・イット・ゴー~ありのままで~」は前夜が金ローのアナ雪の放送だったのでグッドタイミング!と思いました。聴き応えがあって、とてもよかったです。
3曲めはときどき通信の「大空」という歌。札幌で「WAVE2008」というHIVのイベントで、地元のとある陽性者の手記をきっかけに生まれた歌で、HIV陽性であることを聞いた人の気持ちを歌にしてくれて、というお話を、ぷれいす東京の加藤さんがしてくれました。もともといい歌なのですが、そのエピソードにも胸が熱くなりますし、ゲイインディーズシーンから生まれた歌が今でもこうして歌われていることの感慨もあり、いろんな意味で心に沁みる演奏でした。
ラストは、ミュージカル『サウンド・オブ・ミュージック』より「Climb Ev’ry Mountain」。この曲は「すべての山を登れ」と訳されますが、みんなそれぞれつらいことを乗り越えている途上であり、一緒にそれを乗り越えていこうという意味だと思っています、というお話がありました。これまでのコンサートでも歌われてきましたが、本当に名曲だなぁとあらためて感じました。感動的でした。大きな拍手が沸き起こりました。
アンコールで「上を向いて歩こう」が演奏され、客席の方も一緒に歌ったりしました。
こんなにたくさんの曲を演奏…大変だったと思います(楽譜が分厚くてビックリ)。何度か練習を重ね、当日は土曜の朝9時から会場に集まって臨んだそうで、本番では「鬼滅」並みの全集中で素晴らしい演奏を聴かせてくれました。みなさん、本当におつかれさまでした。
合唱って、音楽ですが、演劇にも近くて、歌ってる方たちの表情(肉体)から体温や思いが直に伝わってくるし、声を合わせてひとつの音楽をつくるというところも感動的ですよね。
今回のコンサートはエイズ学会の会場で学会の会員向けに演奏された後、一般の方に向けても演奏するというかたちでした。学会の医療関係者や研究者の方なども、何か心に響くものがあったり、LGBTQコミュニティの良いところを感じ取ってくれたりしたのではないでしょうか。
HIV/AIDSごちゃまぜトークセッション すべての垣根を越えた先に見える未来
13:40-15:10 第5会場
コーラスの後は、市民公開講座が2つ開かれました(おそらく16時までに撤収という都合で、同じ時間帯で開催されました)。私はジャンジさんや学さん、奥井さんが出るというので「HIV/AIDSごちゃまぜトークセッション」に参加しました。
座長を務めたのは国立病院機構大阪医療センターでHIV陽性者の支援を行なっている岡本学さん(20年以上前から支援の仕事をしている方です)と、aktaのジャンジさん。登壇したのは、HIV陽性者であることを公表している奥井裕斗さん(こちらのトークショーや、こちらの記事などにも出演しています)、薬害エイズ被害者で一般社団法人アプローズの後藤正善さん、精神・発達障害やHIV+のLGBTQも安心して利用できる就労移行支援事業所(福祉サービス)を運営するReBitの代表理事の藥師実芳さんという多彩な方たちでした。一般演題(市民向け公開講座)で陽性者が登壇するのは初めてだそうです。
そもそもは、学さんと後藤さんとジャンププラスの高久さんが飲んでいたときに、こういういろんな人がごちゃまぜで話せる場があったらいいよね、という話になり、学さんとジャンジさんがそれを引き受け、このトークセッションが実現したんだそうです。
一般市民に公開されている講座ということで、学会とはまた違う層の方たちがたくさん詰め掛けていました。
初めに学さんが日本のHIV/エイズの歴史と自分のヒストリーを重ね合わせながら、友達のHIV感染をきっかけに大阪医療センターでHIV陽性者のためのソーシャルワーカーとして働くようになり、自身で陽性者のためのカフェイベントなども開くようになった、今でも会社を辞めさせられたりという差別がある、といったお話をされました。
後藤正善さんは、血友病患者で、子どもの頃からエイズといじめられ、周りでは感染告知すらされずに亡くなった方もいて、家族にうつってしまって両親も亡くなったりという悲惨な出来事もあり、中1の時にHIV感染の告知を受けた、薬害訴訟で一次原告として闘った、当時中3だったが証言台にも立った、だんだん実態が明らかにされ、川田龍平さんが顔出しで闘い、人間の鎖をやったりして96年に勝訴、救済の仕組みができた、薬害エイズの被害者1433名ののうち748名が亡くなった…という壮絶なお話でしたが、後藤さんのキャラクターなのでしょう、あまり深刻さを感じさせない明るい雰囲気で、笑い話なども交えながらお話してくれました。
奥井さんは(個人的に、いま最も「この人の話をもっと聞きたい」と思う方ですが)、感染告知を受けて9年が経った人として、いまどういう生活をしてるかとか、何を感じ、考えているかということをお話しました。
HIV陽性であるということは自分で言わない限り周囲の人には伝わらない(不顕性)、完治しないので、拒まれうるという意識をずっと持ち続けたままの状態に置かれ続ける、そのことは人格の全体に負の影響を与え続け、非常に抜け出しにくいと、その状態を固定化するものとして、善意だったり、恐怖を煽るような予防施策だったり、“かわいそう”と言って泣かれたり、「言わなくていいよ」と言われたり、“普通に”という言葉自体も総体となって、言い換えると「マイクロアグレッション」として機能している。善意の人の功罪ということがあって、傷つけたり、諦めさせたり(惰性的な容認)、これは慢性疾患にありがちな問題だが、諦めは社会ににじみ出ると思う。僕には描きたい未来がある、もっと幸せになれると思っている。諦めない陽性者を応援してほしい。自由は連鎖する。僕はかつてLGBTQは自由だという記事を見て、HIV陽性者も、と思えた。思いは伝播する。HIV陽性者も「与えられる存在」になれかもしれないと思っている。という、素晴らしいと一言でまとめてしまうのは心苦しいくらい、本当に素晴らしいお話でした。
薬師さんのお話。性別違和(というより、周囲の理解や支援のなさ)に苦しみ、高校2年で自殺未遂をした、自分はパンセクである、トランス男性で男性とセックスする人もいる、しかし、性感染症についての相談がしづらい、LGBTQやHIV陽性者の就労支援をしているが、複合的なマイノリティの就労不安は深刻で、医療の現場でもHIV陽性であることを言えない、お薬手帳を分けている人もいる、今後マイナンバー保険証で履歴を見られたり、アウティングされないかという不安を抱えている、といったお話でした。
それぞれの登壇者が、いま話されたことについて感想を言い合いましょう、ということになりました。
学さん:
「奥井さんの話は、耳に痛い。善意として言ったことが傷つけてしまうこともあるということを気をつけながらやっていきます」
奥井さん:
「今の治療が始まる前と後とでは、状況がまるで違うと思っていて。以前はそれどころじゃなかったと思います」
後藤さん:
「昔は“いいエイズ”と“悪いエイズ”という言い方がされていて。薬害の裁判の支援者のゲイの人たち…当時は“オカマ”と呼ばれたりもしていたけど、その中に長谷川さんがいて。僕は小6で。その出会いはインパクトがあった。それが今のセッションにつながっています」
薬師さん:
「僕はユース向けのHIV予防施設の「ふぉーてぃ」でバイトしてた時もあって、そこで長谷川さんに知り合いました」
後藤さん:
「恩返しとして就労支援をしています。僕は120社受けて全部落ちた。HIVを理由に。黙っている人もいれば、オープンにしないと働けない人もいて、いろんな事情がある」
奥井さん:
「僕はsoarの井上健斗さんの記事を読んで、ショックを受けて。トランスジェンダーの人たちの困り事を知らなくて、自分はあぐらをかいてたんだと気がついて。それまで直球で差別を受けたことがなかったけど、そこで自分の前に誰かいたんだと気づいた。それがHIV陽性をオープンにした理由です」
薬師さん:
「言わずに働く人が多い。でも、いつか伝えることもあると思います」
学さん:
「働けるんですか?とか、なんかあったらどうするんですか?と言われたり。そういうことを引き受けさせられる当事者がいるということが心苦しいです」
薬師さん:
「なんで感染したの?とか、キッチンで働いていいの?と言ってしまう人もいます…」
この後、会場との質疑応答があり、“ふつう”ということについて議論が交わされたりしました。
今回は座長を務めていたためジャンジさんがあまりしゃべっていないのが残念といえば残念でしたが、バックグランドや経験が異なる、年齢やジェンダーやセクシュアリティも異なる多彩な方たちが一緒に話すというのは、とても意味のある試みだと思いましたし、個人的には、奥井さんのお話をじっくり聴けて、とてもよかったです。
エイズ学会を振り返って
正直に言うと、ぷれいす東京の生島さんが会長を務めた2017年は中野区でTOKYO AIDS WEEKS 2017のイベントが4日間にわたって開催され、連日盛りだくさんな内容で、それだけでも取材が大変なくらい充実していて、今回もそういう感じになるのでは?と勝手に思っていたのですが、意外と市民向けの催しはそこまで多くありませんでした。でもそのおかげで、学会本体を取材しようと思えたのは、怪我の功名というか、ある意味、運命だったのかもしれないな、と思いました。実際に取材してみて、いろんなことがわかったし、新鮮でしたし、同窓会みたいにひさしぶりな方にたくさん会えて、もっと前から来ればよかった…と反省しました。
今年はツルバダがいよいよ薬事承認され、PrEPが公のものになった、大手を振ってPrEPを推奨できるようになったというエポックメイキングというかターニングポイントと言えるような出来事がありましたので、学会でもPrEPについてのセッションが注目を集め、熱い議論が交わされていた印象です。
PrEPの普及には(もともと性感染症を扱っているような)見守りクリニックが鍵になるということがよくわかりました。海外からジェネリック薬を自己輸入する方も、PrEPを始める前に必ずHIV検査を受けなければいけないし、始めてからも3ヵ月に一度は検査を受けたり、他の性感染症にかかっていないかというチェックを受けたり、医師に相談したりという「見守り医療」が大事です。
これまで(東京でも、地方でも)いろんなクリニックがPrEPの普及のために、ジェネリック薬を処方しながら採算度外視で頑張って来られたということを知りました。ジェネリック薬も有効期限がありますし、クリニックでたくさん買っても利用者がいなければ在庫を抱えたり廃棄したりということになってしまいます。ゲイ・バイセクシュアル男性への調査でも5000円までだったら出せるという方が多いことがわかっていて、料金もできるだけ安くなるよう工夫しないといけないし、そうじゃないとPrEP自体をやめてしまう人も出てきます。東北にはPrEPの見守りクリニック自体がなく、やろっこの方がいろいろアドバイスはしているものの、本当はクリニックがあってほしい、しかし、地方でクリニックを運営することの厳しさも、北海道の事例で明らかになりました。
こういう現状なのに、今年、ツルバダが薬事承認されたことをきっかけに、ツルバダのジェネリック薬が輸入できなくなり、ただでさえ利用するなら月に5000円までと考える方が多いなか、毎月7〜8万円もする高価なツルバダを買えない、しかも、オンデマンドPrEPにはもう一つのPrEP薬であるデシコビは使えない(使ってはいけないということではなく、臨床研究のエビデンスがなく、現在研究途上である)ため、PrEP自体をやめてしまう方も出てきたり、先述の北海道のクリニックの方もPrEPの見守り診療をやめることを考えていたり(他のクリニックもそうなるかもしれません)という、皮肉な事態が起こっています。オーストラリアをはじめ海外の国々では、無料だったり安価で利用できたりするのに、日本では…。
HIVのことは、治療法が進歩しさえすればよいという話ではなく、(かつてHIV陽性者がエイズ予防法などにおいても差別的な取扱いを受けていたように)法制度や社会のありように大きく左右されるし、今まさにそういう局面にあるということを強く感じました(ACT UPのように製薬会社に抗議すべきという声も聞かれました)。ACONの青木さんもおっしゃっていたように、国が公衆衛生をどう考えるか、ということなんだと思います。億単位の予算をつけて新規感染者を何十人も減らせるのであれば、そうすべきですよね。僕らのコミュニティにはそれができる優秀な人材がたくさんいるわけですから、もっと予算をつけてほしいです。そして2030年までの流行の終結を本気で目指してほしいと思います。
そういう意味でも、社会領域からaktaの岩橋さんが選ばれて座長を務めたことに意義があったのではないでしょうか。
もう一つ、ACONの青木さんが、日本は性的なことに対して臭い物に蓋をするように扱う社会であるという指摘をしていたことも重要で、HIV(をはじめとする性感染症の)予防の根本にかかわる話だと思いました。
昨今の梅毒の感染増加について、マスコミでは、セックスワーカーのせいだとかマッチングアプリでの即ヤリが増えたからだとか、女性が“ふしだら”になったからだと煽るような論調が目立っていてゲンナリさせられますが、エイズ学会の会場は、性に対する「けしからん」的な反応や、家父長制的(あるいはホモソーシャル)なバイアスみたいなものがほとんど感じられず、みんながふつうにゲイやトランスジェンダーやセックスワーカーの話をフンフンと聞いて、親身に寄り添う雰囲気で、それが当たり前になっているのがスゴいと思いました。日本中こういうふうになればいいのに、と思いました。(とはいえ、奥井さんが、ゲイのセクシャルな話は避けられていると指摘していて、言われてみれば確かに、そこまで露骨なセックスの話は聞かれなかったな、と思いました)
もっと性のことがオープンに語られ、表現され、人間の当たり前の営みだということが広く認識され、学校では包括的性教育が行なわれ、同性愛のことも性感染症のこともきちんと教えられる、そんな日本になるといいなと思います。
ゲイコミュニティでも性のオープン化(ゲイセックスへの後ろめたさや内面化されたフォビアを払拭し、肯定していくこと)は、(六尺ナイトやよつんばいナイトなどのおかげもあって)ずいぶん進んできていると思うのですが、2000年代のような、HIVのことがゲイコミュニティの真ん中にドーンとあった(イベントにも勢いがあった)時代に比べると、みんなでHIV/エイズのことを考えよう、何かできることをしようという空気は薄れてしまっている気がしますし、相変わらずネット上にはHIV陽性者に対する差別的な言葉があふれています。(予算も少なく、活動が大変なのはわかりますが、コミュニティ内でも無償で快く協力してくれる方も少なくないはずですし)どうしたらそういう状況を変えていけるのか、あらためてみんなで考えていきましょうよ、と思いました。
INDEX
- レポート:Queer Space Tokyo
- 特集:レインボーイベント2026(上半期)
- レポート:年忘れお楽しみイベント「gaku-GAY-kai 2025」
- 特集:2026年1月の映画・ドラマ
- レポート:BUFF Fetish Xmas
- 2026年への希望を込めて――年忘れ&年越しイベント特集2025
- レポート:高雄同志大遊行(KHPride)
- レポート:レインボーフェスタ和歌山2025(2日目)
- 2025-2026 冬〜新春のクィア・アート展
- レポート:涙、涙の院内集会「第8回マリフォー国会」
- 特集:2025年12月の映画・ドラマ
- レポート:東京トランスマーチ2025
- 2025-2026 冬〜新春の舞台作品
- レポート:レインボーフェスタ那智勝浦(2日目)熊野古道パレード
- レポート:レインボーフェスタ那智勝浦(1日目)
- レポート:みやぎにじいろパレード2025
- レポート:香川プライドパレード
- レポート:岡山レインボーフェスタ2025
- レポート:九州レインボープライド2025
- 特集:2025年11月の映画・ドラマ
SCHEDULE
記事はありません。