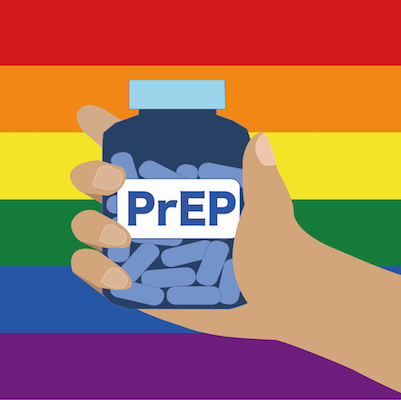FEATURES
レポート:エイズ学会2024(1)
NPO法人aktaの代表・岩橋恒太さんが大会長を務める「日本エイズ学会学術集会・総会エイズ学会」が11月28日〜30日に新宿の京王プラザホテルで開催されました。PrEPが承認されたことを受けての課題や、最新のさまざまな事柄について話し合われた学会というだけでなく、ゲイコミュニティの方たちが多数活躍し、同窓会のようなコミュニティイベントのような趣もあるイベントでした。3日間のエイズ学会を3回に分けてレポートします

日本エイズ学会学術集会・総会エイズ学会(以下「エイズ学会」)は、HIV/エイズの諸問題の研究の促進、会員相互の交流および知識の普及と啓発を図る目的で、毎年全国のいろんな都市で持ち回りで開催されている学会です(昨年は京都で開催されました)。大会長は日本のHIV/エイズ対策において重要な役割を担う臨床・基礎・社会の3つの領域のいずれかで活躍している方から選ばれるのですが、今回は2017年の生島さん以来7年ぶりに社会領域からNPO法人aktaの代表である岩橋恒太さんが選ばれ、大会長を務めることになりました(ニュースでお伝えしていた通りです)。歴代の最年少の大会長でもあるそうです。aktaという二丁目コミュニティをベースに活動してきた団体の方が会長を務めること、素晴らしいと思い、また、以前から見知っている身近なゲイの方が会長を務めることに親近感を覚え、実は初めてなのですが(おそらくこの先、取材できる機会もそうそうないので)エイズ学会自体も取材させていただくことにしました。
主に医療関係の方や公衆衛生の研究者、予防啓発や陽性者支援に携わっているNPOやCBOの方々、陽性者の方たちなどが参加し、アカデミックだったり専門的で難しかったり堅苦しかったりする話合いを行なうような学会、という先入観を抱いていたのですが、イメージと大きく違い、まるでゲイコミュニティイベントのような場面も多々ありましたし、HIVに関わる人たちの年に一度の同窓会のような、アットホームな雰囲気がありました。もちろん、最新の情報を得られたり、いま問題となっているイシューをめぐっての熱い議論が展開されていたりもして、学びや知見を深める機会ともなりました。意義ある3日間でした。
というわけで、エイズ学会のレポートをお届けします。ボリュームが多いので3回に分けてお送りします。
1回目は11月28日(木)の模様です。
(取材・文:後藤純一)
★2日目のレポートはこちら、最終日のレポートはこちらです
【関連記事】
aktaの岩橋さんが今年の日本エイズ学会学術集会・総会の会長に就任しました
https://gladxx.jp/news/2024/01/9191.html
世界エイズデーキャンペーン2024
https://gladxx.jp/column/goto/9792.html
特集:新宿の街へ出よう
https://gladxx.jp/features/2024/scene/9804.html
都庁に行くときなど(先日の東京トランスマーチの際も)横を通り過ぎたり見上げたりする京王プラザホテル。羽田からリムジンバスも出てますし、海外の方の利用も多そうな高級ホテルです。ついぞ利用する機会などなかったのですが、エイズ学会をきっかけに、初めてその中に入りました。
黄色く色づいたイチョウの並木も美しい都庁前中央通りには「HIVの新たな感染ゼロ」「差別ゼロ」「エイズ関連死者ゼロ」の「0(ゼロ)」をあしらった6種類の啓発フラッグ(PrEPやU=Uのフラッグも)がたなびいていました。京王プラザホテルの正面玄関にエイズ学会の大きな立て看板が出ていて、中にもわかりすく案内が出ていました。
4階に総合受付があり、その奥にポスター展(※2日目のレポートでお伝えします)の部屋と第4会場(「花A」)があり、廊下に企業や団体のブースが出展されていて、南館のほうに第2会場(「錦」)、第3会場(「扇」)があります。エスカレーターで5Fに昇ると第1会場(「エミネンス」という大きなホール)が、3Fに降りると第5会場(「グレースルーム」)がありました。この日は朝8:15分から開会式が行なわれ、8:30から第1〜第3会場でシンポジウムやセッションがみっちり入っていて、第4、第5会場でも一般演題(口演)などが入っています(19:30から二丁目で『HIV陽性者が直面する社会的障壁の解消に向けて』というパートナー共済の共催シンポもありました)。シンポジウムやセッションは基礎、臨床、社会、国際と分類されていて、分野があまりかぶらないようになってはいるものの、それでも関心のあるシンポが重なって迷う方もいらっしゃるだろうなと思いました。
私は夜まで取材するつもりだったので、自分自身の体力と相談し、午後の部から参加することにしました。
「3つの0の達成のために オーストラリアのエイズ予防啓発の現在の活動から、日本のこれからの予防、啓発を考える」
13:30-15:30 第1会場
今年7月のaktaでの「LGBTQコミュニティとの協働研究:これまで、そしてこれから」にも登壇していた(ゲイ・バイセクシュアル男性コミュニティ向けのHIV予防啓発や研究にも長年携わってきた)名古屋市立大学大学院看護学研究科の金子典代先生と、長年多くのHIV陽性者・エイズ患者の診療に携わってきた都立駒込病院の感染症センター長である今村顕史先生が座長を務めていました。
はじめに厚労省の感染症対策課長である荒木裕人氏がご挨拶。20年前にもエイズ対策に携わっていて、当時はコミュニティとの協働を立ち上げる時期だったと、今は仙台のZELから那覇のmabuiまで全国のコミュニティセンターや団体との連携をしているというお話が印象的でした。
続いて、オーストラリアのHIV予防啓発団体「ACON(エイコン)」の青木大さんのお話。2002年に渡豪してすぐにエイズを発症したり、薬物依存にもなり、人生をあきらめかけめた時期もあったが、ACONの正規スタッフになることができ、ハッテン場との連携などにも携わってきたそうです。
ACONは1985年、シドニーがあるノース・サウス・ウェールズ(NSW)州で設立され、HIV/エイズをはじめLGBTQの健康課題に取り組んできた団体です。州や国からの資金プラス寄付で運営されています(15名くらいのスタッフが専従として働いているそう)。NSW州には1万人以上の陽性者がいて、GB男性の10%が陽性だと見られています。2013年から「Ending HIV」キャンペーンを展開し、だんだん新規感染が減り、2022年はNSWで167人だけだったそうです。GB男性のためのSTI検査のクリニックを開設し、無料匿名で受けられます、専門のピアスタッフが対応し、通常の施設に行くのをためらう人にも人気です。
政府の施策で2021年から全員(一時滞在者も)無料で治療できるようになりました。PrEPは2018年から健康保険の対象となり、2020年にはすべての医師が扱い、すべての薬局での処方も可能になりました。国民健康保険を使えば1ヵ月3000円くらいで利用できます。医療費控除カードを持ってる人は700円程度、学生なども同様で、ワーホリで来てる外国人なども1800円程度で利用できます。本当にお金のない人にはコミュニティが配布しています。
ゲイコミュニティ向けキャンペーンのビジュアルも紹介されました(こちらのポスターはアワードも受賞しています。うまく探せなかったのですが、もっと多様な方がモデルになっているポスターシリーズもありました)
(実は20年くらい前、aktaにACONの方が来てお話する機会があって、億単位の予算で活動しているというお話に衝撃を受けたのを今でも記憶しています。今回の青木さんのお話も、実にうらやましい、目の覚めるような、ため息が漏れるようなお話でした。と同時に、一時は人生をあきらめかけた青木さんが活躍の場を得たこと、本当によかったと思いました。日本ではこうはいかなかったことでしょう)
続いて、MASH大阪とaktaという、日本でMSM向けに予防啓発の取組みを行ってきた団体から発表がありました。
MASH大阪の町さんは、病院で花粉症の薬をもらおうとしたところマイナ保険証で履歴を見られて処方されなかったケースがあるとして、今後もマイナ保険証で履歴を調べられると抗HIV薬を飲んでいることがわかってしまう可能性がある、そこをどうしていくかと問題提起していました。また、PrEPについて、本当に必要なのは、自分の意思より他者が優先されるケースに直面しやすい方(セックスワーカー、発達障害の方、貧困層の方など)なのに、薬価が高くて買えない、という指摘もしていました。
aktaの木南さんは、(今回もジャンジさんがガイドを務めてaktaや新宿区保健所などをバスで巡る映像が流れていましたが)aktaがサマーブラストで毎年アンケート調査を行なったり、ヤローページを発行したり、検査キットのディスペンサーを設置したりという、意欲的な取組みを多数展開してきたことを発表していました。ある意味、華やかといいますか、コミュニティ向けに目立った活動をしていることが学会の参加者にも伝わったと思います。この場で「Living Togetherのど自慢」が今回の学会での開催と年明けの二丁目での開催を最後に終了するという話もされて、残念、との思いを禁じえませんでした。aktaは今回、エイズ学会の事務局も務めていて、木南さんも通常の業務に加えて忙殺されていたなか、こうして発表にも臨んでいたと思います。おつかれさまでした。
続いて、福岡のコミュニティセンターhacoの舩石翔馬さん、ぷれいす東京の(映画『カミングアウト・ジャーニー』の)福正大輔さん、SWASH/MASH大阪のげいまきまきさん、東京カレッジ(東京大学)のLi Chunyanさんという4名のコメンテーターの方々が、今あった4人のお話を受けてコメントし、質疑応答も行なわれました。
質問は、オーストラリアはなぜそんなにエイズ対策に予算を割いてくれるのか、というところに集中(日本では専従は数えるくらいしかいません)。それは政府が公衆衛生のことをわかっているから、HIVに感染する人が増えたらそれだけ政府の出費も増えるわけだし、という答えで、本来そうあるべきだよね、と。また、福正さんがコミュニティ向けのポスターなどについて、日本ではイケメンをモデルに使うのが通常だが、オーストラリアでは多様な人たちが起用されてますね?と質問し、青木さんが、ACONでも以前は白人のイケメンモデルを使っていたが、自分には関係ないと思われてしまう、自分事として受け止めてもらえるように多様な人種・年齢・体型の人たちの写真を使っていると答えていました(今村さんが「いい質問ですねー」としみじみおっしゃっていたのも印象的でした)
また、げいまきまきさんがセックスワーカーにはコミュニティセンターどころか事務局すらないんです、というお話をしていて、身につまされました(「なんか荒木さんに陳情してるみたいになっちゃって」と笑っていましたが、本当に、これを機に考えていただけたら、と思いました)。これに関して青木さんが、オーストラリアではセックスワークが合法で、セックスワーカー(店舗の従業員)は必ず検査を受けることになっている、それはワーカーを守るためだ(仕事で感染してしまった際の保障などを考えて)というお話もありました。本当に素晴らしいです。
最後に青木さんは、日本は性に対するうしろめたさというか「臭いものに蓋」で性について語られない傾向がある、オーストラリアでは性は生活の一部と認知されている、といったお話をされていて、そこが根源だよね、と強く思いました(性解放なくしてゲイ解放なし、です)
座長のお二人もゲイセックスについての偏見が微塵も感じられず、会場にも大勢のゲイの方たちがいて、まるでゲイコミュニティのイベントのような雰囲気でした。そのことにも感銘を受けました。
ポジティブトークセッション
16:10-17:40 第3会場
aktaの岩橋さんと、日本HIV陽性者ネットワーク「JaNP+」の高久さんが座長を務めるHIV陽性者のトークセッションです。
私が今回、エイズ学会自体を取材しようと思った理由の一つは、公式サイトに載っていたこのセッションの登壇者のなかに、古くからの友人の名前を発見したことです(当日知ったのですが、もう一人、古くからの友人が登壇していました)。今までそのことを知らずに接してきましたが、HIV陽性であることを知って、そうか…と、彼が、きっと、彼なりの思いを持って、この舞台に登壇することを決意したのだろうなと思い、その話を聞きたいと思ったのでした。
公式サイトに名前が出てはいるのですが、念のため、5名の登壇者の方のお名前はイニシャルで表記します。
Kさんは高知県在住で、2013年に献血で感染が発覚したそうです。赤十字の先生から連絡があり、覚悟したものの、一人で話を聞くのが不安で、当時の職場の同僚にカムアウトし、立ち会ってもらったそうです。世間が狭い田舎の町で、あっという間に噂が広がることも危惧されましたが、職場の方が理解し、秘密を守ってくれたそうで(素晴らしい)、今でも特に差別を受けてないし、噂にもなっていないそうです。比較的早い段階でわかったので、手帳がもらえず、投薬も始められず、数年後にCD4(免疫の数値)が下がりましたが、その時は投薬を拒否したそうです。世間の助けになれば、という気持ちで、現在は「JaNP+」のスピーカーも務めているそうです。
KKさんは名古屋在住で、2003年に感染告知を受けました。医師や看護師からも温かい支えをいただきましたが、何よりも他人にうつしてしまうことを恐れていて、U=Uが勇気づけてくれたそうです。しかし、昔から変わらないのは陽性者への偏見・差別だといい、KKさんは、なぜ人が陽性者を差別するのかについて、行動免疫システムや集団心理などの概念を利用しながら独自に考察し、いちばん大事なのは正しい情報をしかるべき人が発信しつづけることだと語りました。「変わらなければいけないと思う。変化への恐れはみな同じ。変わることは素晴らしいことです」
Sさんは大阪在住で、若い頃から精神疾患を患っています。以前、HIV予防啓発活動に携わった経験もありますが、コロナ禍の間に感染しました。知識があれば予防行動がとれるかというと、そうではないと、セーファーセックスをずっと続けるのは結構大変で、メンタル面のこともあり、行動のコントロールが難しいと語っていました。
Sさんのスピーチの後、高久さんは「予防をやってた人が感染したと言えることを誇りに思います。それはコミュニティの成熟を物語っています。20年間感染せずにいてくれてありがとう」と泣きながら語りました(自身も陽性者であり、長年、たくさんの陽性者を支援してきた方だからこその言葉。このセッションの中で最もエモーショナルな瞬間でした)
Nさんは学生の方で、最近の刑法改正(性的同意に関する新たな法律)によってHIV陽性者が刑罰の対象になる可能性があるという懸念を表明しました。
性的同意に関する新たな法律は、性犯罪の未然防止や被害者の保護を目的としていますが、刑罰法規は明確でなければならないのに、そうなっていない(恣意的に運用される可能性がある)という懸念です。法改正がすべての人に平等に理解され適用されるわけではなく、HIV陽性者がどのような影響を受けるか考慮する必要がある、偏見が根強い社会では法が偏見を助長する懸念があり、一部の人に不利にはたらかないよう社会教育が必要だといいます。「開示義務はセンシティブな問題。各々の責任であり、国家が過度に干渉すべきではありません」
なお、Nさん自身はSEXの相手とLINEでコミュニケーションをとり、これ持って行く必要があるかな?とメッセージを送ることでコンドーム使用を含めた性的同意をとることができると話していました。事前の同意を得ることは法的にも重要だそうです。
最後に、Hさんが登壇。2008年、22歳のときに感染がわかりました。B型肝炎で入院したときにHIVの治療も始めたそうです。病院で献身的な看護を受けたことがきっかけで、自身も看護師になろうと思い、学校に通う道があるとのことで、その病院で看護助手として働けるよう内定をもらいましたが、働き始める前に一応言っておこうと思ってHIV陽性であることや検出限界以下であることを伝えましたが、驚かれて、そもそもHIV陽性者が医療従事者になっていいの?などと言われ、あなたを守れる体力がないから、と言われ、内定を取り消されたそうです。いい病院だと思ったのに、HIV陽性者に対してはそんな仕打ち…Hさんは打ちひしがれました。周囲の人には「訴えれば勝てる」と言われましたが、そこまでしようとは思わず、別の分野で働くことにしました。今はLGBTQの相談を受けたりする仕事に就いていて、「20代の頃にほしかった言葉」を言っているそうです。

世界エイズデー メモリアルサービス 〜いのちをつなぐ〜
17:40-18:40 第3会場
ポジティブトークセッションと同じ会場で、エイズで亡くなった方を追悼する場として「メモリアルサービス」というイベントが行なわれました。
もともとこのイベントは、仏教者の方と、キリスト者の方(京都で「バザールカフェ」を始めたり、関学レインボーウィークを推進したり、LGBTQやHIV陽性者の支援に携わってきた榎本てる子さん)が、エイズ学会に亡くなった方を追悼する場が必要じゃないかと提案し、始まったものだそうです。
前方のスクリーンに映像が映し出され、司会の方が、薬害エイズで亡くなった方のご遺族からのお手紙を代読したり、歌を捧げたり。何人もの方が亡くなった方を追悼するスピーチを行なったり(駒込病院で長年、患者の診療に当たってきた根岸先生や、ぷれいす東京の加藤さんなどもスピーチしていました)。そして、参加者のみなさんがそれぞれキャンドル(本当の火ではなく、電球の明かりがつくタイプ)を持ち、前方のテーブルに並べ、追悼しました。
長谷川博史さんや、佐藤郁夫さんなど、エイズを発症してなくなったわけではないものの、HIV陽性であることを公にしながら活動してきた故人に思いを馳せた方も多いはずです。(いくさんのパートナーの方が泣いていらして、ジャンジさんがそばで支えてあげていて…胸がいっぱいになりました)
こういう場があることは本当に大切だと感じましたし、ずっとこのイベントを開催してくださっている方の思いの尊さにも感じ入りました。
エムポックス対策シンポジウム:ヨーロッパと日本の現場から学ぶ!
19:30-21:00 akta
厳密に言うとエイズ学会のプログラムではないのですが、日本とヨーロッパの最前線で対応してきた専門家たちが集まり、成果と今後の課題を共有するシンポジウムがaktaで開かれました。重症化しやすい強毒型の(性行為でも感染する)新たな変異株「クレード1b」がアフリカで猛威を奮っていて、遠からず日本にも入ってくるのではないか(そうなったら死者も出るのではないか)と懸念されるエムポックスについて、より深く知りたいという思いがあり、同時刻に二丁目で開催された『HIV陽性者が直面する社会的障壁の解消に向けて』とどちらに行くか迷い、aktaに行きました。
国立国際医療研究センター国際感染症センターで実際にエムポックス患者の診療に当たってきた石金正裕先生の発表では、以前流行したクレード2bのエムポックスが(患部の写真なども含めて)どのような症状を呈するか、治療はどうするのか、ワクチンはどうなのか、どのように対策に当たってきたのかといったことが総合的に伝えられました。
皮疹は典型的な白いぷっくりした水疱瘡的なものだけでなく、小さくてにきび(吹き出物)と区別がつかないようなケースもあって、これでは気づかない方もいるだろうなと思いました。石金先生も、無症状の方もいらっしゃいますし、診断されてない、受診されてないケースも多く、これまで確認されているのは氷山の一角だとおっしゃっていました(先月、福岡県で20代男性の感染が報告され、まだ流行が終結していないのかと驚いたのですが、その理由の一端がわかった気がしました)
なお、日本ではクレード1bはまだ確認されていないそうです。
エムポックス対策については研究者とコミュニティと政府関係者が参加する円卓会議で話し合いが設けられてきて、当事者目線でツールを作ったり、科学的に正しいかどうかも検証されてきた、とのことです。
ロンドン大学のクイーンメリーという臨床研究もしている病院に勤務するChloe Orkin先生のお話。HIV陽性者も含む経験豊かなコミュニティアドバイザリー委員会が毎年、何を調査研究するかを社会学的に優先すべき課題だと思われるテーマを決めていて、例えばエムポックスの前は、HIV陽性者の服薬治療について人種や性別、SOGIなどの面で公正かどうかというテーマだったそうです。2022年にエムポックスが流行した際は、早い段階で社会科学公衆衛生の人とつながり(何百人ものつてをたどったそう)、女性はどうか、HIV陽性者、とりわけ治療されていない、エイズを発症した方の場合はどうかとか、何度も再感染する人などについて研究論文を書いたそうです。CD4(免疫値)が200以下のエムポックス患者は免疫再構築症候群を患ったり、ひどい症状を呈し(写真を見ましたが、本当に痛々しかったです)、Chloeさんが診たそうした患者さんのうち、15%の方が亡くなったそうです。
UKとUSAではMSMに向けたワクチン接種が行なわれましたが、その様子の写真(例えばこちら)を見せながら、エムポックス患者のうち白人が占める割合は30%にすぎないのにワクチンを受けた人の52%が白人だった(人種的な偏りがある)として、UK BLACK PRIDEのような黒人のクィアが集まるイベントに出張してワクチンを打ったというお話や(ワクチン自体に偏見やスティグマがあったりする方もいるそうです)、「誰に向けてメッセージを発しているのか。本当に対象としなければならない人たちにメッセージを届けることが重要だ」というお話が強く心に残りました。
最後にChloe先生は、自身の症状や治療の様子をSNSで克明に発信した方を紹介し、「このことでわかるように、誰にでもできることがあります。特に当事者が発信することで社会が変わったりします」と語りました。
質疑応答では、「なぜ日本ではMVAワクチン(海外で使用されているHIV陽性者などにも安全なワクチン)が打てないのかと思う。声を上げることは大事だが、どうやって国を動かすのか」という質問が出て、Chloe先生は「どんなことがあっても辛抱強く言い続けることが大事です。私は何かあるたびに、どんなトピックの会合であっても必ず、女性が除外されていると話します」と答えていました。エムポックスについても米CDCやいろんなところに訴えて、いくつか反響があり、EUのCDCからは「話しに来てください」と言われたそうです。
時間がなくて、コミュニティの人たちからの質問に答えたりというような活発な議論にまでは及びませんでしたが、臨床研究に携わった方のリアルなお話を聞けて学びになりましたし、コミュニティとしては「本当に対象としなければならない人たちにメッセージを届けることが重要」だし、あきらめずに言い続けることも大事だということも学びました。
昨年末、埼玉県の30代男性がエムポックスで亡くなったわけですが(日本のエムポックス対策の敗北だと思います。心からご冥福をお祈りします)、今後、アフリカで流行中のクレード2bが(先月にはついに米国でも最初の患者が確認されましたが)日本で流行した場合、もっとたくさんの方が亡くなってしまうのではないかと危惧します。HIV感染に気づかず免疫不全状態になってしまう方が一人でも少なくなるよう、もっと検査を受けやすくすることや、性的にアクティブな方たちにいかにメッセージを届けるかといったことが重要になってくると思われます(ワクチンが行き渡るとは思えないですし…)。もっとコミュニティ内でも議論が活発になるといいな、と思いました。
INDEX
- レポート:Queer Space Tokyo
- 特集:レインボーイベント2026(上半期)
- レポート:年忘れお楽しみイベント「gaku-GAY-kai 2025」
- 特集:2026年1月の映画・ドラマ
- レポート:BUFF Fetish Xmas
- 2026年への希望を込めて――年忘れ&年越しイベント特集2025
- レポート:高雄同志大遊行(KHPride)
- レポート:レインボーフェスタ和歌山2025(2日目)
- 2025-2026 冬〜新春のクィア・アート展
- レポート:涙、涙の院内集会「第8回マリフォー国会」
- 特集:2025年12月の映画・ドラマ
- レポート:東京トランスマーチ2025
- 2025-2026 冬〜新春の舞台作品
- レポート:レインボーフェスタ那智勝浦(2日目)熊野古道パレード
- レポート:レインボーフェスタ那智勝浦(1日目)
- レポート:みやぎにじいろパレード2025
- レポート:香川プライドパレード
- レポート:岡山レインボーフェスタ2025
- レポート:九州レインボープライド2025
- 特集:2025年11月の映画・ドラマ
SCHEDULE
記事はありません。