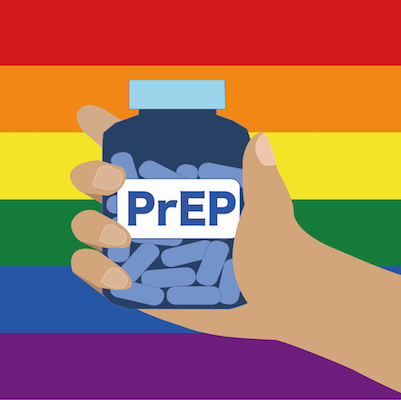COLUMN
2024年を振り返って(1)同性婚実現への希望
2024年はゲイコミュニティにとってどんな年だったのか、この1年の出来事を振り返りながら考えてみます。1回目は同性婚実現に向けた動きについてまとめました

(「結婚の自由をすべての人に」訴訟に携わっているみなさんに拍手!)
2024年という年は、実は様々な面でエポックメイキングだったりターニングポイントだったりする動きがあった年としてLGBTQ史のなかに位置づけられるのではないかと思います。そう思える重要な出来事がいろいろありましたので、1年を振り返って総まくりコラムをお届けしたいと思います。1回目は、「同性婚実現への希望」です。
昨年は種々の差別発言や理解増進法をめぐる、落胆や怒りを禁じえない動きに翻弄された感がありましたが、今年は司法の面で本当に喜ばしい、大きな前進が見られました。いよいよ何年後かに同性婚が実現しそうだと希望が持てるような素晴らしい判決でした。
司法での前進
2019年、婚姻平等を求めて全国で一斉に起こされた「結婚の自由をすべての人に」訴訟が5年目を迎えて大きな前進を見せました。2021年から始まった東京二次訴訟の一審判決が3月に出て全国5箇所・6つの訴訟の判決が出揃いましたが(これを受けて院内集会も開催。慶應義塾大の駒村圭吾教授の講演、力強かったです)、同じ日に北海道訴訟の二審(控訴審)判決が札幌高裁で出され、初めて24条1項(両性の平等)についても違憲判決が出ました。10月の東京一次訴訟の東京高裁判決も完璧に近い素晴らしい判決で、先日の福岡高裁の判決では初めて憲法13条(幸福追求権)での違憲も出て、画期的でした。振り返ると、今年は3つの高裁が連続して違憲判決を出したわけで(極めて異例なことです)、国に対して早急に法制化を求める(別制度などではなく異性婚と同等の婚姻です)動きになっています。
正直、昨年までは、果たして生きている間にパートナーと結婚できる日が来るのだろうか…との不安をぬぐいきれないものがありましたが、今年の3つの高裁判決のおかげで、最高裁でも間違いなく違憲判決が出るだろうし、きっと5年後くらいには同性婚が実現するんじゃないかという希望が持てました。
3月には最高裁が、同性パートナーも犯罪被害者等給付金支給法の「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に含まれるとの画期的な判決を下しました。この判決はあくまでも犯給法についての判断ですが、最高裁が同性カップルも事実婚夫婦と同様に法的権利が認められなければならないとしたことは本当に重要で、以降の司法判断にも影響を与えるものです。
5月には名古屋家裁が「婚姻に準じる関係」だとして同性パートナーの名字変更を承認しています。
「結婚の自由をすべての人に」訴訟が行なわれていない金沢や愛媛、沖縄などの地域では「結婚の平等にYES!」キャンペーンが展開され、今年は参加地域も増えましたが、宮城ではそれだけでなく、同性カップルが同性婚を認めないのは違憲だとして男性カップルが仙台家裁に家事審判を申し立てました。こちらも要注目です。
トランスジェンダー関連の裁判でも前進がありました。
6月には最高裁が性別変更後に生まれた子の親子関係を認めるという判決を下しています。
7月には、最高裁大法廷が昨年、特例法の不妊化要件を違憲だとする初判断を示したものの、外観要件については審理を高裁に差し戻していた、その広島高裁の判断が示されました。外観要件について「憲法違反の疑いがあると言わざるをえない」と裁定し、申立人の性別変更を認めるものでした。
地方自治体の革新的な取組み
今年の10大ニュースがあるとすれば、長崎県大村市が今年5月、住民票の続柄について同性カップルにも事実婚と同じ表記(「夫(未届)」「妻(未届)」)を認めたことが最上位にランクインするでしょう。夫や妻という文字が記された住民票を受け取った方たちは感激するでしょうし、最高裁が犯給法について事実婚と同等の権利を認めたことと相まって、同性カップルにも事実婚並みの権利を与えようとする動きを後押しするような意義もありました。2015年の渋谷区・世田谷区の同性パートナーシップ証明制度はLGBTQ史上の大きなターニングポイントとなりましたが、今回の住民票のことも、行政に「ふうふ」として認めてもらえる「承認」としての意味が非常に大きいです。
大村市の英断に触発され、同様の対応を行なう自治体も増えてきました(一覧はこちら)。また、つい先日、杉並区の岸本区長の呼びかけで東京都の10区が連名で厚労省と総務省に要望書を提出しました。
今年も多くの自治体が同性パートナーシップ証明制度の導入を進めました。11月には全国19の府県と150の市町村が加入する自治体間連携ネットワークがスタートしました。12月には仙台市がついに「パートナーシップ宣誓制度」を導入し、全国の政令指定都市全てで制度導入が実現し、これまで全国唯一の制度導入自治体ゼロ県だった宮城県でもようやく空白が解消されることになりました。これで全国の制度導入自治体数は少なくとも474に上り、人口カバー率は89.686%となりました。9割近い自治体が同性パートナーシップも婚姻相当であると承認するようになったことは「結婚の自由をすべての人に」裁判などにおいても重要な判断材料となることでしょう。
大阪市議会が「同性婚や事実婚を認める新たな法制度の確立に向けた議論の促進を求める意見書」を可決したり、埼玉県知事が同性カップルの権利保障の早急な議論と対応を国に要望したり、福岡県古賀市が同性婚の法制化を国に要望したことなども国の重い腰を上げさせるうえでの重要な動きだったと思います。ありがたいです。
民間企業・団体の応援
7月には同性婚に賛同する企業がついに500社を超え、その後もハイペースで増え続け、12月には580社を超えました。
日本百貨店協会が同性婚推進団体とコラボして「いいふうふの日」キャンペーンを展開したり、大手芸能事務所のアミューズが東京高裁の違憲判決を受けて異例の声明を発表したり、札幌や仙台の弁護士会が婚姻平等の実現を求める声明を発表したことなども、実に心強い、拍手したくなるような取組みでした。
京大病院が同性パートナー間の生体腎移植を実施したのも、同性カップルを家族と認めることで命が救われたケースであり、素晴らしいニュースだったと思います。
一方、国会では
司法も、地方自治体もこれだけ当事者に寄り添い、時代を前に進めるようと動いてくれている一方、国会は相変わらず後ろ向きです…しかし、つい先日、少しだけ、灰色が薔薇色に変わるような出来事がありました。
今国会で、同性婚法制化が「日本全体の幸福度にプラスとなる」と石破総理が川田龍平議員の質問に対し答弁する場面がありました。同性婚の法制化を進めると明言したわけではないのですが、「じゃあ進めましょうよ」と言いやすくなりますし、この10年近く(壊れたテープレコーダーのようだと評する声も上がるくらい)「家族のあり方の根幹に関わる」という消極的な答弁が繰り返されてきた国会で、ようやく前向きなコメントが得られたというだけでも気持ち的に違いますよね。
3月には、石川大我議員の質問に岸田総理が「トランスジェンダーへの誤解に基づく誹謗中傷は許されない」と答弁する場面がありました。昨今のSNS上でのトランスバッシングに釘を刺すことにもつながるような、重要なコメントだったと言えます。6月には福祉現場でのSOGIハラは虐待に該当しうると政府が答弁しています。
(なお、尾辻かな子さんが国会に返り咲きましたし、かずえちゃんが来夏の参院選に出馬するので、当選を果たしたあかつきには、さらに国会でLGBTQのことが活発に議論されるようになることでしょう)
(文:後藤純一)
INDEX
- 世界エイズデー2025のキャンペーン
- 差別について考える――自分自身が加担してしまわないように
- ゲイの孤独と「社会的健康」
- 2025年6月のHIV検査キャンペーン
- 教えて先生! 実践的SAFER SEX(1)セックスその前に
- 2024年を振り返る(3)海外の動き
- 2024年を振り返って(2)実はいろいろあったスゴいこと
- 2024年を振り返って(1)同性婚実現への希望
- 世界エイズデー2024のキャンペーン
- ゲイの世界におけるルッキズムとは?
- 2024年6月のHIV検査キャンペーン
- TVドラマ史上最もLGBTQが花盛りだった2024年1月クールを振り返って
- 2023年の世界エイズデーキャンペーン
- エムポックス(サル痘)のワクチン接種について
- 2023年6月のHIV検査キャンペーン
- サル痘(mpox)が感染拡大しています。予防に努め、みんなで力を合わせて感染拡大を防いでいきましょう
- PrEPユーザーのリアリティ――2022年の現在地
- 2022年の世界エイズデーキャンペーン
- サル痘への偏見や感染者への差別を克服しながら予防に努めましょう
- 私が地方のパレードを応援する理由
SCHEDULE
記事はありません。